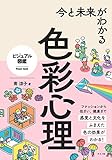「最近、黒い色ばかり使っているけど大丈夫?」
「やたらと赤が多いのは、何か怒っているサイン?」

この記事の内容
わが子の描く「色の世界」にドキッとする瞬間
画用紙いっぱいに描かれた、真っ黒な円。
あるいは、画面が血の海のように見えるほど真っ赤に塗られた太陽。
それを見た瞬間、パパやママの頭の中には、どこかで聞いた「色彩心理」の知識がよぎりませんか?
- 黒は不安のサイン……?(うちの子、闇を抱えてる?)
- 赤は攻撃的な気持ち……?(幼稚園で誰かと喧嘩した?)
- 肌の色が紫……。(体調が悪いの? それとも……)
- そもそも色が少なすぎて寂しい。(心が枯れてる?)
「この色選び、何か深い意味があるの?」と、スマホを片手に「子どもの絵 色 心理」なんて検索してしまう親心、本当によくわかります。私も教諭時代、保護者の方から「うちの子、黒ばっかり使うんです……」と、消え入りそうな声で相談されたことが何度もありました。

でも、最初にお伝えさせてください。
検索している時点で、あなたは十分、お子さんの小さなサインをキャッチしようとしている“愛ある親御さん”です。
今日は「この色はこういう病気です」なんていう、怖い診断の話はしません。子どもの色が持つ、もっと自由で、もっと単純で、そしてもっと面白い「本当の理由」を一緒に紐解いていきましょう。
読み終える頃には、お子さんのカラフル(あるいは真っ黒!)な絵を見るのが、少し楽しみになるはずですよ。
まず大前提|子どもの絵は色彩心理だけでは読めない
巷には「色の意味一覧」のような情報が溢れています。でも、子どもの絵をそれだけで決めつけてしまうのは、実はとってももったいない(そしてちょっと危険な)ことなんです。
ネットで見がちな「色=感情」一覧の落とし穴
よくある「色彩心理」では、こんな風に書かれていたりします。
- 黒: 不安、抑圧、恐怖
- 赤: 怒り、生命力、攻撃性
- 青: 落ち着き、寂しさ、内向的
これを見て「うちの子、黒ばかりだから不安なんだ!」と直結させてしまうのは早合点。これらはあくまで「大人の心理学」や「統計」の一つに過ぎません。子どもの場合、もっと「物理的な理由」で色を選んでいることがほとんどなんです。
大人と子どもは色の使い方が違う
大人は「空だから青」「悲しいから暗い色」というように、意味や常識で色を選びます。 対して子どもは、「今の気分」「たまたま目についた」「このペンの描き心地が好き」という直感で動きます。

色彩心理はあくまで「ヒントの一つ」程度。辞書のように正解を探すのではなく、「今日はこの色を使いたかったんだね」と、まずはその事実を丸ごと受け止めることから始めてみましょう。
それでも気になる|色別によくある親の心配と本当の理由
多くの親御さんが不安になる「特定の色」について、子どもの視点から見た「本当の理由」を解説します。
黒ばかり使うとき
「黒=闇」と考えてしまいがちですが、子どもにとって黒は、最高に魅力的な色なんです。

- かっこいいから: 戦隊ヒーローのブラックや、強そうなイメージに憧れる時期があります。
- はっきりするから: 白い紙に対して、一番コントラストが強く、描いた手応えを感じられるのが黒です。
- たまたま一番取りやすい: クレヨンセットの一番端っこにあった、短くなっていたから使いやすかった、なんて理由もザラにあります。
「黒は全部の色を混ぜた色」でもあります。全部の色を重ねて遊んでいるうちに、結果的に黒くなっただけ、ということも多いんですよ。
赤が多いとき
「赤=怒り」と心配されますが、子どもにとって赤は「エネルギー」そのもの。

- 目立つから: パッと目を引く赤は、子どもにとってお気に入りの色になりやすい。
- 強いから: 「一番強い色がいい!」という情熱が、画面を赤く染めます。
- クレヨンの発色が良い: 赤いクレヨンは発色が良く、軽い力で綺麗に描けるため、選ばれやすい傾向があります。
怒っているどころか、むしろ「今、エネルギーに満ち溢れているぜ!」という絶好調のサインであることの方が多いのです。
青・緑が多いとき
「青=冷静、落ち着き」とされますが、これも「たまたまブーム」であることが多いもの。 「アナ雪のエルサが好きだから青」「恐竜が好きだから緑」という、推しキャラの影響をダイレクトに受けているだけだったりします。

色が少ない・塗らないとき
「色が少ない=感情が乏しい?」と心配になりますが、これも発達の過程です。
- めんどくさい: 描きたい形(輪郭)を描き終えたら、本人的には満足。塗る作業は重労働なんです。
- 早く次に行きたい: 頭の中のイメージが次々湧いてくる子は、1枚をカラフルに仕上げるより、何枚も白い紙に形を描くことを優先します。
- 形に集中している: 物の形を正確に捉えようとしている時期は、色まで意識が回らないことがあります。
年齢別|色の選び方はこう変わる
年齢によって、色の使い方の「ブーム」は変わっていきます。今、お子さんがどのステージにいるかチェックしてみてください。

2〜3歳|意味より「ある色」
この時期は「色に意味を持たせる」という概念がまだ薄いです。 「たまたま手に取った色」がその時の正解。 「なんでパパを緑で描いたの?」と聞いても、本人は「そこにあったから!」という感覚。たまたまの連続を楽しんでいる時期です。
4〜5歳|好きな色が固定される
「好きな色」がはっきりしてくる時期です。 「今日は全部黄色で描く!」といった、自分の中のこだわりを試しています。 特定の1色ばかり使うのは、自分の好みを確立しようとしている成長の証拠。心配どころか、個性が育っている証ですね。
6〜7歳以降|少しずつ意味を意識
「空は青」「リンゴは赤」といった、現実の色と合わせようとする意識が芽生えます。 一方で、わざと「紫のライオン」を描いて、フィクションの世界を楽しむ遊びも始まります。
【あわせて読みたい内部リンク】
元教諭の視点|「色」より見てほしい3つのポイント
色の意味(色彩心理)を気にするよりも、もっと大切にしてほしい「見方のコツ」があります。
① 前と比べてどうか
「今の色」だけを見るのではなく、以前と比べて「変化」があるかを見ます。 色が「増えた」のか、「変わった」のか、「塗り方が広がった」のか。 変化があるということは、心が動いている証拠。それ自体を「成長」として楽しみましょう。
② 絵の中に動きや物語があるか
「何色を使っているか」よりも「何を描いているか」に耳を傾けてみてください。 たとえ真っ黒な絵でも、「これ、夜の火事で消防車が来ているところ!」という物語があれば、それは不安の表れではなく、ダイナミックな想像力の発揮です。
③ 絵以外の様子
これが一番重要です。
- 表情: 楽しそうに描いているか。
- 会話: ご飯や遊びの話をいつも通りしているか。
- 遊び: 他の遊びにも興味を持っているか。 絵が黒くても、元気に走り回って笑っているなら、全く問題ありません。
⑤ これは少し気にしてもいい?判断の目安
それでも「やっぱりうちの子、何かが違う気がする」と感じる時のための、慎重な目安です。
色だけで判断しない
単色ばかり使う、色が黒い、といった**「絵の特徴だけ」で問題を決めつけないでください。** 専門家でも、絵1枚で診断を下すことはありません。
相談してもいいケース
以下の状態がセットで現れる場合は、園の先生や専門機関に「ちょっと最近の様子が気になっていて……」と相談のきっかけにしても良いでしょう。
- 極端な変化が長く(1ヶ月以上)続く: 明らかに絵の雰囲気が暗くなり、元気が戻らない。
- 絵以外でも元気がない: 食欲がない、眠れない、友達と遊ばなくなった。
- 親であるあなたが、ずっと苦しくて不安でたまらない。
相談は「悪いところを見つけるため」ではなく、「ママの安心を取り戻すため」に活用してくださいね。
色と感情の関係を、もう少し広く知りたい方へ
子どもの絵を読む視点だけでなく、 大人自身の「色の感じ方」を見直すヒントにもなります。
⑥ 親の関わり方|色を「聞かない・決めつけない」
お絵描きを「心の診断テスト」にしないために、おすすめの声かけをご紹介します。
NGになりやすい声かけ
- 「なんで黒なの?」(「黒はダメ」というメッセージに聞こえてしまいます)
- 「怒ってるの?」(色から感情を決めつけると、子どもは心を閉ざしてしまいます)
- 「普通はこの色だよ」(子どもの自由な表現を枠にはめてしまいます)
おすすめ声かけ
- 「この色、力強いね! 好きなの?」(色そのものを認める)
- 「このあたり、かっこいい塗り方だね」(部分を褒める)
- 「今日はこの色を使いたい気分だったんだね」(その時の選択を丸ごと受け止める)
正解探しより、受け取り
子どもの色は、コロコロ変わります。 昨日の黒は「かっこいい黒」だったかもしれないし、今日の黒は「夜の黒」かもしれません。 「正解」を探すのをやめて、「今、この色を楽しんでいるんだな」と受け取ってあげる。その安心感こそが、子どもの表現をさらにカラフルに広げていく一番の栄養になります。
『この色しか使わない』『同じ道具ばかり』というときには…
色の幅だけでなく、道具の種類が豊富なので、 「子どもが色をどう使うか」「どの道具を選ぶか」からも 心理や発達のヒントが得られます。
まとめ:色は心の答えではなく、今の「気分」
「子どもの絵の色がおかしい……」と不安になっていたパパやママ。
少しは、肩の力が抜けましたでしょうか?
子どもの絵は、テストの答案用紙ではありません。 その時、その瞬間に感じた「この色、塗るの楽しい!」「このペン、はっきり書ける!」という生のエネルギーが爆発した跡なんです。
もし、お子さんがまた真っ黒な絵を描いてきたら、「おっ、今日は黒の気分なんだね! 迫力あるね」と、面白がってみてください。
「この色、大丈夫かな」と検索してまで心配したあなたの優しさは、もう十分お子さんに伝わっています。その優しさがあれば、お子さんの心はいつだって、どんな色を使っていようと、健やかに育っていきます。
今日描かれたその1枚。ぜひ、日付を書いて取っておいてください。
いつか「あの時、黒ばっかり使っててママ心配しちゃったんだよー!」なんて笑い合える日が、必ず来ますから。
次に読んでほしいおすすめ記事 「色の次は形が気になる……」そんな方はこちら。
👉 【元教諭が解説】子どもの絵に顔がない?手が長い?心配いりません。年齢別の発達ルール
いかがでしたか? 「うちの子、こんな不思議な色の使い方をするんです!」というエピソードがあれば、ぜひ教えてくださいね。子どもの描く自由な世界、一緒に楽しんでいきましょう!
💭もっと深掘りしたい方はこちら
🔗「紫や青ばかり使う子どもは何を考えているの?色から探る気持ちのヒント」
「黒い色」「赤い色」など、色には感情が表れます。詳しくはこちらの記事で解説しています。
関連記事: – 危ない絵の心理 – 病んだ絵の心理 – サイコパス 絵 – 残酷な絵 – ホラー絵ホーム » 子どもの絵の色が気になる?色彩心理だけで判断しないでほしい理由
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。