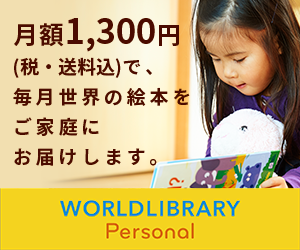この記事の内容
- 「育児書通りなのに…」子どもが泣く・ぐずるのはなぜ?
- おもちゃが多すぎると逆効果?子どもが飽きっぽくなる理由
- 「また同じおもちゃ?」繰り返し遊びが子どもに必要なワケ
- 「赤ちゃん中心の生活に慣れない…」まじめなママほどしんどくなる理由
- パンとバナナの順番より大事なこと|ママの優先順位のヒント
- 「無理しない子育て」ができなかった日のこと|リアルな体験談
- 子どもの“体調管理”ができてきたら、次に見えてくること
- “ママの忙しいオーラ”が、子どものサインを見えなくすることもある
- 正解より「満たされる」育児を|がんばるママへ贈るメッセージ
- 🧡 小さなルールが、親子の安心につながることもある
- 🌏 世界の絵本で子どもとワクワク体験!
「育児書通りなのに…」子どもが泣く・ぐずるのはなぜ?
“がんばってるのにしんどい”ママへ。子どもがまとわりつく本当の理由
あるママの家での出来事。義理のお父さんから「孫のおもちゃが多すぎる」と書置きをされたそう。
聞いたときは「余計なお世話!」と思ったけれど、実際に子どもがおもちゃに囲まれて遊んでいる様子を見たら、思わず「たしかに多すぎるかも…」と感じてしまった。
おもちゃが多すぎると逆効果?子どもが飽きっぽくなる理由
実はおもちゃが多すぎると、子どもは逆に飽きっぽくなってしまうこともあります。 目移りして集中できず、どれも中途半端。おもちゃが「子どもを静かにさせる道具」になってしまうと、本来の役割から離れてしまうのです。
「また同じおもちゃ?」繰り返し遊びが子どもに必要なワケ
子どもは繰り返し遊ぶことで学びを深めていく存在です。 同じおもちゃでも、日々の発達に応じて遊び方が変わっていきます。 「またこれで遊んでるの?」と思うようなことでも、子どもにとっては試行錯誤の連続。
でも、おもちゃが多すぎるとその「深まり」が薄れ、どれも表面的に触れて終わってしまうことがあります。
そして大人がぐずるたびに「これやってみる?」「じゃあこっちは?」と次々におもちゃを出してしまうと、まるでドラえもんのポケット状態。 一時的には気が紛れるかもしれませんが、子どもの心の満足にはつながりません。
「赤ちゃん中心の生活に慣れない…」まじめなママほどしんどくなる理由
こういった状況によくあるのが、「育児書通りに育てたい」と頑張るママたち。 経済的な余裕もあり、家事も効率的にこなしたい。だからこそ育児も「正解通りに」やりたい。
仕事は、自分のペースで物事を進められる。
予定を立てて、計画的に、順序よくこなすことが得意な人ほど、赤ちゃんとの生活にはギャップを感じやすいかもしれません。
赤ちゃんのお世話は、まさに“他人軸”。
いつ寝るかも、いつ泣くかも、いつ体調を崩すかもわからない。予測できない日々が続きます。
この「他人軸に切り替わる期間」は、人によって本当に差があります。すぐに慣れる人もいれば、何ヶ月たっても「こんなはずじゃ…」と感じる人も。
実際、子どもは育児書の通りには動きません。 たとえば「夜ぐずるからこの時間に昼寝させて」「バナナを先に食べたがるからパンを先に食べさせて」と、細かく計画しても、その通りにならないのが育児。
そうした状況で「ぐずる」=「対策が足りない」と思い、また新しいおもちゃや声かけ、工夫を次々試す。でも、子どもはどこか満たされない。
そうなると、子どもはますます「ママ、ママ〜」とまとわりつくようになります。 本当は、おんぶしたり、だっこしたり、目を見て安心させることの方が、子どもにとっては必要だったりするんです。
パンとバナナの順番より大事なこと|ママの優先順位のヒント
パンとバナナをどう出すか悩む前に、子どもの目を見て話してあげる。 おもちゃをきれいに並べるより、ひとつを一緒にじっくり遊ぶ時間を作る。
そうすることで、子どもは「納得」し、「満足」する。 結果的に、動き回ったりぐずぐずする時間が減ることもあります。
「無理しない子育て」ができなかった日のこと|リアルな体験談
ちょっと無理をして、家族でお出かけした年末のこと。
普段なら「人混みは避けよう」「帰ったらすぐ手洗い」って気をつけられていたのに、疲れていたせいで、つい気が緩んだ。
その結果——
子どもが40度の高熱。年末年始で病院も閉まっていて、1週間ずっと、気が気じゃない毎日を過ごすことになりました。
「ちゃんと休めてたら、防げたかも」
そう思うことはあっても、過去は変えられません。でも、これをきっかけに「もう無理はしない」と決めました。
子どもの“体調管理”ができてきたら、次に見えてくること
子どもの生活リズムが整ってきて、熱や咳などの体調管理にも少しずつ自信がついてくると、ふと気づくことがあります。
「今、この子の気持ちを、ちゃんと受け止められているかな?」
子どもが出すサインは、本当に小さいものです。
ちょっとした表情、いつもと違う声のトーン、急に甘えてくる態度。
でもその裏にある気持ちまでは、まだうまく言葉にできない子も多くいます。
たとえば、突然泣き出したり、急に癇癪を起こしたり。
あとから振り返って「あのとき、少し寂しかったのかも」「不安だったのかも」と思い当たることがある。
体調と同じように、感情も“早めの対応”ができれば落ち着くことがあるんだと、後になって気づくことも多いものです。
“ママの忙しいオーラ”が、子どものサインを見えなくすることもある
毎日の家事に育児に、やることが山積み。
そんなとき、ママが心の中で「今それ言わないで…」という状態になっていると、知らず知らず“忙しいオーラ”が出てしまいます。
子どもはその空気を敏感に感じとります。
「今は話しかけちゃいけないのかな」
「この気持ち、言ってもムダかも」
そう思って、自分のサインを小さくしていきます。
ママのほうも、見ようとしていなかったり、気づかないふりをしてしまうことがあります。
でも、あとから振り返って「なんで気づけなかったんだろう」と自分を責めてしまうことも——。
子どもが発しているのは、ほんの小さな「ここにいてね」のサイン。
本当は、ちゃんと見て、聞いてもらえるだけで落ち着く気持ちがたくさんあるのです。
正解より「満たされる」育児を|がんばるママへ贈るメッセージ
育児って、本当に正解がない世界。 がんばってるからこそ、しんどくなることも多いです。
でも、少し視点を変えて「子どもの心が満たされているか」に目を向けてみると、案外スッと楽になることがあります。
おもちゃはあくまでサポート役。 大事なのは、子どもと一緒に“いま”を感じることかもしれません。
🧡 小さなルールが、親子の安心につながることもある
たとえば、わが家には「なんだか不安なときは“7秒抱っこ”しよう」というルールがあります。
きっかけは、幼い頃に子どもが言葉で気持ちを伝えるのが難しい時期に、「どうしてほしいかわからないけど、そばにいてほしい」というサインを感じ取ったこと。
ぎゅっと7秒間だけでも抱きしめると、子どもも落ち着き、こちらも気持ちを切り替えられる——そんな時間が何度もありました。
この“7秒ルール”、実は今でも続いていて、小学6年生になった今でも時々「抱っこして」と言ってくれるんです。
ほんの一瞬、手を止めて、気持ちを受け止める。
それだけで、子どもは「大丈夫」と思えるのかもしれません。
💡 「こんな行動も気になる?」シリーズ記事
🔗 ティッシュをひたすら出し続けるのはなぜ?
🔗ドアを無限開け閉め
🔗おもちゃを並べるだけで遊ばないのはなぜ?
🔗突然、同じ言葉を繰り返し言うのはなぜ?
「うちの子もやってる!」と共感したら、ぜひシェアやコメントで教えてください!
「赤ちゃんの成長を記録しませんか?」
👉毎日の育児、大変だけどかけがえのない時間ですよね。スマホやカメラで、赤ちゃんの“今”をたくさん残しておくのもおすすめです📸
🔗赤ちゃんをおうちでかわいく撮る方法
|
🌏 世界の絵本で子どもとワクワク体験!
普段手に取らない世界各国の絵本が毎月届くサービスです。
異文化に自然に触れることで、子どもの好奇心や想像力をぐんと伸ばせます。
「どんなお話かな?」届いた瞬間のワクワク顔も嬉しいポイント!
- ✅ 自分では選ばない絵本に出会える
- ✅ 翻訳済みだから気軽に世界の文化を体験
- ✅ 1歳から年齢に合った本が届く
- ✅ グローバルな視点で育児をサポート
英語絵本を取り入れる前のステップとしても最適!
「どんな世界かな?」って親子で話しながら読むのも楽しみです。
ホーム » 「育児書通り」でも子どもが泣く理由。ほんとうに必要なのは?
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a347e0f.a2dc6f96.4a347e10.6fca4a62/?me_id=1392273&item_id=10000377&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Feasyjoy-shop%2Fcabinet%2Fplaymat%2Fsp%2Fimgrc0104114580.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)