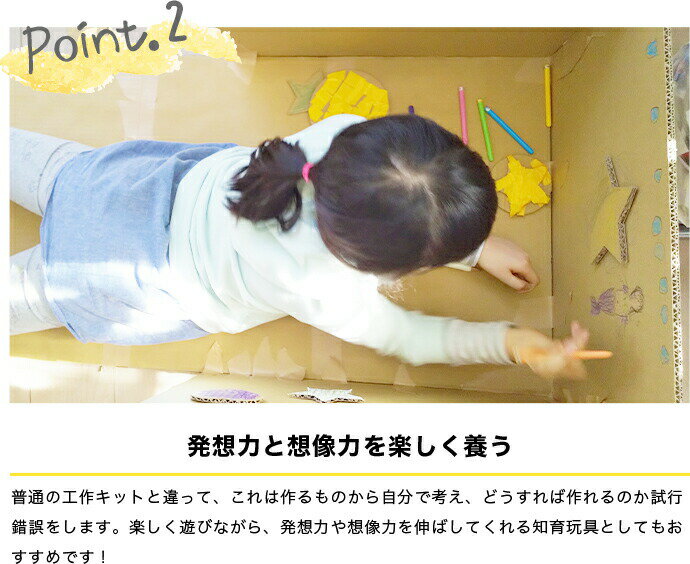「ママ、見て見て!」
工作に夢中になって、目をキラキラさせる子どもの姿。思わず笑顔になりますよね。
でもふと、こんなふうに思ったことはありませんか?
「なんでこんなに夢中になるの?」
「家は汚れるし、片付けも正直ちょっと大変…」
実はこの造形遊び、子どもの心と頭を育てる宝の時間なんです。
この記事では、元教諭の視点から、
✔子どもがなぜ造形遊びに夢中になるのか?
✔家でどう環境を整えるといいのか?
✔どんな声かけが子どもの成長につながるのか?
をお伝えします。
なぜ夢中になる?
造形遊びをもっと楽しめる環境と声かけのコツ
「ママ見て〜!これ、作ったんだよ!」
子どもが夢中になって工作している姿、見ているこちらまでワクワクしますよね。でも、どうして子どもはこんなにも“作ること”に熱中するのでしょう?
実はそこには、自己表現の喜びや思考力の成長といった、子どもにとって大切な意味が隠れています。
子どもが夢中になる理由
「作ること」は心の言葉
子どもにとって、造形遊びは“自分を表現する手段”です。
言葉ではうまく伝えられない感情やアイデアを、絵や形にして表現する——それは、心の中を整理する時間にもなっています。
- 「この色、今の気持ちにぴったり!」
- 「こんな形、見たことないけど作ってみたい!」
こうした衝動は、創造力や思考力の芽。だからこそ、子どもは夢中になるのです。

造形遊びで育つ力
「遊び=学び」になる瞬間
- 創造力・発想力
思い浮かんだことを形にする体験を通して、子どもの内なる想像力がグングン伸びていきます。 - 集中力・手先の器用さ
切る・貼る・こねる・塗る…いろんな動作の積み重ねが、自然と集中力や巧緻性(こうちせい)を育てます。 - 自己表現力
「なんとなく描きたい」「ちょっと作ってみたい」
その気持ちは、言葉にしきれない思いを伝えたいサイン。
だからこそ、造形遊びには心のケアとしての側面もあるのです。
🔗遊べる作品を作ろう!【造形遊び】で子どもの成長をサポート – itti-blog
親にできる“環境づくり”の工夫
子どもが「やってみたい!」と思える環境がポイントです。
1. 素材は“選べる”ように
クレヨン、紙、粘土などは子どもの目線の高さに置いて、自分で選べるようにしてあげましょう。
→「今日は何を使おうかな?」とワクワクしながら選ぶ時間が、自立心と自己肯定感を育てます。
2. 作業スペースは“安心できる場所”に
新聞紙やレジャーシートを敷くだけでも、「汚れてもいいよ」のメッセージに。
→「思い切って作っていいんだ!」という安心感は、自由な表現の後押しになります。
3. 静かな音楽も“集中スイッチ”に
BGMにリラックス系の音楽を流すと、気持ちが落ち着いて自然と集中力がUP。
→音楽に合わせて手を動かすことで、感覚やリズム感も育まれます。
4. “片付け”も遊びの一部に
片付けがストレスにならないように、ラベル付き収納など「自分で戻せる仕組み」を。
→整理整頓の習慣や自己管理力も育ちます。
🔗子どもの絵をアート作品の保存方法とおしゃれな飾り方。フレームからライトまで – itti-blog
声かけのコツは?
「すごいね!」の一歩先へ
作品を見たとき、つい「上手だね」「すごいね!」と言いたくなりますが、こんな声かけもおすすめです。
- 「この色、どうやって選んだの?」
- 「ここにストーリーがある気がするね」
- 「この形、どうやって思いついたの?」
→ 子どもは「わかってもらえた!」と感じると、もっと表現したくなります。
年齢別・遊びの広げ方と関わりのコツ
| 発達段階 | 特徴 | 親の関わり方 |
|---|---|---|
| 幼児期(3〜5歳) | 触覚・感覚が豊かに育つ時期 | 形にこだわらず「触る・感じる」を大切に。過程を褒めて「挑戦する気持ち」を育てよう。 |
| 低学年(6〜8歳) | 「どうしたらうまくできるか」を考え始める | 子どものアイデアを引き出す声かけで、計画的に表現する経験を。 |
| 中学年(9〜10歳) | 論理的に考え、工夫する力が伸びる | 作品づくりの“過程”を一緒に考えよう。「失敗しても大丈夫」と伝える声かけを。 |
| 高学年(11〜12歳) | 自分の世界観やテーマを持ち始める | 発表や共同制作など、表現を「人と共有する」機会を作ろう。 |
🔧 中高学年が盛り上がる造形活動の特徴
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① テーマがある・目的がある | 「この街にあったらいいなと思う公園を作ろう」「自分だけのオリジナルキャラを商品化するなら?」など、ストーリー性や社会性があると、のめりこみます。 |
| ② 工夫や仕組みが必要 | 「動く工作」や「立体的な構造物」など、設計・試行錯誤・完成までが楽しい!特に男の子は“ギミック”好き。 |
| ③ チームで取り組める | 「友達と協力して大きなものを作る」「役割分担で作品を仕上げる」など、仲間と関わる中での達成感も大きなやりがいに。 |
| ④ 評価される・見てもらえる機会がある | 展示、発表、コンテストなど、“誰かに伝わる”ことがモチベーションに。SNS世代なので「発信」も大好物。 |

🎨 具体的な活動例
| 活動 | 盛り上がる理由 |
|---|---|
| 段ボール建築/巨大迷路づくり | 実際に入れるサイズを作るとテンションMAX!設計図→制作→修正…プロジェクト型学習にもぴったり。 |
| アニメ風キャラづくり+グッズ化(缶バッジ、カード) | 自分の世界観をカタチにできる。完成品を友だちと交換したり、見せ合ったりするのも楽しい。 |
| 動く工作(ゴムの力で走る車、簡単ロボット) | 試行錯誤のプロセスが楽しい!理科とのつながりもあり、男子の食いつきが◎ |
| 街のミニチュア模型づくり(理想の未来の町など) | 社会科やSDGsとのつながりもOK。協力して1つの大作にする達成感がある。 |
| ストップモーションアニメ制作(コマ撮り) | 自分の作ったキャラが動くのが嬉しい!タブレットやスマホ活用で「見せたくなる」仕上がりに。 |
うちの子はダンボールを見つけると、「これ、使っていい?」と必ず言います。
🔗「子どもの塗り絵、はみ出しちゃうのはダメ?自由な表現の大切さ✨」
まとめ|造形遊びは“心と脳の栄養になる時間”
造形遊びは、ただの「お絵描き」や「工作」ではありません。
それは、子どもの心をほぐし、自己表現を支える大切な時間です。
家庭でも「やってみたい!」を引き出す関わり方を意識すれば、親子で楽しめる時間がもっと増えていきますよ🌱
🔗 「子どもの創造力を伸ばす5つの方法」
🔗 「得意を伸ばす親の接し方」
🔗「絵がうまくなる秘訣は自由な造形活動!おうちでできる簡単アイディア5選」
STEAM教育、ご存じですか?
STEM教育は聞いたことあるかもしれませんね!STEM教育にアートの分野を追加したものがSTEAM教育です。これからの時代に必要になるスキルってどんなものなのでしょう。STEAM教育については別記事で詳しく紹介しています。
家庭での造形遊びに加えて、STEAM教材を取り入れると学びの幅が広がります。すでにアートに興味がある場合は特に取り掛かりやすいのではないでしょうか。たとえば、アートと科学の融合テーマの教材では、構造や色彩の理論を遊びの中で学ぶことができ、創造性と知識の両方が養えます。
- おすすめポイント:
- 毎月新しいテーマが届き、家庭で簡単に始められるため、日々の造形活動の新たな刺激として活用できます。
- 年齢別の教材がそろっており、段階的にスキルアップを目指せます。
STEAM通信教材は、子どもたちの「やってみたい!」をサポートする頼れるパートナーです。
おえかき おもちゃ選び方 お母さんの絵 お母さんの絵が笑っていない お母さんの絵怖い お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描き お絵描きの心理 お食事エプロン くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 友達が小さい 友達の絵が小さい 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 工作 工作苦手 残酷な絵 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 育児グッズ 育児用品 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理 1歳おすすめおもちゃ
itti-blogをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。