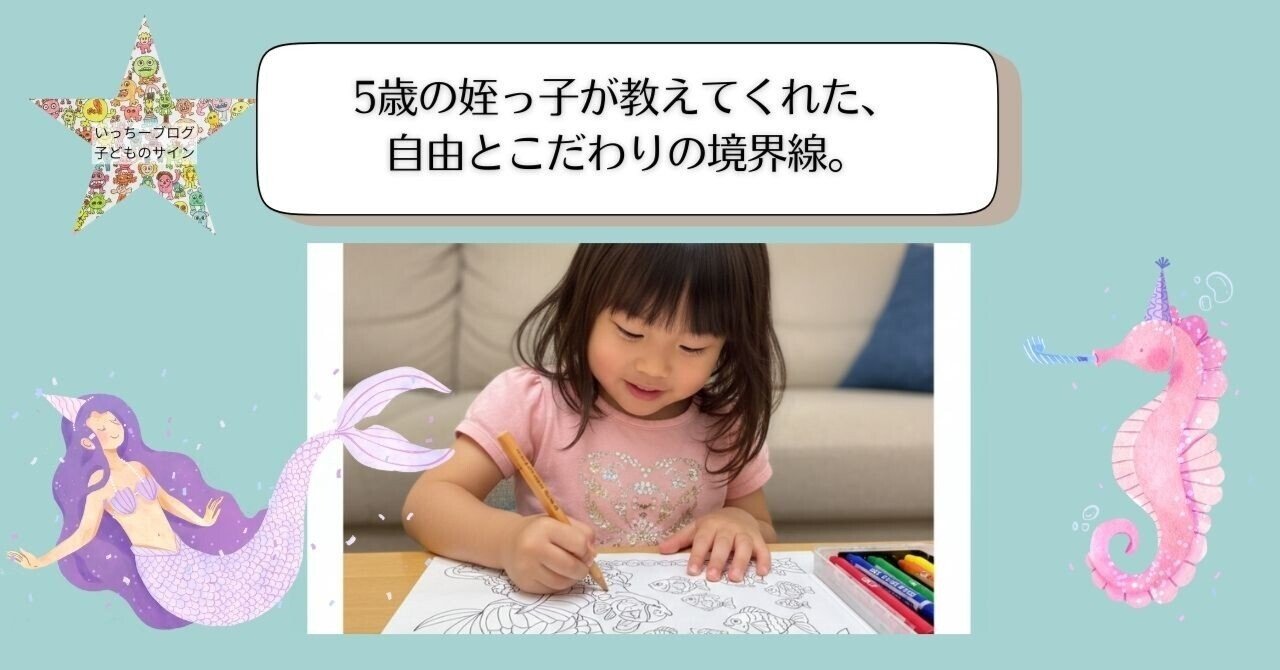こんにちは!ITTI-BLOGへようこそ。
リビングのテーブルで、画用紙いっぱいにクレヨンを走らせるお子さんの背中。
ふと覗き込むと、せっかくのキャラクターが、枠なんてお構いなしの豪快な線で塗りつぶされている……。
「ああ、またそんなにはみ出して・・・」
「もっと丁寧に塗ればいいのに・・・」
子育てをしていると、つい「こうしたらいいのにな」と溜め息をついてしまうこと、ありますよね。
今回のテーマは「ぬりえ」。

実は私自身も、子どもの頃からはみ出すのが大嫌いなタイプでした。
枠の内側をきっちり埋めることが自分の「当たり前」で、私にとって、ぬりえの「枠」は守るべき絶対のルール。そこからはみ出すことは、どこか「正解」から外れてしまうような、落ち着かない気持ちになりました。
でも、5歳の姪っ子と並んで座った日、私はその「枠」というものの本当の意味を、彼女から教わることになったのです。
この記事の内容
ぬりえがはみ出すのは「色」にじっくり集中しているから
「ぬりえ はみ出す 心理」と検索すると、集中力がないとか、乱暴だとか、不安になるような言葉が出てくるかもしれません。でも、実際に子どもたちの手元を見ていると、事実はもっとシンプルだと気づきます。
「はみ出す子」は、色の変化という魔法に夢中
枠をはみ出して塗る子は、決して集中していないわけではありません。むしろ、「色の変化」という面白さに、じっくりと集中しているのです。
「赤の上に青を乗せたらどうなる?」
「もっと強く塗ったらどう見える?」
彼らにとってぬりえは、形をなぞる作業ではなく、色というエネルギーの実験場。
枠という制限よりも、色の面白さが勝ってしまっているだけなのです。クレヨンと紙がこすれる気持ちよさが好きっていう子もいます。
「はみ出さない子」は、枠を守るというミッションに夢中
一方で、はみ出さずにきっちり塗る子。私と姪っ子が、まさにこのタイプ。 私たちは「枠というルール」に全神経を注いでいます。はみ出す子よりもじっくり座って取り組めるように見えるのは、彼らにとって「枠を守ること」自体が重要なミッションになっているからです。
どちらも、自分の興味がある対象に「じっくり」向き合っている点では同じ。
「はみ出すからダメ」「はみ出さないから良い」ではなく、その子が今、何に心を動かしているのか。まずはそこを面白がってみたいのです。
「枠」を死守する、切実な熱量
姪っ子はもともと、一ミリのはみ出しも許さないほど、きっちり塗ることに集中する子でした。
私がすこしでも枠をはみ出そうものなら、「そこはダメ!」「おばちゃん、ここは赤だよ!」と、鋭い指摘が入ります。
それは単なる几帳面さというより、「ここはこう!これ以上は入ってこないで!」という、あのイヤイヤ期特有の爆発的なエネルギーが、そのまま「枠という正解」を死守することに向けられているような、そんな切実な力強さでした。
「はみ出さないこと」に必死なその姿は、どこか、自分自身を一生懸命に守っているようにも見えました。私自身も、はみ出すことが怖くて「枠」に自分を押し込めてきたタイプなので、彼女の鉄壁ガードがどこか気持ちよくて。
だからこそ、そんな彼女が、ある日ふっと見せた変化は、理屈を超えて私の心に深く響くものとなりました。
5歳の姪っ子が教えてくれた「自律」への昇華
5歳になった今の彼女は、かつての「ぬりえ監督」とは別人のようでした。
「おばちゃん、どこでもいいよ。好きなところ塗って」
「え?いいの?」
ふわりと笑って私に「自由」をくれたその理由は、彼女の手元にありました。
彼女がいま没頭しているのは「曼荼羅(まんだら)」のような、複雑で緻密な塗り絵。
人魚のプリンセスの、爪の先ほどの鱗やドレスの装飾。そこだけは、彼女は驚くような集中力で、一色ずつ丁寧に塗り込んでいました。
「ここさえ自分が納得できていれば、他の場所はどうなってもいい」
そんな潔さが、彼女の背中から伝わってくるようでした。
あんなに周囲を気にし、私に細かな指示を出していたトゲトゲした姿は、もうどこにもありません。
外側の枠に自分を合わせるのではなく、ただ自分の内側にある「ここだけは」という場所を静かに整えていくのです。
欠けたクレヨンと、譲れないこだわり
彼女のクレヨン箱には「黄色」がありませんでした。
「弟が遊んでて、なくしたの」
彼女はそれを、責めるでもなく、淡々と受け入れていました。
道具が完璧でなくても、誰かに邪魔されても、彼女の世界はもう崩れません。今ある色で、自分の表現をじっくりと続けていく。そのレジリエンス(折れない心)に、私は静かに圧倒されました。
もちろん、すべてが自由なわけではありません。私が人魚のプリンセスの横にいる小さな「おさかなフレンズ」を塗ろうとした瞬間、「そこは違う」と静かに制止が入りました。
背景はどこでもいいけれど、お魚の色だけは、彼女が世界を解釈するための、どうしても譲れないこだわりだったからです。 (そして、色の指示はさらに厳しくなっていました。)
私は「ああ、ここがこの子のこだわりなんだな」と、
彼女の指示に従い、彼女の見ている正解を一緒に形にしていきました。
さて、今回ご紹介した「塗り絵」の話には、実は続きの物語があります↓
note|エピソード編 「黄色いクレヨン、弟が失くしちゃったの」
「黄色いクレヨン、弟が失くしちゃったの」
5歳の姪っ子が教えてくれた、自由とこだわりの境界線。
かつて「ぬりえ監督」だった彼女が、曼荼羅(まんだら)と出会って手に入れた「自分を整える喜び」。
その変化の裏側にある、切なくて愛おしい物語。
ぬりえを通じて親ができる「一番のこと」
もし今、お子さんの「はみ出し」に不安を感じているなら、それを「これからどんな成長をしていくんだろう」というワクワク感に変えてみませんか。
はみ出す子は、いつかそのエネルギーを注ぐべき「自分の核」を見つけた時、じっくりとした集中力を見せてくれるはずです。 はみ出さない子は、いつか自分を信じられた時、枠の外へ飛び出す勇気を見せてくれるはずです。
親ができる最高の関わり方は、子どもの「こだわり」の中に、あえてお邪魔させてもらうことです。大人の正解を押し付けるのをやめて、その子のルールに身を委ねてみる。それだけで、ぬりえの時間は「指導」から「対話」へと変わります。
結び:色がいっぱいの未来を、君に。
あの日、彼女が教えてくれた「自由と自律のバランス」があまりに眩しくて、私は思わず心の中で叫びました。
「おばちゃん、色がいっぱいの画材セットをプレゼントするわ!!!」
彼女が守り抜いた「おさかなフレンズ」の美しさも、はみ出してもいいと言ってくれた心の広さも。
そのすべてを応援するために、もっとたくさんの色を彼女の手に届けたい。
ぬりえの枠は、子どもを閉じ込めるためのものではありません。いつかその枠さえも自分の表現として乗りこなしていくための、大切な足場なのです。
今日、あなたの隣で、お子さんは何色を選んでいますか? その一色一色に込められた意思を、一緒に面白がってみませんか。
🎨 ぬりえでわかる性格と心理サイン
| タイプ | ぬり方の特徴 | 心の傾向 | 親の関わり方 |
|---|---|---|---|
| 🎯 こだわり | はみ出さず丁寧 | 慎重・完璧主義 | プロセスを肯定 |
| 🎨 自由 | はみ出し・勢い | 想像力・自分軸 | 発想を承認 |
| 🌈 気分屋 | 中断・ムラ | 感情の波 | ありのまま受容 |
| 💤 興味なし | 関心が薄い | 主体性が強い | 別の遊びを探す |
どのタイプも「発達の途中」であり、優劣はありません。
むしろ「塗り方」は、その子が自分をどう表現しているかを知る大切な手がかりなんです。
むしろ「塗り方」は、その子が自分をどう表現しているかを知る大切な手がかりなんです。
あわせて読みたい関連記事
コメント募集中! 「うちの子、こんな不思議な塗り方をします!」「こだわりが強くて大変だったけど、こう考えたら楽になった」など、皆さんのエピソードをぜひコメント欄で教えてくださいね。
次回の記事予告 「お絵描きが苦手な子への、遊び心をくすぐる誘い方」をお届けします。お楽しみに!
関連記事
🔗「子どもの塗り絵、はみ出しちゃうのはダメ?自由な表現の大切さ✨」
🔗「造形遊びをもっと楽しむための環境作りと指導方法」
ホーム » ぬりえの「はみ出し」は心の成長サイン。5歳の姪っ子が教えてくれた、自由と自律の絶妙なバランス
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
ちょっと塗ってみたくなった方へ♡よかったらプリントしてぬりぬりしてみてくださいね♡

この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。