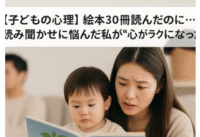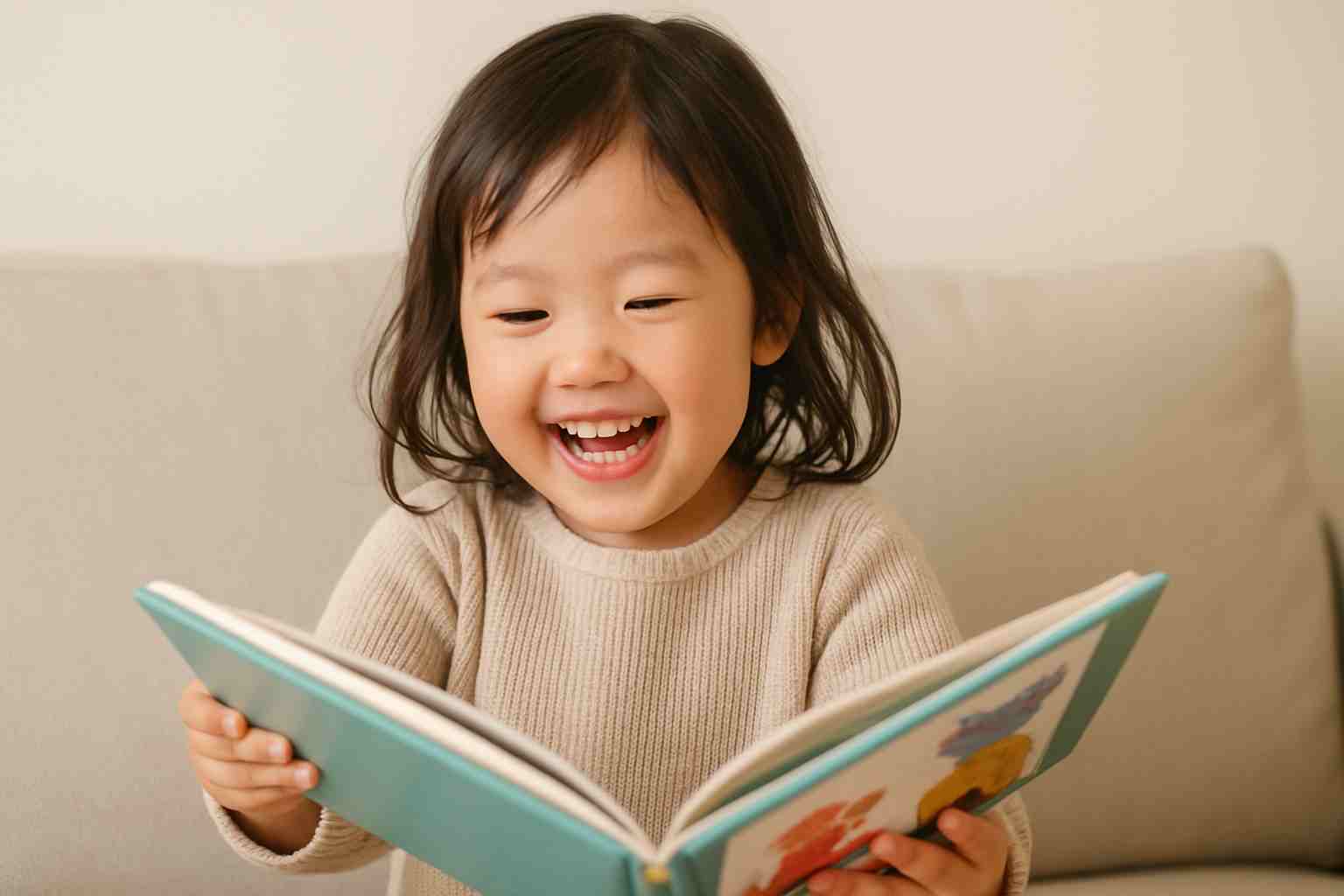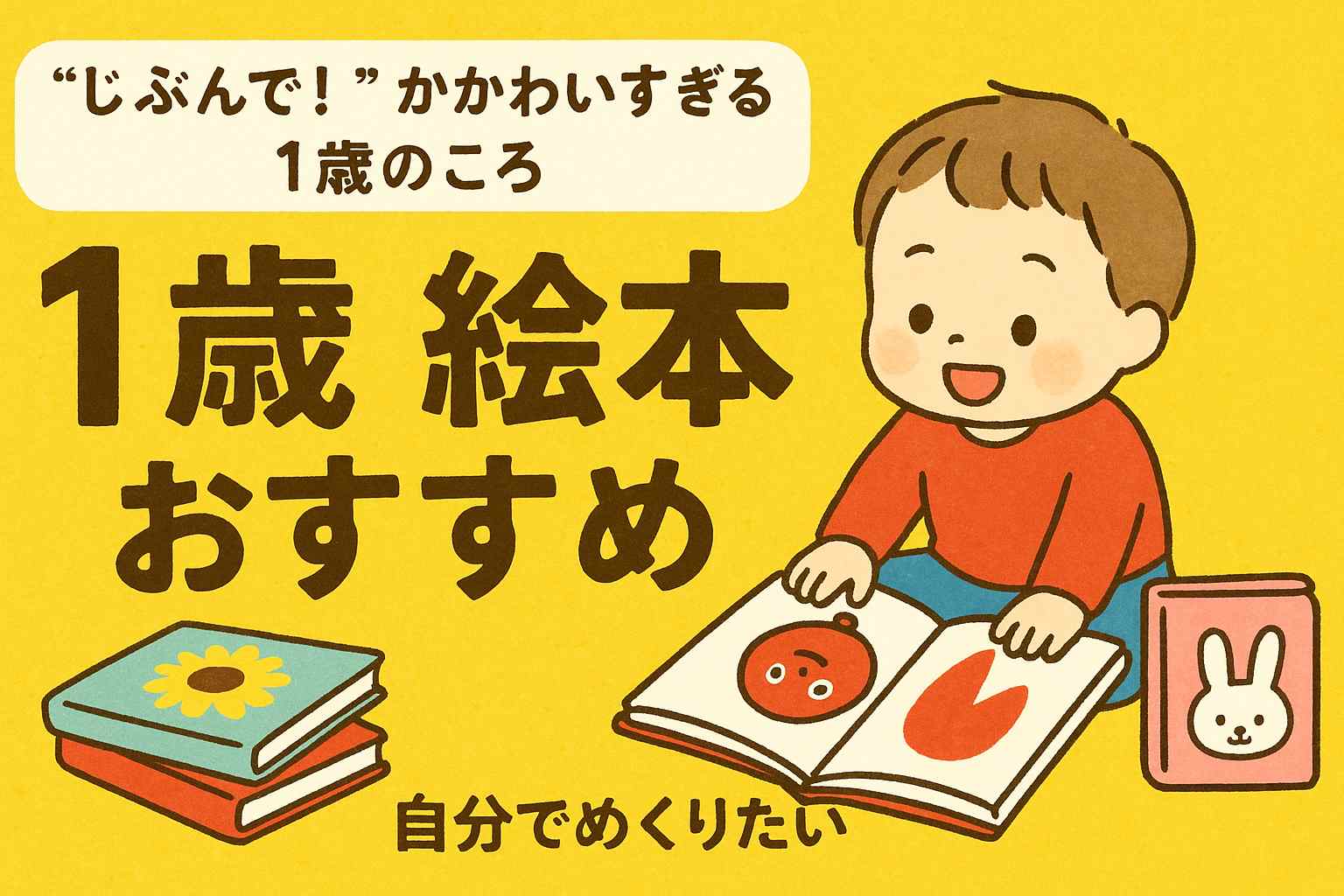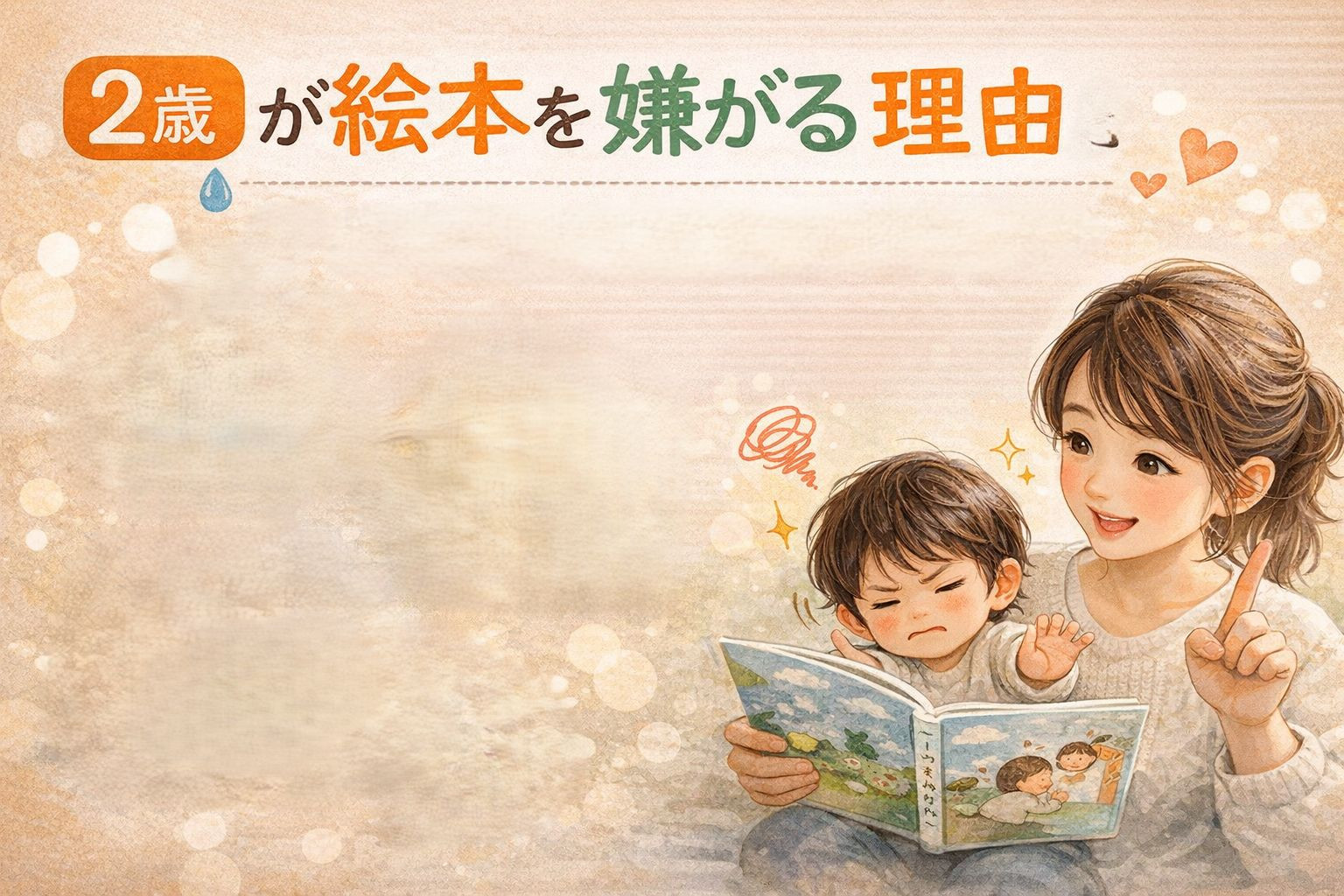「じぶんでやる!」って、なんでこんなに突き放すように言われるんでしょうね? 😂ずっと仲良くしてきたじゃないですか・・・。
子どもがイヤイヤ期に突入すると、急に「じぶんで!」と主張し始め、親はそのたびに心の中で「えっ、もう無理!」って叫びたくなりますよね…。服を着るのも、食事をするのも、お片付けをするのも、何もかもが一人でやりたくて、でも実際にやるのはちょっと無理!😅
でも実は、これ、子どもの成長にとってめちゃくちゃ大切な時期なんです!👶✨
そう、これは「自立心」の芽生えのサイン!

「じぶんでやりたい!」という気持ちが、これからの成長に大きく影響します。親としてはハラハラするけれど、その気持ちをどう受け入れ、どうサポートするかがポイント!
この記事では、イヤイヤ期の「じぶんで!」に対する親の理想的な対応法を、実践的に紹介します。お子さんの成長をサポートしながら、親もストレスなく過ごせる方法、試してみたくなること間違いなしです!😊
この記事の内容
この記事を読んでわかること
この記事を最後まで読んでいただければ、こんなことがわかりますよ!👇
- 「じぶんで!」の背後にある心理
どうして子どもは急に「じぶんで!」って言い始めるの?その心理を深掘りして、自立心の育成がいかに大切かがわかります! - 親がついイラっとしてしまう瞬間にどう対応するか
ついつい手伝いたくなっちゃうけど、やり過ぎると自立心を妨げちゃう…でも、どうすればいいの?具体的な対応法をお伝えします。 - 自立心を育てるサポート術
ただ見守るだけじゃなく、どうサポートすれば子どもはもっと自分でできるようになるか。実践的なアドバイスが満載! - 実際の例を交えた対応方法
「じぶんで!」が出るシーン別に、どう対処すればいいのか具体的に紹介。これで「あれ?」って思う場面がスッキリ解決! - うまくいかない時の対処法
もし「じぶんで!」がうまくいかず、泣き出してしまったらどうする?そんな時に試したい対応法もチェック!
子どもの「じぶんで!」には、成長の嬉しいサインが隠れています。これをどう活かすかで、お子さんの自立心をぐっと引き出せるチャンスが広がるんです!💡
自立を促すことで、子どもが自分でできることが増えて、結果的に親も楽になります😊✨
最初は大変でも、少しずつ「じぶんで!」をサポートしていくことで、お互いにとってハッピーな結果が待っていると思います!
親がリラックスできる時間が増え、子どもも自信を持って「じぶんで!」ができるようになる…まさにwin-winの関係です!🫶
この記事では、イヤイヤ期にありがちな「じぶんで!」という主張を、親がどんな風に受け入れてサポートするべきかを、わかりやすく解説していきますね。実際の育児のシーンを交えて、親としてどう向き合うべきかも考えていきますので、すぐに試せるアイデアも満載です!
それでは、さっそく「じぶんで!」にどう対応するか、見ていきましょう!👇
1. 「じぶんで!」の背後にある心理とは?🧠
子どもが「じぶんで!」って言い始める時、実はその背後には大きな心理的な変化が隠れています。お子さんが急に「じぶんで!」と主張するのは、自立心が芽生え始めたサインなんです!👏
この時期、子どもは自分のことを「自分でやれる!」と思うようになり、親からの手助けを拒否することが増えるんですよね。でも、これは反抗期だけの問題ではなく、成長の一環。その自立心を尊重してあげることが大切です。
例えば、お子さんが「じぶんでお着替えしたい!」と言ったとき、実は「自分でできるよ!」という自信がついてきている証拠!🎉
それに、お子さん自身がその「じぶんで」を成功させることで、達成感や満足感を感じます。これがさらに「自分でやりたい!」という気持ちを強くしていくんです。
でも、何でもかんでも「じぶんで!」と突き放してしまうと、無理が生じることも…。そのバランスを取ることがポイントなんですよ!
2. 親がついイラっとしてしまう瞬間の対応法😣
「じぶんで!」って言って、結局全然できない…子どもが焦ったり泣き出したりして、どうしても手を出したくなりますよね。ですが、親としても冷静に対応することが大切!
そんな時、イラっとするのをぐっとこらえて、「うまくいかなかったね。でも、大丈夫!一緒にやってみよう!」と優しく声をかけてあげるだけで、子どもの気持ちが落ち着きますよ。

例えば、服を着る時。お子さんが「じぶんで!」って言って、袖が逆さまだったり、ボタンがうまく留まらなかったりすることありますよね。そんな時、親としては「もう、どうしてできないの!」って思うかもしれませんが、ここはぐっと我慢。お子さんは「できない」ことを通して学んでいるんです。
そんな時に、「じゃあ、少し手伝ってあげるね」と声をかけながら、うまく手を貸してあげると、お子さんの自立心をサポートできるんですよ!💡
3. 自立心を育てるサポート術👪
子どもの「じぶんで!」をどうサポートするかが、成長のカギです。親としては手を貸したくなるけれど、子どもができることはできるだけ自分でやらせてあげるのがポイント!
例えば、お着替えの時。最初はうまくいかなくても、簡単な服から挑戦させてあげると、自信を持って「じぶんで!」と言えるようになりますよ。👕

また、食事の時も同じ。最初はスプーンを持つだけでこぼしてしまうこともありますが、「やったね!自分で食べられたね!」と褒めてあげることで、次回の自信に繋がります。
ただし、親としては「これじゃあ危ない!」という場面では、サポートが必要です。危険を避けるためには、必要なときだけ手を貸し、あとは子どもが試す場を作ることが大切です。
イヤイヤ期の“自分でやりたい!”を上手に伸ばしたいママへ
イヤイヤ期の困りごとの裏には「自分でやりたい」「思いどおりにしたい」という成長の芽があります。ぶつかり合う毎日を“自立につながるチャンス”に変えたいママにおすすめの1冊です。
自分で考えて動ける子になるモンテッソーリの育て方
「できないから泣く」「全部自分でしたい」が落ち着くヒントが満載。
声かけ・環境づくり・親の関わり方がとても実践しやすく、今日から家庭で取り入れられる内容です。
追い詰められる子育てから、「成長が見える子育て」へ。
4. シーン別!「じぶんで!」に対応する実際の声かけ例👶✨
じゃあ、実際にどんな声かけをすればいいのか? 具体的なシーンを想像してみましょう。
【お着替えの時】
お子さん:「じぶんで!」
あなた:「お!すごい!でも、このボタン、少しむずかしいよね?手伝ってもいい?」
(子どもがうまくボタンをかけられたら、すかさず褒めてあげる!)
あなた:「できたね!すごい!じぶんでできたね!」
【食事の時】
お子さん:「じぶんで食べる!」
あなた:「おっ、スプーンも持てるようになったね!でも、お皿がこぼれちゃうかもしれないから、ちょっとだけお手伝いするね。」
(こぼしてしまっても「大丈夫、次は気をつけてみようね!」と前向きに伝える。)
【お片付けの時】
お子さん:「じぶんでお片付けする!」
あなた:「えらい!じゃあ、このおもちゃをお片付けするところを見せてくれる?」
(うまくいかなかったら、「ちょっと手伝おうか?」と声をかけて、上手にサポート!)
5. うまくいかない時の対処法!😭
もちろん、うまくいかないこともありますよね。そんな時、子どもが泣いたり、イライラしたりすることも。焦って無理に自立を促すのではなく、「一緒にやってみよう」とリラックスした雰囲気でサポートしましょう。
たとえば、お着替えや食事で泣いてしまったら、「今日は少し手伝うね。でも、次はじぶんでやってみよう!」と少しずつ自立へのステップを一緒に進んでいくことが大切です。
6. 「じぶんで!」を楽しさに変えるコツ🎉
「じぶんで!」って言っても、毎回うまくいかないと、親も子どもも疲れちゃいますよね。そこで大事なのは、「じぶんで!」を楽しさに変える工夫です!🌟
例えば、お片付けの時間をゲーム感覚にしたり、服を着るのを「カラフルチームの一員になれるかな?」といった風に遊びながらやると、お子さんも「じぶんで!」を楽しめるようになります。これで、ストレスフリーで自立心を育てられるんです!🎈
お手本を見せるのも効果的!「お母さんも、こんな風に服を着るの早いんだよ!」と、お子さんに見せながらやってみて、楽しさを共有すると、子どもも「次は自分でやりたい!」って思いやすくなりますよ。
7. 親もリラックスできる時間を作るために…🌙
最後に忘れてはいけないのが、親の心のケアです。自分の時間やリラックスできる瞬間を作らないと、どうしても焦ったりイライラしたりして、子どもに対して過度に干渉してしまうことも。
「じぶんで!」の対応を上手にやっていくためには、親がストレスを溜め込まないことが大切。例えば、お子さんが「じぶんで!」って言っている時に少し後ろで見守りながら、自分も一息つける時間を作りましょう。
そして、どうしても「じぶんで!」にイライラしてしまう時は、少し一息ついて、「次回はもっと上手にサポートしよう!」とリフレッシュすることが大切です。
まとめ: 「じぶんで!」を上手にサポートして、子どもの自立を応援しよう!
イヤイヤ期の「じぶんで!」には、子どもの成長にとって大切な意味が込められています。この時期をどうサポートするかで、子どもの自立心がぐんと育ちますよ!💪
ただし、親としてはサポートを過剰にしてしまったり、無理に自立を促してしまうと、逆に子どもにストレスを与えることも。だからこそ、少しずつ、楽しく「じぶんで!」をやらせてあげることが大切です。
もしうまくいかない時でも焦らず、一緒に頑張る気持ちで見守りましょう!そして、親もリラックスできる時間を大事にしながら、無理なくサポートしていけるといいですね!
次回も、お子さんの成長をサポートするための実践的なヒントをお届けしますので、お楽しみに!💖
→ コンパクトで持ち運びやすく、外出先でも手軽にお絵かきできる。
※使用後はケースに戻すと片付けも簡単です。
📖 「子どもに合った絵本を見つけたい!」と思ったら、他の記事もチェックしてみてくださいね✨
一緒に読み聞かせの楽しさを広げていきましょう📖✨
ホーム » 「イヤイヤ期の『じぶんで!』にどう対応する?親が試したい5つのコツ
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。