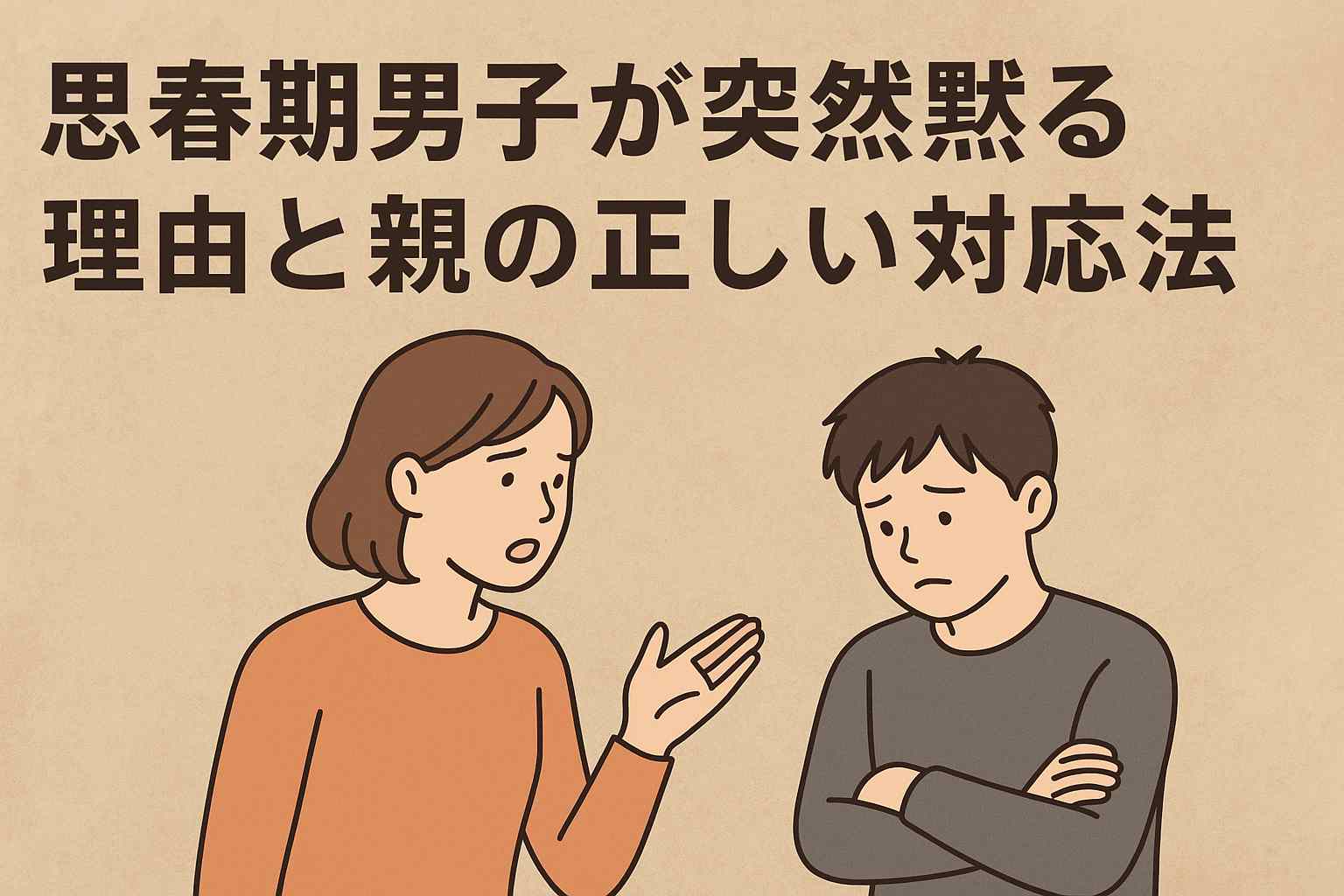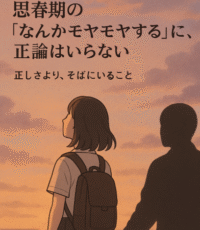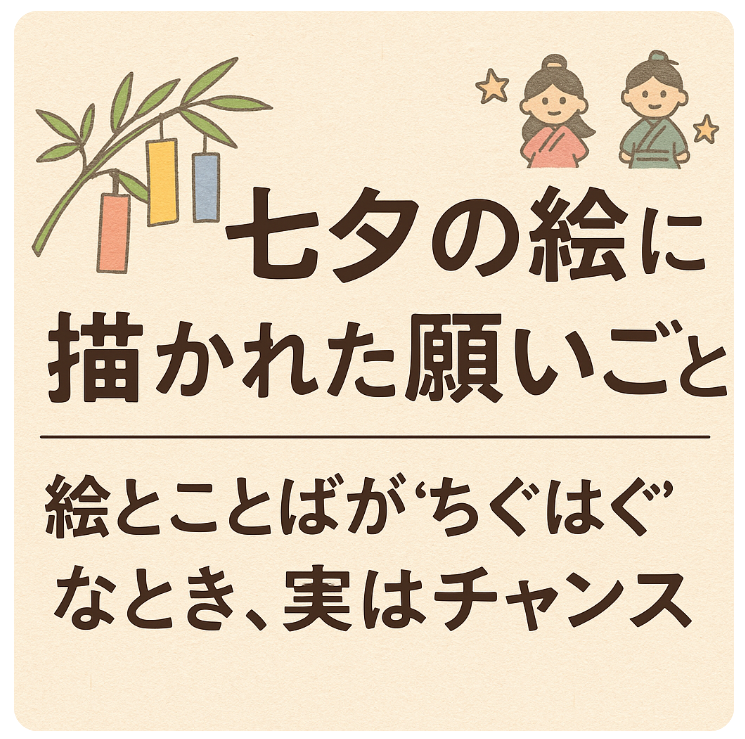「理由がないならやらない」
最近の子どもたちを見ていると、そう思う瞬間が増えた。
部活に入りたくないから入らない。
描きたくないからポスターは描かない。
納得できないなら動かない。
決して投げやりなのではなくて、ちゃんと“自分で考えて選んでいる”。
そんなふうにも見える。
けれど、どこかで「ハイパードライだな」とも思ってしまう。
淡々としている。割り切りが早い。
良くも悪くも、「合理的」なのだ。
この記事の内容
ポスターを描く意味が、見つけられない
iPadでは自由に描ける子が、
「ポスターはつまらない」「どう描けばいいかわからない」と筆が止まる。
最初に構図を決めて、色も決めて、あとはそれ通りに描くだけ。
「もう完成が見えてるものを、なぞる意味ってなに?」
――そんな声が聞こえてきそうな現場が、学校にはある。
「自由に描いていいよ」と言われれば動けるのに、
「テーマに沿って」「きれいにまとめて」と言われると、ぴたりと止まる。
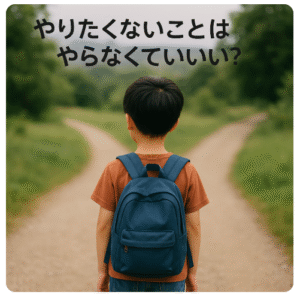
“やりたくないこと”を、やらないという選択
これは一見、とても潔い生き方にも見える。
ムダを切り捨てて、心地よく生きる。
ストレスの少ない選択を、自分で選び取っている。
けれど時々、ふと考える。
「理由がわかること」しか選ばなくなったとき、
「やってみて初めて気づけること」は、どこに行くんだろう。
経験に、後からついてくる“意味”
本当に大事なことの多くは、やってみたあとでわかる。
あの時はつらかった、意味なんてないと思った。
けれど、ずっとあとになって「あれがあったから今の自分がいる」と言えること。
それが“経験”なんじゃないかと思う。
やる前から「意味がない」と切り捨ててしまうと、
その“あとからの気づき”すら得られないまま、通り過ぎてしまうかもしれない。
「やらなくていい」が浸透する社会で
いま、少しずつ世の中は変わってきている。
好きなことを仕事にする。無理なことはしない。
それ自体はとてもいい流れだと思う。
でも、誰かがやらなければ回らない仕事、
誰もがやりたくないけれど、必要な役割。
それらが少しずつ見えなくなっていくのは、やっぱり少し怖い。
「やりたくないことはやらなくていい」の先に、
本当に誰も引き受けない“社会の穴”が生まれるのではないかという不安もある。
中間に立つ大人たちのしんどさ
今の大人たちは、「右へ倣え」が当たり前だった時代を生きてきた。
でも、その中で「みんなと同じじゃなくていい」と気づき始めた世代でもある。
空気を読んで、周囲に合わせながら、
同時に「自分の意思」も大切にしようとしてきた。
このふたつを同時に抱えている大人たちにとって、
今の子どもたちの“正しすぎる自己主張”は、時にまぶしく、時に戸惑いをくれる。
子どもたちに伝えたいこと
やりたくないことには、理由がある。
でも、やってみたからこそわかることも、確かにある。
すべてに「意味」や「納得」を求める必要はないけれど、
たまには「よくわからないけど、やってみる」ことが、
あとになって自分の世界を広げてくれるかもしれない。
そしてそれを、無理に押しつけず、でもそっと伝えていくのが、
今この“移行期”を生きる私たち大人の役目なのかもしれない。
|
🔗給食がもっと楽しくなる!家庭でできる練習5選|ジャムが開けられない子にできるサポートとは? – itti-blog
ホーム » やりたくないことはやらなくていい?――「選ぶ時代」を生きる子どもたちへ、大人が立ち止まって考えること
学校に行かない選択、でも「学び」は止めない
「学校に行かなくても、ちゃんと学べる場所がある」
それを知ってから、私も子どもも少しずつ前を向けるようになりました。
クラスジャパン小中学園は、全国対応のオンラインフリースクール。
出席扱いになる可能性があるから、今の学びが将来につながります。
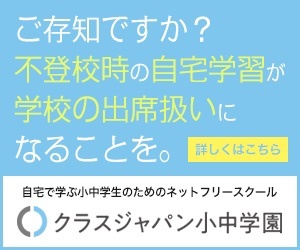
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3494c5.bd14c8e2.4a3494c6.37431968/?me_id=1421621&item_id=10000990&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fangelingg%2Fcabinet%2Fag-r-00141%2Fag-r-00141.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)