この記事の内容
お友達を描かないのは心配?「友達はいるのに、絵には出てこない」子どもの心理と親の関わり方
「幼稚園ではお友達と仲良く遊んでいるって聞くのに、家で描く絵はいつも自分一人。」
「たまに人を描いても、パパやママだけ。お友達を全く描かないのは、何か問題があるの?」
園では楽しそうなのに、画用紙の中は「ひとりぼっち」
参観日や持ち帰った作品袋を見て、ふと手が止まる瞬間。
周りの子の絵には、手を繋いだお友達や、みんなで遊んでいる様子が描かれているのに、わが子の絵は……。

- いつも「自分一人」だけ。
- 大好きな「動物」や「乗り物」ばかり。
- 登場するのは「家族」まで。
「もしかして、本当は園で馴染めていないの?」「お友達に興味がないのかな?」と、心の中で小さなアラートが鳴ってしまう親御さんの気持ち、本当によくわかります。
お子さんのことを大切に想っているからこそ、その「不在」が気になってしまうんですよね。
まず、最初にお伝えさせてください。
お友達を絵に描かないからといって、人間関係に問題があるとは限りません。むしろ、お子さんなりの「心の整理の仕方」や「今の発達段階」が、たまたまそういう形に見えているだけなんです。
今日は「描かない=問題」という思い込みを一度脱ぎ捨てて、お子さんの頭の中で起きている不思議で愛おしい世界を一緒にのぞいてみましょう。
「お友達を描かない」って、やっぱり変?
結論から言うと、全く変ではありません。むしろ、非常に「よくあること」です。
実はとてもよくあること
クラス全員を並べて描いたり、特定の親友を欠かさず描いたりする子のほうが、実は少数派。 多くの子どもにとって、絵は「今日あった出来事を正確に記録する日記」ではありません。その瞬間に「自分の心が一番動いたもの」を映し出す魔法の鏡なのです。

描かない=心が離れている、ではない
「一緒に遊んだはずなのに描かない」のは、薄情だからではありません。「遊び」は全身を使った動的な体験であり、「絵」は静止した内面的な表現。生活(外の世界)と表現(内の世界)は、必ずしも一対一でつながらないのが子どもの面白いところです。
子どもが「友達を描かない」主な理由
なぜ、あんなに楽しく遊んでいたお友達が、画用紙の上では姿を消してしまうのか。そこにはいくつかの「子どもなりの理由」があります。

① 人より「関係性」を描いていない
子どもにとって、お友達と遊ぶのは「楽しさ」という体感です。 「砂場で山を作った」という事実が一番楽しかった場合、描かれるのは「山」と「自分」。お友達は、その「楽しさという空気」の中に溶け込んでいて、わざわざ独立したパーツとして描く対象になっていないことがあります。
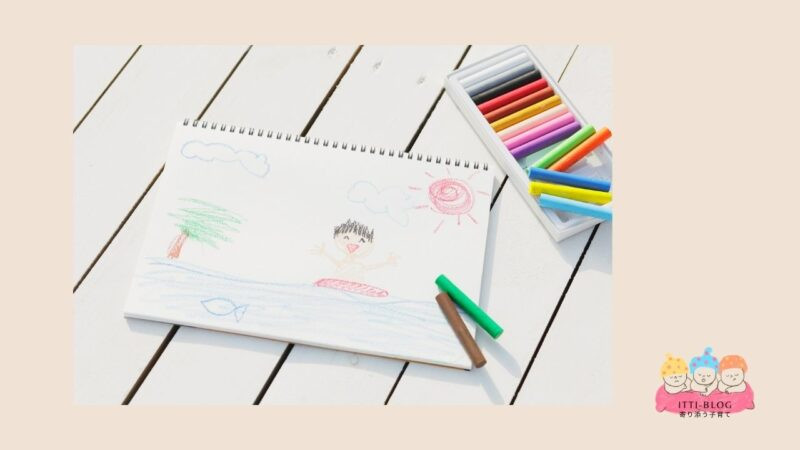
② 友達がまだ“流動的”な存在
特に未就学児の場合、人間関係はとてもフレキシブルです。 「今日はAちゃん、明日はBくん」。固定された「親友」という概念が育つ前の時期は、お友達は景色の一部のようなもの。特定の誰かを「描こう!」と思い立つほど、まだ対象が固定されていないだけかもしれません。
③ 人を描くのが単純に難しい
「人を描く」というのは、顔のパーツ、体、手足……と、実は工程が多くて大変な作業です。 「お友達を描きたいけど、5人も描くのは疲れちゃうな」「隣に描くと重なっちゃって難しいな」という、技術的なハードルで避けていることもよくあります。
④ 比べられるのがイヤ
「これ、だれ? 〇〇ちゃん?」と大人に聞かれるのが負担になる子もいます。 「違うのに……」と思っても、うまく説明できない。そんな誤解や詮索を避けるために、最初から「自分だけの世界」を完結させている慎重派さんもいます。
⑤ 世界の中心が“まだ自分”
発達段階として、世界を「自分中心」に捉える時期があります。 これはワガママではなく、「自己認識(自分という存在)」を一生懸命に確立しようとしている真っ最中だということ。自分が中心にドーンといる絵は、心が健やかに育っている証拠でもあるんです。
元教諭の視点|友達を描かない子の“心の内側”
多くの子どもたちを見てきて気づいた、ちょっと意外な「心の真実」をお話ししますね。
安心できる存在ほど、描かなくても大丈夫
意外かもしれませんが、子どもにとって「確認作業」が必要なものほど、絵に現れやすい傾向があります。 逆に、「あえて描かなくても、そこにいるのが当たり前」というほど安定した関係(仲の良い友達や、空気のような存在)は、あえて描かないこともあるんです。「描かなくても、心の中にちゃんといるから大丈夫」という安心感の裏返し。素敵だと思いませんか?
「描かない自由」を持てている
周りの子が描いているからといって、自分も描かなきゃ……と周りに合わせず、自分が今描きたいもの(恐竜や花やパパ)を貫けている。 これは、「自分の表現を自分で選べる」という、強い心が育っているサインでもあります。
親がやってしまいがちな心配の深読み
「うちの子、もしかして孤立してる……?」 一度そう思い始めると、ママやパパの脳内では勝手に「ぼっち会議」が開催されてしまいます。
- 「なんでお友達を描かないの?」と問い詰める
- 「嫌われてるの? 喧嘩したの?」と深読みする
- 「次はお友達も描いてみようね」と誘導する
これらはすべて、親御さんの「愛情」からくるもの。
でも、子どもにしてみれば「えっ、自由に描いちゃダメなの?」と戸惑う原因になります。心配のしすぎは、時に「表現の正解」を子どもに押し付けてしまうことにもなりかねません。くすっと笑って、「まあ、今は自分が主役の時期なのね」と受け流してあげましょう。
📒自己肯定感を育むための子どもとの接し方
📒自信を持てない子どもにかけるべき言葉とは?
今日からできる、親のちょうどいい関わり方
お絵描きの時間を、親子でもっと気楽に楽しむためのヒントです。

「誰描いたの?」は聞かなくていい
主語を「お友達」に持っていくのではなく、「お子さん」に戻してあげましょう。 「お友達はどこ?」ではなく、「〇〇ちゃんは、ここ(自分)を描くのを頑張ったんだね」「この色が好きなんだね」と、目の前の絵そのもの、描いている本人に光を当ててあげてください。
友達を描かせようとしない
「お友達を隣に描いたら賑やかだよ」というアドバイスも、今は封印。 描かない選択も、立派な表現です。お子さんの「今の世界観」をそのまま尊重してあげることが、将来的な自信に繋がります。
絵以外で“人との関係”を見る
どうしても心配なら、絵ではなく「生活」を見ましょう。
- 園の先生に、普段の様子をさらっと聞いてみる。
- 家で「今日、誰と遊んだの?」と聞いた時の表情を見る。
- 遊びの中で、お友達の名前が自然に出てくるか。 そこで楽しそうなら、画用紙に誰もいなくても、全く問題ありません。
それでも少し気になるときの見守りポイント
基本的には大丈夫ですが、「これだけはセットで見ておこう」という目安をお伝えします。
- 極端な変化が続いているか: 以前はよく友達を描いていたのに、ある日を境に一切描かなくなり、さらに元気がない。
- 絵以外での「困り感」: 登園を極端に嫌がる、表情がずっと暗い、などの変化が伴っている。
- 描こうとすると泣き出す: 「人を描く」ことに対して、強い拒否反応や恐怖心を見せる。
これらが当てはまらなければ、それは「今は自分(や家族、好きな物)を描くのが楽しい時期」なだけ。安心して見守っていてくださいね。📒子どもの絵からわかる不安のサイン
\ 友だちとの関係に悩む時期におすすめ /
気持ちをそっと整理できる絵本・書籍
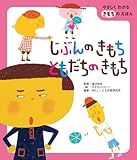
じぶんのきもち ともだちのきもち
(やさしくわかるきもちのえほん)
「相手の気持ちってどうやって想像するの?」を、
やさしいイラストと例えでわかりやすく描いた絵本です。
友だちとうまくいかない・距離を置きたい・思い通りにならずイライラする…。
そんな時に、「自分の気持ち」と「友だちの気持ち」を整理するきっかけになります。

小学生が身につけたい!
考えるチカラ 友だち関係のモヤモヤ
「仲良くしたいけどうまくいかない」
「距離感がむずかしい」「グループの中でしんどい」など、
小学生ならではの友だちトラブルを豊富な事例で解説。
「どうすれば少しラクになる?」を、
子どもの言葉でていねいに伝えてくれる一冊です。
- 友だちとのトラブルで落ち込むことが増えた
- 描く絵に、友だちが小さく登場しがち
- 距離を置きたい・近づきたい気持ちが揺れている
子どもの「友だちとの関係の悩み」にそっと寄り添い、
気持ちを言葉にするヒントをくれる本たちです。
まとめ:描かれなくても、ちゃんと育っている関係がある
いかがでしたか? 「お友達を描かない」という事実は、決して「友達がいない」という答えではありません。
絵は、お子さんの心の一部。すべてではありません。 お子さんにとって、今は自分を深掘りしたり、大好きな世界に没頭したりすることが、何より大切な心の栄養なんです。
親にできることは、その小さなアーティストの「今の世界」を、決めつけずに面白がってあげること。
締めの一文: たとえ画用紙に描かれなくても、お子さんの心の中には、ちゃんと育っている大切な関係があります。
その関係を信じて、今日も「いい絵が描けたね!」と笑ってあげてくださいね。あなたのその笑顔が、お子さんを一番安心させ、いつか「お友達」を描き始めるための、心の貯金になりますよ。

【あわせて読みたい専門記事】
いかがでしたか? 「うちの子も、恐竜しか描きません!」なんていう“あるある”があれば、ぜひコメントで教えてくださいね。焦らず、ゆっくり、わが子の個性を一緒に楽しんでいきましょう!
🔗発表会や参観日で自信がない子へ|自己肯定感を伸ばす教材ガイド
子どもの絵から気持ちを読み取ったり、日々の小さな変化に気づけるようになると、 「この子に合う学びの形ってなんだろう?」と考える機会も増えてきます。
そんなときに、無理なく“子どものペース”を大事にできる学び方として 私がよく耳にするのが スマイルゼミ です。 もちろん押しつけではなく、気になるご家庭だけの参考としてご紹介しますね。
まずは“わが家に合うか”を資料でチェック
スマイルゼミは、実際の教材イメージや学習の進み方がわかる 無料の資料請求ができます。 子どもの気質やペースに合うかどうか、落ち着いて比べられるので安心です。
- 子どもの興味を引きやすいポイントがわかる
- 学年別の教材サンプルをチェックできる
- 費用・サポート体制がすぐ理解できる
「ちょっと見てみたい」「比較材料がほしい」 そんな軽い気持ちでも大丈夫。資料なら気負わず確認できます。
あなたにおすすめの記事
ホーム » お友達を描かない子が伝えていること|子どもの絵にあらわれる本当の心理
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。








