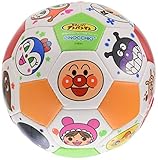最近「うちの子、やたらと物を投げるなぁ」と感じたことはありませんか?
おもちゃを手に持ったかと思えばポイッ、食事のスプーンもポイッ…。

拾っても拾ってもまた投げる姿に、「なんでわざとやるの?」「𠮟った方がいいの?」と戸惑う親御さんも多いものです。
実はこの「投げる」という行動、ほとんどの場合は赤ちゃんの自然な発達の一部。成長の階段を登る大切なプロセスなのです。
この記事の内容
1. 赤ちゃんが物を投げるのはいつから?発達の“正常範囲”を知ろう

赤ちゃんが「投げる」しぐさを見せ始めるのは、生後6ヶ月〜8ヶ月ごろが目安です。
この時期には手のひらを開いたり閉じたりする動きがスムーズになり、物をつかんで放すことができるようになります。
1歳前後で「投げる」が増える理由
赤ちゃんが1歳を過ぎたころから、やたら物を投げるようになった…という声、よく聞きます。
実はこれ、成長のごく自然な流れです。
腕や手の筋肉が発達してきて、ボールやおもちゃを「持つ」「離す」動きがスムーズにできるようになる時期なんですね。
つまり、“投げる”という動作ができるようになった=成長の証なんです。
赤ちゃんはまだ言葉で伝えられない分、「投げてみる」という動作を通して世界を知っていきます。
2.赤ちゃんにとって「投げる」は実験と学び
赤ちゃんは物を投げることで、「これを落としたらどうなるんだろう?」と観察しています。
音が鳴る、お母さんが振り向く、転がる——それぞれの結果を見て、頭の中では“原因と結果のつながり”を学んでいるのです。
言葉にできないけれど、心の中では小さな研究者のように試行錯誤をしています。
つまり「投げる=悪いこと」ではなく、「世界を確かめるための実験」なんですね。

- 「原因と結果」がわかるのが楽しい!
投げたら「音がする」「落ちる」「転がる」「ママが反応する」――
それを見て「自分が何かを起こした!」という体験をしているんです。
つまり、“世界を動かせた!”という小さな達成感。 - 「繰り返し」が脳を育てる
赤ちゃんは同じことを何度も繰り返すことで、
「こうしたらこうなる」という法則を少しずつ覚えています。
投げるたびに、脳の中では「原因→結果→記憶」の回路が強化されているんです。 - 大人の反応も“社会的なおもしろさ”
ママやパパが「わっ!」とか「だめだよ〜」と反応すると、
赤ちゃんにとってはそれも「投げたらママが動く!」という発見。
実は、人との関わりの第一歩にもなっているんですよ。 - 感覚の刺激が気持ちいい
物が手から離れる感覚、音、視覚の変化――
五感を通して感じる刺激そのものが心地よいのです。
何度も繰り返すのは「脳の発達」のサイン

「何回言ってもまた投げる…!」とイライラしてしまうこともありますよね。
でもそれは、赤ちゃんの脳がどんどん発達している証拠です。
脳の神経回路は、同じ行動を繰り返すことで強化されていきます。
投げて、音を聞いて、また投げて…という繰り返しは、記憶力や集中力を育てている大事な時間なんです。
3. “投げ期”はいつ終わる?落ち着く時期とサイン
投げる行動は、成長とともに必ず落ち着いていきます。とはいえ「いつになったら終わるの?」と気になる親御さんも多いですよね。目安となる時期と、その変化を見ていきましょう。
1歳半〜2歳がピーク
投げる行動は、だいたい1歳半〜2歳ごろがピークです。
この時期は「自分の思いどおりに動かしたい」という欲求が強まり、なんでも手当たり次第に投げることもあります。
しかし成長とともに、だんだんと「これはやっていい」「これはダメ」という区別がついてくるようになります。
徐々に「投げたい衝動」が落ち着く理由
2歳を過ぎるころから、ことばで伝える力や我慢する力が育っていきます。
そうなると、自然と“投げたい衝動”も落ち着いていきます。
つまり、「いまはまだ“投げたい時期”なんだ」と思って、長い目で見てあげることが大切です。
投げたい気持ちを満たすおすすめおもちゃ①
4. 投げる行動をやめさせるより、“導く”対応が大事

「発達の一部だとわかっていても、やっぱり困る!」――これが正直な親心ですよね。
床に転がるおもちゃを何度も拾うのは大変ですし、食事中にスプーンやご飯を投げられると、ついイライラしてしまうこともあります。
🔗自分で食べたいけどうまくいかない!スプーンを握る赤ちゃんに試したいサポート法
ここでは、成長を妨げずに安全に見守れる対応のポイントを紹介します。
① 大きく反応しすぎない
赤ちゃんが投げた時に「こら!」「ダメ!」と強く反応すると、それ自体が“楽しいイベント”になってしまうことがあります。
大人のリアクションを面白がって「もっと投げよう」と繰り返すことも少なくありません。
👉 ポイントは、落ち着いて短く伝えること。
「投げると危ないよ」「そっと置こうね」と、シンプルに声をかけるだけで十分です。
② 投げていい物・だめな物を分けて伝える
すべてを禁止するのではなく、「これは投げてもいい」「これはダメ」 を区別することで学びにつながります。

例えば、
- 柔らかいボールやぬいぐるみ → 投げてもOK
- スプーンや硬いおもちゃ → 投げると危ないからNG
赤ちゃんは繰り返しの中で少しずつ理解していきます。
③ 投げる欲求を“安全な遊び”に切り替える

「投げたい!」という気持ちを無理に抑える必要はありません。
むしろ、安全に投げられる環境を用意してあげる方が、赤ちゃんも満足しやすいです。
例:
- 柔らかいボールでキャッチボール
- 洗濯かごをゴールにしてポイ遊び
- お手玉や紙を丸めたボールを使う
「危ないからダメ」ではなく「ここなら楽しくできるよ」と示すことで、行動の置き換えができます。
投げたい気持ちを満たすおすすめおもちゃ②
④ 言葉が出てきたら“伝え方”をサポートする
1歳半〜2歳を過ぎると、「もっと!」「いや!」といった簡単な言葉で気持ちを表せるようになります。
この時期に「投げる」以外の表現をサポートすることで、行動も落ち着いていきます。

例:
- 投げそうになったら「もう一回って言ってみようね」
- 食事中に投げそうなときは「いらないときは“バイバイ”って言おうね」
感情を行動から言葉に切り替えていくのは、成長の大きなステップです。
⑤ 危険な場合はしっかり止める
もちろん、安全を守ることが最優先。
- 硬い物を人に向かって投げた
- 食器を投げて割れそうになった
こうした場合は「危ないからダメ」ときっぱり伝え、行動を止めましょう。
「命やケガに関わることは絶対にしてはいけない」という線引きは、小さなうちから繰り返し伝えてOKです。
💡 まとめると
- 強く𠮟るよりも落ち着いて対応
- 投げたい気持ちは安全な遊びで発散
- 成長に応じて“言葉”へ切り替えていく
- 危険な時は毅然とストップ
こうした関わりが、やがて「投げる」を卒業し、次の発達へつながっていきます。
🧩Q&Aコーナー

Q1:投げた物が人に当たったとき、叱るべき?
→ A:感情的に叱るより「危ないね」「当たると痛いね」と具体的に伝え、どうすれば安全かを一緒に考えるのが効果的です。
Q2:わざと投げて笑っている時は?
→ A:「反応が楽しい」段階なので、反応を減らし安全に切り替える環境づくりを。
Q3:発達障害のサインではない?
→ A:単発の投げ行動だけでは判断できません。言葉や視線、模倣など他の発達要素も総合的に見る必要があります。
💭投げ行動のチェックリスト
- □ 毎回同じ物を投げる
- □ 投げるたびにこちらを見て反応を確かめる
- □ 1歳半を過ぎても頻繁に投げ続ける
- □ 言葉が出てきても投げる行動が減らない
→ ✅2つ以上当てはまる場合:「遊び・発達・感情表現」のどれが原因かを見極めて対応を変えていきましょう。
まとめ:“投げる=悪い”ではない。親の安心を取り戻すポイント
叱るより「見守る」で伸びる
赤ちゃんが物を投げる姿は、
「困った行動」ではなく「成長の過程」そのものです。
叱るよりも、「今はこんなことが楽しいんだな」と見守ることで、
赤ちゃんは安心して新しい動作や感覚を身につけていきます。

「悪いこと」ではなく「発達の証」
物を投げる時期はずっと続くわけではありません。
やがて「どうすればいいか」を学び、次のステップへ進んでいきます。
今日も、赤ちゃんは自分なりに世界を学び中。
小さな“投げる手”の中には、大きな成長のエネルギーが詰まっています。
\こんな記事も読まれています/
📒0歳育児「やってよかった」TOP10|愛おしい今を残す方法も解説
📒赤ちゃんにおすすめの絵本15選|0歳から楽しめる
📒【0歳からの知育】おもちゃのサブスクで賢く遊ぶ!メリット&デメリット
📒100日祝い(百日記念)とは?赤ちゃんの“はじめての節目”を祝う、家族の物語と写真の残し方
「気持ちの切り替え」で困ったときに、こちらも参考にどうぞ:
- 子どもをスムーズに動かす方法
- なんでもイヤ!な時期の子どもの心理
- 着替えたくない!イヤイヤ期に着替えを嫌がる子どもへの対応法
- 育児書通りでも赤ちゃんが泣く理由
- 2歳児の謎行動にツッコミながら学ぶ!育児あるある&成長サポート集
🌼 学資保険、そろそろ…?
「学資保険そろそろかな…でもよくわからない…」
「調べても難しい…後回しになってる…」
忙しい毎日の中で、
“ちゃんとしてあげたい気持ち”があるほど迷ってしまうのが学資保険。
そんな悩みに寄り添うサービスがあります。
🌸 「ベビープラネット」はママの味方
妊娠〜子育て期に特化した保険の無料相談サービス。
「営業が強そう…」という心配はいりません。
ママのペースで、やさしく丁寧に説明してくれます。
- 20社以上の中から最適な学資保険を比較できる
- むずかしい仕組みも、わかりやすく噛み砕いて説明
「知らなかった不安」が
「これなら準備できる」の安心に変わる時間です。
🎁 相談後には “ちょっと嬉しいプレゼント” も
無料相談でもらえる、かわいいギフトが人気。
「相談してよかった」と思える小さなごほうびです。
✨岡山発・ママにうれしいおしゃれ育児アイテム
出産祝いに悩んでいる方へ。くすみカラーの落ち着いたデザインで、 おでかけでも自分らしさを楽しめるラインナップ。滑りにくく自分で食べやすい食器や、 人とは違うシリコン歯固めなど、忙しい育児をちょっと楽しくするアイテムが揃っています。
出産祝いに◎ 滑りにくい食器 個性的な歯固め くすみカラー
商品を見に行くホーム » 赤ちゃんが物を投げるのはなぜ?叱る前に知りたい“発達の意味”
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。