「いつもカラフルだった絵が、急に真っ黒に…」
「家族を描かなくなって心配になった」
実際にそんな声をよく聞きます。もしかして“心のSOS”かも?と不安になることもありますよね。でも、絵の変化は“心の成長のひとコマ”であることも多いのです。
この記事でわかること
- 絵の変化が示す子どもの本当の気持ち
- 発達段階別の絵の見方と安心のサイン
- 親ができる寄り添い方と声かけのヒント
この記事の内容
✅子どもの絵からわかる「心のサイン」—黒や構図に込められた意味とは
子どもがクレヨンをにぎって夢中に描く姿。
ぐるぐると線を走らせたり、真っ黒に塗りつぶしたり。大人から見ると「何を描いているんだろう?」と首をかしげることもありますよね。
でも、その“よくわからない絵”には、子どもなりの気持ちや発達のサインがたくさん隠れています。
| 描写の特徴 | 心理的サイン |
|---|---|
| 人物の大きさ | 安心・憧れ・注目の対象を表す |
| 人物の距離 | 心理的な親密さや関係性 |
| 描かれない人 | 意識が離れている・関係を整理中のことも |
| 表情 | 感情表出・安心や不安のバロメーター |

発達心理学では、子どもの絵は「自己表現」「情動調整」「社会的理解」という3つの発達領域を映すものとされています。
言葉で上手く伝えられない幼児期だからこそ、絵は心の中をのぞく“もうひとつの言葉”です。
✅ 心理学で見る「絵と発達の関係」
心理学者ローウェンフェルド(V. Lowenfeld)は、子どもの絵の発達を「なぐり描き期 → 前図式期 → 図式期 → 写実期」と段階的に整理しました。
つまり、子どもの絵は“心の成長の記録”でもあります。

たとえば、公園の滑り台を何度も描くのは「楽しかった体験をもう一度感じたい」という感情の再現。
家族の絵を描くのは、愛着や安心を確かめる行為でもあります。
子どもは絵を通して「私はこう感じた」「これが私の世界」と伝えているのです。
🌷 家族の「だいすき」を育む絵本
 あなたのことが だいすき(角川書店単行本)
あなたのことが だいすき(角川書店単行本)家族への「だいすき」を言葉にする時間にぴったり。
子どもが描く“ママ”“パパ”の気持ちを、
やさしい読み聞かせで育む絵本です。
✅ 年齢別:子どもの絵の特徴と心の発達
【1〜2歳ごろ:なぐり描き期】
この時期は、手や腕の動きを楽しむ段階。線を引くこと自体が喜びであり、「自分で動かせた!」という自己効力感を育てます。
紙いっぱいに力強く描く姿は、運動機能と情動表現の両方が育っている証拠です。
【3歳ごろ:前図式期】
円や点を使って“顔”らしきものを描くようになります。発達心理的には「自分」と「他者」を区別しはじめ、人への関心が芽生える時期です。
「これはママ」「これはぼく」と説明できるようになるのは、言葉とイメージがつながってきた証拠です。
【4歳ごろ:図式期のはじまり】
「家族で食事」「お友達と遊ぶ」など、簡単なストーリー性のある絵が増えます。
これは、自分の経験を再構成しながら「人との関わり方」を理解しようとしている段階です。

【5〜6歳ごろ:図式期】
登場人物の大きさ・位置・色づかいに、感情や関係性が表れます。
心理学的には「自己概念(自分はこういう人)」を築く時期で、絵を通して“自分と世界のつながり”を整理しています。
【7歳以降:写実期】
観察力が高まり、現実に近い表現が増えます。友達の絵と自分の絵を比べるようになり、社会的比較も始まります。
この頃に「うまく描けない」と感じると自信を失いやすいため、周囲の大人が「表現する楽しさ」を守ってあげることが大切です。

✅ 子どもの絵に出る色の意味|黒・赤・青の心理とは?
色は感情を映す鏡です。色彩心理学では、子どもが選ぶ色はそのときの気分や情動と深く結びついていると考えられます。

赤:活力・自己主張・「見てほしい」気持ち
青:落ち着き・安心感・少しの寂しさ
黄:好奇心・明るさ・ときに不安定な感情
緑:安定・調和・安心
紫:感受性の高さ・繊細さ・心のゆらぎ
黒:強い感情・気持ちの整理・コントロールしたい思い
ピンク:愛情・優しさ・安心
オレンジ:社交性・楽しさ
白(余白):落ち着き・安心・境界の意識
同じ色でも、描くタイミングや体験によって意味は変わります。
「どうしてこの色にしたの?」と優しく聞くだけで、心の中の小さな声が聞こえてくることがあります。たとえ今“黒い絵”を描いていても、それは心の整理の途中。成長のプロセスの一部です。
✅ 家族の絵に出る“心の距離”とは?—安心と不安を見分けるヒント
発達心理学では、家族の絵は「愛着(アタッチメント)」の状態を読み取る手がかりになります。
誰をどの位置・大きさ・表情で描くかに、子どもが感じる“心の安全基地”が反映されるのです。

・誰が大きく描かれているか → 安心・憧れ・注目の対象
・誰が描かれていないか → 心理的な距離を感じていることも
・誰と誰が近くにいるか → 仲良し・信頼関係の象徴
とはいえ、「お父さんが小さい」「お母さんが真ん中」といった描写がすぐに不安のサインとは限りません。
「どうしてこう描いたの?」と聞くと、「お父さんはお仕事中」「お母さんが好きだから」など、純粋な理由が多いものです。
大切なのは“正解を探すこと”ではなく、“会話を楽しむこと”です。
📚 発達心理をやさしく学びたい方におすすめ
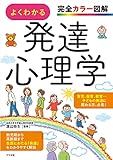 完全カラー図解 よくわかる発達心理学
完全カラー図解 よくわかる発達心理学絵の読み取りや発達段階を深めたい方に最適。
イラストと図解で基礎がしっかり理解できます。
子どもの心理を学びたい保護者や教育関係者にもおすすめです。
✅ 心配しすぎないでOK!親ができる3つの寄り添い方
- 「上手だね」より「ここが好き!」
→ 評価より共感を伝えると、表現の意欲が育ちます。 - 「これなに?」より「どんな気持ちで描いたの?」
→ 正解を求めず、感情に寄り添う言葉かけを。 - 絵を“作品”として扱う
→ 壁に飾る・ファイルにまとめる・写真で残すなど、「自分の表現が認められた」と感じる体験が自己肯定感を育てます。
絵を通して育つ「創造力」と「自己肯定感」
お絵かきは、心を整理し、想像力を広げる時間です。
親が一緒に描くことで「共感的関係(empathic relation)」が生まれ、安心感や信頼関係を強めます。
上手に描く必要はありません。「一緒に描く」「一緒に笑う」——その体験が、子どもの心を育てます。
作品の保存・飾り方のアイデア
・壁に飾ってローテーション(週ごと・月ごとに入れ替え)
・スマホで撮ってクラウドやアルバムにまとめる
・フォトブックにして家族で見返す
こうした「飾る」「残す」行為は、心理学的に“承認の可視化”と呼ばれます。
「自分の表現は価値がある」と感じることが、子どもの心を支える力になります。
📸 その場で印刷して飾れるミニプリンター
 Canon スマホプリンター iNSPiC PV-123-SP(ピンク)
Canon スマホプリンター iNSPiC PV-123-SP(ピンク)スマホで撮った写真をその場で印刷。
小さなサイズで飾れるから、子どもの喜びも倍増!
シールタイプの用紙にも対応しています。
✅ 注意サイン:専門家に相談したほうがいい絵とは?
多くの変化は自然な発達過程ですが、次のような場合は専門家に相談してみましょう。
・暴力的・自己否定的な絵を繰り返す
・急に絵の内容が変わる、または描かなくなる
・説明できず、極端に無表情な絵が続く
小児科・臨床心理士・保育士などに早めに相談することで、家庭での関わり方のヒントが見えてきます。
よくある質問(Q&A)
Q:「黒い絵を描くのは不安のサインですか?」
A:必ずしもそうではありません。黒は「強い感情」や「集中」を表すこともあります。描く状況や言葉のやりとりを合わせて見てみましょう。
Q:「家族を描かないと愛情がない?」
A:いいえ。今関心のあるテーマ(友達・動物・乗り物)に夢中なだけということも多いです。
子どもの絵を見るときのチェックポイント
- 描くときの表情や口ぐせを観察している?
- 色の変化に気づいている?
- 誰をどんな位置に描いている?
- 本人に「どうしてこの絵?」と聞いてみた?
まとめ — 絵は「もうひとつの言葉」
子どもの絵は、心を映す鏡であり、言葉よりも正直な“もうひとつの会話”です。
そこには「うれしい」「かなしい」「だいすき」「がんばった」という、日々の小さな感情が詰まっています。
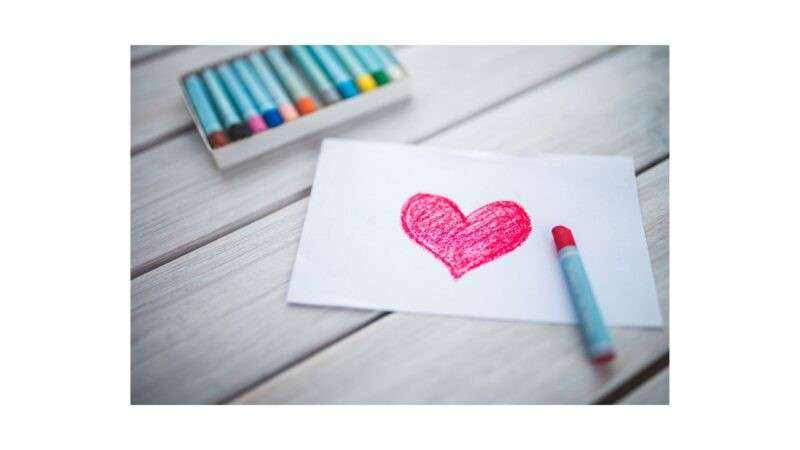
発達心理学の視点から見ても、「どんな気持ちで描いたの?」と寄り添うことが、心の成長を支える最良のサポート。
今日描いた一枚が、10年後に家族の宝物になるかもしれません。
「この絵、すごくいいね」「描いてくれてありがとう」と、あたたかい言葉を添えてあげてくださいね。
関連記事
👉 絵の変化でわかる“心の成長サイン”まとめ
👉 家族の絵に出る“本音”の見方を心理学で解説
忙しい家庭でも続けやすい“表現力が育つ教材”を知りたい方へ
→ 子どもの表現力を育てる通信教育5選
ホーム » 子どもの絵の変化には理由がある。発達心理で読み解く“心の整理”
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
\こんな記事も読まれています/
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。








