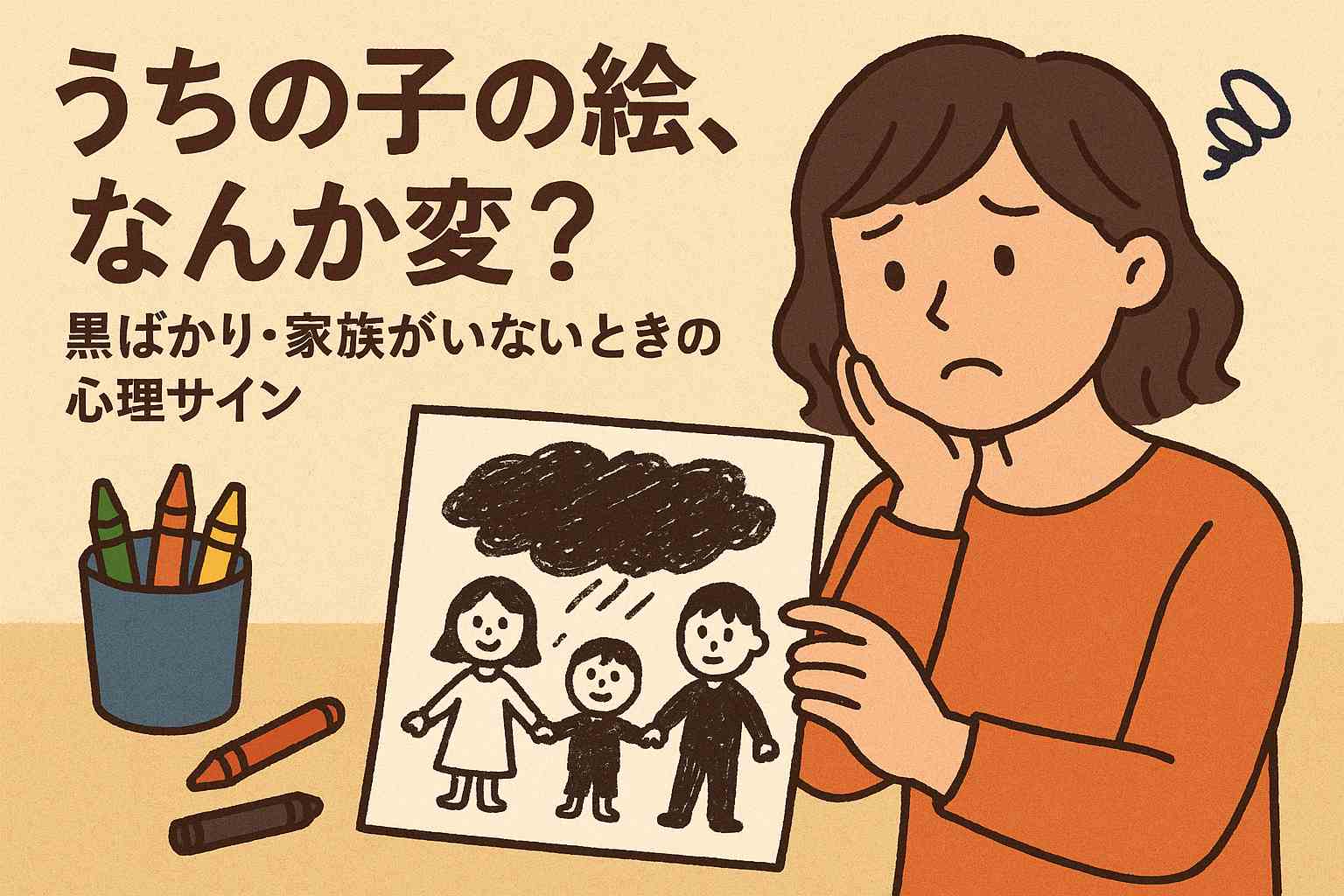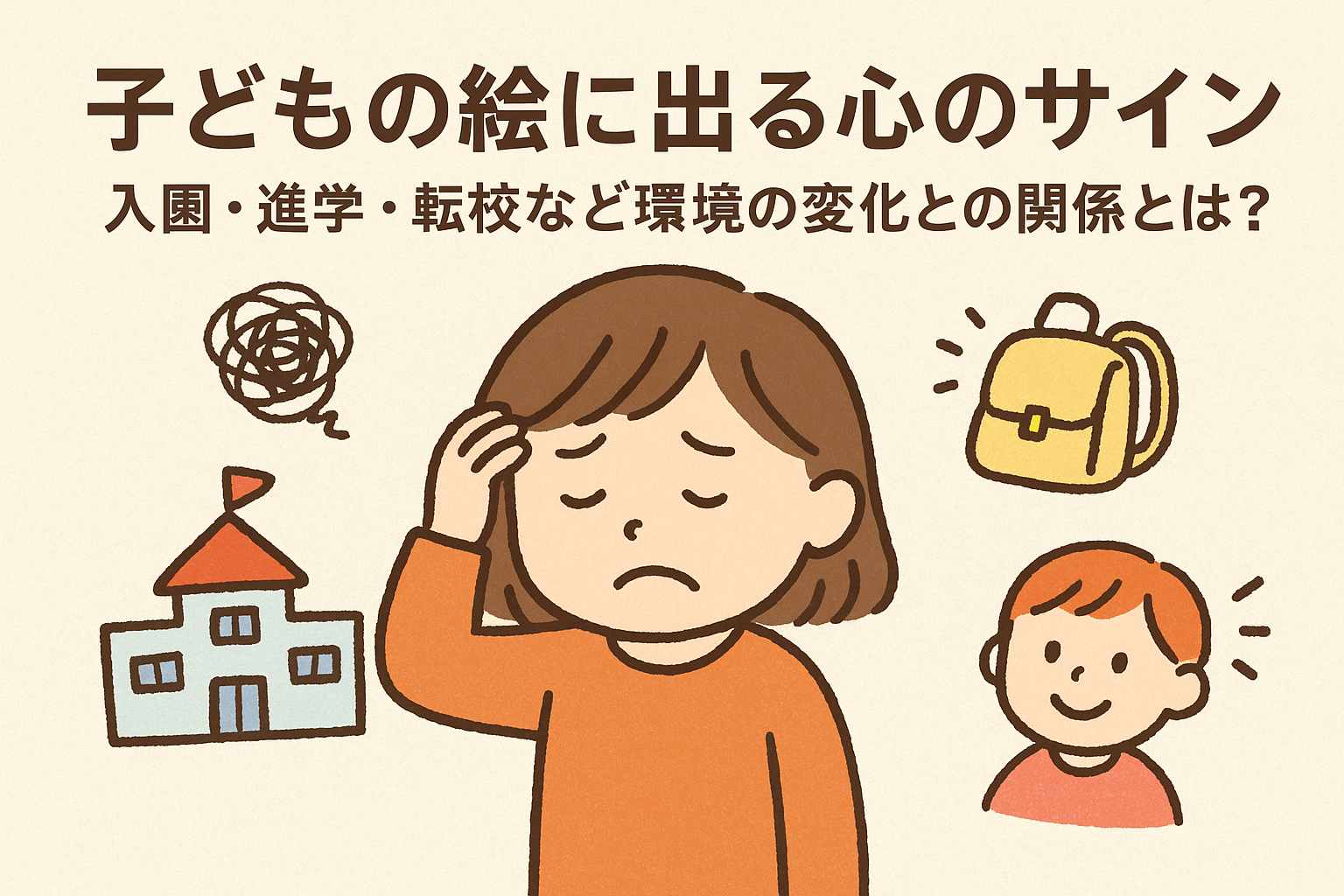この記事の内容
「親がどこまで手伝えばいいの?」と悩んでいませんか?
うちもそうでした。夏の絵の宿題って、放っておけないけど、全部やるのも違う…。そんな親の“葛藤”をほどくヒントをまとめました。
親も子もつらい…夏休みの“絵の宿題ストレス”を減らすには?
「失敗した…もうやる気なくなった」
「下書きはよかったのに、本番がイマイチ…」
「テーマがぼやっとしてて、何が言いたいのかわからない」
——そんな経験、ありませんか?
夏の宿題のポスターや標語の絵って、自由なようでけっこう難しいんですよね。
そして何より、親のサポートが思った以上に必要になる…!
うちの子も、構図や色使いは少しずつ上達してきたけれど、
やっぱり“ひとりで完走する”のはまだ難しい。
今回は、わが家で実践している「夏の絵の宿題サポート術」をご紹介します。
子どもの“伝えたい気持ち”を引き出す質問のコツ
うちでは、まずこう聞きます。
「どんなポスターにする?」ではなく
「何を言いたい?」って。
たとえば子どもが言ったのはこんなこと:
「自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶってほしい!」
この一言でテーマが決まります。
あとは「それを伝える絵って、どんな感じがいいかな?」と話し合いながら、絵の方向性を固めていきます。
🔗白い絵(描き込みが少ない絵)から読み取れる子どもの心の整理
いらない紙に下書き → 情報整理
いきなり画用紙に描くのはNG。
まずはコピー用紙やチラシの裏にラフスケッチを描かせます。
- ヘルメットは何色?
- 人は何人描く?
- 空いてる場所に文字やマークを入れる?
など、必要な要素をメモ感覚で書き込んでおくと、構図がしっかりしてきます。
絵が小さい子にどう声をかける?“構図の感覚”を育てる練習法
子どもが本番用紙に描くとき、よくあるのが…
「なんか絵が小さい…」問題。
気づいたら真ん中にポツンとキャラクターがいて、余白だらけ。
これって、子どもにとって「大きく描く」ことがかなり難しい証拠なんです。
うちでは、本番用紙の大きさを目で確認させながら、
別の紙に「もっと大きく」描く練習をさせます。
これだけで、最終的な仕上がりがグッと良くなります!
色ぬりは「丁寧に」「薄い色から」
色ぬりにも声かけが必要です。
ポイントは:
- 薄い色から塗る(例:空→服→小物など)
- ベタ塗りしない、ムラが出ないように丁寧に
- 色鉛筆なら同じ方向にぬるときれいに見えるよ、などちょっとしたコツを伝える

特に背景色(空など)は、子どもにとって「つまらない作業」になりがち。
そんなときは、親が横で一緒に空を塗ってあげることもあります。

絵本作家えがしらみちこの はじめての小さな水彩イラスト
やさしい水彩表現が学べて、子どもの絵の宿題サポートにも役立つ一冊。水彩表現の基本や、小さな作品づくりのコツが「親が教えやすい形」でまとまっています。
▶️ Amazonで詳しく見るわからないところは「ネットで画像検索」!
子どもが「この花ってどんな葉っぱ?」「茎の色って何色?」と悩んでいるとき、
うちでは一緒にネットで画像検索します。
たとえば「ひまわり」の場合。
- 花びらの黄色はどんな明るさ?
- 茎や葉の緑はどれくらい濃い?
- 茎には毛がある?
- 葉っぱの形や、影のつき方は?
細かいところに気づくと、絵にもリアリティが出てきます。
また、見たままを塗るのではなく、
「この色を出すには、何色と何色を混ぜたらいい?」
ということを一緒に考えるのも◎
実際にパレットで色を試してみて、
「この緑は、黄色多めの黄緑にちょっとだけ青を足すと近いね!」と発見しながら進めると、
子どもの“描く目”がどんどん育ちます。
🔗【夏休み絵日記】描けない・塗れないのはなぜ?“空白”と“黒”に見える子どもの心 – itti-blog
うまく描けなくても大丈夫。“伝わる絵”を育てる親の関わり方
つい手を出したくなってしまうけれど、
本当に大事なのは「自分の絵で、自分の思いを伝えること」。
多少色がはみ出しても、背景にムラがあっても、
テーマが伝わる絵なら、それはもう立派な作品。
🔗小3ごろの絵ににじむ“人間関係”とその微妙な距離感 – itti-blog
🗨 よくある質問Q&A
- Q. 子どもが全然描きたがりません…どうしたら?
A. 無理に描かせず「どんなことを伝えたい?」と気持ちを言葉にするところから始めてOKです。 - Q. 親がどこまで手伝っていいの?
A. 「描く」手伝いではなく「考えを整理するサポート」なら◎。構図や色は子どもに任せましょう。 - Q. テーマが決まらないときは?
A. 「最近うれしかったこと」「守ってほしいこと」など、生活の中からキーワードを拾うと決まりやすいです。
🎨 親のサポートチェックリスト
- □ 子どもの「伝えたい気持ち」を聞けた
- □ 下書き段階で構図の確認をした
- □ 色塗りの声かけができた
- □ 本人が「できた!」と感じて終えられた

Shuttle Art 水彩絵の具 36色セット(チューブ)
混色や発色が良く、ポスターや夏休みの絵の宿題で色を試すのに便利。大容量のチューブで家での練習にも最適です。初心者〜上級者まで使えます。
▶️ Amazonで詳しく見るまとめ:親が“助けすぎず、見捨てず”の絶妙サポートを
夏のポスター宿題って、
子どもにとっても、親にとっても“試練”のようなもの。
でも、以下のステップを意識するだけで
完成度も、子どもの達成感も大きく変わります。
✅わが家のサポートステップまとめ
- テーマは「何を伝えたい?」から決める
- いらない紙で構図をざっくり描く
- 画用紙に描く前に「もっと大きく」練習
- 色塗りは薄い色から、丁寧に
- わからないモチーフをわからないままにしない
最後に一言だけ。
完璧な作品じゃなくていい。
子どもが「自分の言葉で、自分の絵を描けた」ことに拍手を。
親子で一緒にがんばった夏の思い出、きっと大切な宝物になりますよ◎
🧩 この記事とあわせて読みたい
- ▶️ 子ども同士のケンカやトラブル…どう関わる?
- ▶️ 「なんでこの絵、ひとりぼっち?」絵にお友達がいない理由
- ▶️ “いい子”すぎるわが子が心配…その理由と声のかけ方
- ▶️ 引っ越し・入園・転校…子どもの絵に出る“変化のサイン”
ホーム » やる気が出ない・描けない子に効く!夏休みの絵の宿題サポート術
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。