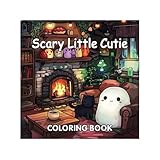※この記事は「子どもの絵に出てくるモチーフ全体の意味」をまとめた
親記事の一部です。
→ 子どもの絵に出てくるモチーフ一覧はこちら
「最近、うちの子、またおばけ描いてる…」
「怪獣が火を吹いてる絵ばっかり!大丈夫かな?」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
黒や赤を多く使ったり、牙やツノがついていたりすると、
つい「怖い」「不安」「何かストレスがあるのでは?」と心配になるものです。
でも実は――
おばけや怪獣の絵には、子どもの心の中の“大切な動き”が隠れています。
それは、
・怖さと向き合おうとする勇気
・強さへのあこがれ
・想像の世界がどんどん広がっている証
など、成長のサインでもあるんです。
このページでは、
「なぜそんな絵を描くのか」
「そればかり描くときはどう受け止めたらいいのか」
「ストレス?教育的に悪い?」などの疑問に、
ひとつずつ丁寧にお答えしていきます。
この記事の内容
- 第1章|【心理分析】子どもがおばけや怪獣を描く3つの理由
- 同じ怖い絵を繰り返し描くのは危険?安心の見極め方
- 怖い絵=ストレス?絵からわかる“注意サイン”
- 「教育的に良くない?」と感じるとき
- 子どもの怖い絵を否定しない関わり方・声かけ例
- 【タイプ別診断】怖い絵を描く子どもの心理傾向
- おばけや怪獣を描く“時期”はいつまで?
- 親が不安になる理由と、安心して見守るための考え方
- 「そろそろやめさせた方がいい?」と思ったとき
- 見守りながらできる関わり方
- まとめ:おばけや怪獣の絵は「成長の証」
- 絵の中の「色」と「表情」に見えるヒント
- 表情・構図にも注目してみよう
- 子どもがよく描く怖いものランキング
- 本当に注意が必要なのはこんなとき
- 親が安心できる“見守りのコツ”
- 🧠 Q&A|「怖い絵」に込められた心理を解説
- 🔍 チェックリスト|見守り方と安心のサイン
- 🌿 まとめ|怖い絵を描く子への見守り方と対処法
- こんな記事もおすすめ👇
第1章|【心理分析】子どもがおばけや怪獣を描く3つの理由

子どもが怖いものを描く理由は、ひとつではありません。
でも根底にあるのはいつも、「怖いものを理解したい」「自分の力で扱いたい」という気持ちです。
1. 「怖いけど気になる!」 ― 好奇心のあらわれ
子どもにとって“怖いもの”は、禁断の世界。
怖いけれど、どうしても気になってしまう対象なんです。

おばけ、怪獣、ドラゴン、ゾンビ…。
絵に描くことで、子どもはその“未知の存在”と少しずつ距離を縮めようとしています。
つまり、「怖いものを描く」という行動は、
怖さに支配されるのではなく、自分の手の中で扱う練習なんです。
2. 想像の世界が広がる発達のステップ
4~6歳ごろになると、子どもの頭の中では「現実」と「空想」の境界がゆるやかになります。
まるで心の中に映画館ができたように、次々と物語やキャラクターが浮かんでくるのです。

この時期の子が描くおばけや怪獣は、
怖さよりも「面白い!」「強い!」という感情から生まれていることも多くあります。
「ぼくの怪獣は100本の牙がある!」
「このおばけは人を助けるんだよ!」
そんなふうに、怖い存在を“自分流”に作り変えることで、
子どもは世界を理解し、自分の力を感じています。
3. 不安やストレスを整理する方法として
一方で、怖い絵を描くことが心の整理につながっているケースもあります。
子どもはまだ、言葉で自分の気持ちをうまく伝えられません。
「怖かった」「びっくりした」「怒られた」などの体験を、
言葉の代わりに“絵”で表現していることがあるのです。
たとえば、
・テレビで見た怖い場面
・幼稚園で感じた緊張
・叱られたあとにモヤモヤした気持ち
こうした体験が、おばけや怪獣の姿になって出てくることも。
でもそれは、“悪いサイン”ではなく、心を回復させるための自然な行動です。
同じ怖い絵を繰り返し描くのは危険?安心の見極め方
「このところ、おばけの絵ばかり描いてる」
「前も怪獣だったのに、また同じような絵を描いてる…」
そんなとき、親としては少し心配になりますよね。
でも、同じモチーフを繰り返し描くのは、子どもが“心の中のテーマ”を整理している証拠でもあります。
子どもは「怖い」「強い」「不思議」といった気持ちを、まだ言葉でうまく説明できません。
その代わりに、何度も何度も絵を通して“確認”しているのです。
たとえば──
- 🦖 怪獣を繰り返し描く子は、「強さ」や「支配」「守る力」などに憧れを抱いていることが多い。
- 👻 おばけを繰り返し描く子は、「怖いものを自分の手で描く」ことで恐怖をコントロールしようとしている場合があります。
つまり、おばけや怪獣は“自分の中の怖さを見える形にした安心の象徴”なのです。
怖い絵=ストレス?絵からわかる“注意サイン”
もちろん、絵の中に“ストレスのサイン”が隠れていることもあります。
ただ、それは「おばけを描く=ストレス」とは限りません。
絵全体の雰囲気や、描くときの様子にも注目してみましょう。

✅ 気をつけたいサインの例
- 表情が暗く、話しかけても反応がない
- 黒や赤だけでぐるぐると塗りつぶすことが多い
- 「怖い」「怒ってる」「倒す」といった言葉を繰り返す
- 絵の内容が暴力的で、本人が楽しそうではない
こうした場合は、少し疲れていたり、園や家庭での緊張がたまっているのかもしれません。
まずは「何かあったの?」と聞くよりも、「今日はどんなおばけかな?」と穏やかに関心を向けることが大切です。
絵を通して“安全に発散している”なら、実はとても健全なことなのです。
「教育的に良くない?」と感じるとき
「怖いものばかり描くなんて、ちょっと不安」
「おばけの絵って、悪影響じゃない?」
そんなふうに感じるのは自然なことです。
でも、子どもにとってのおばけや怪獣は「悪」ではなく、“自分を守る力”の象徴なのです。
心理学的には、これは“投影(とうえい)”と呼ばれる現象。
子どもは自分の中の不安や怒りを、絵の中の存在に投影して外に出すことで、心を整理しています。
つまり、
おばけを描く → 怖い気持ちを出す → 安心する
という、とても自然な心のリズムが働いているのです。
子どもの怖い絵を否定しない関わり方・声かけ例
絵の内容に驚いたり、少し怖く感じることもあるかもしれません。
でも、そこで「そんな絵はやめなさい」「怖いの描かないで」と止めてしまうと、
子どもの“心の出口”をふさいでしまうことになります。
代わりにこんな声かけがおすすめです。
🌱 やさしい声かけの例
- 「このおばけ、どんな性格してるの?」
- 「こわそうだけど、ちょっとかわいいね」
- 「今日はどんなところにいるのかな?」
このように、絵を否定せず、興味を持って聞くことで、
子どもは“怖い”気持ちを言葉に変える練習ができます。
【タイプ別診断】怖い絵を描く子どもの心理傾向
心理的には、以下のような傾向が見られることが多いです。
| タイプ | 特徴 | 心のテーマ |
|---|---|---|
| 想像力豊かなタイプ | ストーリーを作って描く | 自分の世界を広げたい |
| 敏感で繊細なタイプ | 音や表情に敏感、怖がり | 恐怖との折り合いを学びたい |
| 負けず嫌い・がんばり屋タイプ | 戦いのシーンが多い | 強さや正義への憧れ |
どれも「成長の途中」に見られる健全な心の働きです。
怖いモチーフを描くこと自体を、“悪いこと”と決めつけないようにしましょう。
おばけや怪獣を描く“時期”はいつまで?

多くの子どもが「おばけ期」「怪獣期」を迎えるのは、3歳〜6歳ごろ。
ちょうど“空想の世界”が豊かになり、現実と想像の境があいまいになる時期です。
この時期は、「怖い」「強い」「不思議」「正義」など、
心の中で新しい感情が次々と生まれては消えるタイミング。
おばけや怪獣は、そうした“見えない気持ち”を形にするための
心のキャンバスなんです。
年齢ごとの特徴イメージ
| 年齢 | よく描くモチーフ | 心のテーマ |
|---|---|---|
| 3歳ごろ | 顔だけのおばけ、丸い怪獣 | 「怖い」への興味が芽生える |
| 4〜5歳 | 戦うおばけ・ヒーローと怪獣 | 「強さ」「勇気」を学ぶ時期 |
| 6歳前後 | ストーリー性のある怪獣絵 | 善悪・感情の整理を始める |
つまり、「また怪獣か〜」と思っても、
その繰り返しの中に“心の成長”があるのです。
親が不安になる理由と、安心して見守るための考え方

「おばけばっかり描いて…大丈夫かな?」
「そんな怖い絵を描かせておいていいのかな?」
こんなふうに感じる親御さんはとても多いです。
実は、その不安の根底には──
『子どもの心がネガティブな方向に傾いているのでは?』
という“守りたい”気持ちがあるんです。
でも心理学的には、怖いものを描ける=心が安心しているサインです。
怖さを絵にできるということは、
それを受け止められるだけの“内的な安全基地”があるということ。
むしろ、怖いことを避けすぎて何も描けない子のほうが、心の抑圧が強い場合もあります。
「そろそろやめさせた方がいい?」と思ったとき
園や家庭で「怖い絵ばかり描くからやめさせよう」と言われることもあるかもしれません。
でも、無理にやめさせるのはおすすめしません。
それは、心の中で“整理しきれていないテーマ”が残ったままになるからです。
一度止めると、別の形(夜泣き・反抗・不安)で出てくることもあります。
☘️ 自然に卒業するタイミングは…
多くの子は、
「怖いけど勝てた!」「守れた!」という達成感の絵を描けた頃に、
自然とおばけや怪獣の絵を卒業していきます。
つまり、“怖い→強くなる→安心する”というプロセスを描ききったとき、
おばけは心の中で“役目を終える”のです。
見守りながらできる関わり方
もし「怖い絵」に少し抵抗があるときは、
次のような“やわらかい提案”をしてみるのもおすすめです。

- 「今日はおばけの家族を描いてみる?」
- 「怪獣がお散歩してるところも見てみたいな」
- 「このおばけ、何が好きなんだろう?」
こうした声かけで、
“怖い存在”が少しずつ“親しみあるキャラクター”へと変化していきます。
絵の世界の中で、子どもは「怖い」を「楽しい」に変える練習をしているのです。
まとめ:おばけや怪獣の絵は「成長の証」
おばけや怪獣を描くのは、
心が不安だからではなく、
“怖さと向き合える力”が育っている証拠。
それは、感情を理解し、整理し、乗り越える力を育む大切な時間。
絵を通して、子どもは少しずつ「自分の心の地図」を描いているのです。
絵の中の「色」と「表情」に見えるヒント

おばけや怪獣の絵は、見た目のインパクトが強いですよね。
でも、大切なのは“どんな気持ちで描いているか”。
その手がかりは「色」と「表情」に隠れています。
🔗子どもの絵に出る「色の心理」|赤・青・黒…どんな気持ちが隠れてる?
🎨 色づかいのヒント
| 色 | 心理的な傾向 | 見守りのポイント |
|---|---|---|
| 黒・赤を多く使う | 怒り・恐怖・緊張の発散 | 強く塗りつぶしていても止めないで。出せていること自体が安心。 |
| 青・紫など寒色系 | 静かに整理したい・落ち着きたい | 少し疲れ気味かも。スキンシップや休息を多めに。 |
| カラフル・多色使い | 想像力が豊か・怖さを遊びに変換中 | 楽しみながら描けていれば心は安定中。 |
色には「良い・悪い」はありません。
そのときの心の温度を映しているだけ。
毎回同じ色ばかりでなければ、心のバランスは自然に戻っていきます。
表情・構図にも注目してみよう
おばけや怪獣の顔が「怒っている」だけでなく、「笑っている」「泣いている」こともあります。
それは、子どもが“怖さを自分なりに和らげようとしている”サイン。
🔗子どもの絵から読み解く心理学|色・構図・表情・順番に隠れた心
たとえば──
- 🧟♂️ こわい顔でも、周りにお友達や家族が描かれている → 「怖いけど安心」
- 👾 倒されたり逃げたりしている → 「怖さを乗り越える練習中」
- 👻 泣いている・笑っている → 「怖い存在」にも“感情”を見つけ始めている
描くうちに、おばけが“敵”から“キャラ”へと変化していくのは、
まさに心の成長のプロセスです。
子どもがよく描く怖いものランキング
| 順位 | 怖いもの | 心理的背景 |
|---|---|---|
| 1位 | おばけ | 見えないものへの恐怖と興味。空想力が育ってきた証でもあります。 |
| 2位 | 雷・暗闇 | 音や暗さへの敏感さ。安全を確認したいという気持ちの表れ。 |
| 3位 | 怪獣・モンスター | 強い存在に憧れる反面、自分の中の力をコントロールしたい心理。 |
| 4位 | 鬼 | 「悪いことをしたら怒られる」などのしつけの影響が残っている場合も。 |
| 5位 | ゾンビ・骸骨 | 命や死に関する興味。絵を通して「生きること」を理解しようとしていることも。 |
ポイント:怖いモチーフは、必ずしも「不安のサイン」ではありません。 成長とともに「怖さ」→「面白さ」「強さ」へと変化していきます👦👧
本当に注意が必要なのはこんなとき
滅多にありませんが、以下のような状態が続く場合は、
心のエネルギーが少し疲れているサインかもしれません。
- 表情のない人物ばかり描く
- 黒や赤で塗りつぶす絵が長く続く(1〜2週間以上)
- 絵を描くときに泣いたり怒ったりする
- 「こわい」「やだ」などの言葉が増えた
そのときは、「描かないようにする」ではなく「話を聞く」が大切です。
園や先生に相談したり、家庭でゆったり過ごす時間を増やしてあげるだけでも、
子どもの心は自然に整っていきます。
親が安心できる“見守りのコツ”
おばけや怪獣の絵を見て不安になったとき、
思い出してほしいのはたったひとつ。
🎨「描けている」ということは、もう“怖さを外に出せている”ということ。
その絵は、子どもが自分で心を回復させている途中のサインなんです。
🔗「絵が小さくて心配…」そんなときに知っておきたい子どもの気持ち
🌼 親にできること
- 絵を否定せず、物語を一緒に楽しむ
- 「どんなおばけ?」と話しかけるだけで安心感が生まれる
- 絵を飾ってあげる(“受け止めてもらえた”というメッセージになる)
- 無理に上手く描かせようとしない
おばけの絵の向こうには、
“怖いけれど立ち向かいたい”という、子どもの健気な勇気があります。
それをそっと受け止めてあげることが、何よりのサポートです。
🧠 Q&A|「怖い絵」に込められた心理を解説
Q:「おばけばかり描くのはストレスですか?」
A:いいえ。多くの場合、怖さと向き合う練習です。
子どもの絵の心理には、「怖いものと距離をとりたい」「心の中を整理したい」という意味があります。
心が安定しているからこそ、安全に“怖い絵”を表現できます。
Q:「教育的に悪影響はありませんか?」
A:表現力や自己理解を深めるチャンスです。
子どもの絵は心理の鏡。怖い絵には意味があり、「心の整理」や「不安の解放」というプロセスが隠れています。
否定せず、“絵を通したコミュニケーション”の入口として受け止めましょう。
Q:「いつまで続くの?」
A:3〜6歳ごろの発達段階では自然な過程です。
成長とともに世界の見え方が変化し、やがて“怖い絵”から別のテーマへと移っていきます。
もし長期間、同じ怖いテーマが続く場合は、生活環境やストレス要因をやさしく見直してみましょう。
🔍 チェックリスト|見守り方と安心のサイン
🧠 こんなときは安心して見守ってOK
- 絵を描くこと自体を楽しんでいる
- 「怖いけどね」と笑顔で説明してくれる
- 絵にストーリーや登場人物がある(心の発達が見える)
- 怖い絵のほかにも、日常の絵やカラフルな絵を描く
⚠️ 少し気をつけたいサイン
- 黒や赤で塗りつぶす絵ばかりが続く
- 絵の中の人の表情が暗い・説明したがらない
- 暴力的・破壊的なモチーフを繰り返す
- 長期間、同じ怖いテーマに固執している
こうした違いは、子どもの絵の心理を見極めるうえで大切なヒントになります。
絵の中には、子どもの絵に込められたストレスや、心の発達の段階が丁寧に表れます。
無理に直そうとせず、安心できる関わり方を続けましょう。
🌿 まとめ|怖い絵を描く子への見守り方と対処法
「怖い絵」や「黒い絵」には、子どもなりの意味があります。
不安やストレスの表現であると同時に、怖さと向き合う力・成長のサインでもあります。
親としてできることは、絵を通したコミュニケーションで心を受け止め、 「どんな気持ちで描いたの?」とやさしく声をかけること。 それが一番の対処法であり、安心の見守り方です。
「子どもの絵の心理」を理解し、「怖い絵の意味」を正しく受け止めることで、 子どもが自分の感情を表現できる力がぐんと育ちます。
💬 絵は、心の言葉。
怖い絵も、安心して話せる“こころの対話”の始まりです。
▶他のモチーフとあわせて見ることで、より安心して読み取れます。
子どもの絵に出るモチーフ一覧
太陽・家・遊具・食べ物・木
関連記事リスト
こんな記事もおすすめ👇
子どもの絵から気持ちを読み取ったり、日々の小さな変化に気づけるようになると、 「この子に合う学びの形ってなんだろう?」と考える機会も増えてきます。
そんなときに、無理なく“子どものペース”を大事にできる学び方として 私がよく耳にするのが スマイルゼミ です。 もちろん押しつけではなく、気になるご家庭だけの参考としてご紹介しますね。
まずは“わが家に合うか”を資料でチェック
スマイルゼミは、実際の教材イメージや学習の進み方がわかる 無料の資料請求ができます。 子どもの気質やペースに合うかどうか、落ち着いて比べられるので安心です。
- 子どもの興味を引きやすいポイントがわかる
- 学年別の教材サンプルをチェックできる
- 費用・サポート体制がすぐ理解できる
「ちょっと見てみたい」「比較材料がほしい」 そんな軽い気持ちでも大丈夫。資料なら気負わず確認できます。
ホーム » 「怖い絵ばかり描く子ども」それって大丈夫?おばけや怪獣に隠れた心のサイン
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。