著者:ITTI
更新日:2025-09-10
読了目安:6分
この記事の内容
『どっちが悪いの?』と聞いてしまう親心
兄弟げんか、毎日のように起こりますよね。
「おやつの数が1個少ない!」
「アイスの棒が短い!」
「赤いクレヨンを先に使ったのは私!」
——正直、親からすると「そんなことで!?」という内容。
でも子どもにとっては大事件。つい私も「で、どっちが悪いの?」と聞いてしまったことが何度もあります。
けれど、それを言った途端……さらにヒートアップ。泣き声は大きくなるし、こちらのイライラも倍増。
あとから気づきました。これは火に油を注いでいたんだと。
なぜ「どっちが悪いの?」は逆効果?
兄弟げんかの本当の原因って、「どっちが悪いか」よりも「自分の気持ちをわかってほしい」なんです。
長男:「取られた気がした!」
次男:「僕の番だったのに!」
そこへ「どっちが悪いの?」と聞くと、子どもはこう感じます。
- 「どうせ僕が悪いにされるんだ」
- 「また“お兄ちゃんだから我慢しろ”って言われるんでしょ」
結果、意地を張り合い、ケンカが長引くんです。
親ができるのは“裁判官”じゃなく“通訳”
親は「正しい・間違い」を決める裁判官ではなく、子どもの気持ちを翻訳する“通訳”になってみるとラクになります。
「○○は、自分の番を楽しみにしてたんだね」
「□□は、急に取られた気がしてイヤだったんだね」
ただ気持ちを言葉にしてあげるだけで、子どもの表情がふっと緩むことがあります。
不思議ですが、それだけで「もういいや」となってケンカが終わることも。
環境づくりでケンカを減らす工夫
とはいえ、毎日ケンカばかりでは親も疲れてしまいますよね。
少しラクになる工夫もあります。
- おもちゃは1人1つずつ用意(難しければ「交代ルール」をあらかじめ決めておく)
- ケンカが起きやすい時間帯(夕方や眠いとき)は、先に声をかけておく
- どうしても手が離せないときは「ママは料理中だから、タイマーが鳴るまで待ってね」と区切りを作る
全部を完璧にやるのは無理。できる範囲で工夫すれば十分です。
まとめ|兄弟げんかは成長の一部
「またケンカ!?」「うるさすぎる!」と親はヘトヘト。
でも実は、兄弟げんかって子どもにとって大事な練習なんです。
- 感情を出す
- 言い方で伝わり方が変わる
- 相手の気持ちを知る
これは大人になっても必要なこと。子どもはケンカを通して少しずつ学んでいます。
次にケンカが始まったら、深呼吸して「どうしたの?」と聞いてみてください。
それだけで空気が少し変わるかもしれません。
さいごに
親だって人間です。毎回冷静になんて無理。
ときには「もう好きにして!」と席を外してしまっても大丈夫。
兄弟げんかは「悪いこと」じゃなく、子どもが社会性を学ぶ大切な時間。
私たち親も一緒に、ゆっくり成長していけばいいんだと思います。
🌟関連記事もどうぞ|きょうだい関係・親子関係に役立つヒント
🔗【上の子の気持ち】兄弟が生まれたとき、絵が語る心のサインとは
🔗【子どもの心理】兄弟げんかが多いのはなぜ?トラブルを減らす親の5つの習慣
🔗兄弟の絵が全然違うのはなぜ?性格や心理がわかる絵の特徴
\子育て心理に関する人気記事/
\こんな記事もおすすめ/
こんな記事も読まれています/
ホーム » アイスの棒で泣くのも成長!兄弟げんかをあたたかく見守る方法
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
|
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。










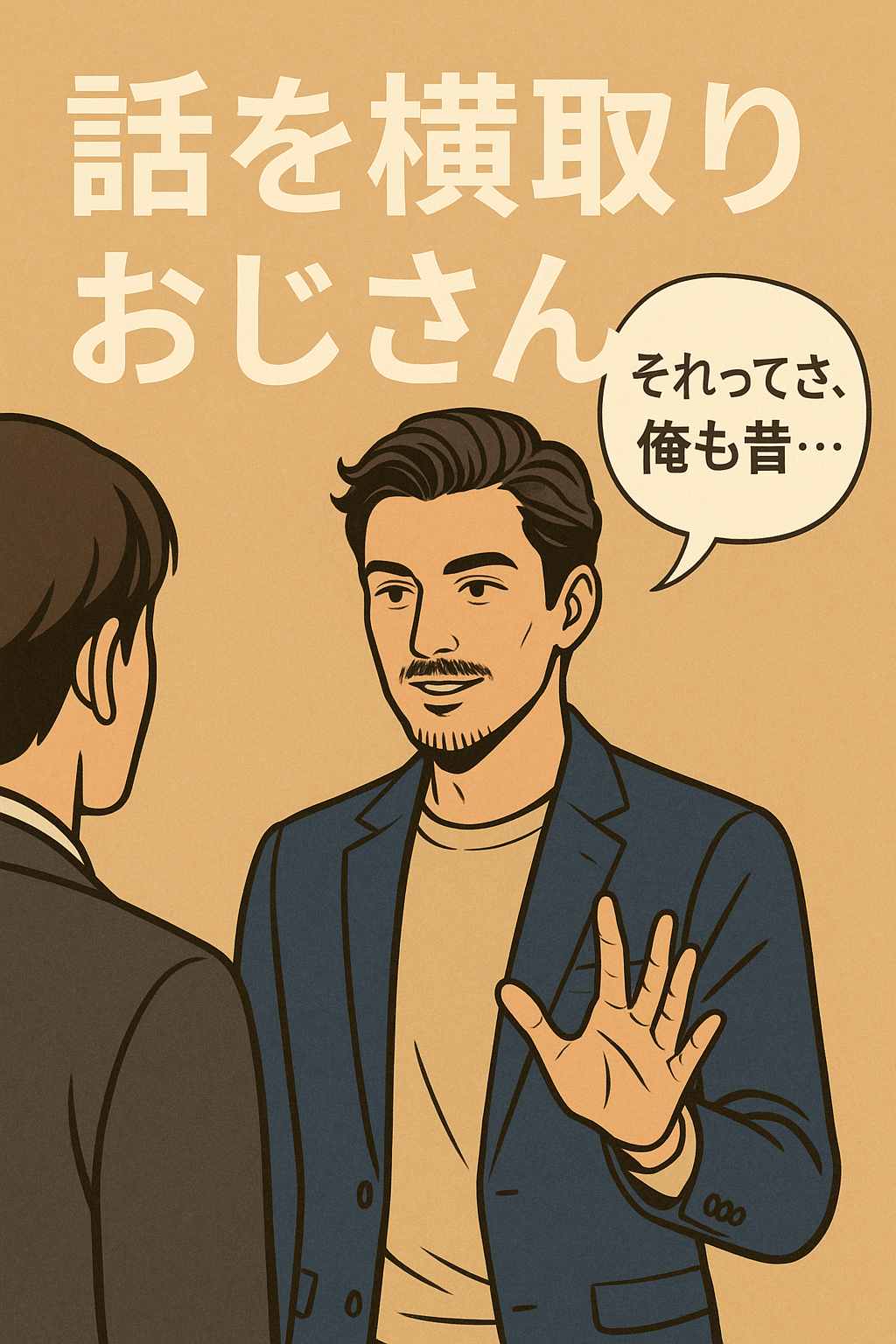
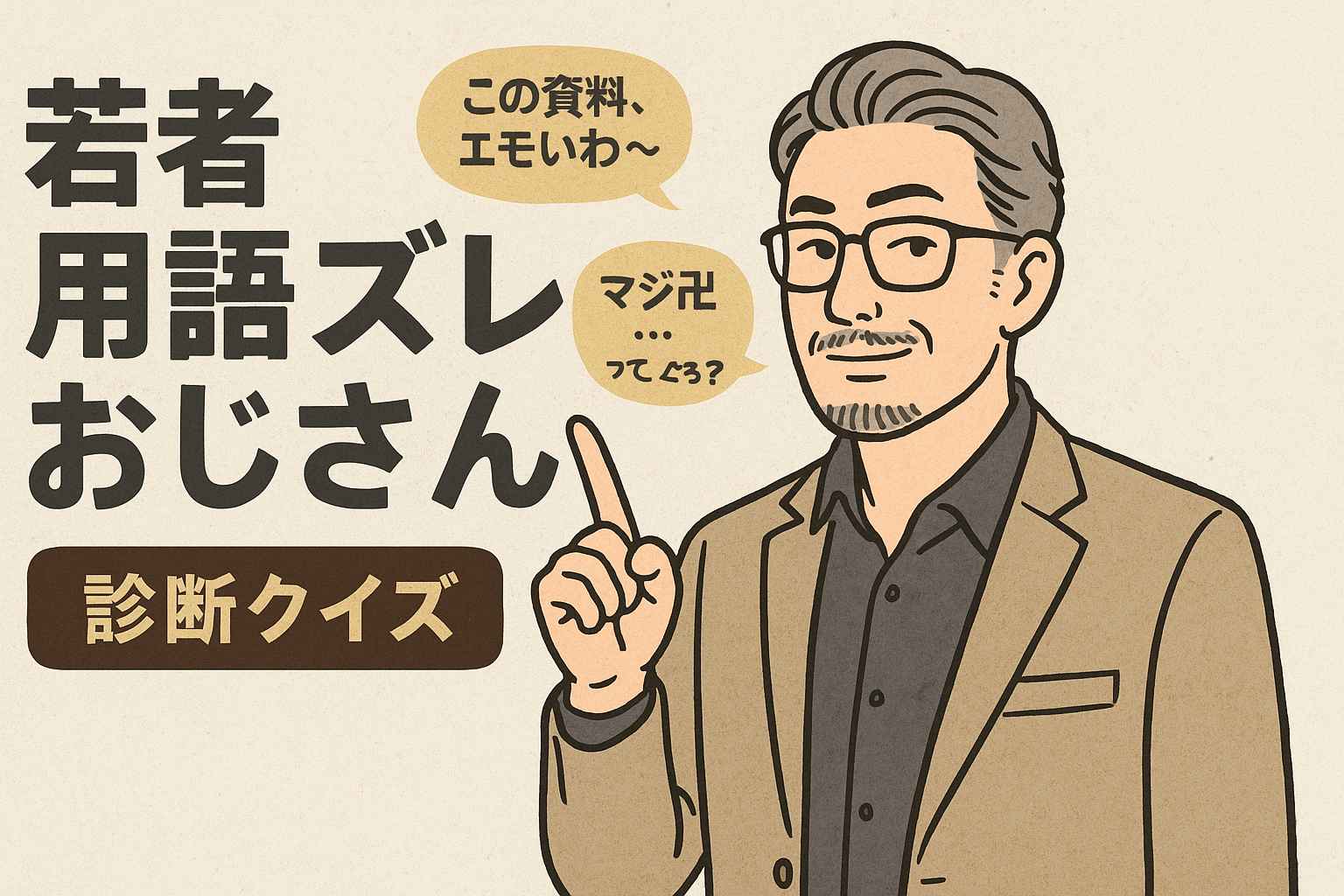







![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49f1f19a.d9ba88d4.49f1f19b.915c7f55/?me_id=1376492&item_id=10000105&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fname-babykids%2Fcabinet%2F10366328%2F11908504%2Fimgrc0107740516.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



