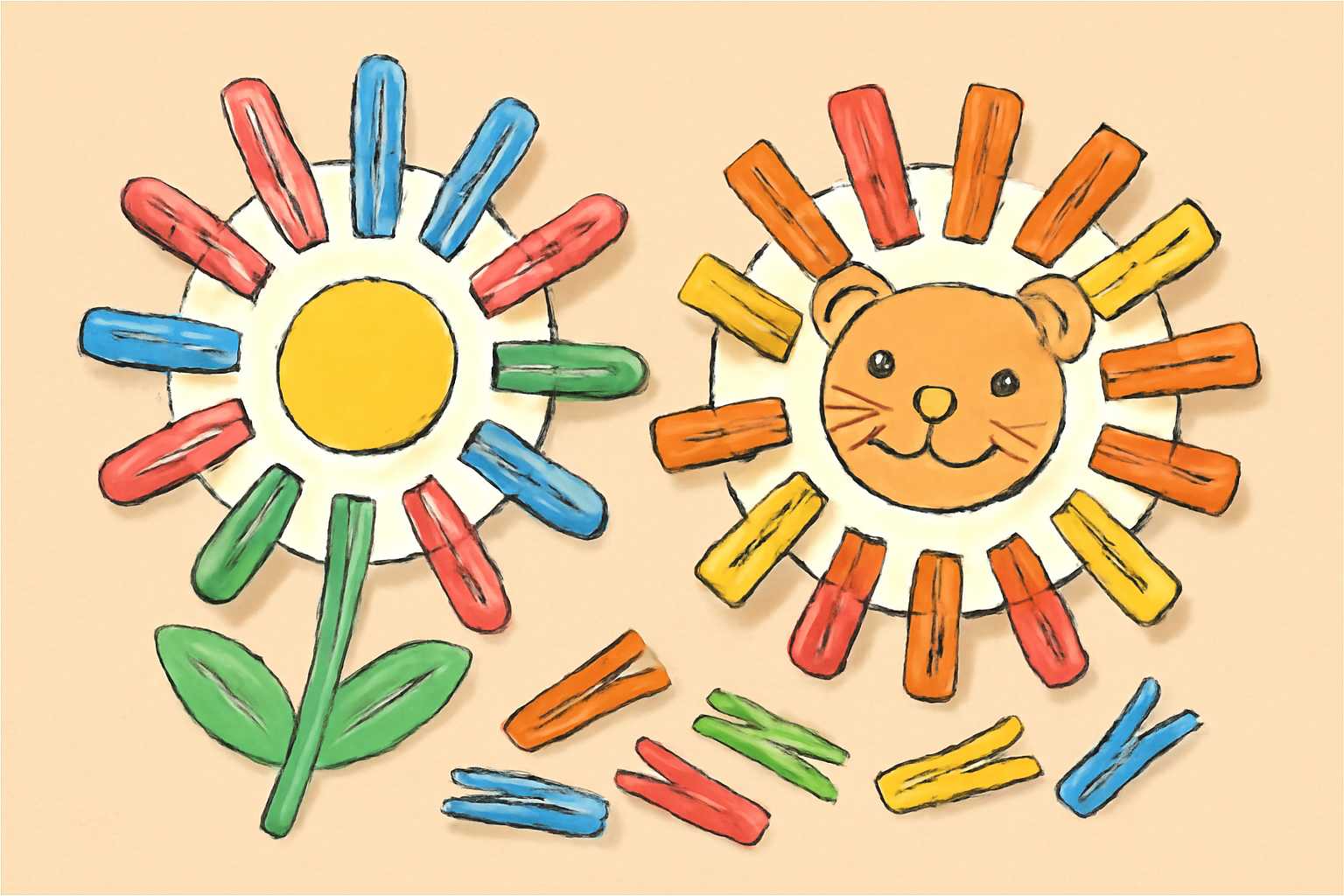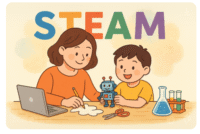「読み聞かせ、大事なのはわかっているけど、毎日続けるのが大変…」と思うことはありませんか?実は、子どもが夢中になる読み聞かせには“心理的な仕掛け”があります。なぜ子どもが「もっと読んで!」と言うときと、すぐに飽きてしまうときがあるのか?その秘密を知れば、親もラクになりながら、楽しい時間を作れますよ😊
この記事の内容
【子どもの心理】読み聞かせを「義務」にすると続かないワケ
「読み聞かせしなきゃ!」と気負ってしまうと、続けるのが苦しくなってしまいます。
でも、子どもにとって大切なのは「毎日読むこと」ではなく、「楽しい時間を共有すること」なんです。
📌 子どもは“好きなこと”じゃないと集中できない → 「読んで!」とせがむ時と、全く興味を示さない時があるのはそのため。
📌 親が楽しんでいないと、子どもも楽しくない → 「義務感」で読むよりも、「楽しいから読もう!」のほうが、自然と続く。
📌 大切なのは、短くても「楽しい時間」を積み重ねること → 1日1冊じゃなくても、数分でもOK!
無理に「毎日読まなきゃ」と思うより、親子で楽しめるタイミングを見つけることが大切です😊
「もう一回読んで!」を引き出す読み方のコツ
子どもが夢中になる読み聞かせには、ちょっとしたコツがあります。
🏆 「この続き、どうなると思う?」と問いかける
物語の途中で、「○○ちゃんは、どうするかな?」と聞いてみると、子どもの想像力がふくらみます。
🏆 登場人物を“子どもに寄せる”
「この子、○○ちゃんに似てるね!」と言うと、親近感が湧き、興味が続きやすくなります。
🏆 声のトーンを変えて演じる
キャラクターごとに声を変えると、子どもがストーリーに没頭しやすくなります。
「読んで!」が増える読み方を取り入れると、無理なく楽しめますよ♪
たとえば、お気に入りの絵本を一緒に見ながら「これ、面白いね!」とおしゃべりしながら読むと、子どもも「もっと読んで!」って思うはず。もし忙しくて時間が取れなかったとしても、「今日はちょっとだけでも読んだ」と思えばOK!その小さな積み重ねが大事です😊仕事で疲れている日は、パパが子どもを膝に乗せて『おおきなかぶ』を一緒に読むようにしました。『うんとこしょ、どっこいしょ』の掛け声を一緒に言うのが楽しいらしく、毎回大笑いしています。
読み聞かせの工夫(実践テクニック)
- 「声色を変えて読む」
- 「絵本のキャラクターになりきる」
- 「途中で子どもに質問してみる」
- 「子どもにストーリーを予想させる」
【親の負担を減らす】毎日じゃなくてもOK!続けるための工夫
「読み聞かせを毎日やるのは大変…」と思う方へ。 続けるためには、無理をしないことが大切です。
✅ 週3回でもOK! 1日10分×週3回でも、十分効果があります。
✅ 好きな絵本を見える場所に 本棚に並べるより、リビングにポンと置いておくと、子どもから「読んで!」と言いやすくなります。
✅ オーディオブックを活用する 親が忙しいときは、プロのナレーターによる読み聞かせを活用するのもおすすめ!
無理をせず、「読めるときに楽しむ」ことが一番大切です😊
毎日読み聞かせをしなきゃ!というプレッシャーを感じている方にこそ試してほしいのが、無理なく続けるための習慣化法。実は、毎日でなくても大丈夫なんです!週に3回、例えば月曜日・水曜日・金曜日にお昼寝後や寝かしつけ前の15分だけでも、習慣にすることが大切。我が家では、毎晩寝る前に5分だけ『ぐりとぐら』を読む習慣があります。最初は1ページ読むのも大変でしたが、1週間もすると子どもから『今日はどこまで読もう?』とワクワクした表情で聞いてくれるようになりました。
例えば、寝る前のリラックスタイムに「今日はこの本!」と決めて、読み聞かせを楽しむ時間を作るのもオススメ。そのうち、「おやすみ前の絵本タイム」が楽しみになり、子ども自身も「今日も読んで!」とリクエストしてくれることも🌙子どもがこの本読みたい!と持ってきてくれたら、うれしいですよね!この気持ちが本好きを育てていくと思うとわくわくします。
忙しい日や、体調が優れない日もあるはず。
でも、「今日はこれで十分」と思える方法を取り入れれば、プレッシャーなく読み聞かせが続けられます。例えば、本を1ページ読むだけでもOK。たった1ページでも、毎日続ければそのうち本の世界にどんどん引き込まれていきます。数ページで物語の概要がわかる読み聞かせの本もあります>>>
リンク
これは筆者の感想なのですが、できれば読み聞かせに使う本は重たくない方が続けやすいです。張り切って買ったものの、読んでいる間に重たくなってきてしまう・・・ということがよくありました。
また、1冊の本を数日にわたって少しずつ読んでいくのもアリです。「長時間じゃなくても、毎日少しずつ」が大切ですよ😊
【発達に合わせた選び方】年齢別・子どもがハマる絵本とは?
毎日読み聞かせを続けるためには、子どもが好きな本を選ぶことがポイント。子どもの反応が良かった本は見える所に置き、その中から何冊かをピックアップしておくと、選ぶストレスも減ります。
たとえば、動物が登場する絵本や、繰り返しのある楽しいストーリーなど、子どもが「もう一回読んで!」と言ってくれる本を中心に選んでみましょう。何度も読んでいると読み手が飽きてきてしまいますが、声のトーンや読み方を変えてお子さんの反応を見てみるのもいいですね。子どもは繰り返しの中で学んでいるので、ここは頑張りどころです。お話の中に子どもの好きなキャラクターやテーマが入っていると、読み終わった後も「もっと読んで!」というリクエストが出やすいですよ。
📖 0~2歳:リズムのある絵本
「いないいないばあ」や「だるまさんシリーズ」など、繰り返しのリズムが楽しい絵本が◎
📖 3~5歳:ストーリーのある絵本
「はらぺこあおむし」や「ぐりとぐら」など、物語性があるものが喜ばれます。
📖 6歳以上:考えさせられる絵本
「100万回生きたねこ」など、少し深いテーマの絵本にも興味を持ち始めます。
年齢に合った絵本を選ぶことで、子どもがより興味を持ちやすくなりますよ😊
🔹 「子どもが途中で飽きちゃう…どうしたらいい?」
→ 絵本の選び方を変える!しかけ絵本や、リズムの良い絵本が◎
🔹 「上の子と下の子、どちらも楽しめる読み聞かせのコツは?」
→ 兄弟一緒に楽しめる本を選び、交互に読むのもおすすめ!
オーディオブックの活用法と、気をつけたいこと
📌 オーディオブックを使うメリット
- 親が忙しいときでも「読み聞かせタイム」を作れる
- プロのナレーターの声で、より臨場感のある体験ができる
- 繰り返し聞くことで、言葉のリズムが身につく
📌 気をつけたいこと
- 「親子の時間」としての読み聞かせとは別物と考える
- スマホやタブレットを使いすぎないように注意する
オーディオブックをうまく活用しながら、親子で楽しむ時間も大切にしましょう😊
オーディオブックを活用した新しい読み聞かせの提案と注意点
近年、オーディオブックが人気を集め、子どもの読み聞かせにも活用する家庭が増えています。忙しい親でも手軽に物語を楽しめるため、親子の時間をより充実させる新しい方法として注目されています。
オーディオブックを活用するメリット
- 親が忙しい時でも物語を楽しめる
料理や家事をしている間でも、子どもに物語を聞かせることができます。特に共働き家庭や、育児と家事を両立させるのが大変な家庭にとって便利なツールです。 - プロの朗読で臨場感が増す
プロのナレーターや声優が朗読することで、登場人物ごとに異なる声やBGMが加わり、物語に入り込みやすくなります。 - 語彙力やリスニング力が育つ
音声だけで物語を理解することで、集中力や言葉の使い方を自然と学ぶことができます。 - 視力への負担が少ない
画面を見る時間が増えている現代の子どもたちにとって、目を休めながら楽しめる点も魅力です。
オーディオブックを活用した新しい読み聞かせの方法
- 親子で一緒に聞く時間を作る
「この場面、どう思う?」と問いかけることで、会話のきっかけになります。 - 寝る前のリラックスタイムに活用する
静かで落ち着いた物語を選び、眠る前の習慣として取り入れると、スムーズな入眠につながることもあります。 - 本とセットで楽しむ
オーディオブックを聞きながら実際の本をめくると、読解力や集中力がさらに高まります。 - 移動時間に聞かせる
車や電車での移動中に活用すると、退屈せずに楽しく過ごせます。 - 子ども自身が操作できるようにする
タブレットやスマートスピーカーを活用し、好きな物語を選ばせることで自主性が育ちます。
オーディオブックを活用する際の注意点
- 親子のふれあい時間を減らさない
オーディオブックに頼りすぎず、親子のコミュニケーションを大切にしましょう。 - 内容を確認してから聞かせる
年齢に合わない表現が含まれることがあるため、事前にチェックすることが大切です。 - 長時間聞かせすぎない
便利だからといって長時間使いすぎないように、バランスを考えて取り入れましょう。 - 視覚的な情報も大切にする
絵本のイラストや文字を読むことも、子どもの想像力を豊かにします。
オーディオブックは便利なツールですが、親子の時間を大切にしながら適度に活用することがポイントです。
まとめ:今日から試せる3つのポイント
この子はこのままで大丈夫🌸
「毎日読み聞かせしなきゃ!」と焦りがちな気持ちも理解できます。
大事なのは、「続けること」よりも「楽しむこと」です。忙しくても、ほんの少しの時間を「親子の特別な時間」として過ごすことが、子どもの心にも響きます。一日の最後に、子どもと「今日も楽しかった」という気持ちでホクホク過ごせたら最高です。読書の習慣は少しずつでも確実に身についていきますし、焦らなくても大丈夫です。
🔹 毎日じゃなくてOK! → 週3回でも習慣になる
🔹 好きな絵本を見える場所に → 自然と「読んで!」が増える
🔹 オーディオブックも活用 → 忙しくても無理せず続けられる
👶 これからももっと楽しい読み聞かせができるよう、たくさんのアイデアをお届けします!
📚 「どんな本を選べばいい?」
🔗子どもが大喜び!おすすめ絵本10選
🔗絵本を選ぶときのポイントやコツ
一緒に読み聞かせの楽しさを広げていきましょう📖✨
おすすめ絵本もご紹介♪
リンク
リンク
これからも、お子さんの成長に役立つ情報をどんどんシェアしていきますので、ぜひブログをフォローしてください!他にも読書に役立つヒントをまとめた記事もありますので、気になる方は【こちら】をご覧ください📚✨親も子どももラクに楽しめる読み聞かせ、ぜひ試してみてくださいね!
読書環境を整えたいなら自分だけの空間づくり>>落ち着いて読める環境を作りましょう♪
リンク
ホーム » 【子どもの心理】読み聞かせが続かないのはなぜ?親がラクになるコツ
|
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a29b147.85d435d1.4a29b148.149b1110/?me_id=1275499&item_id=10005017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatomya%2Fcabinet%2Fgood2%2Fmi-r-cs_m01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)