🎨 親子で「描く時間」を楽しみたい方に
「上手に描く」よりも、描くことそのものが楽しいと思える体験を大切に。
子どもの自由なお絵描きを、そっと後押ししてくれるアイテムです。
クレパスのにじみや重なりを活かした表現がたくさん紹介されており、
3〜5歳の自由なお絵描き時期にも取り入れやすい一冊。
「描いてみたい!」気持ちを自然に引き出してくれます。
著作権 寄り添う子育て・子どもの心と行動を理解するヒント 2026 | Theme by ThemeinProgress | WordPress によって動いてます
「変な絵」に見えても、ちゃんと理由があるんです。
「ねぇねぇ、パパ描いたよ!」
ニコニコ顔で差し出された1枚の紙。期待に胸を膨らませて覗き込むと、そこには……。

「え……あ、ありがとう。……これ、誰かな?」と、引きつった笑顔で返してしまった経験、ありませんか?
「うちの子、心に闇を抱えているんじゃ……」
「発達が遅れているのかも」と、スマホを片手に「子どもの絵 顔がない」「子どもの絵 怖い」なんて検索している、そこのあなた。
まずはお伝えさせてください。
検索している時点で、あなたは十分、お子さんを“ちゃんと見ている”素敵な親御さんです。
子どもの絵は、私たち大人に見えている世界とは全く別のルールで動いています。
いわば、その子の「心の実況中継」。
今日は、ちょっと不思議で、時に笑っちゃう子どもの絵のヒミツを、元教諭の視点から「読み解き方」としてお話ししていきますね。
大丈夫、それは「問題」ではなく、絶賛「成長途中」の証なんです。
お絵描きが始まって、最初に親がソワソワするのが「顔」の問題です。「目・鼻・口」という人間らしさの象徴が抜けていると、なんだか寂しいような、不気味なような気持ちになりますよね。
ネットで「顔を描かない」と調べると、たまに「自己肯定感が低い」「愛情不足」「情緒不安定」なんていう、心臓に悪いワードが飛び込んできたりします。

「私が怒りすぎているから、顔を描きたくないの?」「幼稚園で何かあったの?」と、パパやママが自分を責めてしまうことも。でも、ちょっと待ってください。そんなに深刻にならなくて大丈夫ですよ。
実は、顔をしっかり描くというのは、子どもにとって「ものすごく高度なミッション」なんです。
いわば、「いま一番伝えたいこと(メインディッシュ)」が顔じゃなかっただけ。 決して心が欠けているわけではないんです。
さらに、子どもが大人の予想を超えて「あえて描かない」選択をすることもあります。

これはむしろ、「自分が今できること・やりたいこと」を選択できている成長のサイン。 「省略」ができるようになったんだな、と捉えてみると、少しホッとしませんか?
次に多いのが「バランス」の悩み。胴体から直接、異様に長い手が生えていたり、指が20本くらいあったり。親から見れば「ホラー」に見えるその絵にも、子どもなりの正義があります。
「手は肩から生えているもの」というのは、大人の知識。子どもにとっては、「手がどこから出ているか」よりも「手で何をしているか」の方が重要です。

これ、お絵描きを始めたばかりの子には「あるある」の風景です。
なぜ手が長くなるのか。それは、子どもにとって手が「世界とつながるための魔法の道具」だからです。

子どもにとって「手」は、自分の意思を形にする、一番身近で強力なパーツ。だから、「あのお菓子をとりたい!」という強い気持ちで描くと、手がグーンと伸びちゃうんです。 いわば、感情のパース(遠近法)ですね。手は「できることの象徴」。手が長く大きく描かれているのは、それだけ意欲的に世界に関わろうとしている証拠かもしれません。
「見たままの形を正確に再現する力」は、年齢を重ねるごとにゆっくりと育ちます。
今の段階では、子どもは「見たもの」ではなく「感じたもの」を描いています。
「今日はこのおもちゃで遊んで楽しかった!」という印象が、巨大な手や奇妙なバランスとして現れる。そう思うと、「なんだか力強い表現だな」と見えてきませんか?

子どもの絵の「変(=ユニーク)」さには、年齢ごとのトレンドがあります。
今、わが子がどのステージにいるのかを知るだけで、心の余裕が全然違いますよ。
この時期は「なぐりがき」から「丸(円)」が描けるようになる黄金期。 本人は「これ、パパ!」とドヤ顔で教えてくれますが、大人の目には「ジャガイモかな?」という丸が1つあるだけ。
でも、本人は大満足! 自分の引いた線に意味が宿る。この「命名期」と呼ばれる時期は、形なんてどうでもいいんです。パパと言えばパパ。その想像力の豊かさを一緒に面白がりましょう。
だんだんと人らしくなってきますが、まだまだ突っ込みどころ満載。
「鼻が横についてる」「耳が4つある」「洋服の下に骨(?)が透けてる(レントゲン画法)」など。
「人」として描こうとする意欲と、知識が混ざり合う、一番おもしろい時期です。
表情はいつもニコニコの「一種類」かもしれませんが、それは「描ける表現」で一生懸命に自分の世界を伝えようとしている努力の結晶です。
この頃になると、周りの子の絵や、アニメの完璧な絵と比較するようになります。「うまく描けない!」とイライラしたり、急に「もう描かない」と言い出すことも。

これは「客観的な視点」が育ってきた証拠です。自分の理想と現実のギャップに悩む、ちょっぴり切ない成長期。
【あわせて読みたい】
基本的には「変な絵=元気な証拠」ですが、現場で多くの子どもたちを見てきた経験から、少しだけ「立ち止まって様子を見てほしい」ポイントもお伝えします。不安を煽るためではなく、「もしもの時のアンテナ」として持っておいてくださいね。
一番大切なのは、「絵」という断片だけで診断を下さないことです。
絵はあくまで生活の一部。たまたま黒いクレヨンが気に入って真っ黒な絵を描く日もあれば、疲れていて顔を省く日もあります。
もし「おや?」と思ったら、以下の3点に注目してみてください。
これらが重なる場合は、言葉にできないストレスを絵で表現している可能性もあります。でも、それは「ダメなこと」ではなく、子どもが「助けて」とサインを出せている、前向きな行動。 迷ったら、園の先生や専門機関に「ちょっと絵が気になって……」と相談していいんです。一人で抱え込まないでくださいね。
さて、そんな不思議な絵を前にして、私たちはどう振る舞えばいいのでしょうか。実は、良かれと思ってやっていることが、子どものやる気を削いでいるかもしれません。
「もっとこうすればいいのに」という親心。わかります。でも、以下の言葉は一旦飲み込んでみましょう。
「上手に描く」よりも、描くことそのものが楽しいと思える体験を大切に。
子どもの自由なお絵描きを、そっと後押ししてくれるアイテムです。
クレパスのにじみや重なりを活かした表現がたくさん紹介されており、
3〜5歳の自由なお絵描き時期にも取り入れやすい一冊。
「描いてみたい!」気持ちを自然に引き出してくれます。
評価するのではなく、「関心を持つ」のがコツです。

お絵描きはテストではありません。ましてや、将来の画力を決めるオーディションでもありません。 今の「変な絵」は、今しか見られない貴重な限定アート。
「今日は何を描いたのかな?」と会話を楽しむためのツールだと考えれば、肩の力がふっと抜けませんか?
🌱 顔を描けるようになってほしいな♡という方へ。もう一段、前段階を入れてみませんか?
「顔をつくる遊び」から始めるのも、ひとつの安心なステップです。
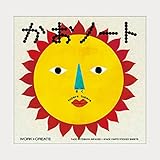
遊びの中で「顔って楽しい」「組み合わせていいんだ」という感覚が育つと、 ある日ふと、絵の中に顔があらわれることもあります。
Q1. 子どもの絵に顔が描かれないのは問題ですか?
多くの場合、問題ではありません。
特に3〜4歳ごろまでは、顔を省略するのは発達として自然なことです。
「描けない」のではなく、「まだ必要性を感じていない」ケースがほとんどです。
Q2. 顔を描かないのは感情が育っていないから?
そうとは限りません。
感情は、遊びや会話、ごっこ遊びなど別の形で十分に表現されていることも多く、
絵だけで感情の有無を判断する必要はありません。
Q3. 何度言っても顔を描かないのは心配ですか?
年齢と「続いているかどうか」がポイントです。
年齢が上がっても毎回描かず、表情の乏しさや生活面の変化が重なる場合は、
少し丁寧に様子を見ると安心です。
Q4. 顔を描くように促したほうがいい?
無理に促す必要はありません。
「なんで描かないの?」ではなく、
「どんな気持ちの子かな?」と想像を広げる声かけがおすすめです。
Q5. 相談したほうがいいタイミングは?
絵以外の変化が重なったときです。
会話が減った、感情表現が乏しい、園や学校でも指摘がある場合は、
「念のため」相談するだけでも親の安心につながります。
「子どもの絵がおかしい」と不安になっていた気持ち、少しは軽くなりましたでしょうか。
子どもの絵は、決して失敗作ではありません。 顔がないのも、手が長いのも、それはお子さんが今、その瞬間を精一杯生きて、感じていることの証なんです。

大人の常識という物差しを一度置いてみると、そこには驚くほど自由で、ユーモアに溢れた世界が広がっています。
最後に、これだけは覚えておいてください。
「この絵、大丈夫かな?」と心配して検索した今日のあなたの行動こそが、もう十分、お子さんを大切に想っている証拠です。
そんな優しいパパやママに、お子さんは明日も「ねぇ、見て!」と、とびきりユニークな新作を持ってきてくれるはず。その時はぜひ、一緒に笑いながら、その不思議な世界を楽しんでくださいね。
「わあ、今日の手は昨日より3センチ長いね!かっこいい!」なんて言えたら、もう最高です。
次に読んでほしいおすすめ記事
「絵は描くけど、色がいつも黒い……」そんな不安に寄り添う記事はこちら。
👉 【色の心理】子どもが黒ばかり使うのはストレス?元教諭が教える色の見方
いかがでしたか?
お子さんの絵で「これはどういう意味?」と気になっている具体的な描き方があれば、ぜひコメントやメッセージで教えてくださいね。一緒に「子どもの世界」を読み解いていきましょう!
🔗子どもが描く頭足人の意味と成長のサイン🔗手だけ大きく描く心理🔗顔を描かない子どもへの対応方法
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。
