この記事を読むと…
🔥 火や🔪 包丁の絵を描く子どもの心理がわかり、
👪 親としてどのように対応すればよいかが学べます。
この記事の内容
ショッキングな絵でも大丈夫!子どもの心を読み解く方法
「うちの子、最近“火事の絵”をよく描くんです」
「包丁を持った人の絵を描いていて、ちょっと怖くなってしまって…」
そんなご相談を受けることがあります。
一見ショッキングなモチーフですが、それだけで「何か問題がある」と決めつけるのは早すぎるのです。
実は、心理学的に見ると「火」や「刃物」には、成長のサインが隠れていることもあります。
この記事では、子どもの心の中で何が起きているのかを、やさしくひもといていきます。
🔗子どもが描く絵の心理をさらに知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
🔥『火事』や『火』の絵を描く理由と親の対応
火の絵は、心理学的には生命力・情熱・変化の象徴といわれます。
子どもが火を描くのは、「燃える」「光る」「変わる」といった現象に心を惹かれているから。
たとえば、
- 花火を見たあとに赤やオレンジで「火」を描く
- 暖炉や焚き火など“あたたかい火”を描く
といった場合は、安心やあこがれの気持ちが反映されています。
一方で、
- 家が燃えている
- 人や物が炎に包まれている
というように“激しい火”が何度も出てくる場合には、
強い感情(怒り・不安・恐怖)を外に出すための表現であることがあります。

火は、「コントロールできない力」への関心でもあります。
成長の途中で「自分の中のエネルギーをどう扱うか」を試している時期なのです。
筆ペンやクレヨンなど、描きやすくて色がはっきり出る道具をそろえてあげると、
子どもはより自由に表現でき、自己肯定感がアップします。
🖍️ 表現を広げるおすすめアイテム
例えばこちらの筆ペンは、柔らかなタッチで感情表現がしやすいのでおすすめです。
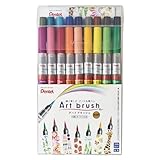 ぺんてる カラー筆ペン アートブラッシュ 18色セット XGFL-18ST
ぺんてる カラー筆ペン アートブラッシュ 18色セット XGFL-18ST [msmaflink id=”4900281″]
🔪『包丁』や『ナイフ』の絵を描く理由と親の対応

包丁やナイフといった“切るもの”を描くと、親としてはドキッとしますよね。
でも、心理的には「切る=分ける」「境界を作る」という意味があります。
これは、発達心理学でいう“自己と他者の区別”が芽生える時期に見られることがあります。
たとえば、
- 「ママとぼくは別の人間なんだ」
- 「好き/嫌いをはっきりさせたい」
といった、自我の発達を象徴する描き方です。
また、包丁は家庭で身近に見かける道具でもあります。
料理を手伝いたい、ママの真似をしたいという思いが背景にあることも多いのです。

ただし、
- 何度も人を傷つける絵を描く
- 表情が暗く、強い恐怖や怒りを伴っている
といった場合は、心の中に整理しきれない感情があるサインかもしれません。
そのときは、叱らずに「どうしてこの絵を描いたの?」と穏やかに聞き取る姿勢が大切です
🌿 親にできること — 「怖い絵」を前にしたときの向き合い方
子どもが“火事”や“包丁”などの絵を描いたとき、多くの親御さんは
「どうしてこんな絵を?」
「心が不安定なのでは?」
と感じるものです。
その戸惑いは、とても自然な反応です。
けれど、まず大切なのは――「描いた」という行為そのものを受けとめること。
心理学的には、絵を描くことは自己表現であり、感情の排出(カタルシス)でもあります。
つまり、「描く」ことによって、子どもは自分の心を整理しているのです。
🌈 1. すぐに否定しないで「受けとめる」
「こわい絵ね」「そんなの描いちゃダメ」
そう言われてしまうと、子どもは「自分の感じていることはいけないことなんだ」と思い込み、
心の奥にしまい込んでしまいます。

たとえばこんな声かけがおすすめです👇
「すごく力強い絵だね」
「どうしてこの色を使ったの?」
「ここは何をしている場面かな?」
“内容の良し悪し”ではなく、描いた過程や気持ちに関心を向けることで、
子どもは「わかってもらえた」と安心します。
安心すると、自然と次の会話が生まれ、
その中で自分の気持ちを少しずつ言葉にできるようになります。
🌸 2. 「背景」を探る — 経験・テレビ・絵本など
子どもは、日常で見たり聞いたりしたことを絵に取り入れます。
たとえば火事のニュースを見た、アニメで戦いのシーンを見た、
絵本で包丁を使う料理シーンを読んだ──そんなきっかけから描くこともよくあります。
ですので、「どんな場面を思い出して描いたの?」とやさしく聞いてみると、
「ニュースで見たの」「ママのお料理のマネ」など、意外と現実的な答えが返ってくることもあります。
つまり、絵は“現実”と“空想”が混ざる場。
「見た」「感じた」「考えた」ことを、子どもなりに組み合わせて表現しているのです。
🍃 3. 「心配すべきとき」と「見守っていいとき」
心理学的に見ると、以下のようなポイントで“見守り”と“相談”の判断ができます。
👀 見守ってOKなサイン
- 絵のテーマが毎回違う
- 絵を描くと気持ちが落ち着いている
- 日常の会話や遊びで笑顔がある
- 「ママ見て!」と自信をもって見せてくれる
これらの場合、感情の整理や想像力の発達の一部と考えて大丈夫です。
🕯️ 注意して見ていきたいサイン
- 同じモチーフ(火事・けが・戦いなど)が繰り返される
- 表情が暗く、人物がいない・孤立している
- 絵に「怖い」「怒り」「悲しみ」が強く出ている
- 学校や家庭での変化(登園しぶり・睡眠や食欲の変化など)がある
こうした場合は、感情の負担やストレスを抱えている可能性があります。
とはいえ、「怖い絵を描いた=異常」ではありません。
むしろ「絵として出せた」ことは、心が外に向かって動いている証拠です。
🫶 子どもの心理と心のケア:絵から読み解く心のサイン
子どもがどんな絵を描くかは、その時々の「心の温度」を映し出しています。
火や刃物のようなモチーフも、そのときの心の中の“強い感情”を整理しようとするサイン。
親がやさしく受けとめてくれるだけで、子どもの心はすっと落ち着いていきます。
💬 1. 「気持ち」を言葉にして返す
心理学では、相手の感情を代弁して受けとめることをリフレクティブリスニング(反射的傾聴)と呼びます。
これは家庭でもとても有効です。
たとえば、火事の絵を見て子どもが「こわかった」と言ったら、
「そうだね、怖かったんだね」
「見たとき、びっくりしたのかな」
「ここは何をしている場面かな?」
と、その気持ちをそのまま言葉にして返してあげます。
すると、「自分の気持ちは理解された」と感じ、安心につながります。
逆に「怖い絵を描かないの!」と否定してしまうと、
子どもは「怖い」と感じた自分そのものを否定されたように感じてしまいます。
絵を描く=心の安全弁です。描けるうちは、心がまだ動けるということ。
🖍️ 2. 「描いたあと」を大切にする
描き終えたあと、「どんな気持ちになった?」と聞いてみましょう。
「スッキリした」「もういいや」「また描きたい」など、
その反応が、子どもの心の回復過程を教えてくれます。
ときには、絵を見せながらおままごとやお絵かきごっこに発展することもあります。
これは「感情の再体験と整理」を自然に行っているサイン。
心理療法でも使われるアートセラピー的な効果が家庭の中でも生まれています。
🎨 家庭でできる表現サポートの一例
親子で取り入れやすいアートセラピー入門書や、家庭で気軽にできる表現ワークも役立ちます。手順がわかる本が一冊あると安心です。
 子どもの心がどんどん軽くなる 家庭でできる”表現アートセラピー”
子どもの心がどんどん軽くなる 家庭でできる”表現アートセラピー” 🌷 3. 無理に「楽しい絵を描かせよう」としない
「もっと明るい絵を描こうね」と励ましたくなることもありますが、
心の中でまだ整理できていない感情があると、かえってプレッシャーになってしまうことも。
子どもは“安心できたとき”に自然とテーマを変えていきます。
時間をかけて、「描きたいものを描ける環境」を用意しておくことが一番のサポートです。
☀️ 4. 日常の中で「安心」を増やす
絵だけでなく、日常の小さな安心感が心の安定につながります。
- 一緒に食事を作る
- 絵を飾ってあげる
- 「今日も描いたね」と笑顔で声をかける
こうした積み重ねが、「自分の世界を安心して表現していいんだ」という
自己肯定感の土台になります。
💡 5. 相談を検討してもいいサイン
もし次のような様子が長く続くときは、早めに専門家に相談してみましょう。
- 絵の内容が極端に攻撃的・悲観的で変わらない
- 学校や家庭での会話が減り、表情が乏しい
- 絵を描くときに強い不安や泣きが見られる
相談の場としては、スクールカウンセラー・児童心理士・地域の子育て支援センターなどがあります。
「相談する=大ごと」ではなく、「子どもの気持ちを一緒に整理してもらう」くらいの気持ちでOKです。
親の不安を解消!子どもの絵から心を読み解くQ&Aとチェックリスト
子どもが描いた絵を見て、「これってどういう意味?」「うちの子、大丈夫?」と不安になることはありませんか?親なら誰でも一度は感じることです。でも安心してください。子どもは絵を通して、自分の気持ちや考えを表現しているだけで、必ずしも深刻なサインとは限りません。
Q&A:子どもの絵に親がどう対応すべきか
Q: 子どもが包丁の絵を描いたらどうしたらいい?
A: 驚く必要はありません。子どもは身近に見たものを絵にすることがあります。包丁は家庭でよく見る道具ですので、特に心配する必要はありません。
ポイントは、「どうしてこの絵を描いたのかな?」と優しく聞くことです。子どもの気持ちを理解しながら、コミュニケーションを大切にしてみましょう。
チェックリスト:心配すべきサインと見守って良いサイン
子どもの絵には、ちょっとした心のサインが隠れています。どんなときに注意すべきか、どんなときは見守って大丈夫かをまとめました。
心配すべきサイン
- 繰り返し「火事」「けが」など怖いテーマの絵を描く
- 絵の中で暗い表情や孤独感が表れている
- 強い恐怖や悲しみを感じさせる表現が多い
見守って良いサイン
- 毎回違うテーマの絵を描いている
- 絵を描くことで気持ちが落ち着いている
- 日常生活で元気に過ごしている、笑顔が見られる
このチェックリストを参考に、絵を通してお子さんの心の状態を理解し、必要に応じてサポートしてあげましょう。
🌸 さいごに — 「絵」は、子どもからの小さな手紙
子どもが描く絵には、「見てほしい」「わかってほしい」という思いが詰まっています。
火も包丁も、子どもにとっては「世界を知りたい」「感情を表したい」という
健全な成長のプロセスの一部なのです。
絵は“心の鏡”であり、“会話のきっかけ”でもあります。
大人がそのメッセージをやさしく受けとめることで、
子どもは「自分の気持ちを表現していい」と学び、
少しずつ感情の扱い方を覚えていきます。
怖い絵を見たときほど、
「この子の中に、どんな気持ちがあるんだろう」と想像してみてください。
そのまなざしが、子どもの心にいちばんの安心を届けてくれます。
🔗お母さんを一番大きく描くこども。子どもの家族の絵でわかる心理
🔍 ちょっと気になる絵の例とその心理
- 黒いぐるぐるや塗りつぶしをよく描く(気持ちがモヤモヤしている、イライラしている)
- 火事・爆発・炎の絵を描く(恐怖心やストレスの発散、憧れ)
- 泣いている顔ばかり描く(悲しみや寂しさの表れ)
- 家族の一部がいない絵を描く(その人への気持ちや関係性を反映)
- 自分が小さく描かれている(自信のなさや不安)
- 武器や戦いの絵ばかり描く(エネルギーが有り余っている、ストレス発散)
- ぐちゃぐちゃの迷路や道が続く絵を描く(考えごとが多い、気持ちが整理できていない)
- 一人ぼっちの絵をよく描く(孤独感や不安感)
- 繰り返し同じキャラクターやモチーフを描く(強い憧れ・安心感を求めている)
🔸 気をつけるポイント
- 1回だけなら気にしすぎなくてOK! たまたま描いたものの可能性大。
- 繰り返し同じようなテーマを描く場合は、気持ちを探るチャンス!
- 「最近何かあった?」とさりげなく話を聞いてみるのも◎
心の整理を助ける遊び・絵本の紹介
🎨遊びで感情表現をサポート
- お絵描き・ぬりえ:自由に表現できるツールとして、子どもが感情を出しやすくなります。
- ごっこ遊び:悲しい役・怒ってる役などになりきって気持ちを出すことができる。
📚共感力を育てる絵本
- 『わたしのワンピース』(西巻茅子):自己表現や自由な想像がテーマ。
- 『おこだでませんように』(くすのきしげのり):叱られてばかりの子の心を描く名作。
- 『ママがおばけになっちゃった!』(のぶみ):死や別れ、不安の気持ちを丁寧に描いています。
🌷 子どもの「気持ち」を読み解くきっかけに
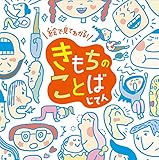 絵で見てわかる! きもちのことばじてん
絵で見てわかる! きもちのことばじてん絵本のように楽しみながら、子どもの感情に寄り添える1冊。
「うれしい」「さみしい」「こわい」など、
子どもが表現しきれない気持ちを、親子でやさしく言葉にできます。💛
ホーム » 包丁や火事を描く子どもの心理と、親ができること
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
\こんな記事も読まれています/
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。


