親子の信頼関係を深めるヒント
ほめ方・叱り方・絵本・お絵かき・心理診断まで、
親子で楽しみながら信頼を育むための実践的なヒントをやさしく紹介します。
ほめ方・叱り方・絵本・お絵かき・心理診断まで、
親子で楽しみながら信頼を育むための実践的なヒントをやさしく紹介します。
今日も子どもと一緒に、心をつなぐやさしい子育て
行動・心理からも、お絵かきや造形遊びからも。親子で楽しみながら子どもの心を理解できます。
このブログはPRを含んでいます

最近、うちの子もゲームばっかりやってるんですよね…。
でも、これってみんなの家でも同じですか?
「他の家もそうだから、うちだけじゃないんだ」と思いたい反面、なんだか不安になる気持ちもありますよね。
「やりすぎじゃないか?」とか「もっと外で遊んでほしいなぁ」とか、ついつい口に出しちゃう。
でも、ちょっと待って。
実は今、ゲームって「子どもの遊び」としてはごく普通のものなんです。というか、今どきの子どもたちにとっては、ゲーム=遊びと言っても過言ではないかもしれません。それも、ゲームの種類が多すぎて、親としてはどれを許容していいのか、どこで線引きすればいいのか、正直わからなくなるんですよね。
でも、ゲームを「やめさせたい」と思う親の気持ちもめっちゃわかります。だって、ゲームばかりしていると、どうしても「学業が心配」「健康が心配」「人間関係や言葉遣いが心配」なんて不安が湧いてきますもん。だから、今日はそのあたりを一緒に考えてみましょう!

「昔は外で遊んでいたのに…」
時代は変わりましたね。
特にコロナで自粛期間もあり、ゲームにハマる子も増えたのではないでしょうか。
今の子どもたちにとっては、ゲームは単なる娯楽じゃなくて、友達と繋がる手段でもあり、想像力を膨らませるツールでもあります。
例えば、オンラインゲームで友達と協力プレイをしたり、ゲーム内で冒険をしたり。

これって、リアルの世界では経験できないようなことを体験できるチャンスなんですよね。だから、昔の「外で遊ぶ」遊びとはまた違う形で、今の子どもならではのコミュニケーションスキルを身につけていってるんですね。
ゲームは単なる「暇つぶし」から、教育的要素や学びのツールにまで進化しています。たとえば、プログラミングを学べるゲームや、英語や数学の力を伸ばせるゲームだってあります。
でも、「ゲーム=時間の無駄」ではないけど、過度にハマると問題になるので気を付けたいところ。
さて、実際に「ゲームばかりしている子どもたち」って、今、どれくらい増えているのでしょうか?ある調査によると、小学生の約1割が毎日ゲームをしているというデータもあるんです。
ただ、ゲームの時間が長くなりすぎると、やっぱり健康や学業に影響が出ることもあります。子どもがゲームを長時間プレイしていると、寝る時間が遅くなる、運動不足になる、集中力が低下する…など、ちょっと心配な点が出てきます。
ゲーム自体は悪いものではありません。むしろ、適切に使うことで楽しい時間を過ごしたり、考える力や反射神経を養ったりすることもできます。しかし、問題となるのは「やりすぎ」と「不適切な使い方」です。特に、子どもたちがゲームにのめり込みすぎると、こんなことが問題になってきます。
ゲームにハマるあまり、勉強やスポーツなど他の大切なことをおろそかになることが・・・。これが続くと、学業成績が下がったり、睡眠時間が削られて健康に悪影響が出ることも考えられます。
こんなことありませんか?
オンラインゲームや対戦型のゲームでは、他のプレイヤーとのやりとりが重要です。しかし、ゲーム内で暴言や煽り行為をしてしまう子どもが増えています。これが習慣になると、現実世界でもコミュニケーションに問題が生じることがあります。

たとえばこんなこと、ありませんか?
ゲームは楽しい反面、依存症になりやすいというリスクもあります。特に、ゲームを長時間プレイすることで、「ゲームなしでは気が済まない」「ゲームが全てになってしまう」といった状態に陥ることがあります。

こんなことあるある!
最近のゲームでは「ガチャ」や「アイテム課金」といったシステムがあり、子どもが知らず知らずのうちにお金を使ってしまうケースがあります。これは親が知らないうちに、無駄にお金を使ってしまう原因になるため、しっかりと管理が必要です。
課金アイテムがほしい!これもよく聞くワード
子どもがゲームに夢中になりすぎないように、1日のゲーム時間に制限を設けましょう。たとえば、「1日1時間まで」や「宿題が終わってから」などのルールを決めて、実行できるようにします。

実践例:
子どもがプレイするゲームの内容を確認し、年齢に合ったものを選びましょう。暴力的な内容や過激な表現があるゲームは避け、教育的な要素を取り入れたゲームや、友達との協力プレイを楽しむゲームがおすすめ。
実践例:
最近では、将棋やピアノのように、「ゲームを習い事」として学べるサービスも登場しています。
フォートナイトやマイクラなどの人気タイトルを、全国大会・世界大会に出場経験のあるトレーナーからオンラインで学べるのが特長です。
ただ遊ぶだけでなく、集中力や情報処理力を伸ばすトレーニングとして注目されています。
外に出にくい時期でも、自宅から安心して参加できるのは嬉しいポイントですね。
まずは気軽に体験会から試してみませんか?
この時期の子どもはまだゲームに対する理解が浅く、視覚的に刺激が強いシンプルなゲームが人気です。ゲームは教育的要素が強いものが好まれます。
小学生の低学年では、簡単なルールのあるアクションやパズルゲームが人気です。また、ストーリー性があり、少し複雑な操作ができるゲームにも興味を持ち始めます。
この時期には、少し複雑なストーリーや戦略が必要なゲームが人気です。ゲームに夢中になり、長時間遊ぶ子も増えます。
中学生になると、よりリアルなゲームや、ストーリー性が強いゲーム、対戦型のオンラインゲームに興味を持つようになります。この年齢では、ゲームを通じて友達とのコミュニケーションを楽しむ傾向があります。
幼児期は教育的なゲーム、低学年は簡単な冒険やパズルゲーム、高学年は戦略やオンライン対戦を楽しむゲーム、中高生は競技性やストーリー性の高いゲームが人気です。
ゲームの中でもモラルやマナーを守ることが大切です。ゲーム内で暴言を吐かない、他のプレイヤーを尊重する、負けても怒らずに楽しむことなど、基本的なルールを教えていきましょう。
オンラインゲームや対戦型のゲームでは、他のプレイヤーとのやりとりが必須です。ゲームの中で相手と協力したり対戦したりする場面が多いため、モラルやマナーを守ることがとても大事になってきます。しかし、ゲーム内で暴言や煽り行為をしてしまうことがあり、それが習慣化してしまうと、現実世界でのコミュニケーションにも悪影響を及ぼす可能性があります。
🌟ゲーム内には、イヤな事をしてくる人もいるということも伝えましょう。
子どもがゲーム内でお金を使わないように、ゲームの設定で課金を制限するか、事前に許可を取るルールを作りましょう。親が子どものゲーム内での課金を把握し、無駄な支出を防ぐために管理することが重要です。
実践例:
ゲームを楽しむことも大切ですが、他のアクティビティ(勉強、運動、読書、家族との時間など)とバランスよく過ごすことが重要です。子どもにとってゲームが全てにならないように、他の楽しみを一緒に見つけていきましょう。
ゲームは過度にのめり込むと依存症のリスクが高まります。特に子どもは感情のコントロールが未熟なため、ゲームに夢中になるあまり、他の重要な活動を後回しにすることが多くなります。
「ゲームばかりしている子どもたち」って、今どきの子どもにとってはごく普通のことです。ゲームは遊びの一つであり、時代背景やテクノロジーの進化によって、子どもたちの楽しみ方も変わってきています。
だからこそ、「ゲームばかりしている」と心配になりますが、適切なルールを設けて、バランスよくゲームとつき合っていけるといいですね。

🔗【小学生の不登校原因ランキング】担任と合わない子への対応は?親が知っておきたいこと
担任がつきタブレット教材で自宅学習をサポート。
プログラミングや声優体験など、子どもが得意を伸ばせるオンラインスクールです。
資料請求で詳しい内容をチェック!
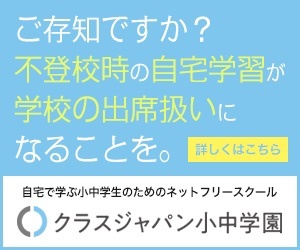
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
気になる診断を選んで、秋のひとときをもっと楽しんでみませんか?
学校に行かない選択、でも「学び」は止めない
「学校に行かなくても、ちゃんと学べる場所がある」
それを知ってから、私も子どもも少しずつ前を向けるようになりました。
クラスジャパン小中学園は、全国対応のオンラインフリースクール。
出席扱いになる可能性があるから、今の学びが将来につながります。
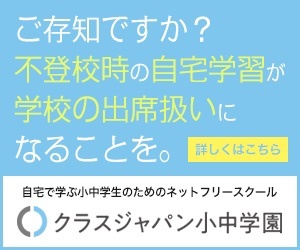

おえかき おもちゃ おもちゃ選び方 お母さんの絵 お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描きの心理 お食事エプロン ぐずる ほかの子と喧嘩 イラスト クレヨン ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 加減を知る 友達が小さい 友達の絵が小さい 子どものアート 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 怖い絵 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 育児用品 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 食器 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理 1歳おすすめおもちゃ
このブログはPRを含みます
こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです!
子どもの心と表現の成長を、親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。
コメントを残す