「血」「包丁」「泣いている人」…不安になる子どもの絵に隠れた本当の気持ちとは?
著者:ITTI
更新日:2025-10-03
読了目安:6分
子どもの絵が「怖い」「不安」…それって大丈夫?
「黒で塗りつぶした絵を見てショックを受けました」
「刃物を描いていて不安になりました」
SNSでも、こんな“怖い絵”に戸惑う親御さんの声をよく見かけます。
でも実は、こうした絵の多くには「子どもなりの心の整理」や「感情の放出」が隠れていることがあります。
見た目の印象だけで「怖い」と感じても、すぐに心配しすぎる必要はありません。
大切なのは、“なぜこの絵を描いたのか”という背景に目を向けることです。

よくある「気になる絵」8タイプと心理サイン
「黒で塗りつぶす」「包丁を描く」「泣いている人を描く」など、
親が「どう受け止めたらいいの?」と悩みやすい絵には、共通の心理的意味があります。
ここでは、代表的な8タイプとその背景を紹介します。
1. 黒で塗りつぶす絵:怒りやモヤモヤの発散
黒は“悪”ではなく、“強い感情”を象徴する色。
言葉で伝えきれない怒りや混乱を、黒で表していることがあります。
黒一色で塗りつぶされた絵を見ると、「なんだか暗い感じがする…」と心配になるかもしれません。でも、これは子どもが「モヤモヤした気持ち」を発散させているだけのことが多いんです。怒りやイライラした気持ちを絵にぶつけていることが多いので、深刻に捉えすぎる必要はありません。
『この色しか使わない』『同じ道具ばかり』というときには…

Okiki お絵描きセット【色鉛筆 クレヨン革新・よくより発色対策】208ピース お絵かきセット 両面イーゼル付き
色の幅だけでなく、道具の種類が豊富なので「子どもが色をどう使うか」「どの道具を選ぶか」からも心理・発達のヒントが得られます。
2. 包丁を描く絵:恐怖や不安の表現

包丁や刃物を描いた子どもを見ると、「もしかして攻撃的な子に?」と心配になりますよね。でも、実際は、恐怖や不安を感じていることを表現しているだけの場合がほとんどです。テレビや本で見た怖いシーンを再現していることもあります。
🔗刃物や火を描く子どもの心理サイン
3. 血の描写:映画や刺激的な体験の整理

血を描くのを見ると、少し驚いてしまいますよね。でも、血を描くのは、映画や絵本の影響を受けている場合が多いんです。子どもは「見たもの」を絵に表現することがあります。特に怖いシーンを描いて心の中で整理していることも。
赤や血の表現は、“印象に残った映像”の再現であることが多く、
実際の暴力性とは関係がない場合がほとんどです。
4. 動物を叩く絵:ストレスや不安のサイン
動物を叩く絵を見ると、「暴力的な子になっちゃうんじゃないか」と心配になりますよね。でも、これは子どもが強いストレスを感じているサインかもしれません。ストレスや不安を感じているとき、無意識に絵に表れることがあるんです。
日常の中で感じた「思い通りにならない」「怒りたいけど怒れない」
そんな気持ちが、絵の中で動物に向かって表れていることも。
5. 泣いている人:共感・悲しみの表現
泣いている人を描くのは、子どもが「寂しい」「悲しい」気持ちを感じているときに見られるサインです。特に、友達と喧嘩したり、家族の間で何か変化があったときに、絵にその感情を表すことがあります。
子どもは人の感情に敏感です。
誰かの悲しみを感じ取って、それを絵にすることで共感を表しています。
🔗言葉にできない子どもの気持ちを知る|「悲しかったことを描く」お絵かき活用法
6. 壊れた家:家庭環境の不安
家は“安心の象徴”。
その家が壊れている場合、「不安」「孤独」「変化へのストレス」などを感じている可能性があります。
壊れた家を描くのは、家庭の中で何か不安を感じている証拠です。引っ越しや両親の関係が変わったとき、子どもはその不安定さを絵に表現することがあります。
7. ゆがんだ顔:怒りや恐怖の表現
顔の歪みは、心の中の「葛藤」や「混乱」の象徴。
怒りや恐怖を感じていることを示しています。子どもが自分の中で抱えきれない感情を表現していることがあります。
8. 無表情の人:感情を抑えている状態

笑顔も涙もない顔は、「気持ちを出すのが怖い」「我慢している」状態を示すことがあります。子どもが自分の気持ちを表現できずにいるときに見られることがあります。
🖍 心を整える時間におすすめの1冊
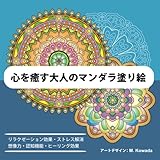 心を癒す大人のマンダラ塗り絵
心を癒す大人のマンダラ塗り絵忙しい毎日に“心のリセット時間”を。
色を塗るだけでストレス解消・リラックス・集中力アップ効果が期待できます。
大人の塗り絵セラピーで、気持ちのバランスを整えましょう。
親ができる3つの安心アプローチ
「怖い絵を描いた=問題」と決めつけるのではなく、
子どもの心に寄り添う関わり方が大切です。
① 否定せず「どうしたの?」と受け止める
「そんな絵ダメ!」と言うよりも、
「この色が多いね」「この人はどうしたの?」と穏やかに声をかけてみましょう。
安心して話せる雰囲気が、次の気持ちの表現につながります。
② 日常の変化を振り返る
絵は心の鏡。
家庭・学校・友だち関係など、最近の出来事を思い返してみると、
絵の意味が見えてくることがあります。
③ 安心して気持ちを出せる場をつくる
お絵かきや会話、遊びなど、自由に感情を表せる時間を。
「怒りの気持ちを絵に出す意味」や
「家庭でできる感情表現のサポート法」も参考になります。
心のサインを見逃さないためのチェックリスト
「少し気になる…」と感じたら、次のポイントを見てみましょう。
✅ 絵のテーマがいつも同じ
✅ 黒や赤など強い色ばかり使う
✅ 人物が毎回泣いている
✅ 家族がいない、またはとても小さい
ひとつでも当てはまる場合は、こちらの記事も参考に:
👉 子どもの絵でわかる家庭環境の心理サイン
Q&Aでわかる「怖い絵」と心の関係
Q1. 黒い絵ばかり描くのは危険?
→ いいえ、必ずしも危険ではありません。
感情が強いとき、黒は「自分の気持ちを守る色」として使われることもあります。
Q2. 残酷な絵を描くとき、怒るべき?
→ 怒るよりも、「何が印象に残ったの?」と話を聞くほうが大切。
絵は感情の出口であり、危険信号そのものではありません。
Q3. 絵でストレスがわかるって本当?
→ はい、ある程度のヒントにはなります。
ただし“絵だけ”で判断せず、言葉や行動と合わせて見ることがポイントです。
まとめ:不安を“観察力”に変えていこう
子どもの絵は、心の中をのぞく「小さな窓」。
「怖い」「不安」と感じるときこそ、
子どもがどんな気持ちを抱えているのかを知るチャンスです。
不安をただ抱えるのではなく、
「観察して」「受け止めて」「寄り添う」力に変えていきましょう。

そして、もし不安な気持ちを感じたときには、親として寄り添い、共感しながらサポートしてあげましょう。子どもが安心して自分の感情を表現できるような環境を作ることが、何より大切です。
もっと深く理解したい方にはこちらの本を参考に
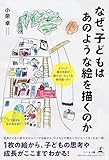
なぜ、子どもはあのような絵を描くのか
絵に表れる心理を解説する定番書。親や先生向けの理解にぴったりです。
この記事で紹介したように、子どもの絵には色やモチーフにさまざまな意味が隠れています。
もし気になる絵があれば、以下の記事も合わせて読んでみてくださいね👇
- 【黒い絵ばかり描く子の心理と親の対応法】
- 【青・紫ばかり塗る子どもの気持ち】
- 【血の絵が示す子どもの心理】
- 【パパがいない絵を描く理由】
- 【家がない絵からわかる子どもの心】
- 【おばけや妖怪を描く子の気持ちと向き合い方】
気になるテーマをクリックして、子どもの気持ちに寄り添ってみませんか?
🖇️ あわせて読みたい!関連リンクで「子どもの心」をもっと知る
🧠「戦いの絵」以外にも、こんな子どもの表現、気になったことありませんか?
🎨「絵」でわかること、まだまだあります!
子どもの絵って、ほんとうに奥が深いんです。たとえば……
こんな記事もあわせて読むと、子どもの絵の“読み解き力”がぐんとアップするかも。
「ちょっと気になる」を、「ちょっと声をかけてみよう」に変えることから、はじめてみましょう。
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
\こんな記事も読まれています/
こちらもおすすめ
このブログはPRを含みます
🖍 子どもの絵でわかる心理チェック
こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです。
このブログでは、子どもの絵から心理を読み取り、心の成長や表現力を親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。
「子どもの絵で心を読む専門サイト」として、日々の子育てに役立つ情報をお届けします。


コメントを残す