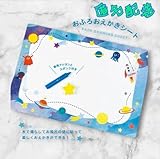このブログはPRを含みます
著者:ITTI
更新日:2025-09-11
読了目安:7分
「お母さんだけすごく大きく描いてる」「お父さんがいない絵ばかり描く」──そんな子どもの絵を見て、少し不安になったことはありませんか?
教育や心理の現場でも、家族の絵は“心の鏡”といわれます。この記事では、実際の親御さんの声をもとに、絵が伝えるメッセージと、安心につながる関わり方をお伝えします。
詳しくは▶ 子どもの絵から読み解く心理サイン一覧
子どもの家族の絵に表れる“心の声”とは?

子どもは「こう描こう」と考えているのではなく、心の中にある思いを自然に絵に表すことがあります。まだ言葉でうまく説明できない年齢の子ほど、絵が気持ちを伝える手がかりになるのです。
特に家族の絵は、安心できる存在や日常の感情が強く出やすいものです。
「お母さんだけ大きい」子どもの絵に隠れたメッセージ

「お母さんだけが大きく、目立って描かれている」絵はよく見られます。
これは「大好き」「安心できる」という気持ちの表れ。
毎日一生懸命頑張っているママへ。
その頑張り、子どもはちゃんと見ています。
絵に出る「大きなママ」「にこにこママ」は、子どもからの「大好き」「安心」のサイン」です。
完璧じゃなくても大丈夫。今日のママの思いは、そのまま子どもに届いています。
おうちで飾れる!子どもの絵の展示にぴったりなフレーム
子どもの絵を大切に残したい方におすすめ。
軽くて安全、貼って飾れるタイプなので、リビングや子ども部屋にもぴったりです。

Haojiaho アートフレーム 12個セット 子供の絵 展示用 フォトフレーム(白)
ただし、極端に大きい場合は「もっとそばにいたい」「ちょっぴり不安で頼りたい」というサインかもしれません。
子どもがお父さんを描かないときの心理と接し方
家族の絵にお父さんがいないと、つい何かあったのかなと心配になる方も多いでしょう。でも、子どもの絵の心理を読み解くと「描かない=嫌い」ではないことがほとんどです。
たとえば、お父さんが仕事で忙しく普段あまり一緒に過ごす時間が少ない場合、子どもの記憶の中で印象が薄くなっていることがあります。これは寂しいや会いたいといった気持ちの裏返しでもあります。
また、子どもはその日の気分や描きたいテーマによって自然に登場人物を選んで描くこともあります。たとえば公園で遊んだ日を思い出しながら描いた絵に、たまたまお父さんがいなかっただけということも多いのです。
一方で、家族の絵でお母さんだけが大きく描かれる、お父さんが小さく描かれる・描かれないなどの表現には、子どもの中の安心感や依存のバランスが表れていることもあります。お母さんに甘えたい気持ちが強い時期は、絵の中でも自然とお母さんが中心になります。
大切なのは、「描かない理由」を無理に探そうとせず、子どもが安心して気持ちを表現できる環境をつくることです。「パパも描いてみよう」と直接誘うよりも、「この絵の中で誰が楽しそう?」と問いかけて、気持ちを言葉にするきっかけをつくってあげると良いでしょう。
子どもの絵にはその子なりの心の世界が表れています。焦らずに受け止めながら、絵でわかる子どもの気持ちを少しずつ感じ取っていくことが、親子の信頼を育てる第一歩です。

だから、描いていない=気持ちがない、ではありません。絵だけで判断しないことが大切です。
あわせて読みたい▶ パパを描かない子どもの心理と接し方
兄弟を小さく描く・描かない子どもの心理

兄弟の絵を見て、どうして下の子がすごく小さいの?お姉ちゃんを描かないのは仲が悪いのかな?と感じることはありませんか。実はこれも、子どもの絵の心理を読み解くうえでよくある表れのひとつです。
たとえば、下の子が小さく描かれている場合は、単に「赤ちゃんだから小さい」と現実の印象を反映していることもあります。一方で、「お母さんを独り占めしたい」「もっと見てほしい」という安心感を求める気持ちが隠れているケースもあります。
また、兄弟を描かない場合も、「嫌い」や「仲が悪い」という意味ではなく、その時の関心が別のところに向いているだけかもしれません。たとえば幼稚園や学校での出来事が印象的だった日には、友だちや先生を描くこともあります。
子どもはその日の感情や記憶の中から描きたい登場人物を自然に選びます。ですから「描かない=問題」と捉えるのではなく、子どもが何を感じ、何を大切にしているのかを知る手がかりとして見てあげるのがおすすめです。
もし、いつも同じ構図で兄弟が小さく描かれる・描かれないなどが続くようなら、さりげなく日常の中で安心を積み重ねてあげることが大切です。「最近どうだった?」「一緒に遊べてうれしかったね」といった会話が子どもの心にやさしく届きます。
絵には言葉にならない気持ちがたくさん込められています。親がそのサインをやさしく受け止めることで、絵でわかる子どもの気持ちがより深く見えてくるでしょう
絵本で“怒りの気持ち”をやさしく伝える
感情表現が苦手な子どもにも寄り添える1冊。
「怒り」「かんしゃく」をテーマに、心の整理のしかたをわかりやすく描いています。
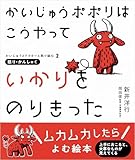
かいじゅうポポリは こうやって いかりをのりきった
(かいじゅうとドクターと取り組むシリーズ2)
- 怒りやかんしゃくを理解しやすいストーリー展開
- 子どもが感情を言葉にする練習にも◎
- 親子で一緒に「気持ちの整理」を話し合える
絵を通して“安心”を育てる親の関わり方
絵はあくまで「今の気分」を切り取ったもの。
昨日はママを大きく描いたけど、今日はパパと楽しく遊んでいる…そんなこともよくあります。
絵と日常の様子を合わせて見ることが大切です。
「どうしてこう描いたのかな?」と一緒に考えることが、子どもにとって安心につながります。
【年齢別】絵でわかる心の発達と特徴

子どもの絵は年齢とともに変化します。
・幼児期:感情が大きさや色に出やすい
・小学校低学年:構図や家族全体の関係性が見え始める
・小学校高学年:個々の特徴や関係性を細かく描くようになる
成長とともに絵の意味も変わるため、年齢に応じた視点で受けとめることが大切です。
Q&A:家族の絵からわかる子どもの気持ち
子どもの絵には、そのときの心理状態や安心感がさりげなく表れます。ここでは「家族の絵」に関してよくある質問をもとに、描かない・大きく描くときの意味や、親の接し方について解説します。
Q:子どもが家族の絵にお父さんを描かないのはなぜ?
A:単に印象に残っていない、遊ぶ時間が少ない、描くスペースが足りないなどの理由が多く、「描かない=嫌い」ではありません。家族の絵を描かない時期があっても、心配しすぎる必要はありません。
Q:お母さんがすごく大きく描かれていて心配です。
A:「お母さんが大きい絵」は「大好き」「頼りたい」という安心感のあらわれです。子どもの絵の心理は一面的に判断せず、日常の関わりの中で気持ちを受けとめることが大切です。
Q:毎回同じような構図や色で描くのは大丈夫?
A:繰り返し同じ構図を描くのは、子どもにとって“安定”を確認しているサインのこともあります。子どもの絵の読み解き方として、変化よりも「今、この子が安心できているか」を見守る視点が大切です。
🔍 絵から読み取れる“気持ちサイン”チェック
- お母さんがいつも大きく描かれる(安心感・愛着のサイン)
- お父さんや兄弟が描かれないことがある(関わり方の違いが反映)
- 家族の誰かの顔が怒っている・色が濃い(その時の感情表現)
- 毎回同じ構図・色づかいで描く(安定を求めているサイン)
→ どれかに当てはまっても「悪いサイン」とは限りません。
子どもの絵の心理を読み取るときは、日常の出来事や感情の一部として受けとめましょう。
まとめ:子どもの絵を通して安心を見つけよう
子どもの絵を読み解くときは、「何を描いたか」よりも「どんな気持ちで描いているか」を見守る姿勢が大切です。
「家族の絵を描かない」「お母さんが大きい」などの特徴も、子どもの心の発達や安心感のバランスが反映されているだけのことが多いです。
絵でわかる子どもの気持ちは、成長とともに変化します。
心配になったときは、子どもの絵の心理を一緒に読み解きながら、「どう感じているのかな?」と穏やかに声をかけてみましょう。
日常の関わりの中に、小さな安心が積み重なっていきます。
家族の絵には、そのときの気持ちや関心が反映されています。
「描いてくれて嬉しいな」「家族のことを思ってくれてありがとう」と伝えるだけで、子どもは安心できます。
家族の絵は親子の会話のきっかけにもなります。ぜひやさしい気持ちで受けとめてみてください。
この記事のまとめ
- 家族の絵には、子どもの安心や甘えの気持ちが表れやすい
- 「お母さんが大きい」は「大好き」「安心」のサイン
- 「お父さんを描かない」は「会いたい」「印象が薄い」場合も
- 絵だけで判断せず、日常の言葉や行動と合わせて見ることが大切
\あわせて読みたい人気記事/
🔗あわせて読みたい:「子どもの絵に顔がない?心理状態のサイン」
描いた絵を飾って楽しめるアイテム

Haojiaho アートフレーム 12個セット 子供の絵 展示用 フォトフレーム
透明保護フィルム+壁掛け用粘着シート付きで、子どもの作品を安全に飾れます。軽量・厚紙製でおしゃれに展示可能。家庭や教室でも活躍。
デジタルでの手書きやイラストに挑戦してみたい方は、ぜひXP-PENペンタブレットをチェックしてみてください。
お手頃価格で高性能、ペイントソフトもセットで届くので、今日からすぐにお絵描きスタートできます。
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
このブログはPRを含みます
こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです。
このブログでは、子どもの絵から心理を読み取り、心の成長や表現力を親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。
「子どもの絵で心を読む専門サイト」として、日々の子育てに役立つ情報をお届けします。