子育ての中で「叱らないと伝わらない」「優しく言うだけじゃダメなのでは」と感じる瞬間は少なくありません。
しかし心理学の研究では、繰り返される“叱責”が子どもの自己肯定感を下げ、挑戦する意欲や安心感を奪ってしまうリスクがあると指摘されています。
本当に必要なのは、子どもを傷つけずに成長へと導く関わり方。
つまり、“叱る”のではなく、“導く”言葉です。
この記事では、心理学の知見をもとに、日常でできるちょっとした声かけの工夫をご紹介します。
この記事の内容
なぜ「叱る」が子どもの自己肯定感を下げるのか?
「叱る」こと自体が悪いわけではありません。
危険な行動を止めたり、社会のルールを教えたりするために必要な場面もあります。
しかし、繰り返し強い口調で「なんでできないの?」「どうして言うことを聞かないの?」と責められると、子どもは「自分はダメな人間なんだ」と感じやすくなります。
心理学でいうラベリング効果が働き、親からの言葉をそのまま「自分の価値」として受け止めてしまうのです。
すると、失敗や挑戦を避けるようになり、自己肯定感の低下につながっていきます。
💡 一口メモ:ラベリング効果
「ラベリング効果」とは、人にラベル(評価や性質の言葉)を貼ることで、その人の行動や自己認識に影響を与える心理現象のことです。例えば、「あなたはやさしい子ね」と言われた子は、やさしい行動をとろうとすることがあります。
声かけひとつで子どもの自己肯定感や行動に変化をもたらせる、身近で強力な心理効果です。
「叱る」から「導く」へのシフト
ではどうすればいいのでしょうか?
大切なのは「否定する言葉」ではなく、「成長につながる問いかけ」に変えることです。
✨ 具体的な声かけの工夫
NG例:「どうしてできないの?」
OK例:「どこがむずかしかった?」
NG例:「早くしなさい!」
OK例:「あと5分で出発だよ。準備どう進める?」
NG例:「また失敗したの?」
OK例:「次はどうしたらうまくいきそう?」
こうした問いかけは、子どもが「考えるきっかけ」を与えられるだけでなく、「自分でできる」という感覚を積み重ねることにつながります。
それこそが、自己肯定感を守り、育てるための大切なステップです。
親だって完璧じゃなくていい
もちろん、毎回冷静に「導く言葉」を選べるとは限りません。
仕事や家事で疲れているとき、イライラして強く言ってしまうのは自然なことです。
大切なのは「叱ってしまったあと」どう関わるか。
「さっきは強く言いすぎちゃったね。でもあなたができるって信じてるよ」とフォローを入れるだけで、子どもの心は安心し、信頼関係を取り戻すことができます。
「つい言ってしまいがち」なNGフレーズチェックリスト
忙しいとき、余裕がないときほど、つい口から出てしまうフレーズがあります。
まずはご自身がよく使っている言葉がないか、チェックしてみてください。
「早くしなさい!」
「なんでできないの?」
「また同じことして!」
「ちゃんとしなきゃダメでしょ」
「いい加減にしなさい」
これらの言葉が悪意で出ているわけではありません。
むしろ「子どもにちゃんとしてほしい」「困らないようにしてあげたい」という思いから出てくるものです。
でも、心理学的には“叱責”として伝わりやすく、子どもの自己肯定感を削ってしまうリスクがあるのです。
年齢別「導く声かけ」例
子どもの発達段階によって、響く言葉のかけ方は少しずつ変わります。
年齢ごとに意識したいポイントを見てみましょう。
👶 幼児期(2〜6歳)
- 「ジュースこぼれちゃったね。どうすればよかったかな?」
- 「あとで一緒に拭こうね」
👉 感情を否定せず、「行動を学ぶ機会」として声をかける。
👦 小学校低学年(6〜9歳)
- 「ここ、どこがむずかしかった?」
- 「次はどうやったらうまくいくと思う?」
👉 自分の考えを言葉にする練習をサポートする。
👧 小学校高学年(10〜12歳)
- 「どう工夫したらもっとできそう?」
- 「失敗しても挑戦したこと自体がすごいよ」
👉 自分で試行錯誤する力を育てると同時に、努力を認める。
🧑 思春期(中学生以降)
- 「あなたの意見を聞かせてほしい」
- 「どういうサポートがあったらやりやすい?」
👉 自立を意識した関わり方で、対等に「一人の人」として尊重する。
まとめ
- 繰り返される叱責は、子どもの自己肯定感を下げるリスクがある。
- 「叱る」から「導く」へシフトすることで、子どもは安心して挑戦できる。
- 年齢や発達に合わせた声かけで、子どもの考える力と自信を育てられる。
- 親も完璧でなくてよい。叱ったあとにフォローするだけで十分に関係は修復できる。
小さな声かけの積み重ねが、子どもの「自分は大丈夫」という心の土台になります。
今日から少しずつ、“叱る”より“導く”声かけを意識してみませんか?
🌸 同じ気持ちのママへ…
子育てしていると、
「また強く言っちゃった…」
「もっと優しく伝えたいのに」
そんなふうに落ち込むこと、ありませんか?😢
実は私も同じで、毎日の声かけに悩んでいました。
でも “伝え方コミュニケーション講座” を知ってから、
少しずつ子どもとの会話が楽になったんです🌸
- 自宅でスマホから動画を見られる
- 今日からすぐ使える声かけのヒントが学べる
- 子どもの自己肯定感がぐんぐん育つ
「もっと子どもに寄り添いたい」
「イライラより笑顔でいたい」
そんなママにぴったりです💛
🔗 この記事を読んだ人におすすめの関連記事
▼こちらもおすすめです
「気持ちの切り替え」で困ったときに、こちらも参考にどうぞ:
- 子どもをスムーズに動かす方法
- なんでもイヤ!な時期の子どもの心理
- 着替えたくない!イヤイヤ期に着替えを嫌がる子どもへの対応法
- 育児書通りでも赤ちゃんが泣く理由
- 2歳児の謎行動にツッコミながら学ぶ!育児あるある&成長サポート集
\こんな記事もよく読まれています/
- 黒い絵ばかり描く子、何を感じているの?
- 包丁や血と同じくらい相談が多いのが“パパがいない絵”です✅「パパがいない絵」を描いたら気にしたほうがいい?
- うちの子、落ち着きがない?絵と行動から見えること
- 子どもの乱暴な言葉遣いが気になったら読む記事
- もし“目を描かない子”についても気になるならこちら✅目を描かない子ども、その心理とは?
🌟 おうち時間でプログラミングを楽しめる教材
興味を広げ、学びを深める Z会プログラミングシリーズ 。家庭で安全に取り組めるから、忙しいママ・パパも安心です。
➡ 資料請求するとプログラミング学習に役立つ情報誌プレゼント✨
|
ホーム » 「叱る」より「導く」へ。心理学でわかる子どもの自己肯定感を守る言葉
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






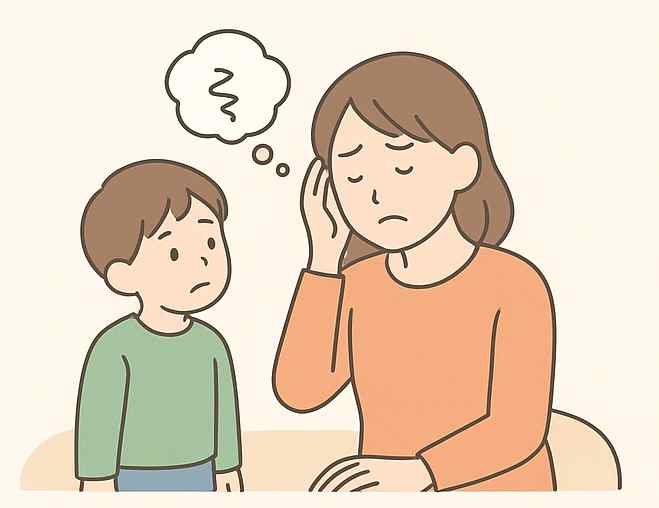
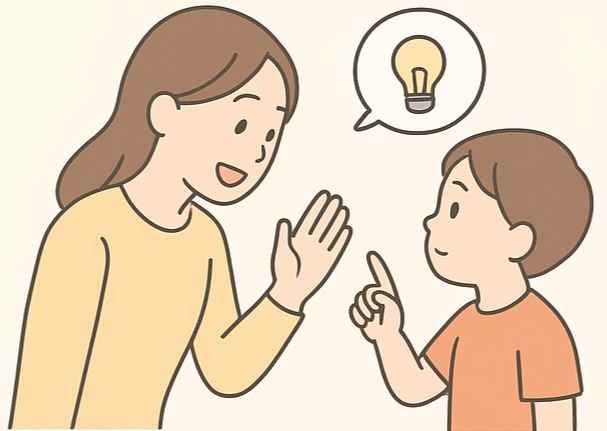

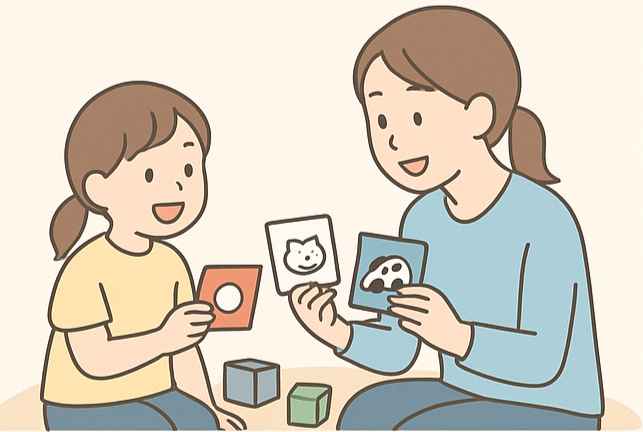





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a21f051.8e280e79.4a21f052.b4a891df/?me_id=1381750&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fluckyspread%2Fcabinet%2F07240546%2F10248259%2Fimgrc0078419063.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




