この記事の内容
お絵かきって本当に必要?そんな疑問に答えます
「うちの子、最近ずっと絵ばかり描いてるけど…勉強しなくて大丈夫?」
「ゲームやYouTubeに興味を示さず、お絵かきばかり。逆に心配…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。
実は“絵を描く”という行為には、子どもの脳や心を大きく育てる力があるんです。
お絵かきはただの遊びではなく、将来につながる「学びの基礎トレーニング」。
今回は「お絵かきの効果とメリット」を、できるだけわかりやすく解説していきます。
🧠 お絵かきで脳が鍛えられる理由|集中力・記憶力との関係
絵を描くとき、脳のさまざまな部分が同時に働いています。

- 想像力を使ってイメージする(右脳)
- 手を動かす(運動野)
- 形や空間を捉える(視覚野)
- 色を選ぶ(感情や記憶ともつながる)
まり、お絵かきは「脳の総合エクササイズ」。
机に向かって計算ドリルをするのと同じくらい、いやそれ以上に脳をフル稼働させているんです。
特に子どもは脳の回路が発達途中。絵を描くことは、自然とネットワークを広げ、集中力や観察力を伸ばしていきます。
💡「言葉にできない気持ち」を描く力

子どもにとって言葉で気持ちを整理するのは難しいこと。
でも、絵なら自然と心の中を表現できます。
- 淋しい気持ち → ひとりぼっちの絵を描く
- 怒っているとき → 強い線や赤い色を使う
- 楽しいとき → カラフルでにぎやかな絵になる
大人にとっての「日記」のように、絵は子どもの心を映し出す鏡。
描くことで安心できたり、自分の気持ちを消化したりすることができます。
🧘♀️ マインドフルネス効果もある
絵を描くとき、子どもは「今この瞬間」に没頭します。
余計なことを考えず、手と目と心を集中させる時間は、まさに小さなマインドフルネス。
夢中で描き終わったあと、なんだかスッキリしている様子が見られるのは、脳や心のストレスがリセットされているからなんです。
🌱 お絵かきで育つ「非認知能力」とは?
「で、実際にうちの子にはどんな良いことがあるの?」と思う親御さんのために、具体的に挙げてみます。

- 集中力がつき、勉強や作業への持久力が伸びる
- 自分の気持ちを表現する力が育つ → 人間関係にもプラス
- 色や形に敏感になることで観察力が高まる
- 「やりきった!」という達成感で自己肯定感が育つ
つまりお絵かきは、ただ絵が上手になるためだけじゃなく、
「生きる力の土台」を育ててくれる活動なんです。
🔗絵を描くと脳にいいってホント?子どもの心と発達にも効く“お絵かきパワー”とは
この本、子どもの絵の見方が一気に深まります!
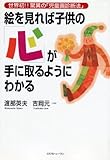
絵を見れば子供の心が手に取るようにわかる: 世界初驚異の児童画診断法
「子どもの絵ってどう読めばいいの?」という親御さんの不安にこたえてくれる一冊。 発達段階・心理状態・かかわり方のヒントまで、やさしく具体的に解説されています。
🎨 絵を描きたがらない子の心理と対処法
「さあ、描いてみよう!」と画用紙とクレヨンを渡しても、子どもの反応はさまざまです。
- 「えー、めんどくさい」
- 「何描いたらいいかわからない」
- そもそも興味を示さない
こんな姿を見ると、親としてはちょっとガッカリしますよね。かといって、どう促せばいいのかもよくわからない。
でも、安心してください。子どもが自然に描きたくなるコツは、環境づくりと声かけにあります。
🔗子どもがお絵かきに興味を持たないときの対処法|自然に楽しむ3つのステップ
✨ 1. お絵かきの環境を工夫する
ただ机に紙とクレヨンを置くだけでは、刺激が少なくて子どもは動きません。
「描きたい!」と思わせる工夫がポイントです。

おすすめの工夫
- 特別感のある紙
- 大きな模造紙やロール紙を用意すると、自由に描ける解放感があります。
- 描きやすい画材
- 太めのクレヨンやマーカー、色鉛筆は小さな手でも扱いやすいです。
- 描いたら飾れる場所を作る
- 冷蔵庫や壁に「ギャラリー」を作ると、子どもは自分の作品を見てもらえる喜びを感じます。
- 音や光の工夫
- 好きな音楽を流す、明るい場所で描かせるだけでも集中力がアップします。
✨ 2. 親の声かけでやる気スイッチを押す
「自由に描いていいよ」だけでは、意外と動かない子もいます。
ポイントは「遊び心」と「ちょっとしたテーマ」を加えること。
🔗子どもの想像力を伸ばす!おとぎ話の続きを描くお絵かきアイデア
🔗お絵かきがもっと楽しくなる!魔法のアイスで親子の時間を彩ろう
声かけの例
- 「○○くんのヒーローって、どんな顔してる?」
- 「今日は雲が面白い形だよ。どんな形に見えるかな?」
- 「ママと一緒に、変な生き物を描いてみよう!」
- 「今日の気分を色だけで描いてみるのも面白そうだね」
テーマや問いかけがあると、子どもは自然と手を動かします。
大事なのは「描く楽しさ」を優先すること。「上手に描くこと」や「正しい形」は気にしなくて大丈夫です。
✨ 3. 最初におすすめの簡単テーマ
子どもが描きやすく、興味を持ちやすいテーマをいくつか用意しておくと、自然に描き始めます。
- なぞなぞ系:「空を飛べる動物を描いてみよう」
- 家族や友だち:「ママがヒーローだったら、どんな服?」
- 気持ち表現:「今日の気分を色だけで描こう」
- ごっこ遊び:「ピザ屋さんごっこ!どんなトッピングにする?」
遊び感覚で始めることが、何より子どもに響きます。
🔗「みんなが幸せになる世界を描こう!」— 思いやりと想像力を育むお絵かきワーク
🌱 親ができるちょっとした工夫の効果
- 「大きな紙に自由に描く」 → 発想力と空間把握力アップ
- 「テーマや問いかけをする」 → 想像力と自己表現力が育つ
- 「描いたら飾る」 → 達成感と自己肯定感が育つ
これだけの工夫で、子どもは自然と「描きたい!」という気持ちに変わります。
ポイントは「親が楽しそうに関わること」。一緒に描いたり、驚いたり喜んだりするだけで、子どものモチベーションはぐっと上がります。
次は、お絵かきの具体的なメリットをさらに掘り下げ、子どもにどんな力がつくのかを実例付きで紹介します。
💡 ここまでのまとめ
- ただ紙とクレヨンを渡すだけでは反応しない
- 環境を工夫することが大事
- 声かけやテーマで自然に描きたくなる
- 小さな達成感や特別感で子どもの自己肯定感が育つ
✏️ 絵で伸びる6つの力|家庭で伸ばせる“生きる力”
「うちの子、ただ絵を描いているだけ…?」
と思っている親御さんも多いかもしれません。
でも、実は絵を描くことで子どもの脳と心はたくさんの力を育てています。
今回は「具体的にどんな力がつくのか」「日常でどんな変化が現れるか」を解説します。

🧠 1. 脳の働きが活性化する
絵を描くときは、頭の中で「イメージを作る → 手で表現する → 色や形を選ぶ」という動作を連続で行います。
- 想像力:頭の中のイメージを形にする力
- 観察力:モノや人の特徴に気づく力
- 集中力:「今ここ」に集中して描く力
- 空間認識力:配置やバランスを考える力
つまり、絵を描くことは脳の同時並行トレーニング。
ゲームや動画と違い、自分で考え、選び、作る作業が脳をフル稼働させます。
💡 2. 感情の整理と自己表現
子どもは言葉で気持ちをうまく伝えられないことがあります。
でも絵なら自然と心の中を表現できます。
絵で表れる感情の例
- さみしい → ひとりぼっちの世界を描く
- 怒っている → 力強い線や赤色を使う
- 楽しい → カラフルでにぎやかな世界を描く
こうした表現は、子どもが自分の気持ちを整理する助けになります。
「描くことで安心できる」「気持ちをコントロールできる」という心理的メリットもあるんです。
🔗子どもの絵に出る心のサイン|入園・進学・転校など環境の変化との関係
✋ 3. 自己肯定感と達成感が育つ
絵を描き終えたときの「できた!」という体験は、子どもにとってとても大きな自信になります。
- 「自分で考えて表現できた」 → 自己肯定感アップ
- 「描いた絵を見せたら褒めてもらえた」 → 他者とのコミュニケーション力アップ
- 「次はもっと面白く描こう」 → 挑戦意欲や創造力の向上
小さな成功体験の積み重ねが、子どもの成長につながります。
🌱 4. 日常で見られる変化の具体例
- 描く前よりも集中力が長く続くようになる
- 色や形に敏感になり、観察力が育つ
- 自分の気持ちを少しずつ言葉で伝えられるようになる
- 学校や習い事で主体的に取り組む姿勢が増える
こうした変化は、遊び感覚で始めたお絵かきから自然に育まれるんです。
💡 まとめ:絵はただの遊びじゃない
- 脳の働きを活性化する総合トレーニング
- 気持ちを整理する心のサポート
- 自己肯定感と挑戦意欲を育てる達成感
- 日常生活での集中力や観察力、主体性につながる
が「また描いてるの?」と思うその時間こそ、
子どもにとっては“心と脳の栄養タイム”。
家庭でできる!子どもが夢中になるお絵かき環境と画材
「うちの子、せっかくお絵かきしてほしいのに、興味を示してくれない…」
そんな親御さんも多いと思います。
でも、ちょっとした工夫とアイテム選びで、子どもは自然に描きたくなります。
今回は、家庭で用意できる具体例と夢中になるコツを紹介します。
✨ 1. 描きやすい画材を選ぶ
子どもが扱いやすく、色や感触で楽しめる画材を選ぶことがポイントです。

おすすめ画材
- クレヨン(太め)
- 小さな手でも持ちやすく、力加減で色の濃淡が出せます。
- 色鉛筆
- 細かい描写や色の混ぜ方を体験でき、表現の幅が広がります。
- 水性マーカー
- 発色がよく、線がはっきり出るので達成感を味わいやすいです。
- 水彩絵の具
- 色の混ざり方を観察でき、創造力や実験心が育ちます。
- ポスターカラーやパステル
- 手や筆で塗れる楽しさがあり、手指の感覚も育ちます。
※大事なのは「上手に描くため」ではなく、「自由に表現できること」です。
お家でも外でも“描きやすい環境”を作るおすすめアイテムです!
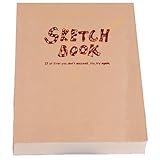
fogman スケッチブック 紙質 おしゃれ かわいい アート 120枚 絵画 デッサン 持ち運び (A4, ベージュ)
とにかく紙質が良くて、子どもが描くときにストレスが少ないタイプ。 しっかり枚数もあるので、“気にせずたくさん描ける環境づくり”にぴったりです。

IKEA/イケア MALA ポータブルお絵描きケース(604.598.92)
外出先でも“すぐ描ける”環境をつくれる便利アイテム。 収納と作業スペースが一体化しているから、散らかりにくく親としても助かります。

こどもちゃれんじ 幼児用 色鉛筆 三角軸 太軸 ケース付き 12色 ぺんてる共同開発
幼児が“正しく握りやすい”三角軸。 力加減がまだ不安定な子でも滑りにくく、しっかり発色するので描く意欲が高まりやすいです。
🎨画材別!お絵かきで広がる遊びアイデアコラム
おうちでお絵かきタイムをもっと楽しくするなら、画材選びと遊び方を少し工夫するだけで、子どもの集中力や表現力がぐっと伸びます。
ここでは、代表的な画材ごとに「こんな遊びができる」「こんな遊び方が子どもに響く」をまとめました。
1. 太めクレヨン

ぺんてる クレヨン 水でおとせるふとくれよん GWM1-12 12色
特徴:小さな手でも握りやすく、力の入れ具合で色の濃淡を楽しめる
遊びアイデア
- ぬりえにワークに幅広く使える。かすれ具合がまた味を出してくれる。
- 線の強弱で表現遊び:強く塗ると濃く、軽く塗ると薄くなることを試す。力加減で感情表現も体験できる
- 大きな紙でぐるぐるお絵かき:部屋の床に紙を広げて、自由に線や形を描く。体全体で描く楽しさが味わえる
ポイント:大きく描けることで解放感が生まれ、初めての子でも「描くこと=楽しい」と感じやすいです。
2. 色鉛筆

HIFORNY 80色鉛筆セット 大人用 塗り絵 72色 3色のスケッチブック付き 大人用塗り絵 シャープペンシル 0.5 無色ブレンダー
特徴:細かい描写や色の混ぜ方を体験できる
遊びアイデア
- 色の重ね塗り実験:赤と青を重ねて紫になるなど、色の変化を観察
- 模様・マンダラ描き:小さなパーツや繰り返し模様を描く遊び。集中力や手先の器用さが育つ
- キャラクター作り:自分だけの動物やヒーローを細かく描いてストーリーを作る
ポイント:塗りや線で微調整できるので、表現の幅を感じやすく、観察力や集中力のトレーニングにもなります。最近は塗り絵で図鑑を作るタイプのものもあり、恐竜好きな子や動物好きな子におすすめ。
3. 水性マーカー

サクラクレパス 洗たくでおとせるふとふとマーカー 6色セット MK-L6
特徴:発色がよく、線がはっきり。描くとすぐに目に見える
遊びアイデア
- お絵かき宝探し:線で道を描いて、キャラクターやボールをゴールまで導く迷路作り
- 色あてゲーム:テーマに合わせて「青だけで描いてみよう」「赤と黄色だけで表現してみよう」
- スタンプ遊び:ペットボトルの蓋や紙コップで形を押して、マーカーで色を塗る
ポイント:線がはっきり見えるので、成功体験を感じやすく、「描いた!」という達成感が味わえます。
4. 水彩絵の具

クレヨラ (Crayola) ボトル絵の具 10色セット 水で簡単に落とせる クラシック 541205 正規品
特徴:色の混ざり方を観察して実験心が育つ
遊びアイデア
- 色水実験:水の量や色の組み合わせで変化を楽しむ
- にじみ絵:濡れた紙に色を置いて広がる様子を観察。偶然できる模様にワクワク
- 空・海・雲の世界を描く:淡い色のグラデーションで自然の風景を表現
ポイント:色の広がりや変化が目で見えるので、子どもは「どうなるかな?」と試す楽しさを体験できます。
5. ポスターカラー・パステル

ぺんてる パステル GHSR-20 20色
特徴:手で塗る楽しさで手指の感覚も発達
遊びアイデア
- 手でぐりぐり塗り絵:紙いっぱいに手のひらで色を広げる
- 指で混色遊び:赤と青を混ぜて紫を作るなど、触覚と色彩感覚を同時に育てる
- テクスチャー遊び:紙に塩や砂を混ぜて独特の模様を作る
ポイント:触感を使うことで感覚が刺激され、手指の器用さだけでなく、感性や表現力も同時に伸びます。
✨ 2. 描く場所や環境を工夫する
環境次第で、子どものやる気は大きく変わります。

家庭での工夫例
- 広めの作業スペース
- ダイニングテーブルに大きな紙を広げるだけでも、自由に描く開放感があります。
- 飾れる場所を用意
- 冷蔵庫や壁に貼る「ギャラリー」を作ると、描くモチベーションが上がります。
- 明るい場所で描く
- 光が入る場所やお気に入りの席で描くと、集中しやすくなります。
- 道具は出しっぱなしにせず、見えるところに置く
- 「描きたいときにすぐ手に取れる」状態が理想です。
✨ 3. 親の声かけで自然に手を動かす
子どもが描きたくなるのは、声かけ次第でも変わります。
具体的な声かけ例
- 「今日は雲が面白い形だよ。どんな形に見えるかな?」
- 「ママと一緒に変な生き物を描いてみよう!」
- 「今日の気分を色だけで描いてみる?」
- 「ヒーローの顔を描いてみよう。どんな服かな?」
ポイントは「遊び心」と「問いかけ」です。
テーマがあると手が動きやすく、描き始めるきっかけになります。
🌱 4. 小さな成功体験を作る
- 描き終えた絵を褒める
- 作品を飾る
- 「次はどんな絵にしよう?」と次回につなげる
こうした積み重ねが、自己肯定感や表現力、集中力につながります。
お絵かき習慣で「伸びているサイン」チェックリスト
- 描く時間が長くなっている
- 色や形のバリエーションが増えている
- 「見て見て!」と伝えたがる
- ストーリーをつけて話す
- 描くことを自分から選ぶ
これらが見られたら、お絵かきを通して「思考力」「自己表現力」「集中力」がしっかり育っています。
よくある質問
Q. 絵ばかり描いていて勉強しないのは大丈夫?
A. 問題ありません。お絵かきで育つ集中力や思考力は、後の学習の基礎になります。
Q. 下手な絵を描いたとき、指摘していい?
A. 正解・不正解を言わず「この色きれいだね」と感想を返すのが◎です。
💡 まとめ:家庭でできる“お絵かき習慣”の作り方
- 扱いやすい画材を用意する
- 描きやすい環境を整える
- 声かけで興味を引き出す
- 小さな達成感を積み重ねる
この4つのポイントで、子どもは自然に「描きたい!」と思えるようになります。
遊び感覚で始めたお絵かきが、実は脳と心を育てる大切な時間になるのです。
ホーム » 絵ばかり描く子、放っておいて大丈夫?|お絵かきが育てる“生きる力”
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。







