このブログはPRを含んでいます

ゲームばかりしている子どもたち。今どきはこれが普通?
最近、うちの子もゲームばっかりやってるんですよね…。
でも、これってみんなの家でも同じですか?
「他の家もそうだから、うちだけじゃないんだ」と思いたい反面、なんだか不安になる気持ちもありますよね。
「やりすぎじゃないか?」とか「もっと外で遊んでほしいなぁ」とか、ついつい口に出しちゃう。
でも、ちょっと待って。
実は今、ゲームって「子どもの遊び」としてはごく普通のものなんです。というか、今どきの子どもたちにとっては、ゲーム=遊びと言っても過言ではないかもしれません。それも、ゲームの種類が多すぎて、親としてはどれを許容していいのか、どこで線引きすればいいのか、正直わからなくなるんですよね。
でも、ゲームを「やめさせたい」と思う親の気持ちもめっちゃわかります。だって、ゲームばかりしていると、どうしても「学業が心配」「健康が心配」「人間関係や言葉遣いが心配」なんて不安が湧いてきますもん。だから、今日はそのあたりを一緒に考えてみましょう!

時代背景とテクノロジーの進化、そして現代の子育て事情
「昔は外で遊んでいたのに…」
時代は変わりましたね。
特にコロナで自粛期間もあり、ゲームにハマる子も増えたのではないでしょうか。
今の子どもたちにとっては、ゲームは単なる娯楽じゃなくて、友達と繋がる手段でもあり、想像力を膨らませるツールでもあります。
例えば、オンラインゲームで友達と協力プレイをしたり、ゲーム内で冒険をしたり。

これって、リアルの世界では経験できないようなことを体験できるチャンスなんですよね。だから、昔の「外で遊ぶ」遊びとはまた違う形で、今の子どもならではのコミュニケーションスキルを身につけていってるんですね。
ゲームは単なる「暇つぶし」から、教育的要素や学びのツールにまで進化しています。たとえば、プログラミングを学べるゲームや、英語や数学の力を伸ばせるゲームだってあります。
でも、「ゲーム=時間の無駄」ではないけど、過度にハマると問題になるので気を付けたいところ。
ゲームばかりでも大丈夫?みんなも悩んでる
さて、実際に「ゲームばかりしている子どもたち」って、今、どれくらい増えているのでしょうか?ある調査によると、小学生の約1割が毎日ゲームをしているというデータもあるんです。
ただ、ゲームの時間が長くなりすぎると、やっぱり健康や学業に影響が出ることもあります。子どもがゲームを長時間プレイしていると、寝る時間が遅くなる、運動不足になる、集中力が低下する…など、ちょっと心配な点が出てきます。
ゲームが悪いわけではないが、やりすぎには注意が必要
ゲーム自体は悪いものではありません。むしろ、適切に使うことで楽しい時間を過ごしたり、考える力や反射神経を養ったりすることもできます。しかし、問題となるのは「やりすぎ」と「不適切な使い方」です。特に、子どもたちがゲームにのめり込みすぎると、こんなことが問題になってきます。
1. ゲームのやりすぎで勉強や生活習慣が乱れる
ゲームにハマるあまり、勉強やスポーツなど他の大切なことをおろそかになることが・・・。これが続くと、学業成績が下がったり、睡眠時間が削られて健康に悪影響が出ることも考えられます。
こんなことありませんか?
- ゲームに夢中になりすぎて、宿題を後回しにしてしまう。
- ゲームを長時間しているため、夜更かしが習慣になり、翌日の学校に支障をきたす。
2. ゲーム内でのモラルやマナーの欠如
オンラインゲームや対戦型のゲームでは、他のプレイヤーとのやりとりが重要です。しかし、ゲーム内で暴言や煽り行為をしてしまう子どもが増えています。これが習慣になると、現実世界でもコミュニケーションに問題が生じることがあります。

たとえばこんなこと、ありませんか?
- 他のプレイヤーに対して暴言を吐いたり、いじわるな行為をしてしまう。
- 負けるとすぐにゲームを投げ出したり、相手を責めたりする。ドアをバターンと閉めてこもっちゃう。
3. ゲームの依存リスク
ゲームは楽しい反面、依存症になりやすいというリスクもあります。特に、ゲームを長時間プレイすることで、「ゲームなしでは気が済まない」「ゲームが全てになってしまう」といった状態に陥ることがあります。

こんなことあるある!
- ゲームが終わらないと気が済まず、他のことを後回しにする(食事やお風呂、友達との遊びなど)。
- セーブできるところまで待って!が口癖に。
- 休みの日にずっとゲームをして、家族との時間を楽しめない。
4. 課金問題
最近のゲームでは「ガチャ」や「アイテム課金」といったシステムがあり、子どもが知らず知らずのうちにお金を使ってしまうケースがあります。これは親が知らないうちに、無駄にお金を使ってしまう原因になるため、しっかりと管理が必要です。
課金アイテムがほしい!これもよく聞くワード
- ゲーム内でレアアイテムを手に入れるために、無断で課金してしまう。
- ゲーム内での「課金=強さ」や「課金アイテム=勝利」という考え方が定着してしまう。
親としてできること:ルールや価値観を一緒に作る
1. ゲームの時間制限を決める
子どもがゲームに夢中になりすぎないように、1日のゲーム時間に制限を設けましょう。たとえば、「1日1時間まで」や「宿題が終わってから」などのルールを決めて、実行できるようにします。

実践例:
- 毎日、ゲームをする前に「1時間だけね」と言って、時間を計測する。
- ゲーム時間の後に「おやつの時間」や「家族との時間」を設けることで、バランスを取る。うちの子の場合は、宿題を終わらせてからゲームにする方が比較的ゲームも楽しくできるようです。
2. ゲームの内容を確認し、適切なゲームを選ぶ
子どもがプレイするゲームの内容を確認し、年齢に合ったものを選びましょう。暴力的な内容や過激な表現があるゲームは避け、教育的な要素を取り入れたゲームや、友達との協力プレイを楽しむゲームがおすすめ。
実践例:
- ゲームを購入する前に、レビューや評価を確認して、適切なゲームかをチェックする。
- 一緒にゲームをすることで、どんな内容かを把握し、会話をしながらプレイする。
🌸 新しい習い事のかたち
最近では、将棋やピアノのように、「ゲームを習い事」として学べるサービスも登場しています。
フォートナイトやマイクラなどの人気タイトルを、全国大会・世界大会に出場経験のあるトレーナーからオンラインで学べるのが特長です。
ただ遊ぶだけでなく、集中力や情報処理力を伸ばすトレーニングとして注目されています。
外に出にくい時期でも、自宅から安心して参加できるのは嬉しいポイントですね。
まずは気軽に体験会から試してみませんか?
年齢別人気ゲーム紹介
1. 3〜5歳:幼児期(未就学児)
この時期の子どもはまだゲームに対する理解が浅く、視覚的に刺激が強いシンプルなゲームが人気です。ゲームは教育的要素が強いものが好まれます。
人気のゲーム:
- 「ぴよちゃんのどこかな?」(スマホ・タブレット用)
- 絵本のようなゲームで、親子で一緒に遊べる。色や形、動物を覚えるための簡単なゲーム。
- 「スーパーマリオラン」(スマホ用)
- 簡単な操作で楽しめるマリオシリーズのゲーム。視覚的にカラフルで、簡単なステージが子どもでも楽しめる。
- 「はじめてのゲーム」(Nintendo Switch)
- 幼児向けの教育ゲーム。数字や色、形を覚える内容が多く、親子で一緒に学びながら遊べます。
特徴:
- 短時間で終わるゲーム
- シンプルな操作と視覚的な刺激
- 教育的要素(色、数字、形、動物など)
2. 6〜8歳:小学生低学年
小学生の低学年では、簡単なルールのあるアクションやパズルゲームが人気です。また、ストーリー性があり、少し複雑な操作ができるゲームにも興味を持ち始めます。
人気のゲーム:
- 「スーパーマリオオデッセイ」(Nintendo Switch)
- 冒険をしながら世界を探索するゲーム。操作も簡単で、家族や兄弟姉妹と一緒に遊べる。
- 「Minecraft」(PC・スマホ・Nintendo Switch)
- ブロックを使って世界を作ったり探索したりするサンドボックスゲーム。創造力が養われ、低学年でも簡単に楽しめる。
- 「どうぶつの森」(Nintendo Switch)
- ゆったりとした生活を楽しむゲームで、アイテム集めや村の発展など、短時間でも楽しめる内容。
特徴:
- 冒険や探索をテーマにしたものが人気
- ゲーム内での目標達成感
- マルチプレイヤー機能で友達や家族と遊べる
3. 9〜11歳:小学生高学年
この時期には、少し複雑なストーリーや戦略が必要なゲームが人気です。ゲームに夢中になり、長時間遊ぶ子も増えます。
人気のゲーム:
- 「フォートナイト」(PC・PS4・Nintendo Switch)
- バトルロイヤルゲームで、友達と一緒に対戦する楽しさが魅力。無料でプレイできる点も人気の理由。
- 「ポケモンソード・シールド」(Nintendo Switch)
- ポケモンを育て、バトルで戦うRPG。キャラクターやストーリー性が魅力で、長期間楽しめる。
- 「スプラトゥーン2」(Nintendo Switch)
- インクを使って陣地を塗り合うアクションシューティングゲーム。友達との対戦が楽しい。
特徴:
- 戦略性や協力プレイが求められる
- 複雑な操作やルールを理解できるようになり、自由度の高いゲームが増える
- オンラインプレイやバトル要素が強くなる
4. 12〜14歳:中学生
中学生になると、よりリアルなゲームや、ストーリー性が強いゲーム、対戦型のオンラインゲームに興味を持つようになります。この年齢では、ゲームを通じて友達とのコミュニケーションを楽しむ傾向があります。
人気のゲーム:
- 「Apex Legends」(PC・PS4・Xbox)
- バトルロイヤルゲームで、リアルなグラフィックと戦略的なプレイが求められる。友達と一緒にプレイするのが楽しい。
- 「フォートナイト」(PC・PS4・Nintendo Switch)
- 引き続き人気のバトルロイヤルゲーム。エモートやスキンなど、カスタマイズ要素が多い。
- 「ドラゴンクエストXI」(PS4・Nintendo Switch)
- 長編RPGで、ストーリーに没入できる。キャラクター育成や冒険が楽しい。
特徴:
- ストーリー性や深い世界観があるゲーム
- 対戦型ゲームやオンラインプレイに積極的
- ゲームのプレイ時間が長くなる傾向
幼児期は教育的なゲーム、低学年は簡単な冒険やパズルゲーム、高学年は戦略やオンライン対戦を楽しむゲーム、中高生は競技性やストーリー性の高いゲームが人気です。
3. ゲームのマナーを教える
ゲームの中でもモラルやマナーを守ることが大切です。ゲーム内で暴言を吐かない、他のプレイヤーを尊重する、負けても怒らずに楽しむことなど、基本的なルールを教えていきましょう。
ゲーム内でのモラルやマナーの欠如
オンラインゲームや対戦型のゲームでは、他のプレイヤーとのやりとりが必須です。ゲームの中で相手と協力したり対戦したりする場面が多いため、モラルやマナーを守ることがとても大事になってきます。しかし、ゲーム内で暴言や煽り行為をしてしまうことがあり、それが習慣化してしまうと、現実世界でのコミュニケーションにも悪影響を及ぼす可能性があります。
具体例:
- 暴言や煽り行為
- 例: ゲーム内で自分の思い通りにいかなかったり、負けたりすると、「お前、下手すぎ!」とか「もうやめろ!」など、相手に暴言を吐いたりすることがあります。このような言動は、相手を傷つけるだけでなく、本人が他者との関わりで攻撃的になる原因となります。
- 影響: 子どもがゲーム内で暴言を吐くことが常態化すると、現実世界でも「言葉で相手を傷つけること」に対する感覚が鈍くなり、学校や家庭での人間関係に悪影響を与えます。特に、友達との遊びや学級活動の中で協調性を欠いた行動をすることがあります。
- 負けたときにゲームを投げ出す
- 例: 対戦ゲームや競争型のゲームで負けてしまうと、すぐに「つまらない!」と言ってゲームを投げ出し、相手を責める子どももいます。「お前が嫌がらせするから勝てなかった!」と相手を責めたり、ゲームを途中で諦めてしまうことがあります。
- 影響: 負けることを受け入れられない態度が習慣化すると、現実世界でも失敗を恐れて行動しなくなる場合があります。また、相手を責めることで、責任転嫁や自分の非を認めない傾向が強くなるかもしれません。
親ができること
- ゲーム内でのマナーを教える
- ゲームを始める前に、ルールやモラルについて子どもと話し合い、ゲーム内でも「他人を尊重する」ことを伝える。
- 例えば「ゲーム内で負けても相手を尊重する」「暴言はNG」というルールを設け、守れたかどうかを確認する。
- 他の人とのコミュニケーションを大切に
- ゲーム内で協力する場面を積極的に設け、チームワークを学ばせる。例えば、協力型ゲームを親子で一緒にプレイすることで、コミュニケーションスキルを高める。
🌟ゲーム内には、イヤな事をしてくる人もいるということも伝えましょう。
4. 課金を管理する
子どもがゲーム内でお金を使わないように、ゲームの設定で課金を制限するか、事前に許可を取るルールを作りましょう。親が子どものゲーム内での課金を把握し、無駄な支出を防ぐために管理することが重要です。
実践例:
- ゲームの課金設定を親が管理し、確認コードを設定しておく。
- 「課金をしても良いタイミング」を決め、子どもが納得する形でルールを作る。
5. ゲームと他の活動をバランスよく
ゲームを楽しむことも大切ですが、他のアクティビティ(勉強、運動、読書、家族との時間など)とバランスよく過ごすことが重要です。子どもにとってゲームが全てにならないように、他の楽しみを一緒に見つけていきましょう。
ゲームの依存リスク
ゲームは過度にのめり込むと依存症のリスクが高まります。特に子どもは感情のコントロールが未熟なため、ゲームに夢中になるあまり、他の重要な活動を後回しにすることが多くなります。
具体例:
- ゲームが終わらないと気が済まない
- 例: 例えば、ゲーム内で「クエスト」や「チャレンジ」が終わらないと気が済まない子どもは、時間が経つのを忘れてゲームを続けてしまいます。親が「そろそろお昼ご飯だよ」と声をかけても、「あと少しで終わるから待ってて!」とゲームを続けることがあります。こうした姿勢が長時間続くと、他の大切なこと(食事、学校の宿題、友達との遊びなど)が後回しになり、健康や生活習慣に悪影響を与えることがあります。
- 影響: 食事を抜いたり、運動不足になったり、睡眠不足になったりします。さらに、他の活動(例えば友達との遊び)よりもゲームを優先するようになり、社交性や協調性が低くなる恐れもあります。
- 家族との時間を楽しめない
- 例: 休みの日、子どもがゲームに集中していると、家族で過ごす時間が犠牲になりがちです。例えば、「今日は家族で公園に行こう!」という提案に対して、「ゲームをしていたいから行きたくない」と拒否することがあります。また、家族が集まって食事をしているときも、ゲームに夢中になり、会話が少なくなったり、食事をおろそかにしたりすることもあります。
- 影響: 家族とのつながりやコミュニケーションが減少し、孤立感を感じることがあります。さらに、家族のイベントや共同活動を楽しめなくなると、親との関係性にも影響を及ぼし、子どもが家族の一員としての役割を果たさなくなります。
親ができること
- ゲーム時間を管理する
- ゲームの時間をあらかじめ決めておく(例えば「1日1時間」など)。また、ゲームをしている間に食事や休憩を取るように促し、他の活動を忘れないようにする。
- ゲームの合間に「休憩タイム」を設けて、運動や家族と過ごす時間を確保する。
- 家族との時間を優先する
- 休みの日には家族全員で過ごす時間を作り、ゲームを一時的に休止するルールを設ける。たとえば「家族時間を楽しむためにゲームは午後2時まで!」など、明確なルールを作り、家族全員が楽しめるアクティビティを提案する。
- ゲーム以外の楽しみを見つける
- 子どもがゲームをしているだけでなく、他の興味や趣味を見つけられるようにサポートする。例えば、ボードゲームやスポーツ、アートなど、家族で楽しめる代替アクティビティを提案する。
まとめ
「ゲームばかりしている子どもたち」って、今どきの子どもにとってはごく普通のことです。ゲームは遊びの一つであり、時代背景やテクノロジーの進化によって、子どもたちの楽しみ方も変わってきています。
だからこそ、「ゲームばかりしている」と心配になりますが、適切なルールを設けて、バランスよくゲームとつき合っていけるといいですね。

🔗【小学生の不登校原因ランキング】担任と合わない子への対応は?親が知っておきたいこと
🎁関連記事おすすめ:
- ▶【小学生の不登校原因ランキング】担任と合わない子への対応は?
- ▶不登校でもOK!小学生が家でできる学習アイデア10選
- ▶フリースクールやオンライン学習ってどうなの?小学生の不登校に合う学び方を探すヒント
- ▶不登校の小学生、家での過ごし方どうする?ゲーム漬けを防ぐ1日スケジュール
- ▶【思春期のイライラ対処法】「うちの子、なんでこんなに怒ってるの?」
🔗よかったらこちらもどうぞ:
- 👉 子どもの心のサイン?「家族の絵」にあらわれる心理とは
- 👉 小1が素直になる!男の子&女の子別・魔法の声かけフレーズ集【今日から使える】
- 👉反抗期きた!?と思ったら…小1の“言い返し”は愛だった件。
- 👉小1のうちに知っておきたい「困ったとき、誰にどう言えばいい?」
- 👉優しすぎる子が小学校でつまずく理由|“自己主張できない”は家庭で変えられる
自宅で安心して学べるオンライン学習
担任がつきタブレット教材で自宅学習をサポート。
プログラミングや声優体験など、子どもが得意を伸ばせるオンラインスクールです。
資料請求で詳しい内容をチェック!
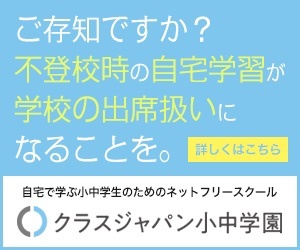
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
\こんな記事も読まれています/
\子育て心理に関する人気記事/
\こんな記事もおすすめ/
🍁 秋の心理診断シリーズ 🍁
気になる診断を選んで、秋のひとときをもっと楽しんでみませんか?
学校に行かない選択、でも「学び」は止めない
「学校に行かなくても、ちゃんと学べる場所がある」
それを知ってから、私も子どもも少しずつ前を向けるようになりました。
クラスジャパン小中学園は、全国対応のオンラインフリースクール。
出席扱いになる可能性があるから、今の学びが将来につながります。
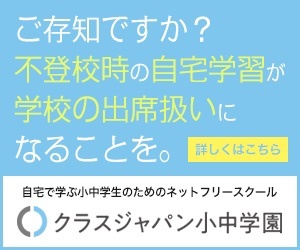

16タイプ診断 MBTI診断 おえかき おもしろ心理テスト お母さんの絵 お父さんの絵 お絵描き お絵描きの心理 りんご イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 大人の心理テスト 女性心理 子どものアート 子どものサイン 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 当たる心理テスト 心理テスト 心理学 心理診断 性格タイプ分析 性格診断 恋愛心理テスト 恋愛心理診断 朝の果物 果物 果物で元気 残酷な絵 深層心理 無料心理テスト 男性心理 秋の果物 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 自己肯定感 行動心理学 造形 食欲の秋 黒い絵
このブログはPRを含みます
こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです!
子どもの心と表現の成長を、親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。









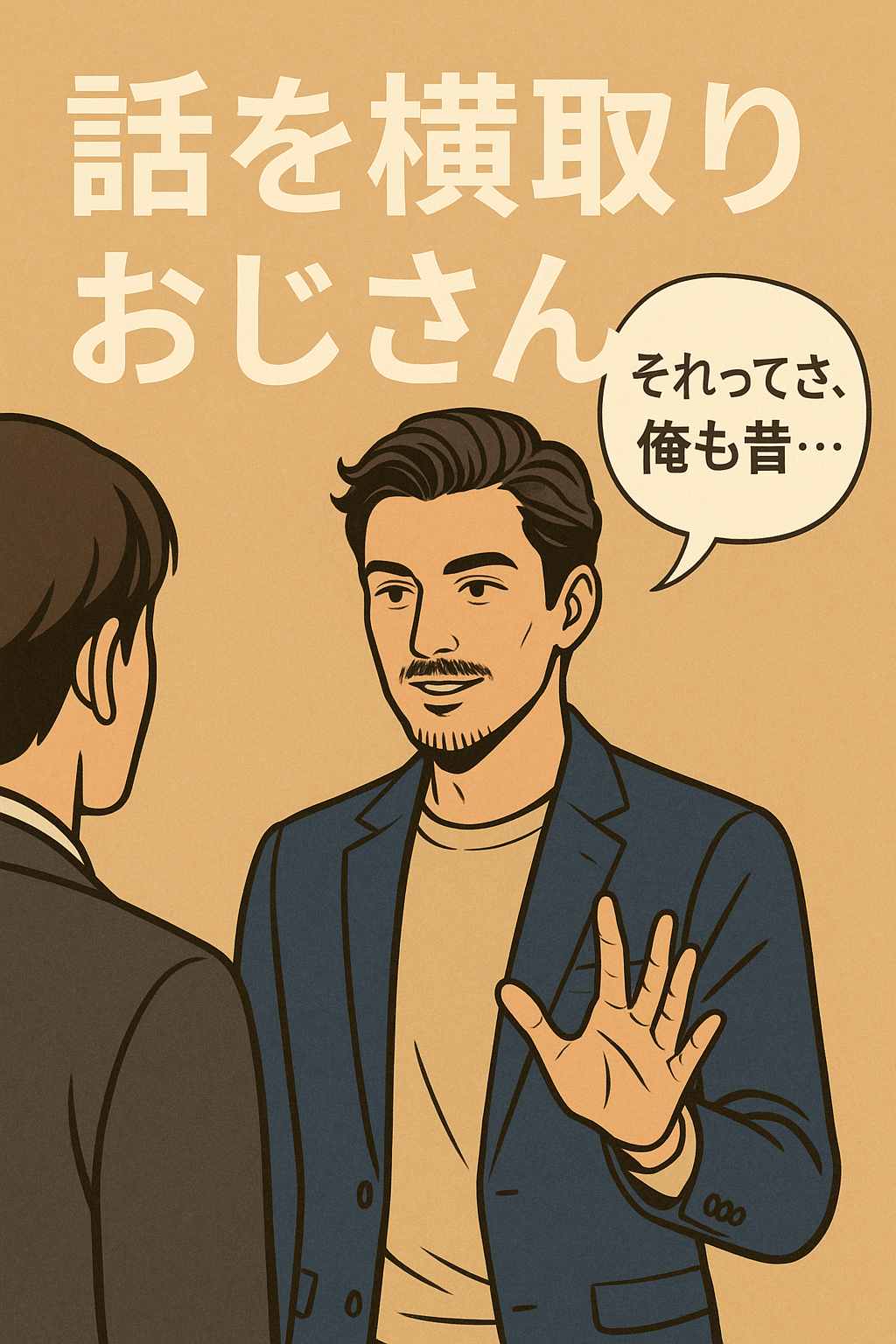
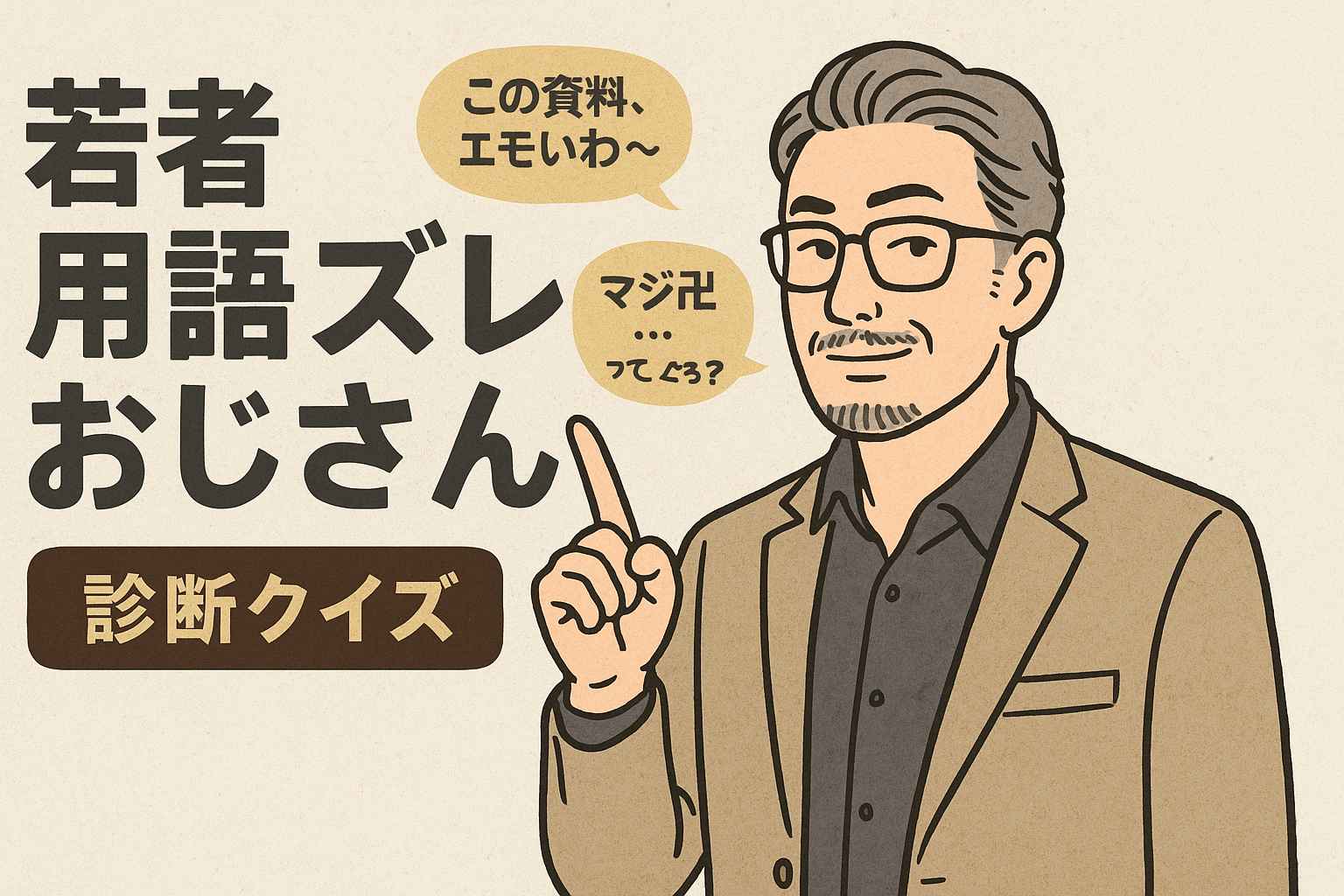





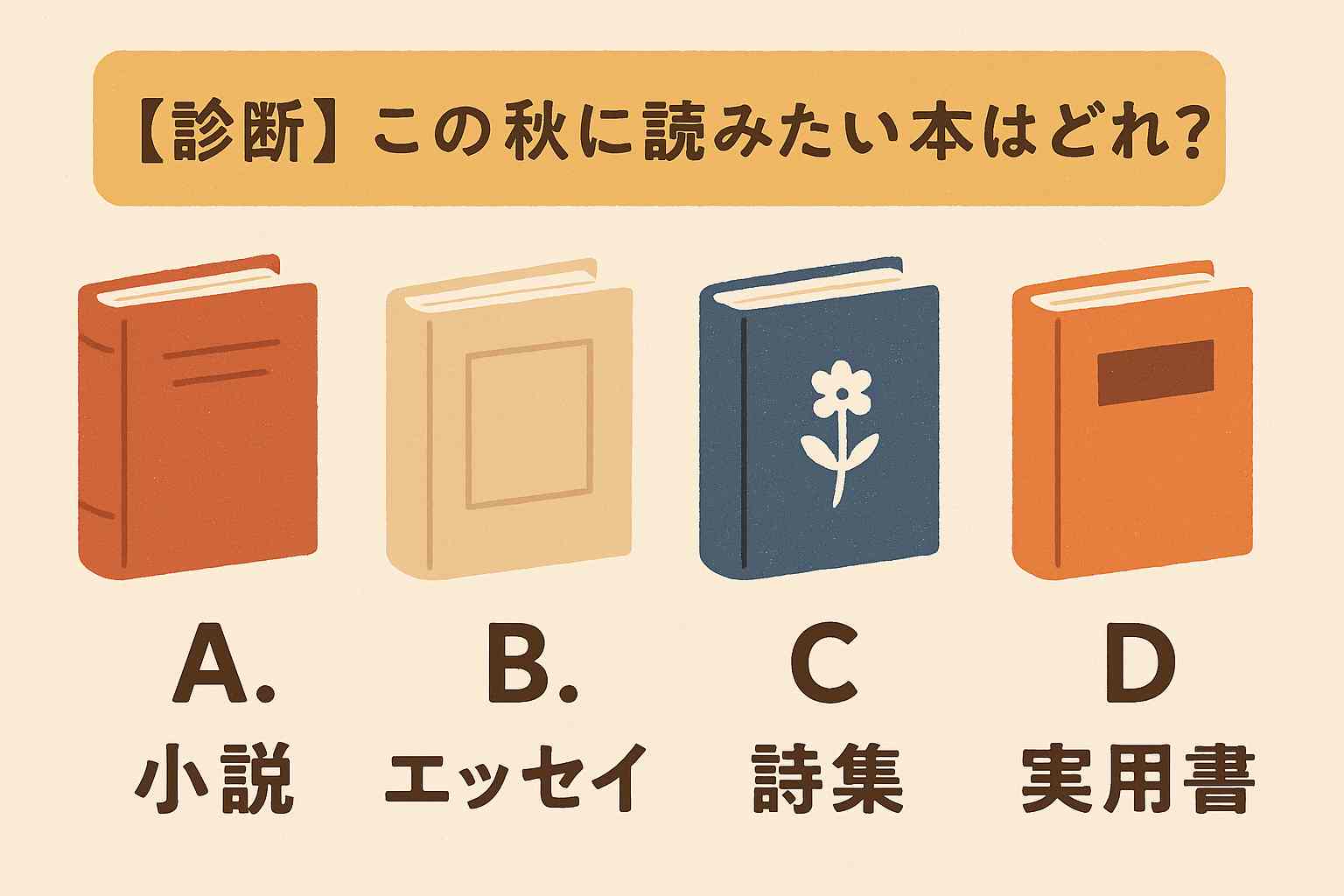




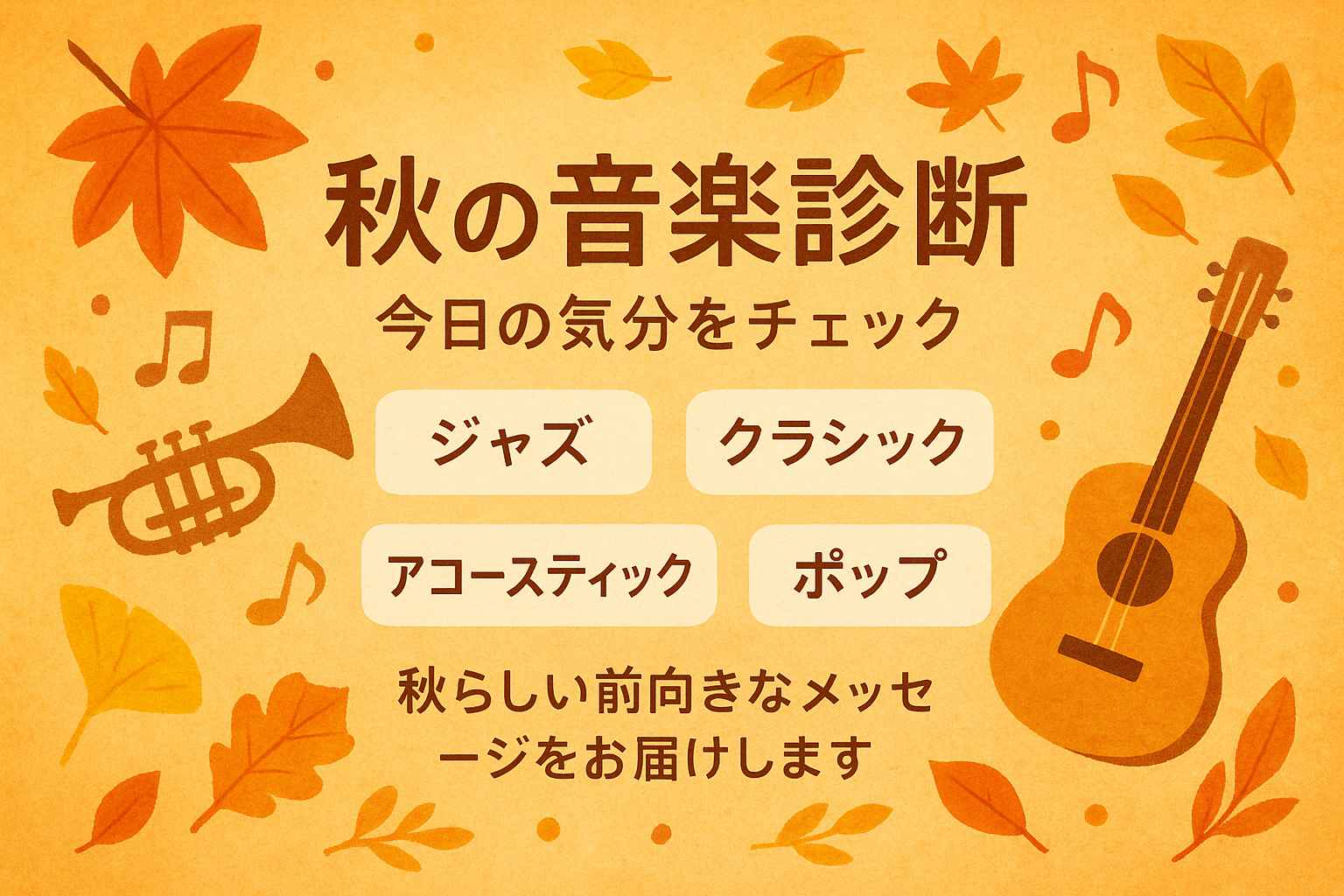


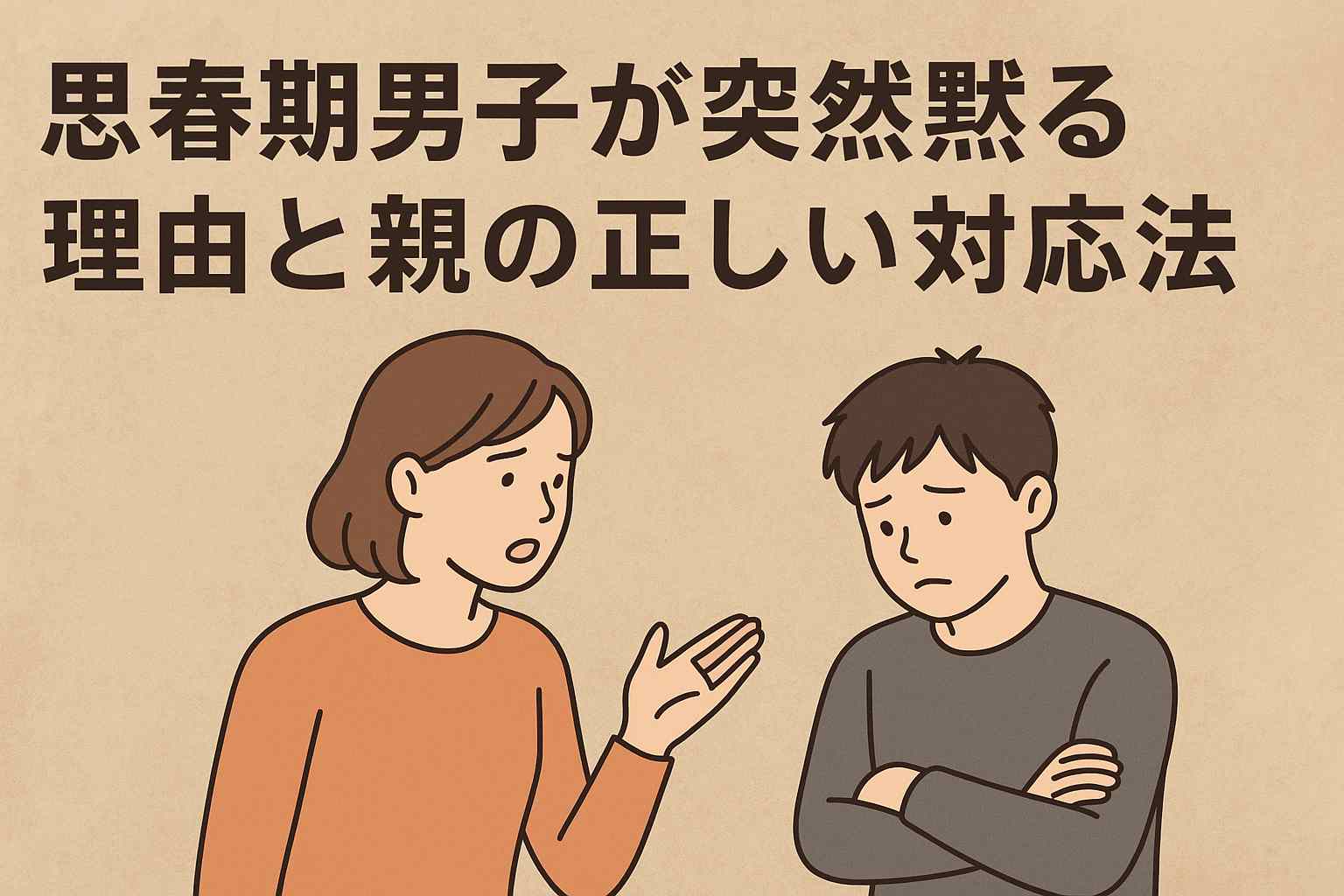
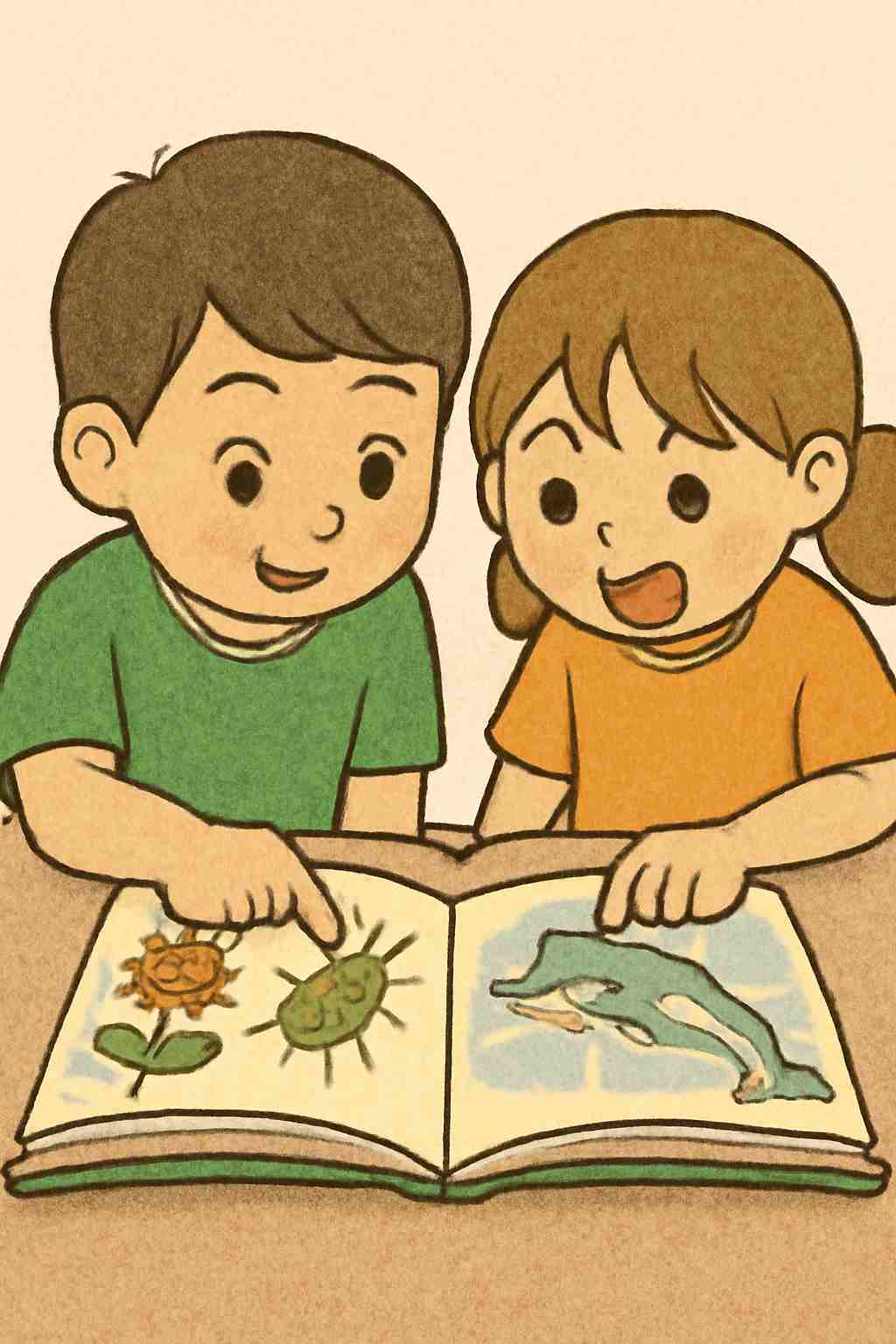


コメントを残す