このブログはPRを含みます
はじめに|「もしかしてうちの子、普通じゃないのかも…?」と検索したあなたへ
子どもがまだ小さいうちは、泣いたり怒ったり、
何を考えているのかさっぱりわからないことってよくありますよね。
それでも最近、「あれ?気持ちが読めないな」と感じたり、「他の子と比べて、なんだか感情の出し方が違う?」と心配になった方もいらっしゃるかもしれません。
検索欄に「幼児 発達障害 気持ち」「人の気持ちがわからない 幼児」なんて言葉を打ち込んで、このページにたどり着いたあなた。
大丈夫です。ここでは、焦っている心を少しほぐしながら、冷静に今のお子さんの様子を見つめ直せるヒントをご紹介します。
「気持ちをうまく表現できない=発達障害」と決めつける必要はまったくありません。
でも、「なんだか気になる」という親の直感も、とても大切なもの。
このブログでは、幼児期の感情表現と発達障害の違い、チェックすべきサイン、相談先、そして家庭でできるサポートについて、わかりやすくお伝えしていきます。
「普通じゃないかも」と不安になったその気持ちも、お子さんの未来にちゃんとつながっていきますように。
【チェックリスト】幼児の“気持ちが読めない・表せない”行動例
まずは、「気になる行動」をひとつずつ整理してみましょう。
ここで大事なのは、“すぐに発達障害だと決めつけないこと”と、“見えにくいサインに気づくこと”のバランスです。
親として、「あれ?」と思った感覚は、たいてい的を射ています。
以下にご紹介する行動例に、当てはまるものがあるかどうか、ゆったりとした気持ちでチェックしてみてくださいね。
□ 他人の気持ちに無関心なように見える
・お友達が泣いていても、気にしていない
・人の表情や言葉にあまり反応しない
→「共感力が育ちにくい」傾向は、発達障害の一部でも見られる特徴です。
□ 表情が乏しい or 感情表現が極端すぎる
・楽しくても笑わない/怒ると大暴れ
・状況に合わないリアクションをする
→「感情のコントロール」がうまくできず、表現が極端になることがあります。
□ 空気を読まずに突飛な行動をする
・列に並ばずに走り出す
・静かな場所で急に叫ぶ・歌う
→「場の雰囲気を読む力」が育ちにくいケースも。
□ 一人遊びばかりで友達と関わらない
・公園や園でもずっと一人
・声をかけられても返さない
→「社会性の発達」がゆっくりな子もいますが、継続して見られるときは注意が必要です。
□ 急に怒り出す・パニックになる
・気持ちの切り替えができない
・こだわりが強く、思い通りにいかないとパニックに
→「感情の調整機能」が未熟なケースで見られる反応です。
これらの行動のうち、“頻繁に・継続的に”見られるかが、ひとつの目安になります。
どの子にも“その日によって違う”時期はありますので、「今週ずっとこうだったな」といった継続性に目を向けてみましょう。
感情の発達と発達障害|どこがどう違う?
さて、「気持ちが表せない」「人の気持ちがわからない」と聞くと、
つい「それって発達障害なのでは…?」と心がざわついてしまいますよね。
でも実は、幼児期というのは、どの子も“感情表現が未熟”なのがふつうなんです。
ただ、その“未熟さ”が自然な発達の途中なのか、あるいは発達障害のサインなのか。
この見極めこそが、親として一番気になるところですよね。
ここでは、幼児の感情の育ち方と、発達障害による特性との違いを、ざっくりと整理しておきましょう。
感情って、どうやって育つの?
感情は、言葉やコミュニケーションと一緒に、少しずつ育っていきます。
たとえば──
・「泣いている子を見て、自分ももらい泣きする」
・「ありがとうって言われて嬉しくなる」
こんな共感や気持ちのやりとりは、経験の積み重ねで身につくものです。
3歳ごろから「共感」の芽が育ちはじめ、4~5歳で少しずつ気持ちを言葉にできるようになっていきます。
一方で、発達障害の子に見られやすい“感情”の特徴は?
発達障害、特に自閉スペクトラム症(ASD)傾向のある子には、以下のような感情面の特徴が見られることがあります。
- 気持ちの理解に時間がかかる(自分の感情にも、他人の感情にも)
- 言葉で気持ちを説明するのが苦手
- 感情が爆発しやすく、切り替えに時間がかかる
- 相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取るのが苦手
ポイントは、「年齢のわりに極端な苦手さ」があるかどうかです。
たとえば、5歳なのにまったく他人の感情に無関心だったり、日常会話で“気持ち”に関する言葉がほとんど出てこないなど。
個人差と発達障害の境目って、どこ?
難しいところなのですが、「感情表現の未熟さ=発達障害」とは限りません。
ただし、「いくつかの特徴が重なっていて、しかも生活に支障が出ている」となると、一度専門機関に相談してみる価値はあります。
✔️ ポイントは、「他の子と違う」ではなく「その子にとって困りごとになっているかどうか」。
「困っていないなら、今は様子を見る」でもOK。
「親がどう関わっていいか困っている」なら、相談してみるのも十分アリ。
では、次はその見極めをもう少し深掘りしていきましょう。
次の章では、「気になる行動の背景に何があるのか?」をじっくり探っていきます。
【見極めのヒント】気になる行動、その背景には何がある?
子どもって、ただでさえ予測不可能な行動をします。
でも親としては、「なぜそうなるの?」「これってやっぱり発達障害?」と、不安がぐるぐるしてしまいますよね。
そこで大切なのが、「行動の裏側にある“気持ち”や“理由”を探る視点」です。
実は、ちょっとした困った行動にも、子どもなりの“理由”がちゃんとあることが多いのです。
【例1】急に怒り出す・パニックになる
→背景にあるかもしれないのは?
「言いたいことが伝わらないもどかしさ」「予定が変わる不安」「感覚の過敏さ」など。
たとえば、「靴下がチクチクしてるのに伝えられない」「いつもと違う順番で保育園に行った」など、大人が気づきにくい“違和感”がトリガーになっていることもあります。
【例2】他人の感情に気づかない
→背景にあるかもしれないのは?
「表情や声の変化を読み取るのが難しい」「“気持ち”という概念の理解がまだ育っていない」など。
「ママが怒ってるのになぜ平然としてるの?」とイライラすることもあるかもしれませんが、
“怒っている”という感情そのものを認識できていない場合もあります。
【例3】一人遊びばかりしている
→背景にあるかもしれないのは?
「集団が苦手」「どう関わればいいかわからない」「自分の世界に集中しているだけ」など。
発達障害の子どもに見られる特徴の一つではありますが、
実は“想像力が豊かで自分の世界に浸っている”という、素敵な個性であることも。
子どもの行動を「こうすべき」で見るのではなく、
「なぜそうしているのか?」という目で見てあげると、ほんの少し心が軽くなることがあります。
そして、「これ、親だけで抱えるのはしんどいな…」と思ったときは、次のステップへ進みましょう。
【相談先まとめ】一人で悩まないでOK|こんなときは誰に相談すればいい?
「育てにくさを感じるけど、相談するほどじゃないかも…」と遠慮してしまう方も少なくありません。
でも、「ちょっと気になる」時点で、相談してOKなんです。
気になるサインがあるときに、気軽に相談できる場所をご紹介します。
● 療育センターや発達支援施設
地域によって名称はさまざまですが、「子どもの発達」を専門にした相談機関です。
発達検査や支援プログラムも受けられます。
● 小児科・かかりつけ医
まずはいつもの先生に「気になる行動があるんですが…」と相談してみましょう。
医師からの紹介で専門機関につながるケースもあります。
● 市区町村の子育て相談窓口(保健センターなど)
無料で相談できる場所も多く、保健師さんや発達支援コーディネーターが対応してくれます。
● 幼稚園・保育園の先生
毎日子どもを見ている身近な専門家。家庭では見えない姿を教えてくれることもあります。
園での様子を伝えてもらうだけでも、気づきにつながることがあります。
相談は「診断してほしい」ではなく、「ちょっと聞いてほしい」でもいいのです。
むしろ早めの気づきが、お子さんの「その子らしい育ち方」を支える大きな力になります。
家庭でできるサポート|“今すぐできること”があるから大丈夫
「相談した方がいいかも」と思いつつも、日々の忙しさや迷いのなかで、なかなか動き出せないことってありますよね。
でも大丈夫。おうちでも、すぐに始められる小さなサポートがちゃんとあります。
焦らず、いまできることから。
「うちの子なりに、ちゃんと育っていける力がある」と信じて関わることが、いちばんのサポートになります。
1.気持ちを言葉にする機会をふやしてみる
たとえば──
「悲しかったんだね」
「それはイヤだったよね」
「わくわくしてる顔だね!」
こんなふうに、子どもの気持ちを“代わりに言葉にしてあげる”ことで、「これは●●っていう気持ちなんだ」と学んでいけます。
最初は反応がなくても、だいじょうぶ。毎日ちょっとずつでOKです。
2.「気持ちに名前をつける絵本」や遊びを取り入れる
感情をテーマにした絵本や、顔の表情をマネっこする遊びなどもおすすめです。

MR.MEN LITTLE MISS あいての きもちを たいせつに Caring
感情を楽しく学べる仕掛けがあると、抵抗感なくすんなりと“気持ちの語彙”が育っていきます。
3.“失敗”よりも“気持ち”に寄り添う声かけを意識してみる
つい言ってしまいがちな…
「なんでそんなことしたの!?」
「また泣いてるの?」
こんな言葉の代わりに、
「びっくりしちゃったのかな」
「どうしたかったのか教えてくれる?」
と“気持ちの中身”に寄り添ってみましょう。
失敗を責めるよりも、「気持ちを分かってもらえた」と感じられることが、安心感につながります。
4.親も「ちょっと困ってるんだけどね〜」と話していい
「子どものために冷静でいなきゃ」と頑張りすぎなくても大丈夫。
「ママも実はイライラしてたんだ〜」「今日ちょっとしんどい日だな〜」って、自分の気持ちも言葉にしてみることで、子どもにとっても“気持ちは話していいんだ”という安心感になります。
最後に:普通じゃないかも、のその先へ
「普通じゃないかも」と感じるとき。
その背景には、「この子をちゃんと育ててあげたい」という深い愛情があるのだと思います。
発達障害のサインに気づくことも大切。
でもそれ以上に、“その子なりの感じ方・育ち方”を見守ってあげることこそ、親にしかできないことです。
不安を抱えながら検索してここまで読んでくださったあなたは、
すでに「大丈夫の一歩目」を踏み出せているのかもしれません。
どうか、深呼吸をひとつ。
そして「うちの子、ちゃんと育ってるんだな」と、ちょっと信じてあげてみてくださいね。
「気持ちの切り替え」で困ったときに、こちらも参考にどうぞ:
- 子どもをスムーズに動かす方法
- なんでもイヤ!な時期の子どもの心理
- 着替えたくない!イヤイヤ期に着替えを嫌がる子どもへの対応法
- 育児書通りでも赤ちゃんが泣く理由
- 2歳児の謎行動にツッコミながら学ぶ!育児あるある&成長サポート集
|
お子さまの成長をサポートする「スマイルゼミ」の幼児コース
「スマイルゼミ」の幼児コースは、入学前に身につけたい大切なスキルを楽しく学べるタブレット型通信教育です。ひらがなやカナ、時計の読み方、数字や図形など、さまざまな分野を10分間の学習でサクッと習得できる仕組みが魅力。
お子さまが自分のペースで学べるので、飽きることなく楽しく続けられます。大画面で安心して学べる専用タブレットで、繰り返し学習ができるため、学びの定着もしっかりサポート。
さらに、2022年4月から始まった「無学年学習[コアトレ]」を活用すれば、学年に関係なく、先取りやさかのぼり学習が可能に!お子さまに合わせた学習スタイルで、学びをもっと広げていけます。
今なら約2週間自宅でお試しいただける「全額返金保証」も実施中。安心してお試しができるので、ぜひチェックしてみてください。
詳細についてはこちら

おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 お絵かきワーク お食事エプロン ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イラスト ケーキスマッシュ リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 育児用品 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳 1歳おすすめおもちゃ
このブログはPRを含みます
こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです。
このブログでは、子どもの絵から心理を読み取り、心の成長や表現力を親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。
「子どもの絵で心を読む専門サイト」として、日々の子育てに役立つ情報をお届けします。





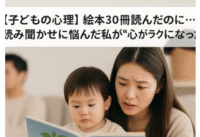
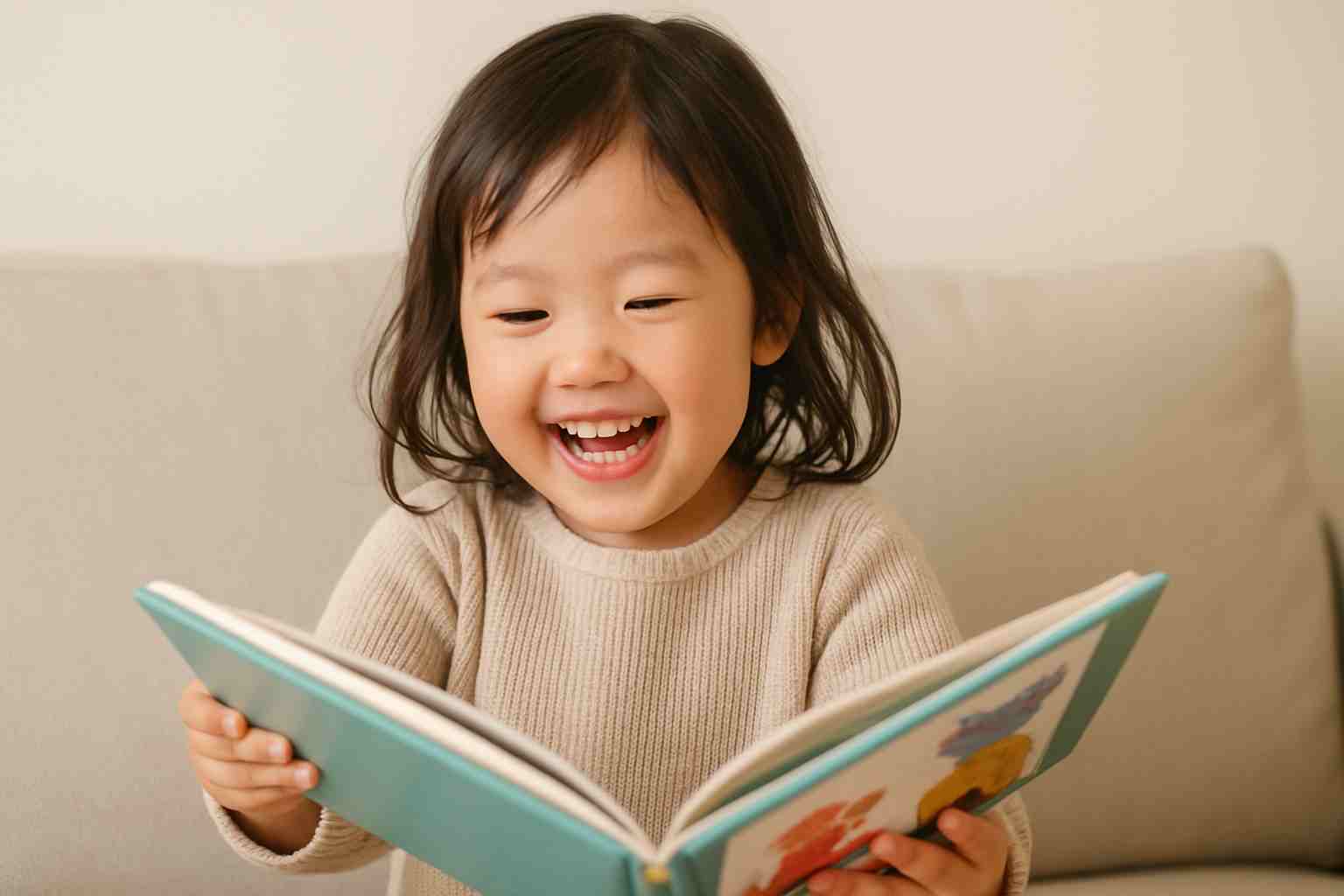
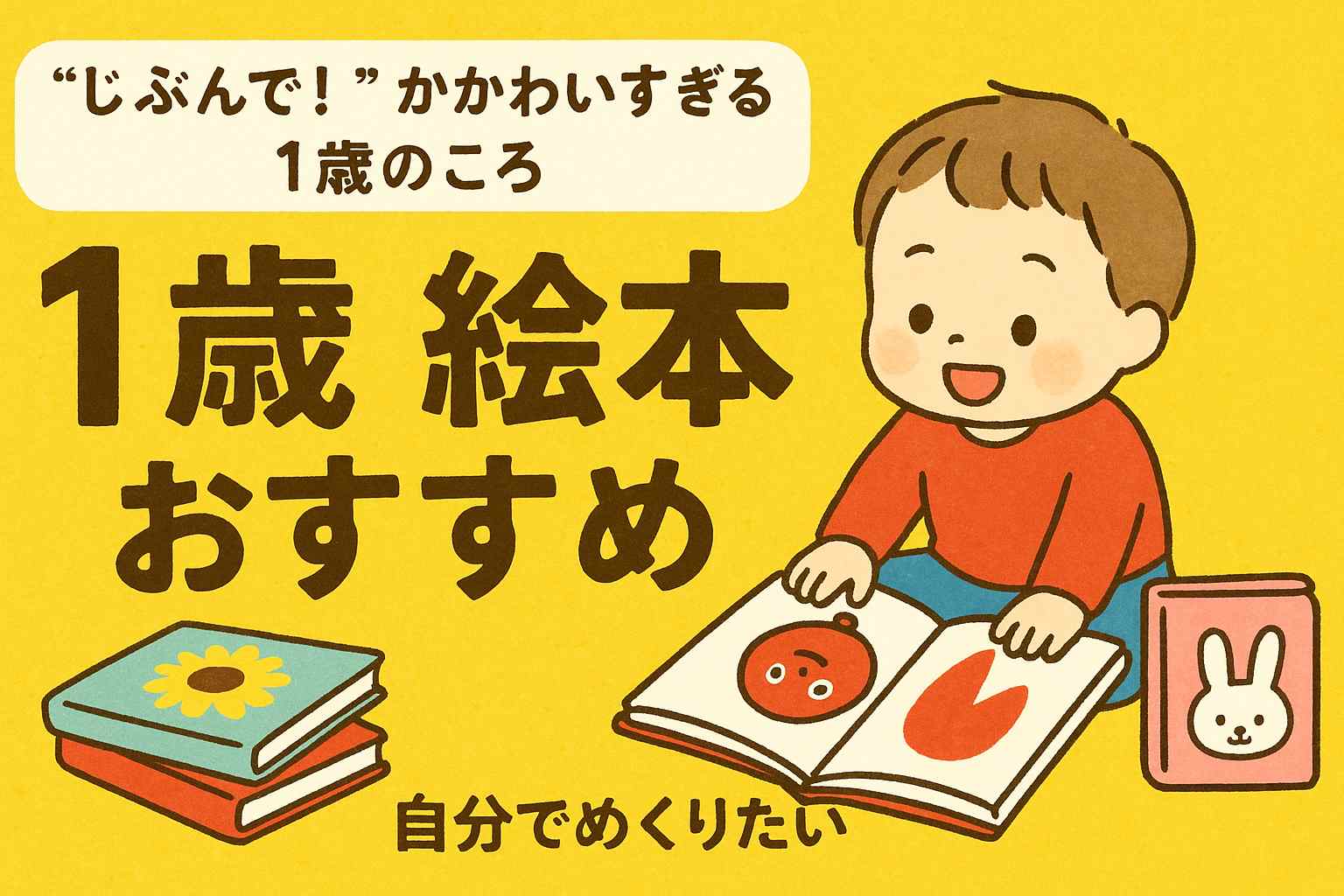
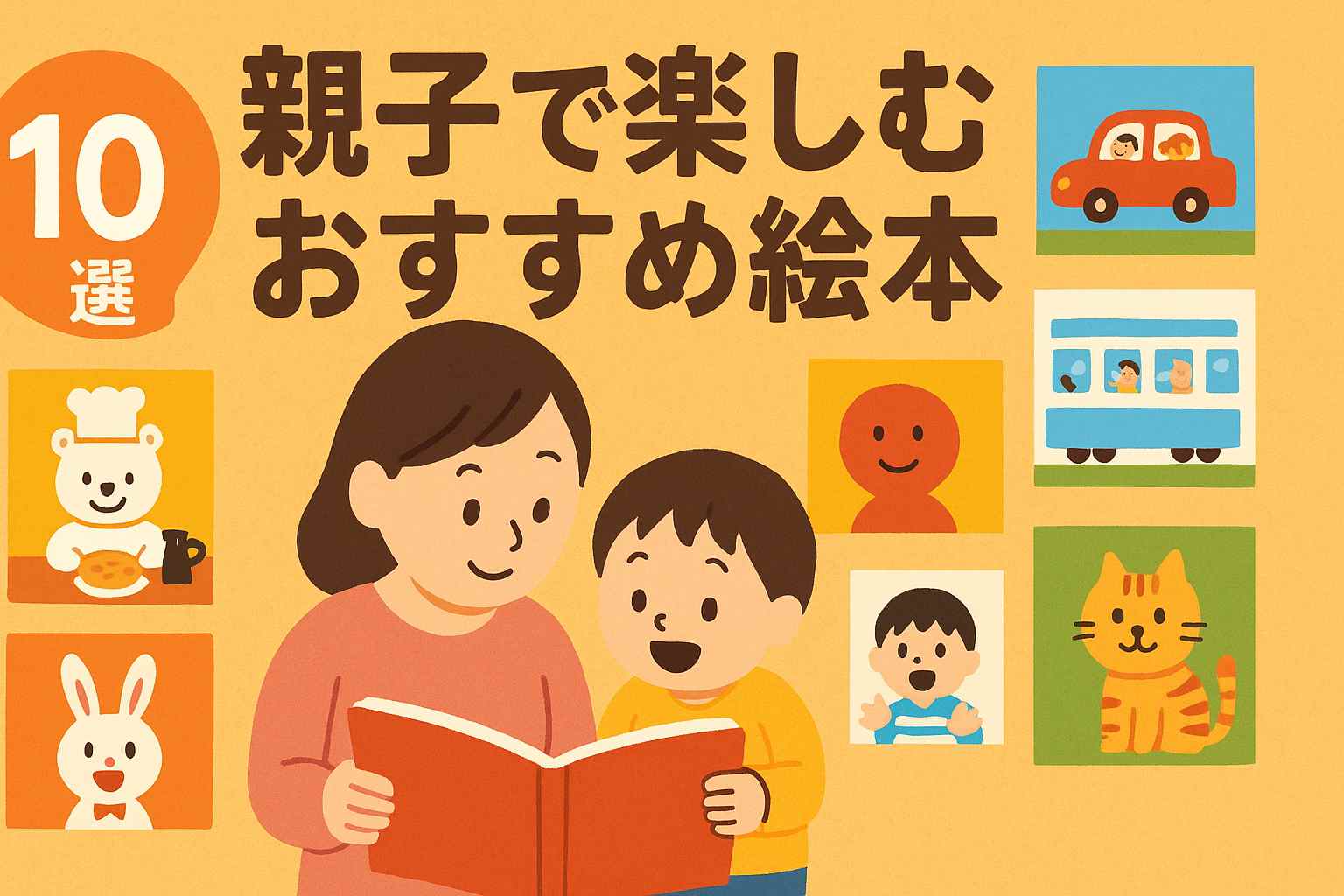

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a21b6c8.2c670885.4a21b6c9.9ab7a430/?me_id=1419335&item_id=10006505&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmakistore%2Fcabinet%2F11932524%2Fpssids2852%2Frng61.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




