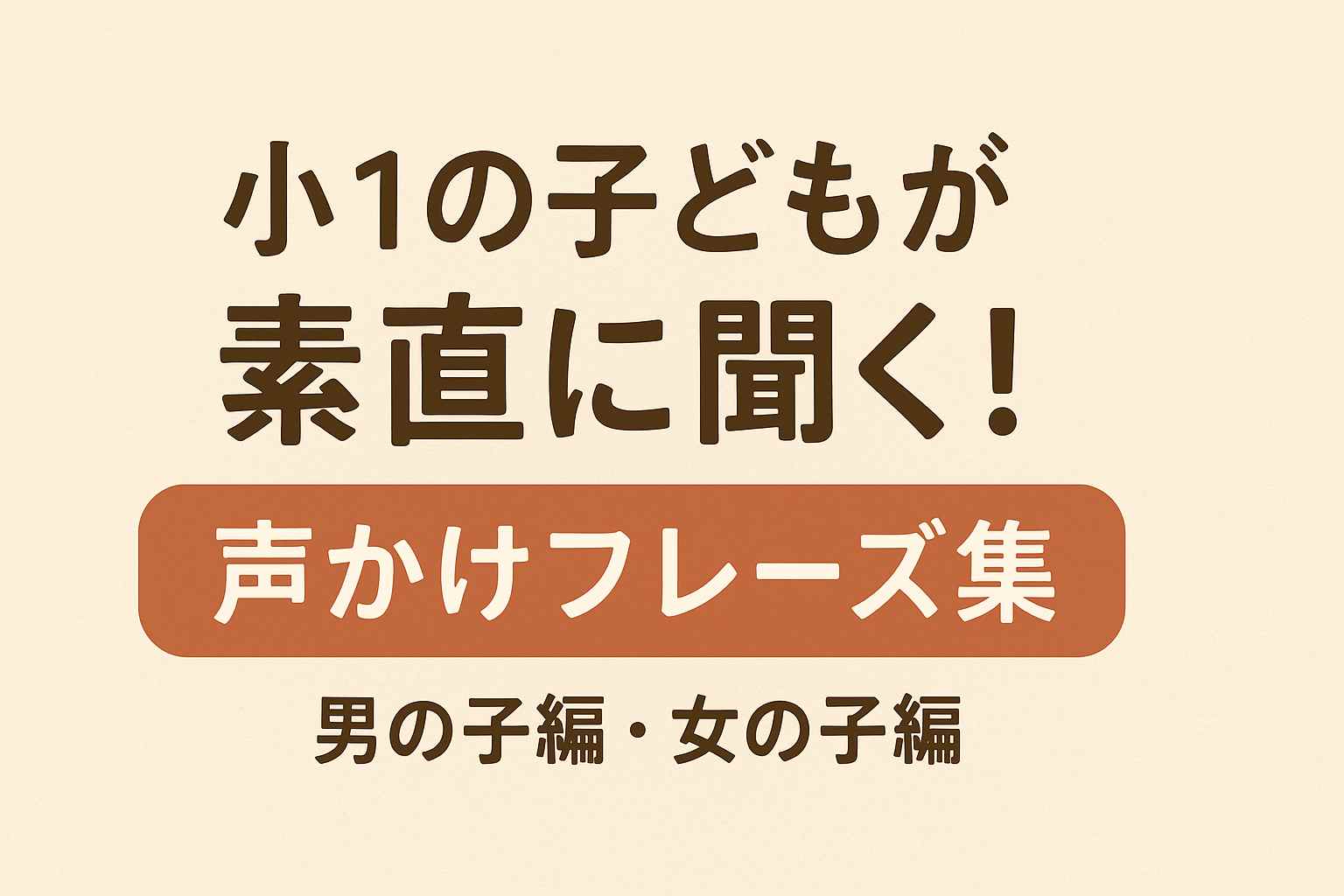小学校に入ってやれやれ。いろいろ気になることはあるけれど、なんとか学校にも慣れてきたみたい。
そんなころ、
「最近、うちの子の絵が…なんだか変わってきたような?」
と感じませんか?

この前まで「○」と「線」だけだった人が、急に空を描き出したり、
なぜか地面にヒーローが埋まっていたり、
木が水色、空がピンクで、犬が5本足――え? どうした???
思わず「それって間違ってない…?」と、口に出しそうになるけど、
ちょっと待ってください。それ、すごく大事な“変化”かもしれません。
小学1年生の絵って、実は「現実」と「空想」のせめぎ合いの真っ最中。
本人も、頭の中のイメージと、見えている現実との間で、行ったり来たりしてるんです。
大人から見ると“なんじゃこりゃ?”でも、
子どもにとっては、その絵こそが「今のわたし」そのもの。
この記事では、小学1年生の絵に表れがちな変化や、そこに隠れている心のヒントを、
元教員の視点も交えて、ちょっとユニークに、でもまじめに(ちゃんと!)解説していきます。
🔗お友達を描かない子が伝えていること – itti-blog
この記事の内容
📍空がピンク、木が水色…!?それ、子どもの“センス”です
大人の目からすると、
「木が水色ってどういうこと?」「空がピンクって夕焼け…にしては濃くない!?」
そんなツッコミを入れたくなる絵、ありますよね。

でも、それ、
センスの問題ではなく、心の成長のあらわれなんです。
小学1年生ごろって、「現実」を観察する力と、「空想」を楽しむ力が入り混じってる時期。
空想の世界にどっぷり浸かっていた年長さんから、
少しずつ「本当は空って青なんだよね」と知るようになって、
それでも「でも今日はピンクで描いてみたい!」という気持ちが共存してるんです。
要するに、
現実も知ってる。でも、自分の中の世界もまだまだ大事にしていたい。
そんな心のバランスが、ピンクの空や5本足の犬ににじみ出てるわけです。
ちなみに、こういう発想、
大人が忘れかけてる柔軟さ
でもあります。
「空は青」「木は緑」と思い込んでるのは、私たちのほうかもしれませんね。
🌱 1年生の柔軟さが育つと、こんな力になります
1. 自分の考えを楽しめる子になる
「これ、ちょっと変かな?」と思うことも、「でも、いいや。楽しいし」と自分で肯定できる。
→ 絵や工作、発表や作文でも、「自分らしさ」を大事にできるようになります。
2. 新しいことへの抵抗が少なくなる
「これはなんだろう?やってみよう!」とワクワクしながら挑戦する気持ちが育ちます。
→ 新しい習いごとや、2年生以降の“学びのステップアップ”にもスムーズに対応できます。
3. 他人の違いをおもしろがれる
「ぼくは空をピンクにしたけど、○○ちゃんはオレンジにしてた!」
→ 自分と違う表現を否定せず、“違うって楽しい”と思える感覚が育ち、共感力や協調性につながります。
4. 自己肯定感の土台ができる
「失敗してもいい」「自分のやり方でもいい」と思える柔軟さが、
→ 学校生活や人間関係でつまずいたときの“心のクッション”になります。
☕ まとめると…
1年生の今って、「型にハマる前の、最高に自由な時間」。
その柔軟さは、想像力・表現力・社会性・自己肯定感――すべての“学びの芽”をぐんぐん育ててくれる、まさに“栄養満点の土壌づくりの時期”なんです。
だからこそ、大人が「どう描くのが正解か」ではなく、
「その子の“今”をのびのび出せる時間」を持たせてあげることが、大きな意味を持つんです。
🔗優しすぎる子が小学校でつまずく理由|“自己主張できない”は家庭で変えられる – itti-blog
そもそも、お絵描きできる環境がすばらしい
小学校に入学したての子どもって、見た目は変わらなくても、毎日ものすごくがんばってるんですよね。時間割、チャイム、係の仕事、集団行動…大人でも「え、急にルール多くない?」って思うようなことに必死に順応しようとしていて、心の中はきっとフル稼働なんです。
そんな中で、家に帰ってきてお絵かきしている時間があるって、それだけで「ほっとする場所がある」ってこと。親にとっては「ただのお絵かき」でも、子どもにとっては「自分を取り戻す時間」だったりします。
そしてそれを「まあ描いてるし、いいか」って見守ってる親御さん。
実はめちゃくちゃいい子育てしてる。

“ちゃんと何か教えなきゃ”とか“宿題やらせなきゃ”よりも、まず“安心して自分を出せる空間がある”ってことの方が、よっぽど大事だったりするんですよ。
子どもの絵は、そんな心の“安心”や“好き”がにじみ出る場所。
その時間を守っているあなたは、すばらしいです。
🔍 チェックリスト|絵に出ている“気持ちのヒント”
さて、そんな子どもの絵には、
ちょっとした「心の変化」や「今、がんばってること」がにじんでいることがあります。
「最近、絵がなんか変わった気がする…」というとき、
こんなサイン、出ていませんか?
✅ 子どもの絵で気になる変化
- 空や地面など、「背景」を描くようになった
- キャラクターの表情が豊かになってきた(でも、怒ってる顔ばかり!?)
- 同じモチーフ(恐竜・プリンセスなど)を何枚も描いている
- 色が極端(すごく濃い・モノクロばかり・派手にカラフル)
- 描きたいものを言葉で説明してくれるようになった
- 「ここは秘密!」と見せたがらない部分がある
こういった変化には、
「観察力が育ってきた」「イメージを形にしたいという意欲が育ってきた」など、
心と頭の発達がリンクしているサインが隠れています。
🔗子どもの絵に出る心のサイン|入園・進学・転校など環境の変化との関係とは? – itti-blog
🧭 親にできる声かけ3つのポイント
~うっかり言いがちなNGワードも~
とはいえ、親としては「どう関わればいいの?」と悩むところ。
まず大切なのは、評価せずに“感じたこと”を伝えることです。
🌱 やってみたい声かけ
- 「その色、いいね!なんでその色にしたの?」
→ 色のチョイスには、子どもの気分やこだわりが表れてることも。 - 「これは○○かな?違ったらごめん、教えて!」
→ 自分の解釈が間違っててもOKだよ、という安心感に。 - 「そのヒーロー、どんな力があるの?」
→ 絵の背景にある“物語”を引き出すことで、世界観を共有できます。
🙅♀️ できれば避けたい言葉
- 「木は緑でしょ」
- 「ちゃんと描きなさい」
- 「これ、何かわからないなぁ」
これらの言葉は、自由な表現をせき止めてしまうことも。
つい口から出そうになりますが、「言い換えスイッチ」を持っておくと安心です。
🔗絵が上手い子は何が違う?育ち方と親の関わりで見える5つのポイント – itti-blog
🎁 おわりに|絵の中には“今のわたし”がいる
子どもの絵って、その子自身の「心の冒険日記」みたいなものです。
うまい・へたじゃなくて、
「今この子がどんな世界を見て、何を感じて、どんなふうに表現したいのか」
それが詰まっているんです。
だからこそ、
ちょっと不思議な色づかいや、想像を超える構図が出てきたら――
それは「すごい成長をしてるサインだな」と、見守ってあげてくださいね。
そしてときどき、聞いてみてください。
「この木が水色なの、どうしてかな?」って。
きっと、あなたの知らない物語が返ってきますよ。
📒小学校1年生の時期に。こんな記事もよく読まれています
🔗小1が素直になる!男の子&女の子別・魔法の声かけフレーズ集【今日から使える】 – itti-blog
🔗給食がもっと楽しくなる!家庭でできる練習5選|ジャムが開けられない子にできるサポートとは? – itti-blog
🔗小1になって見えにくくなった人間関係…親ができる見守り方とは? – itti-blog
筆者がはまっている安眠グッズ♪スマホの見過ぎなのか、夕方くらいから目がしょぼしょぼなんですよね・・・。
|
✏️ 子どもの絵でわかる心理シリーズ

性格診断

家族の描き方
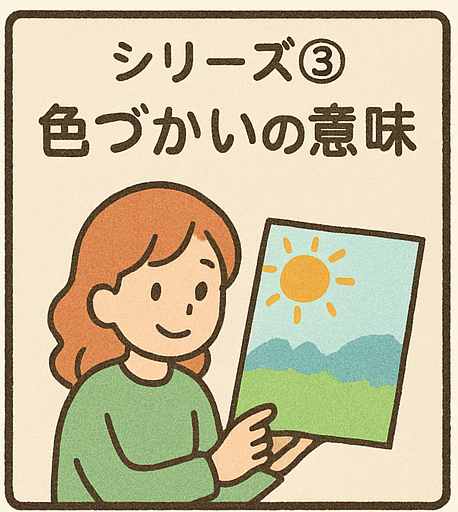
色づかい

同じ絵ばかり

絵が小さい
ホーム » 小1になって絵のテイストが変わった?「現実」と「空想」のはざまで育つ心
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a2e74d4.51a5c01a.4a2e74d5.bc35e2c1/?me_id=1399335&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftokiiro64%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image-2%2F20250523173112_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)