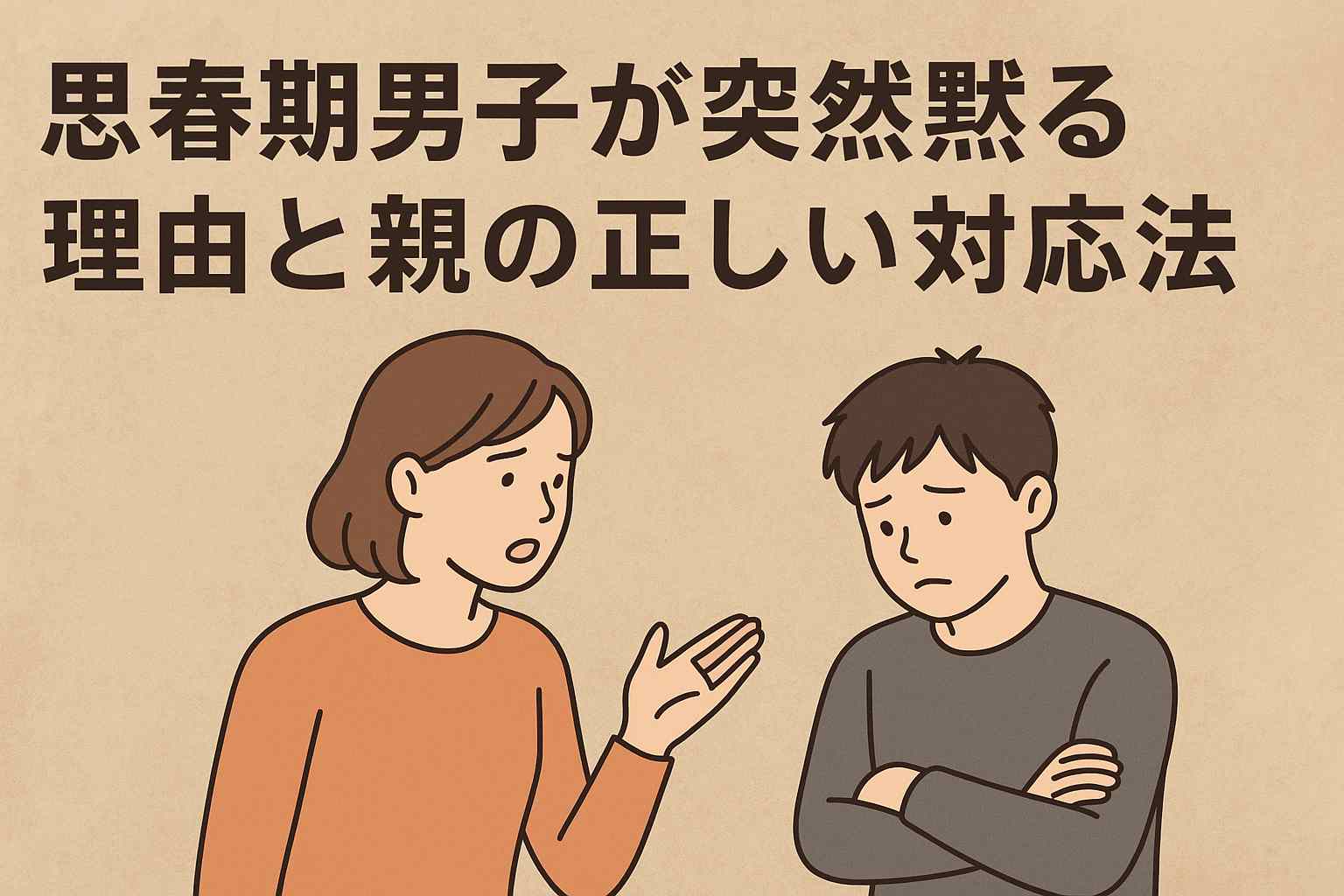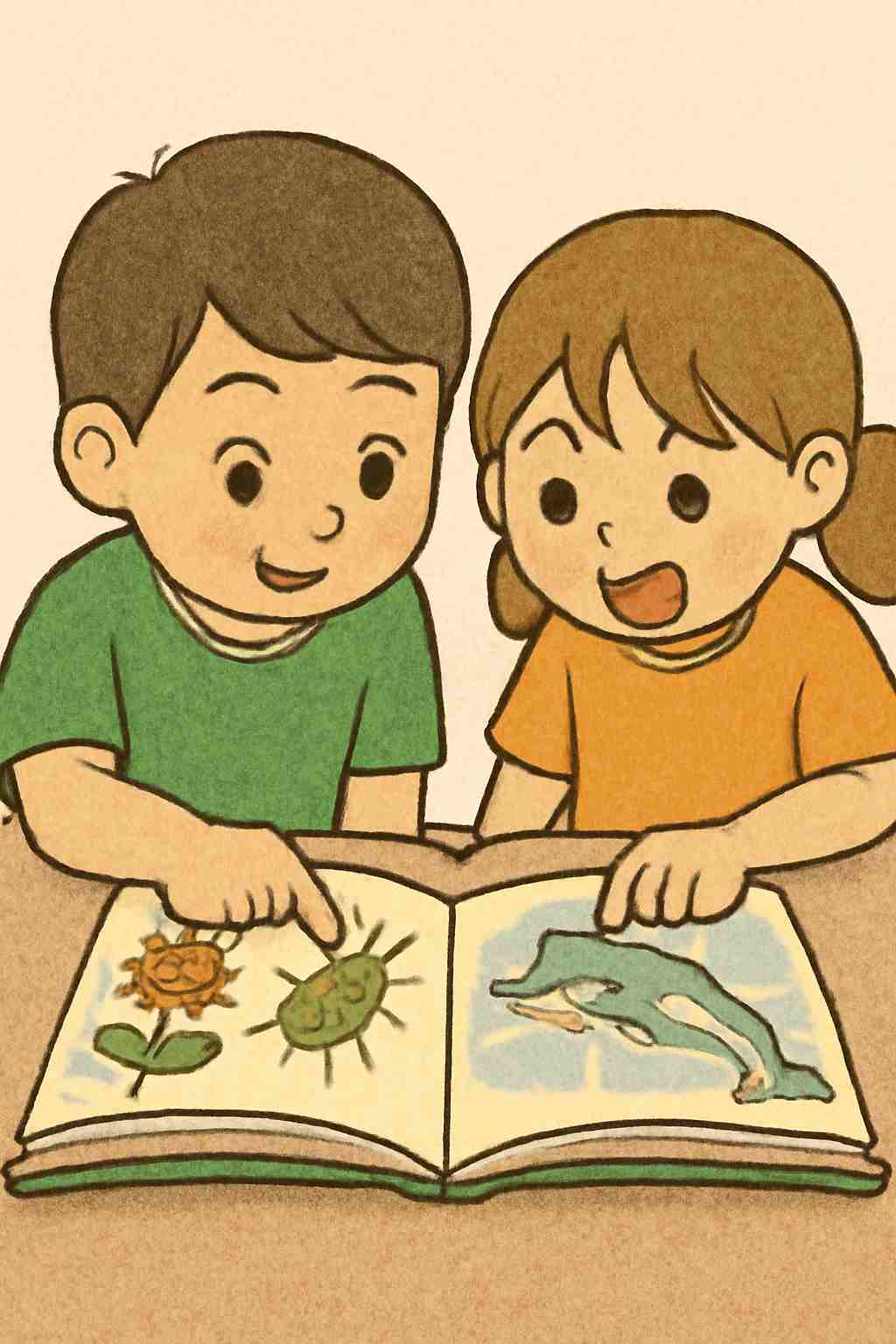この記事の内容
ゲームしているのに学校に行けない?それ、もしかして逆説的かも?
「ゲームばっかりしてるんだから、学校行けるでしょ?」なんて、つい思っちゃいますよね。
見ている側からすると、学校に行かない理由が“ゲームができるから”って、なんだか不思議。
だって、ゲームをしている元気があるなら、学校にも行けるんじゃない?と思いがちですが、
実はこれ、ちょっとした逆説が隠れているんです。

もちろん、ゲームしている時って、子どもにとっての「ひとときの逃げ道」。
現実のストレスから解放されるためのひとときです。だけど、ゲームの世界で得られるのは、一時的な安心感や満足感。学校に行くためのエネルギーとは、また別物なんですよね。
でも、親としては、「どうしてゲームができるのに学校には行けないの?」と、どうしても心配になりますよね。そんな疑問に応えつつ、子どもが学校に行けるための心のエネルギーをためる方法を一緒に考えていきましょう。
ゲームが学校に行けるエネルギーに変わる日が来るかも?
おっと、ゲームをただ制限するだけじゃエネルギーはたまりません!
ゲームは、ストレスを解消したり、友達と繋がったりする大切な手段。でも、これをどう上手にコントロールしていくかがポイント。無理に「ゲーム禁止!」なんて言っても、逆効果になることも。まずは、ゲームをする時間と学校に行くための準備を区切って、両立できるような工夫が大切です。
例えば、「ゲーム後に少しだけお手伝い」とか、「ゲームする前に少しだけ勉強」とか。これで、ゲームが学校に行けるエネルギーに変わるかも、なんてワクワクしませんか?
学校に行くためのエネルギーを蓄える方法!
子どもが学校に行くために必要なのは、実は「エネルギー」。でも、これって意外に見過ごされがち。無理に「学校に行こう!」と押しつけても、心が疲れているとエネルギーは湧いてきません。だからこそ、少しずつエネルギーを蓄えていく方法を試してみましょう。
1. 小さな成功体験を積む
学校に行くことが大きな壁に見えるとき、最初は小さな目標を立ててみるのがオススメ!朝起きて自分で身支度をするだけでも、子どもは「できた!」という自信を持てるんです。その調子で少しずつ自信を積み重ねていくと、行動する力がついてきますよ。
2. リラックス時間を確保
「行けるなら行ってみなよ!」って無理強いしても、心身ともに疲れていると逆効果。心と体をリセットするリラックス時間を作ることで、エネルギーが回復します。深呼吸して落ち着いたり、親と一緒に絵本を読んだり、音楽を聴いて気分転換したり。遊びの時間や自由時間も大事なんです。
3. 学校の不安を取り除く
学校に行くためには、まずは学校への不安を減らすことが必要!どんなことに不安があるのか、少しずつ話してもらうことが大切です。もしかしたら、過去に辛い経験があったり、友達との関係で心配していることもあるかもしれません。学校の先生とも面談して、環境を整えていけると、安心して学校に向かう準備ができるんです。
🔗【小学生の不登校原因ランキング】担任と合わない子への対応は?親が知っておきたいこと
4. 学校に行くための準備を楽にする
朝の準備がスムーズだと、余計なストレスを減らせます。準備を前日からしておくことで、朝もバタバタせずに心を落ち着けられます。さらに「明日は友達と遊ぶ」「授業で面白いことが待っている」と楽しみを考えながら準備を進めるのも良い方法です。
5. 少しずつ慣らしていく
急に学校に行こうとすると、ハードルが高すぎるかも。だからこそ、段階的に慣れていくのがポイント!まずは「今日は短時間だけ行こう」なんて目標を立てて、少しずつ回数を増やしていくことで、行ける日が近づいてきます。
自宅で安心して学べるオンライン学習
担任がつきタブレット教材で自宅学習をサポート。
プログラミングや声優体験など、子どもが得意を伸ばせるオンラインスクールです。
資料請求で詳しい内容をチェック!
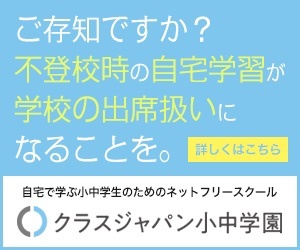
不登校児が家でやっていることランキング!あなたの子どもはどれに当てはまる?
不登校の子どもたちが家でどんなことをしているか、気になりますよね。
学校に行けなくても、家でどんな時間を過ごしているのか知ることで、少しでも親としてサポートしやすくなるかもしれません。それでは、家で不登校の子どもたちがよくやっていることをランキング形式でご紹介します!
第1位:ゲーム!ゲーム!ゲーム!
やっぱりこれ、外せませんよね。ゲームは不登校児の必須アイテムと言っても過言ではないかもしれません。子どもにとって、ゲームは現実逃避の場であり、ストレス解消の手段でもあります。友達とオンラインでつながることができ、勝ち負けに一喜一憂することで、達成感も得られます。
ゲームのいいところ:
- ストレス発散
- 集中できる
- 友達とのコミュニケーション手段(オンラインゲーム)
気をつけるポイント:
- ゲーム依存にならないよう、時間を決めてプレイ
- 他の活動とバランスを取る
第2位:YouTubeや動画視聴
ゲームと並んで人気なのが、YouTubeやNetflix、動画配信サービス。おうちで気軽に視聴できるので、子どもたちにはありがたい存在です。好きなアニメやYouTuberの動画を見てリラックスする時間が多いかもしれません。
動画視聴のいいところ:
- 自分のペースで観られる
- 気になることを調べられる
- 幅広いジャンルから選べる
気をつけるポイント:
- 視聴時間のコントロール
- 内容が偏りすぎないように
動画視聴やゲームの時間に区切りをつける方法、なかなか難しいところですよね。特に子どもが夢中になっていると、終わりを切り出すタイミングが難しくなることがあります。
1. タイマーを使う
- 視覚的に時間を意識させるために、タイマーや時計を使うといいです。例えば、ゲームや動画が終わるまでの時間を「○分後に終わりにしようね」と伝えて、その時間が経過するとアラームや音で知らせると、予告がしやすくなります。タイマーを設定する際に、子どもと一緒に「何分で終わるか」を決めるのもいいですね。
2. 具体的な目標を設定する
- 「あと2ステージクリアしたら終了」や「この動画が終わったらね」というふうに、具体的な目標を設定することで、次のアクションが分かりやすくなります。その後、時間を区切って「次の目標に進む時」に終了させやすくなります。
3. 段階的に終了させる
- 一度に完全に切り替えるのではなく、数分間の「終わり準備」を設けると、切り替えがスムーズです。例えば、「あと5分後におしまいだから、準備をしようね」という感じで、段階的に終了時間を意識させる方法です。
|
第3位:自分の趣味に没頭!
もしかしたら、子どもが普段は忙しくてできなかった趣味を再開しているかもしれません。絵を描いたり、読書したり、プラモデルを作ったり。趣味に没頭することで、時間が有意義に過ぎるだけでなく、心が落ち着いたり、自己表現の方法が見つかったりします。
趣味のいいところ:
- 自己肯定感を高める
- 創造力が育まれる
- ストレスが軽減される
気をつけるポイント:
- 夢中になりすぎて、他のことを忘れないように
- 目標設定をして達成感を得られるように
|
第4位:インドアなスポーツやトレーニング
最近、家でできるフィットネスやトレーニングが人気です。子どもたちも、体を動かすことでリフレッシュできるし、健康管理にもつながります。YouTubeでエクササイズ動画を見ながらトレーニングしたり、ヨガやストレッチをする子も多いです。
インドアスポーツのいいところ:
- 体力や筋力がつく
- 気分転換になる
- ストレス解消になる
気をつけるポイント:
- 無理をせず、自分のペースで進める
- 長時間やりすぎないように
第5位:SNSやLINEで友達とつながる
学校に行けなくても、友達とのつながりを絶やしたくないのが子どもの気持ち。LINEやSNSを通じて、普段会えない友達と連絡を取ることができるので、孤独感を感じにくくなります。ただ、トラブルも起こりやすいので、注意が必要です。
SNSのいいところ:
- 友達と繋がれる
- 自己表現の場
- コミュニケーションの手段
気をつけるポイント:
- トラブルに巻き込まれないように監視
- 使用時間に制限をつける
第6位:家事や手伝いをする
実は、不登校の子どもたちが積極的に家事や手伝いをするケースもあります。何かをやることで、達成感を感じたり、家族との絆が深まることも。掃除や料理の手伝いをしている子も多いです。
家事のいいところ:
- 責任感が育まれる
- 家族とのコミュニケーションが増える
- 自己肯定感が高まる
気をつけるポイント:
- 親が過度に期待しすぎないように
- 楽しくやれる範囲で手伝ってもらう
第7位:寝て過ごす時間も…
もちろん、体調が優れない時や精神的にしんどい時は、寝て過ごすことが多いかもしれません。無理に起こしたり、何かさせたりすることが逆効果になる場合も。子どもが休む時間も大切です。
休養のいいところ:
- 心身の回復
- エネルギーをためる時間
気をつけるポイント:
- 休養が長期間続かないように、少しずつ活動を増やす
不登校の子どもたち、実は色んな過ごし方がある
子どもたちの不登校生活は一人ひとり違って、家で過ごす時間もさまざまです。「これが正解!」というものはありませんが、大事なのはその子がリラックスして過ごせる時間を持つこと。親としては、どうやってサポートできるか、少しずつ寄り添いながら見守ることが大切ですね。
子どもが何をしているかを知ることで、さらに理解が深まり、心のケアにもつながります。あなたの子どもは、どんなことをして過ごしていますか?
親としてのサポート
「学校に行けるように」と焦る気持ちはよくわかります。でも、子どもが無理なく行けるようにサポートするためには、親が安心感を与えることが大切です。子どもがエネルギーをためられるように、無理せず少しずつ進めることが大事!
あなたが心からサポートしてあげることで、少しずつ子どもは自分のペースで進んでいけるはずです。焦らずに、エネルギーをためる時間を大切にしてくださいね!
🌸 新しい習い事のかたち
最近では、将棋やピアノのように、「ゲームを習い事」として学べるサービスも登場しています。
フォートナイトやマイクラなどの人気タイトルを、全国大会・世界大会に出場経験のあるトレーナーからオンラインで学べるのが特長です。
ただ遊ぶだけでなく、集中力や情報処理力を伸ばすトレーニングとして注目されています。
外に出にくい時期でも、自宅から安心して参加できるのは嬉しいポイントですね。
まずは気軽に体験会から試してみませんか?
🎁関連記事おすすめ:
- ▶【小学生の不登校原因ランキング】担任と合わない子への対応は?
- ▶不登校でもOK!小学生が家でできる学習アイデア10選
- ▶フリースクールやオンライン学習ってどうなの?小学生の不登校に合う学び方を探すヒント
- ▶不登校の小学生、家での過ごし方どうする?ゲーム漬けを防ぐ1日スケジュール
- ▶【思春期のイライラ対処法】「うちの子、なんでこんなに怒ってるの?」
🔗よかったらこちらもどうぞ:
- 👉 子どもの心のサイン?「家族の絵」にあらわれる心理とは
- 👉 小1が素直になる!男の子&女の子別・魔法の声かけフレーズ集【今日から使える】
- 👉反抗期きた!?と思ったら…小1の“言い返し”は愛だった件。
- 👉小1のうちに知っておきたい「困ったとき、誰にどう言えばいい?」
- 👉優しすぎる子が小学校でつまずく理由|“自己主張できない”は家庭で変えられる
ホーム » ゲームばかりしている子ども、学校に行けない本当の理由とその解決策
学校に行かない選択、でも「学び」は止めない
「学校に行かなくても、ちゃんと学べる場所がある」
それを知ってから、私も子どもも少しずつ前を向けるようになりました。
クラスジャパン小中学園は、全国対応のオンラインフリースクール。
出席扱いになる可能性があるから、今の学びが将来につながります。
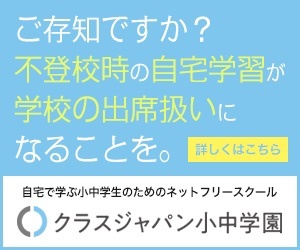

おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fc11db.1838cec5.49fc11dc.b887f1b9/?me_id=1410206&item_id=10000153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F112store%2Fcabinet%2F10788499%2Frakuten_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49f52f1e.27b3c7e7.49f52f1f.d1959570/?me_id=1210719&item_id=10008439&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarutomi-kyouzai%2Fcabinet%2Fdaiwa-s%2F1705.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)