こんにちは、ITTI(いっちー)です。
「読み聞かせ、しなきゃいけないのは分かっているけれど……」
そんなふうに、重たい気持ちで絵本を手に取っていませんか?
せっかく準備したおすすめの絵本。
なのに、読み始めた途端にどこかへ行ってしまったり、強引にページをめくられたり。
「うちの子、ちっとも集中してくれない。本が嫌いな子になっちゃうのかな?」と不安になる夜もありますよね。
でも、安心してください。 2歳の読み聞かせが「計画通りにいく」なんて、実はお天気を当てるくらい難しいことなんです。

今日は、2歳の読み聞かせがうまくいかない理由と、親子の心がふわっと軽くなる「2歳ならではの絵本の楽しみ方」を、たっぷりお届けします。
読み終わる頃には、「あ、明日も1ページだけ開いてみようかな」と思えるはずですよ。
この記事の内容
2歳の読み聞かせがうまくいかない理由【発達の視点】
まずは、「なぜ2歳児は静かに聞いてくれないのか」を、子どもの発達のメガネで覗いてみましょう。
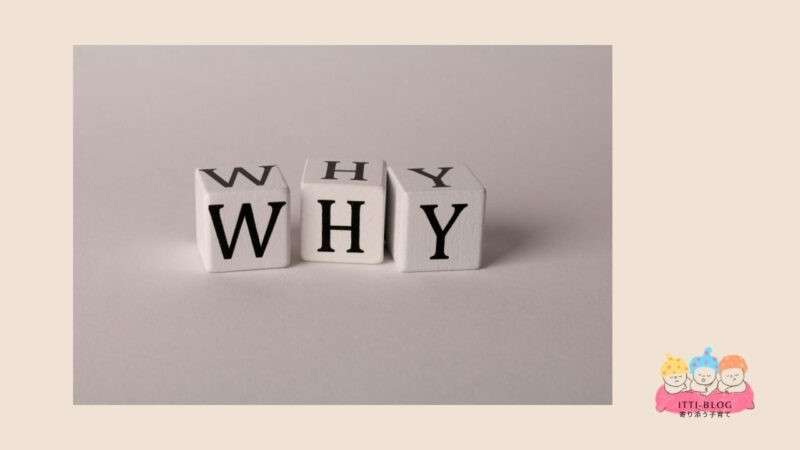
2歳は「聞く力」が育ち途中の時期
2歳という時期は、言葉を吸収する力が爆発的に伸びる一方で、一つのことに注意を向け続ける「持続的な集中力」はまだほんの数分、早ければ数十秒で切れてしまうのが当たり前です。
- 気分の波: さっきまで読みたがっていたのに、今はミニカーの気分。
- 体のエネルギー: じっと座っているよりも、足をバタバタさせたい。
- 想像のスイッチ: 絵本の一つの絵に反応して、そこから自分の世界(妄想)に飛んでいってしまう。
「最後まで聞けない=集中力がない」のではなく、「今、この瞬間の自分の気持ちに正直すぎる」だけ。むしろ、自分の興味に真っ直ぐな、とても健やかな姿なんですよ。
「最後まで聞けない=失敗」ではない
途中で立ってどこかへ行ってしまう。ページをバラバラとめくる。 これ、親としては「あぁ、今日もダメだった……」とがっかりしてしまいますが、実は子どもなりの「参加」の形なんです。
- ページをめくる: 「次が気になる!」「自分で動かしたい!」という意欲の現れ。
- 途中で立つ: 耳では聞いているけれど、体も動かしたいという「並行作業」中。
- 同じところだけ反応する: その子が今、一番必要としている情報がそこにある。
「最初から最後まで読む」という大人のルールに縛られなくていい時期。そう思ってみると、少しだけ景色が変わってきませんか?
2歳の読み聞かせで大切にしたい考え方
アプローチを変える前に、まずはママやパパの心にある「読み聞かせのハードル」を地面につくくらいまで下げてしまいましょう。
「読む」より「一緒に感じる」
絵本に書いてある文字を、一字一句正しく読み聞かせる必要はありません。 2歳児さんにとって、絵本は「知識を得るもの」というより、「大好きなママやパパと同じ世界を共有するツール」です。
文字を追わずに、絵を見て「あ、イチゴあったね」「ワンワン、ねんねしてるね」と会話するだけでも、立派な読み聞かせです。その1ページで終わったとしても、親子で心が通い合ったなら、それは大成功の100点満点です。
親がラクになる読み聞かせの考え方
真面目な親御さんほど、「毎日、寝る前に3冊!」なんて目標を立ててしまいがち。でも、疲れている日は休んでもいいんです。

- 毎日読まなくていい: あなたの笑顔の方が、お子さんには栄養になります。
- 同じ本ばかりでもいい: 「またこれ?」は、お子さんがその本を完全に自分のものにしようとしている、素晴らしい学習の過程です。
- 聞いていなくても“聞こえている”: 背中を向けて遊んでいるようでも、あなたの声のトーンや物語のリズムは、心地よいBGMとして心に染み込んでいます。
「読み聞かせ=教育」ではなく、「読み聞かせ=癒やしの時間」。 そんなふうに捉え直してみると、罪悪感がスルスルと解けていくかもしれません。
2歳の読み聞かせに向いている絵本の特徴
どんな本を選べば、2歳児さんの心に届きやすいのでしょうか。嫌がる子でも、「おや?」と反応しやすい絵本の共通点を探ってみましょう。
2歳向け絵本の共通点
2歳児さんの発達にフィットしやすいのは、次のような特徴を持つ本です。
- くり返しがある: 「次はこうなる」という見通しが持てるので、安心感があります。
- 1ページ1展開: 情報が整理されていて、視覚的に分かりやすいもの。
- 音・リズム・擬音が多い: 「ポン!」「ぐるぐる」といった言葉は、耳に心地よく響きます。
- 「自分の生活」と重なる: 靴を履く、ご飯を食べる、お風呂に入るなど、自分が知っている日常のテーマは食いつきが違います。
避けたい絵本の傾向(無理に読まなくていいもの)
もちろん「絶対にダメ」ではありませんが、この時期に「読まない」原因になりやすいのが、以下の特徴です。
- 文章が長すぎる: 集中力が切れてしまいます。
- 登場人物が多い: 誰が誰だか混乱してしまいます。
- 起承転結が複雑: 「なぜそうなったか」の因果関係を理解するのは、まだ少し先のこと。
「せっかく買ったのに……」という本は、少し寝かせておきましょう。数ヶ月後、あるいは1年後に、嘘のように大好きになることもよくある話です。
【タイプ別】2歳におすすめの読み聞かせ絵本
ここでは、特に「2歳児さんの反応がいい」と定評のある鉄板絵本を、タイプ別にご紹介します。
とにかく反応がいい!鉄板絵本
「まずはここから」という、2歳児の心をつかんで離さない魔法の本たちです。
- 『だるまさん』シリーズ(かがくい ひろし)
- なぜ刺さる?: 独特のリズムと、だるまさんのユーモラスな動き。
- よくある反応: 一緒に体を揺らしたり、「どてっ」と転んだり。
- コツ: 大人も一緒に体を動かして、ちょっとオーバーに読むと盛り上がります。
- 『ぴょーん』(まつおか たつひで)
- なぜ刺さる?: 縦に開く構成と、ページをめくるたびのジャンプ!
- よくある反応: 待ってましたと言わんばかりに、本人もジャンプ。
- コツ: 溜めを作ってから「……ぴょーん!」と読むと、ワクワク感が倍増します。
- 『いないいないばあ』(松谷 みよ子)
- なぜ刺さる?: 時代を超えて愛される「隠れる・出る」の普遍的な楽しさ。
- よくある反応: じっと見つめて、安心したように笑う。
イヤイヤ期の気持ちに寄り添う絵本
日常の「イヤ!」を、絵本が代わりに受け止めてくれることがあります。
- 『ねないこだれだ』(せな けいこ)
- 視点: 「早く寝なさい」と叱るのではなく、少しドキドキするファンタジーの世界へ。
- 生活習慣: 寝る前のルーティンとして、静かな空気を作るのに一役買います。
- 『おふろだいすき』(松岡 享子)
- 視点: お風呂が冒険の場所に変わる、ワクワクするお話。
- 気持ちの切り替え: お風呂嫌いな子も、「次はあのアヒルさんが出るかな?」と期待を持てるようになります。
探す・見つけるのが楽しい絵本
集中力が続かない子には、「参加型」の絵本がおすすめです。
- 『きんぎょがにげた』(五味 太郎)
- なぜ刺さる?: 「どこにいるかな?」と探す遊びが、達成感を与えます。
- 反応: 「ここ!」「いた!」と、指さしが止まらなくなります。
- 『はらぺこあおむし』(エリック・カール)
- なぜ刺さる?: 鮮やかな色使いと、食べ物に開いた穴。
- 反応: 指を穴に入れてみたり、あおむしと一緒に食べる真似をしたり。

きんぎょが にげた
探す楽しさが続く構成
指さしで自然と参加できる
「読まない日」はどうする?2歳の読み聞かせQ&A
現場でよく聞くお悩みに、ゆるっとお答えしますね。
Q:全然聞いてくれません
A:聞かない日があっていいんです。 膝の上に座らせて、じっと前を向かせる必要はありません。お子さんがトミカで遊んでいる横で、あなたが楽しそうに絵本をめくって「おぉ〜、すごいね」と独り言を言っているだけでも、それは立派な共有。興味を持った瞬間だけ、パッと絵を見せてあげれば十分ですよ。
Q:途中でページをめくります
A:それも立派な「参加」です。 「まだ読んでるでしょ!」と止めるより、「お、次はこれが見たかったんだね」「早いね〜!」とお子さんのスピードに合わせてあげましょう。お話の筋が通らなくても、お子さんの「今これを見たい!」という意欲を優先してあげると、絵本への苦手意識がなくなります。
Q:同じ本ばかり持ってきます
A:安心の証です。 大人からすると飽きてしまいますが、子どもにとっては「次は何が起きるか分かっている」という安心感が心地よいのです。言葉を覚えたり、展開を予測したりする力が育っているサイン。100回読んだら、101回目も「いいよ」と言ってあげられたら素敵ですね。
読み聞かせがラクになる親の関わり方
最後に、明日からの読み聞かせが少しだけ楽しみになるヒントを。

「ちゃんと読まなきゃ」を手放す
読み聞かせは「教育」ではなく、「親子のスキンシップ」の一つです。 お話の内容が頭に入らなくても、あなたの温かい体温を感じながら、優しい声を聞いたという「記憶」は、お子さんの心に一生残る安心の土台になります。
今日からできる小さな工夫
- 寝る前にこだわらない: 朝、機嫌がいい時に1分だけ。おやつを食べている横で1ページだけ。そんな「隙間読み」もアリです。
- 1冊30秒でもOK: 「おしまい」までいかなくていい。一番好きなページだけ見て、パタンと閉じても大丈夫。
- 読み手も楽しむ: あなたが「この絵、綺麗だな」と思う本を選んでみてください。あなたの「好き」という熱量は、必ずお子さんに伝わります。
【まとめ】2歳の読み聞かせは「うまくいかなくて当たり前」
いかがでしたか? 2歳の読み聞かせがうまくいかないのは、お子さんが自分の意志で、自分の世界を広げようとしている証拠。決してあなたのやり方が悪いわけではありません。
読み聞かせは、成果を測るテストではありません。
親子で同じページを見つめて、ほんの一瞬でも「あはは」と笑い合えたら。
たとえお子さんが途中で逃げ出しても、「本を広げて待っていた」というあなたの優しさがそこにあったなら。
それだけで、もう十分すぎるほど素晴らしい時間が流れています。
「今日も子どもと向き合おうとしたあなたは、もう十分がんばっていますよ」
今夜は、読めなかった絵本を数えるのではなく、今日お子さんと交わした小さな笑顔を数えて、ゆっくり休んでくださいね。

おやすみなさい。明日も、ほどよく力を抜いていきましょう。
食事(言葉/行動)だけでなく、2歳は心と体が同時に大きく育つ時期です。
▶ 2歳の育児あるあると成長サポートをまとめた記事はこちら
「気持ちの切り替え」で困ったときに、こちらも参考にどうぞ:
- 子どもをスムーズに動かす方法
- なんでもイヤ!な時期の子どもの心理
- 着替えたくない!イヤイヤ期に着替えを嫌がる子どもへの対応法
- 育児書通りでも赤ちゃんが泣く理由
- 2歳児の謎行動にツッコミながら学ぶ!育児あるある&成長サポート集
ホーム » 【2歳】読み聞かせおすすめ絵本|聞かない日があっても大丈夫。発達に合った選び方と関わり方
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。












