こんにちは。「ITTI-BLOG」へようこそ。
リビングの床に散らばる色鉛筆、画用紙の山。
ふと見ると、今日もまた、昨日と同じ「あの絵」を描いている。
「本当に好きだねぇ、よく飽きないなー!」そう思いながらも、心のどこかで、ちょっと不思議に感じることはありませんか?
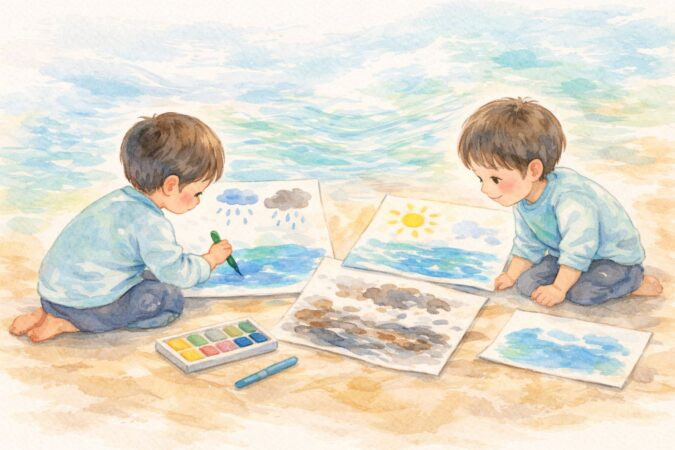
同じ絵を何度も描く姿を見ていると、
「これって大丈夫なのかな?」と
少し気になることもありますよね。
色やモチーフが気になる方は、
こちらの記事も参考にしてみてください。
🔗黒い絵・暗い色ばかり描くとき
🔗色使い・配置で分かる気持ち
アンパンマンの顔、お花、それとも大好きな電車の横顔……。
大人から見れば「また同じ?」と思うことでも、子どもにとっては一筆一筆が新しい冒険であり、大切な「心の言葉」なんです。
今回は、お絵描きが大好きでたまらないお子さんを持つパパ・ママへ。 その「飽きない力」の正体と、絵の中に隠されたキラキラした成長のサインについて、一緒に紐解いていきましょう。読み終わる頃には、お子さんが描く「いつもの絵」が、もっと愛おしく感じられるはずですよ。
この記事の内容
なぜ子どもはお絵描きが好きなの?心の中での「絵」の役割
子どもにとっての「描く」という行為は、私たち大人が「日記を書く」とか「SNSに投稿する」のとは、少し重みが違います。
自分の気持ちを「見える化」する魔法
まだ言葉を自由自在に操れない子どもたちにとって、絵は「心の通訳」です。
「今日これを見てびっくりした!」「これが大好き!」という溢れる感情を、彼らは色や線に託して外に出します。

たとえば、画用紙いっぱいに描かれた力強い赤い線。それは「怒っている」のかもしれないし、あるいは「エネルギーが有り余っていて最高に楽しい!」という爆発した喜びかもしれません。絵を描くことで、彼らは自分の中にある目に見えない「気持ち」を形にし、整理しているのです。
安全で、自分だけの「絶対的な場所」
お絵描きには「正解」がありません。先生に直されることも、誰かに「それは違う」と言われる筋合いもない、子どもにとって聖域(セーフ・スペース)です。

外の世界では「前を向きなさい」「お着替えしなさい」とルールに囲まれている子どもたち。でも、白い紙の上だけは自由です。自分で色を選び、自分の好きな場所から線を引く。この「自分で決めて、実行できる」という感覚が、子どもに大きな安心感と全能感を与えてくれます。
「飽きない」のは心の成長の証?
「また同じキャラクター?」と親は思ってしまいますが、実は「同じ」に見えて、子どもにとっては毎回違う挑戦が行われています。
反復が育む「心の根っこ」
子どもが同じ絵を何度も描くのは、「納得したいから」です。 一回描いただけでは掴みきれなかった形、色の混ざり方、手の動かし方。それを何度も繰り返すことで、自分のものにしようとしています。これは、プロのスポーツ選手が素振りを繰り返すのに似ていますね。
この「繰り返し」を通じて、子どもの心には「予測できる安心感」が育ちます。「こう描けば、こうなる」という手応えを積み重ねることで、彼らは世界に対する信頼感を深めていくのです。
だからこそ、同じ絵に没頭している時間は、
集中力や粘り強さを、知らないうちに心に貯めている時間でもあります。
「飽きずに続ける」経験そのものが、子どもの大切な土台になっていくんですね。
絵に隠された「心の成長」
何度も描くからこそ、昨日とは違う「1ミリの変化」が生まれます。
年齢ごとの絵の変化:サインを見逃さないで
- 1〜2歳頃(なぐりがき期): 手を動かすことそのものが楽しい時期。「自分の動きが跡になる」という発見に興奮しています。
- 3〜4歳頃(象徴期): 丸の中に顔を描いたり(頭足人)、意味を持たせ始めます。この頃の「同じ絵」は、お気に入りを確認する儀式です。
- 5歳〜(図式期): 地面を描き、その上に家や人を配置します。客観的な視点が育ってきた証拠です。
何度も同じものを描くことで、ある日突然「あ、今日は指が5本ある!」「まつ毛が描いてある!」と細部がアップデートされる瞬間があります。これは、観察力と表現力が爆発的に伸びているサインです。
「これも成長のサインなのかな?」
そう感じた方は、
絵のテーマから読み取れる気持ちについても
まとめています。🔗家や家族の絵から分かること
「できた!」が作る自己肯定感

「描けた!」という達成感は、子どもの自己肯定感に直結します。 親が「また同じね」と言う代わりに、「その青、昨日より深くて綺麗な色だね」と、小さな変化を見つけてあげると、子どもは「自分を見てくれている」「自分の表現が認められた」と感じ、さらに自信を深めていきます。
親としてできること:子どもの絵をもっと楽しむ方法
お絵描きが大好きな子に対して、私たちは「特別な技術」を教える必要はありません。一番の栄養は、パパやママの「ポジティブな反応」です。
魔法のフィードバック術
「上手だね」という言葉も嬉しいですが、もっと喜ばれるのは「実況中継」です。
- 「わあ、ここ、すごく力強く描いたんだね!」
- 「この黄色、お日様みたいにポカポカして見えるよ」
- 「今日は画用紙の隅っこまで全部使ったんだね!」
評価(上手・下手)ではなく、「事実を伝える」ことで、子どもは「自分のこだわりが伝わった!」と大満足します。
表現の幅をそっと広げる
お絵描きが大好きな子には、たまに違う素材を提案してみるのも面白いですよ。
- いつもはクレヨンだけど、今日は水彩絵の具で。
- いつもは白い紙だけど、今日は段ボールの裏に。
- お絵描きの延長で、粘土で形を作ってみる。
「描くこと」が「作ること」や「伝えること」に繋がっていく過程を、遊びの中でそっとサポートしてあげたいですね。
「また同じ絵を描いてる」と感じたときの親の気持ちに寄り添う
とはいえ、親だって人間です。毎日何枚も同じ絵を量産されると、「もっと違うもの描けばいいのに」「これ、いつまで続くの?」と、少し焦ったり、マンネリを感じたりすることもありますよね。
その「焦り」の正体は?
私たちは無意識に「成長=変化」だと思いがちです。昨日と違うことができないと、停滞しているように感じてしまう。でも、子どもにとっての成長は、「深く掘り下げること」でもあります。
「同じ絵」は、お子さんにとっての「心の安全基地」です。新しいことに挑戦して疲れた時、外の世界でちょっと嫌なことがあった時、いつもの絵を描くことで自分を取り戻しているのかもしれません。
「またこれ?」と思った時は、「ああ、今は心を充電している時間なんだな」と捉え直してみてください。親の期待を一回横に置いて、ただ隣でお茶を飲みながら、その「飽きない力」を眺めてみる。そんな「余白」の時間が、実は一番の教育だったりします。
そんなふうに見守っていると、
ふと
「この集中を、もう少し深く味わえたらいいのに」
と思うこともあります。
でも、急がせなくても、
描く“モチーフ”を変えなくても、
描き方が変わる余地があれば、
子どもは自分で次に進んでいきます。
たとえばクレヨン。
一般的なクレヨンは、下の色をはじくので、
何度重ねても結果があまり変わりません。
けれど、色が重なって残る画材だと、
「こう塗ったら、ちょっと違う」
「今日はこっちの塗り方にしよう」
同じ絵の中で、
試す材料そのものが増えていきます。
描くものを変えなくても、同じ絵を、もっと深く楽しめる。
それは、
「今を大切にしたい子どもの気持ち」と
「成長してほしい親の気持ち」を
同時に守る、ひとつのやり方かもしれません。
※ 下の色が消えず、重ねた変化がそのまま残るタイプのクレヨンです。
まとめ|「また同じ絵」を、安心して見守れるようになるために
「お絵描き好きだなあ、よく飽きないなあ」
そう感じられる今の時間は、
実はとても静かで、豊かな成長の途中にあります。
同じ絵を繰り返し描くことで、
子どもは自分の世界を確かめ、
「これでいい」「ここが好き」という感覚を、少しずつ積み上げています。
昨日と同じに見える一枚の中にも、
線の強さ、色の重なり、迷いの跡――
昨日とは違う“1ミリ”が、ちゃんと息づいています。
「またそれ描いてるの?」
そう思ってしまったときは、
「いま、心を深く使っている時間なんだな」と
そっと言い換えてみてください。
大人が急がせなくても、
教え込まなくても、
その世界は、ちゃんと前に進んでいます。
「今のままで大丈夫そう」
そう感じられたら、
おうちでの“描く環境”を少しだけ整えてみるのもひとつの方法です。
我が家で実際に使っている、100円ショップで揃う画材収納の工夫をまとめました。
🔗子どものお絵描きがもっと続く|100均でできる画材収納アイデア
FAQ (よくある質問)
Q. 子どもが黒い色ばかり使います。心理的に何か問題があるのでしょうか?
A. 大丈夫、心配いりません!子どもにとって黒は「一番はっきり見える、かっこいい色」です。単に色の濃淡や力強さを楽しんでいることが多いので、他の色が使われていなくても、本人が楽しそうなら見守ってあげてくださいね。
Q. 同じキャラクターばかり描いて、想像力が育たないのでは?
A. むしろ逆です。一つの対象を徹底的に描くことで、その構造を理解し、自分のものにしています。「自分流」にアレンジし始めるための大切な準備運動だと思ってください。
Q. 親が絵の描き方を教えてもいいですか?
A. 「こう描きなさい」という指導よりは、「一緒に並んで描く」のがおすすめです。親が楽しそうに絵を描く姿を見せるのが、何よりの刺激になります。
お子さんが描いた絵、もしよかったら「今日はここが素敵だったよ!」というエピソードをコメントで教えてくださいね。一緒にその「大好き」を応援していきましょう!
ここまで読んでくださった方へ
―― もし、もう少しだけ深く知りたくなったら
お子さんのお絵描きについて考えていると、
「気持ちのこと」「成長のこと」「家でできること」
それぞれ、気になる方向が分かれてきます。
気になったところから、ゆっくり読んでみてください。
📌 気持ち・心理をもう少し深く知りたい方へ
- 🔗 【保存版】子どもの絵にあらわれる感情サイン一覧|不安・安心・怒りをやさしく読み解く
→ 絵が「心の言葉」になる理由を、具体例でまとめています。 - 🔗 黒い絵・暗い色ばかり描くとき|心配なサインと見守り方
→ 「この色、大丈夫かな?」と不安になったときの判断軸に。
📌 成長・発達の流れで捉えたい方へ
- 🔗 年齢・発達段階で変わる子どもの絵|3歳〜6歳までの心の成長サイン
→ なぐりがき期・象徴期・図式期を、発達の流れで解説しています。
📌 家庭でできる工夫を知りたい方へ
- 🔗 子どものお絵描きがもっと続く|100均でできる画材収納アイデア
→ 「もっと描きたい」を邪魔しない、環境づくりのヒントです。
ホーム » 「またそれ描いてるの?」に隠れた成長|同じ絵を描く子どもに育つ自信と集中力
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。









