― 男子も女子も、“原因不明のモヤモヤ”にどう向き合えばいい? ―
この記事の内容
- 「え、怒ってるの?」「いや、怒ってないけど?」の無限ループ🌀
- 🔍 親が知りたい“思春期のイライラ”に関するリアルな疑問
- 1. 思春期のイライラ、原因は“ホルモン”だけじゃない?
- 2. 男子と女子で違う?イライラの出方と傾向
- 3. 親の言葉が火に油?NG対応&OK対応まとめ
- 4. サプリや漢方、食べ物で落ち着くの?気になる対策
- 5. 「いつまで続くの?」親がラクになる“気持ちの持ち方”
- まとめ:思春期のイライラには“共感+余白”が効く
- 🌱 最後に|イライラの奥にある「気づきの芽」を、信じて待つ
- 💬 コメント欄でぜひ、あなたのエピソードも!
- 🔗 関連記事で深掘り!
- 太陽の絵から読み解く、お子さんの心理|親子で楽しむ深層分析
- 【保存版】3歳が「外ではいい子・家で爆発」する理由|叱る前に知ってほしい心の成長サイン
- わが子の描く指が8本ある理由。手足の数がバラバラな時の見守り方
「え、怒ってるの?」「いや、怒ってないけど?」の無限ループ🌀
中学生の息子に「おはよう」と声をかけたら、「は?」と返された朝。
高校生の娘が、突然バンッとドアを閉めたかと思えば、数分後には「今日のごはん何?」と普通に話しかけてくる…。
……あれ?今、地雷踏んだ?それとも空気が悪かった?それとも私、なにかした??

こんなふうに、思春期の子どもの“イライラ”に毎日振り回されている親御さん、いませんか?
安心してください。います。ここにも。
しかも、けっこういます。そして、だいたいみんな「なんで?何が原因なの?」と検索してます。
🔍 親が知りたい“思春期のイライラ”に関するリアルな疑問
- 思春期のイライラ、原因は?どうしてこんなに不機嫌?
- 男子と女子で違う?対処法はあるの?
- サプリとか漢方って効くの?それ以前に、親はどう関わればいいの?
- このイライラ、いつまで続くの?…まさか、ずっと?
この記事では、そんなモヤモヤを抱える親御さんに向けて、
“思春期のイライラを親がどう受け止めるか”を、ユーモアと愛でやさしく解説していきます😊
1. 思春期のイライラ、原因は“ホルモン”だけじゃない?
「まあ、思春期だしホルモンでしょ」と片づけられがちな子どものイライラ。
もちろん、ホルモンの急激な変化は大きな要因です。
男女ともに、体も心も一気に大人へ向かって動き出します。
これにより「なんだかイライラする」「理由はないけどムカつく」という現象が起きやすくなるんですね。
でも実は、イライラの原因はホルモンだけではありません。
思春期は、心も体も大きく変化する時期。
自分でもうまく言葉にできない「なんかモヤモヤする」という感情が、ふと湧いてくるようになります。
たとえばこんな場面、思い当たりませんか?
- クラスの誰かがズルをしても見過ごされている
- 誰かをからかったことで笑いが起きた
- 先生が特定の子だけをひいきしている気がする
- 自分が本当は言いたかったことを言えなかった
どれも一見「些細なこと」に見えるかもしれませんが、本人にとっては心に引っかかる“できごと”。
自分の中で正解がわからず、ただモヤモヤと残る。これが、思春期特有の悩みのかたちです。
- 自分の気持ちがうまく整理できない
- まわりと比べて自己肯定感が下がっている
- 親や先生、友達との関係にモヤモヤがある
- 言いたいことがあるのに、言葉にできないもどかしさ
思春期の子どもは、「感情」と「言語」の交通整理がまだ途中段階。
心の中がまるで“赤信号の交差点”のように混み合ってる状態なんです🚥
2. 男子と女子で違う?イライラの出方と傾向
思春期の「イライラ」は、男子と女子で出方が違うこともよくあります。
👦 男子のイライラあるある
- 「別に」「うるさい」と言ってドアをバンッ!
- 無言になる or いきなりキレる
- 親の目を見ない、スルーされる
→ 感情を外に出すのが苦手で、イライラが“無言の壁”になりやすい。
👧 女子のイライラあるある
- とにかく口調がトゲトゲしい
- SNSでのトラブルや友人関係のストレスを家に持ち帰る
- イライラと泣きが交互にくる
→ 感情を出す力は強いけれど、自分でもコントロールできずに苦しくなりやすい。
どちらにしても、「怒ってるように見えるけど、本当は傷つきやすい心がある」というのがポイントです。
だからこそ、「なに?怒ってるの?」とストレートに聞かずに、“受け止めのクッション”を用意してあげる対応がカギになります。
3. 親の言葉が火に油?NG対応&OK対応まとめ
❌ ありがちだけど逆効果なNGワード
- 「なんでそんなにイライラしてるの?」
- 「思春期だからって甘えるな」
- 「もっとしっかりしなさい」
- 「それはあなたが悪いよね?」
これら、つい言っちゃいそうですが…
子どもにとっては“否定された”と感じやすい言葉。
大人の“正論パンチ”が、子どもの心に「もう何も言いたくない」バリアを作ってしまいます。
「正しいことを教える」だけでは、心は開かれない
思春期の子どもが悩みを打ち明けてきたとき、つい親として「それは〇〇だからこうすべき」とアドバイスしてしまいがちです。
でも、それが正論であればあるほど、子どもは心を閉ざしてしまうこともあります。
「わかってほしい」のに、「正されてしまった」
そんな気持ちが重なって、話すこと自体をやめてしまうことも。
かつて私たちも、そうだったかもしれません。
「それはあなたの考えすぎじゃない?」
「〇〇だったから仕方ないんじゃない?」
…そんなふうに返されて、余計にモヤモヤが残ってしまった経験、ありませんか?
✅ おすすめの声かけや対応
- 「今日はなんか疲れた?」
- 「無理に話さなくてもいいけど、何かあったら聞くよ」
- 「気分が落ちてるときって、誰でもあるよね」
ポイントは、「感情を正さず、受け止めること」。
“聞いてもらえた”という経験は、子どもにとって心を落ち着かせる第一歩になります。
4. サプリや漢方、食べ物で落ち着くの?気になる対策
最近では「思春期 イライラ サプリ」や「思春期 漢方薬」といった検索も増えています。
実際、鉄分・ビタミンB群・マグネシウムなどが不足すると、感情の不安定さに影響することも。
また、「抑肝散(よくかんさん)」という漢方が一部で注目されていたり、
ツボ押しや食事の工夫で穏やかになるケースもあります。
とはいえ、サプリや漢方は“補助的な手段”。
一番大事なのは、「あなたの気持ちを大事に思ってるよ」という親の関わりです😊
5. 「いつまで続くの?」親がラクになる“気持ちの持ち方”
思春期のイライラは、ずっと続くわけではありません。
一般的に、中学生〜高校生の終わりくらいまでがピークとされます。
ただし、子どもによっては早く落ち着く子もいれば、20代になっても「自己形成の葛藤期」が続くことも。
親としては、「この時期は“通過点”なんだ」と受け止めつつ、
“すぐに解決しようとしないスタンス”を持つことが、何より自分の心をラクにします🍵
モヤモヤは、心の成長のサイン
思春期の子どもが抱える「違和感」や「不安定な感情」は、心が育っている証。
他人の言動を観察し、自分の感情を見つめ、うまくできなかった自分にも葛藤する。
この「ぐちゃぐちゃな時間」こそが、自己形成の大切なプロセスなのです。
大人になれば、「あ、この人はこういう人なんだ」と、自分の心を守る術も身につきます。
でも、それはすぐには身につきません。
いまの子どもたちは、その「途中」にいるだけ。
だからこそ、焦らず見守ることが必要です。
まとめ:思春期のイライラには“共感+余白”が効く
- 思春期のイライラの原因は、ホルモンだけでなく自己形成の揺れによるもの
- 男子・女子それぞれに合った「寄り添い方」がある
- 親はアドバイザーではなく、“聞いてくれる人”になるのが一番の支え
- サプリや漢方は補助としてOK。ただし本質は“心の居場所づくり”
- イライラはいつかおさまる。だから焦らず、構えすぎず、ただ見守ろう
💬 あなたの体験、ぜひコメントで教えてください!
- うちの子はこうでした!
- こう接したらうまくいった or 大失敗した…
そんなリアルな声が、他の誰かの救いになります✨
🔗 関連リンクもどうぞ
🌱 最後に|イライラの奥にある「気づきの芽」を、信じて待つ
思春期の子どもがイライラしていると、
親としては「なんでそんなに怒ってるの!?」「こっちが泣きたいよ…」と心が折れそうになりますよね😅
でも、イライラの裏には「自分でもよくわからない不安」や「本当は甘えたい気持ち」が隠れていることもあります。
それは、子どもが自分の心と向き合おうとしている証拠でもあるのです。
🌸 子どもに必要なのは、正解ではなく「安心感」
- 正論よりも、「うんうん」と聞いてくれる人
- 注意よりも、「どうした?」と寄り添ってくれる人
- 解決よりも、「一緒に考えようか」と言ってくれる人
親も、人間です。いつも冷静に聞けるわけではないし、言いすぎてしまうこともあります。
でも、大切なのは「正しくあること」ではなく、「一緒にぐるぐる悩める存在であること」。
「どうしたらいいか」ではなく、「どう感じたのか」を一緒に見つめる姿勢が、子どもにとって安心になります。
💬 コメント欄でぜひ、あなたのエピソードも!
- 「娘の機嫌が3秒ごとに変わります」
- 「息子は無言の圧がすごいです…」
- 「試してうまくいった声かけ、シェアします!」
どんな小さなことでもOK♪
あなたのリアルな経験が、きっと誰かの救いになります🍀
🔗 関連記事で深掘り!
「思春期のイライラ」についてもっと知りたい方は、こちらもどうぞ👇
- 担任と合わないときどうする?不登校を防ぐための親の声かけ – itti-blog
- 「いい子」なのに家で荒れる理由は?──その“わがまま”は信頼のしるしかもしれません – itti-blog
- 【子どもが脱走する理由とは?】家から飛び出す子の心理と親ができる5つの対応|HSC・発達障害の子にも – itti-blog
|
|
ホーム » 【思春期のイライラ対処法】「うちの子、なんでこんなに怒ってるの?」と思ったら読むブログ
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
|
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a3494c5.bd14c8e2.4a3494c6.37431968/?me_id=1421621&item_id=10000990&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fangelingg%2Fcabinet%2Fag-r-00141%2Fag-r-00141.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

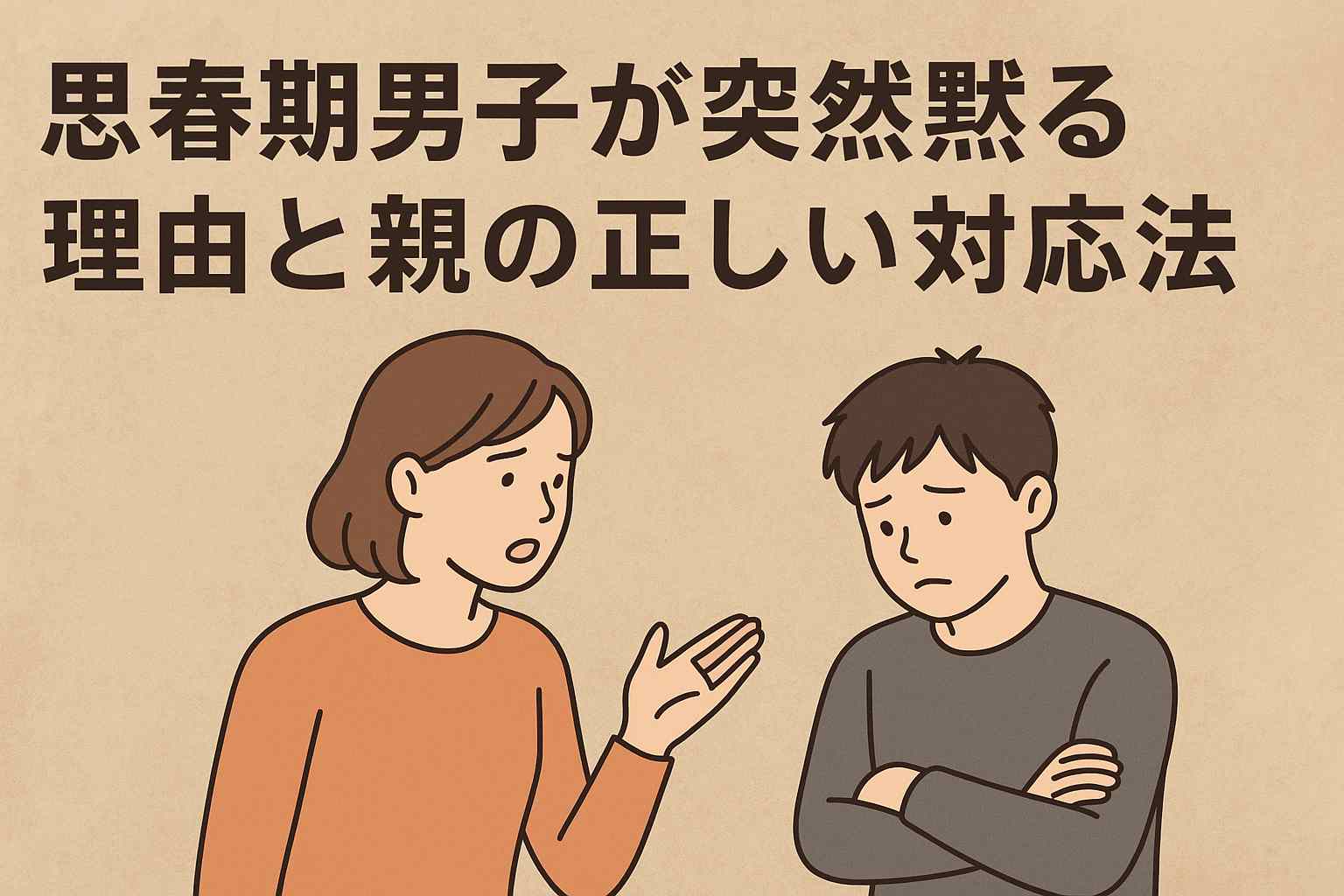
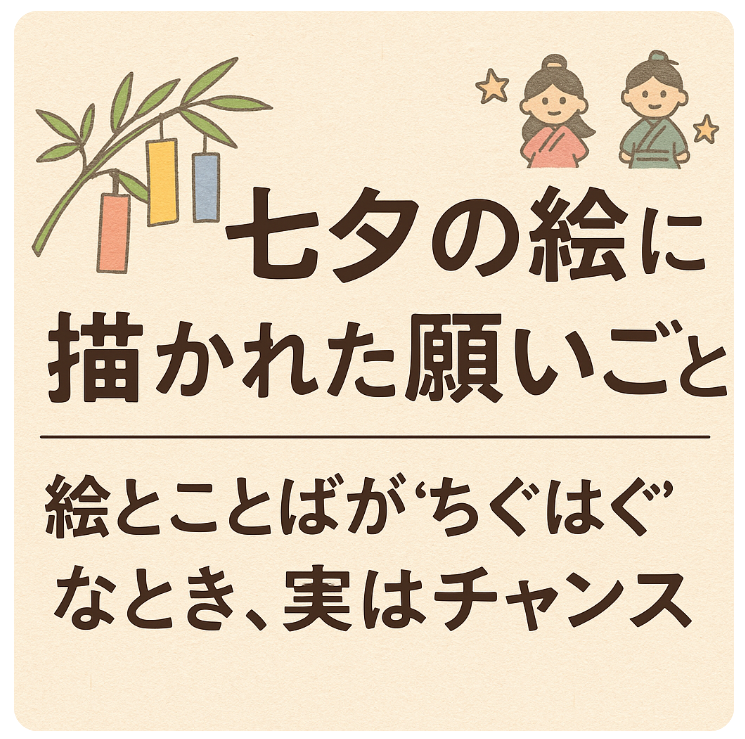


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49f0adcf.3a19a04c.49f0add0.8330ecd0/?me_id=1384549&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fherbgardenmoco%2Fcabinet%2F07613529%2Fimgrc0087513701.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49f0a997.7ef4780a.49f0a998.d6ef5370/?me_id=1274827&item_id=10072642&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftsuruha%2Fcabinet%2Fshouhin58%2F4987045182846.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


