このブログはPRを含みます
いろんな教材があふれているけれど、
「そろそろ何か始めてみたいな」と思っている方へ。
まず大切なのは、“文字を書くこと”そのものよりも、
その前の「考える力」「手を動かす力」「やりとげる経験」を積み重ねること。
小学校に入る前の時期は、知識を詰め込むよりも、
“学ぶことが楽しい”という気持ちを育てるチャンスなんです。
1.【ポピー】親子で無理なく「できた!」を積み重ねるワーク
「ポピー」は、見やすくてやさしいデザイン。
一人でも取り組みやすい構成なので、親は「見守り役」に回れます。
丸つけやシール貼りなど、“関わりやすいしかけ”が豊富。
一緒に「できたね!」を共有することで、
子どもの中に「学ぶ=うれしい」という感情がしっかり根づきます。
特に、
- 褒められると意欲が高まるタイプの子
- 「一人でやってみたい!」が芽生え始めた子
にぴったり。

この時期に「机に座る時間」を少しずつ作るだけでも、
のちの「自分で時間を管理する力」につながります。
じぶんで考えるのがすきな子にぴったり!
2.【Z会 幼児コース】考える力を引き出す“問いかけ型”教材
Z会の教材は、シンプルながら“深く考える”問いが多いのが特徴。
「なぜそう思うの?」「こうしたらどうなる?」と、
親の問いかけを通して、考える力・言葉で表す力がぐんと伸びます。
- 観察や推理が好きな子
- じっくり考えるのが得意な子
には特におすすめ。
Z会で育つのは「正解を出す力」よりも、
「自分で考える姿勢」。
この力は、小学校の作文や理科の観察、発表などにもしっかりつながっていきます。
コツコツがんばるタイプに合いそう!
「まさにうちの子!」と思ったら、まずは無料お試しから始めてみてください。
3.【くもんのドリル】「ちょっとずつ」「繰り返し」で自信を育てる
くもんのドリルは、反復で定着を促すタイプ。
内容が細かく分かれているので、
1日1ページのペースでも着実に力がつきます。
特に、
- 几帳面・コツコツ型の子
- 繰り返しが安心できる子
にぴったり。
線をなぞったり、数字を並べたりする作業は、
手先の巧緻性を高め、文字を書く準備にもなります。
「同じことの繰り返し」も、子どもにとっては安心感。
「今日もできた!」という積み重ねが、
「自分は頑張れるんだ」という自信へと変わります。
手を動かして学ぶのが楽しい子に◎
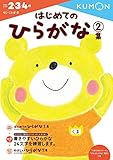
はじめてのひらがな 2集 (もじ・ことば 2)
4.【七田式ドリル】“ひらめき”と“感性”を育てるアプローチ
七田式のドリルは、「右脳教育」で有名。
イメージを使って記憶したり、パターンからひらめきを得たりするワークが多く、
“考えるのが好き”な子の好奇心を刺激します。
- 絵や図形が得意な子
- 感性や想像力が豊かな子
に特におすすめ。
学校での「覚える学習」よりも、
「気づく」「感じる」力を育てることで、
後の読解力や発想力に大きく差が出ます。
発想がゆたかな子におすすめ!
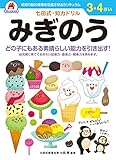
【七田式・知力ドリル 3,4歳 みぎのう 】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備
いろいろ試してわかった、教材それぞれのよさ
うちの子が最初に始めたのはポピーでした。
勉強というより、親子で一緒にあそぶ感覚で取り組めたのがよかったです。
「できた!」のたびに一緒に喜べて、初めてのワークにちょうどいい入り口でした。
そのあとに取り入れたのが七田式プリント。
紙のサイズや文字の大きさが幼児にぴったりで、
もじ・かず・ちえの3つがバランスよく進められるのが◎。
「七田式プリントA」 ◯☓が書ける、大小・長短のわかるお子さまに
年長になるころには、Z会の幼児コースにステップアップ。
考える問題や長い文章も増えて、1問にじっくり取り組む時間が増えました。
そのまま小学生コースへ進んだので、入学後もスムーズに学習できた気がします。
興味を持った分野については、補助的にくもんのドリルも取り入れていました。
見やすくて、1枚ごとに「できた!」が味わえる構成が魅力。
コツコツ積み上げるタイプの子には特におすすめです。
おうち時間がちょっと楽しくなりますね。
家庭で幼児教材を続けるコツ(親子で楽しむ習慣づくり)
「いつやるか」は、子どもと一緒に決めてみましょう。
我が家では、夕飯の支度中の時間に「ドリルタイム」を作っていました。
幼児のドリルはあっという間に終わるので、
親から見ると「物足りない」と感じるかもしれません。
でも大事なのは、毎日机に向かう習慣を作ること。

我が家の長男はこの習慣が今も続き、
小学6年生になった今では、
自分で時間配分を考えながら宿題や予習をこなしています。
一方、次男は自由奔放で、宿題をよく忘れて怒られます(笑)。
でもそれも性格の違い。
「合う教材を、その子のペースで選ぶこと」こそ、長続きのコツです。
✅ 幼児教材を選ぶときのチェックリスト(家庭学習の準備)
家庭で教材を選ぶ前にチェックしたい5つのポイント
- □ 子どもの「今の興味」に合っているか
- □ 無理なく1日5〜10分でできるか
- □ 親が“見守り役”で関われる設計か
- □ 遊び・思考・感性のバランスが取れているか
- □ 続けたくなるしかけ(シール・丸つけ・達成感)があるか
+αおすすめ:赤のサインペンで「がんばり」を一緒に見守る
おうちでの丸つけには、親が使う「プラチナ万年筆 採点ペン ソフトペン レッド」がおすすめです。
なめらかな書き心地と発色のよさで、さっと丸をつけるだけでも気持ちが伝わります。
「今日もここまでがんばったね」と声をかけながら使うと、ちょっとしたごほうびタイムに。
このペンは、インクカートリッジやペン先を交換して長く使えるタイプ。
お気に入りの一本を長く使うことで、“親のがんばり時間の相棒”にもなってくれます。
習慣になってくると、子どもが「まるつけして~!」と、このペンを一緒に持ってくるようになりますよ。
赤ペンは“がんばりのしるし”。
親子で「できたね!」を共有する小さな時間に。

プラチナ万年筆 採点ペン ソフトペン レッド SN-800Cパック#75
💬 Q&A
Q1:どのくらいの時間やればいいですか?
A:最初は「1日1ページ・5分」でOKです。習慣づけが目的なので、長さより“続けること”を大切にしましょう。
Q2:親はつきっきりじゃないとダメ?
A:いえ、むしろ「見守り役」でOKです。声かけや花丸スタンプなど、“関わりやすい形”を工夫してみてください。
Q3:教材を嫌がるときはどうしたら?
A:無理に続けず、“好きなテーマ”に切り替えてみましょう。迷路や観察系ドリルも立派な学びです。
Q4:どの教材から始めればいい?
A:「やりたそう」と思える見た目のものを。最初の印象が“学ぶって楽しい”を作ります。
まとめ
学びのスタートは、「書く」「覚える」よりも、
「やってみたい!」という気持ちから。
家庭でのドリルやワークは、
子どもの“できた”を増やすだけでなく、
考える力・続ける力・感じる力を育ててくれます。
家庭でできる幼児教材は、「学ぶって楽しい」を育てる第一歩。
小学校につながる“考える力”を、親子で楽しく育てていきましょう。
関連記事
📚 子どもの自信と安心をそっと育てるガイド
子どもが「できたかも」と感じられたり、ほっとできる時間が少しずつ増えていくための関わり方をまとめています。
ゆっくり全体を見たいときにどうぞ。
ガイドページを見るこのブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
🔗家でできる知育あそび|年齢別に楽しむ!遊びながら考える力を育てよう
このブログはPRを含みます
こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです。
このブログでは、子どもの絵から心理を読み取り、心の成長や表現力を親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。
「子どもの絵で心を読む専門サイト」として、日々の子育てに役立つ情報をお届けします。



