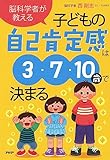「うちの子、褒めても“できた!”って言わないんです」
「せっかく頑張ったのに、あっさり“もういい”って言うんです」
そんなとき、親としては「もっと自信をもってほしい」と思いますよね。
でも実は、“できた!”を言えない子どもの多くは、
「ちゃんとできるかな」「失敗したらイヤだな」という不安をかかえたまま頑張っていることがあります。
今回は、3〜5歳の子どもが「できた!」を言えない心理と、
自己肯定感を育てるための“安心体験”の積み重ね方を、元教諭の視点でお伝えします。
この記事の内容
子どもが「できた!」を言えないのは、失敗が怖いから
頑張りたいけど「うまくいかない自分」がイヤ
幼児期の子どもは、「やってみたい!」という気持ちと「失敗したくない」気持ちを行き来しています。
絵を描いたりブロックを積んだりしていても、うまくいかないと「もういい」とやめてしまうことがありますよね。
それは“投げ出した”のではなく、「これ以上うまくできない自分」にがっかりしているサインです。
「できた!」と言って違う反応をされる不安
「できた!」と伝えても、親が「ここはこうしたほうがいいね」と返すことが続くと、
子どもは「また直されるかも」と感じて言わなくなることもあります。
「できた」と感じた瞬間を、誰かと喜び合いたいだけなのです。
それを否定されると、次第に「言わないほうが安心」と学んでしまいます。
大人の“評価のまなざし”を敏感に感じ取っている
幼児は、大人の反応を想像して行動するほど繊細です。
「まだ下手ね」「もう少し頑張ろう」といった言葉が、
「うまくできないとダメなんだ」と受け取られることも。
親が“見守る目”でいるか、“評価する目”でいるかを、子どもは敏感に感じ取ります。
子どもに必要なのは“成功体験”よりも“安心体験”
結果よりも「やってみても大丈夫」という空気

「うまくできた・できなかった」よりも、
「やってみても大丈夫」という安心があると、子どもは挑戦を続けられます。
逆に、「失敗したら怒られる」「笑われるかも」と思うと、
自分から動く力がしぼんでしまうのです。
できた!楽しい!もっと!
「3できメソッド」で子ども&先生が輝く保育のしかけ
「できた!」が言えない子に必要なのは、成功体験ではなく“安心体験”。
子どもも先生も笑顔になる“3できメソッド”がわかりやすく紹介されています。
「失敗しても笑われない」「最後まで見てもらえる」経験
幼児にとって、安心体験とは“自分が受け入れられる”経験のこと。

たとえば、うまく塗れなかった塗り絵を見て、
「がんばって塗ったね」と言ってもらえること。
途中で失敗しても、最後まで見守ってもらえること。
こうした体験の積み重ねが、「またやってみよう」を支えます。
🔗「できた!」の笑顔が見たい!幼児のお絵描きで自己肯定感アップ
「失敗してもだいじょうぶ」と思える子は、挑戦できる
できた・できないの結果よりも、
「大丈夫」「見てくれてる」という感覚が、自己肯定感の土台です。
安心して失敗できる子は、やがて安心して挑戦できる子になります。
「安心体験」を増やすための親の関わり方
完成より“過程”を見て声をかける

「できた?」よりも、「どんなふうにやってるの?」
「ここに青を塗ったんだね」「工夫してるね」と、
プロセスを一緒に味わう言葉をかけてみてください。
「見てもらえた」という実感が、“できた!”の自信につながります。
失敗を笑わない・助けすぎない・一緒に味わう
失敗して泣いているときこそ、
「そうだったね」「悔しかったね」と共感してあげましょう。
「助けてあげる」より、「気持ちを受け止めてもらえた」経験が、
“次は自分でやってみよう”という力を引き出します。
「見てもらえてる」と思える環境をつくる
完成した作品を壁に貼る、写真を撮って見せるなど、
子どもが「見てもらえてる」と感じられる工夫をしてみましょう。
「ぼくの(わたしの)頑張りは、ここにある」と見える形が、
自信を積み上げていく支えになります。
小学生以降にもつながる「安心の根っこ」
「できる/できない」より「やってみよう」が自然に出てくる

幼児期に“安心して挑戦できた経験”がある子は、
小学校に入ってからも「失敗しても平気」と思える強さを持ちます。
それが、学びへの意欲や粘り強さの土台になります。
親が“見守る目”でいることが、子どもの自己肯定感を守る
「大丈夫、あなたならできるよ」という信頼のまなざしは、
子どもにとって何よりの安心です。
親が「見守る目」でいられること。
それが、子どもが「できた!」と心から言える瞬間を増やしていきます。
おすすめの本紹介
📚 「できた!」が言える子に育てたい親へおすすめの2冊
どちらも、「自分でやってみよう」という気持ちを育てるヒントが満載の1冊です。
💬Q&Aコーナー|「できた!」を言わない子への関わり方
Q1:褒めても「できた!」と言わないのは、なぜ?
A:褒められてもうれしそうにしないときは、照れや不安が混ざっていることがあります。
「うれしかったね」「頑張ったの見てたよ」と、気持ちに寄り添う言葉が安心につながります。
Q2:「できた!」を言わないまま成長しても大丈夫?
A:大丈夫です。幼児期に「安心して挑戦できた経験」があれば、小学生になっても自然と挑戦できる子に育ちます。
焦らず、見守るまなざしを大切にしましょう。
Q3:何かできたとき、どんな言葉をかけたらいい?
A:「できたね!」のあとに「どんなところが気に入ってる?」と聞いてみるのもおすすめです。
自分の工夫を言葉にできることで、「自分のやったことに意味がある」と感じられます。
🪞チェックリスト|「安心して挑戦できる環境」になっていますか?
□ 「うまくいかなくても大丈夫」と伝えられている
□ 子どもの作品を評価より先に「見てくれてる」と伝えている
□ 失敗したときに「悔しかったね」と気持ちに寄り添えている
□ 「できた?」ではなく「どうやってやったの?」と聞けている
□ できた瞬間を一緒に喜べている
□ 子どもの挑戦を、最後まで見守れている
□ 家の中に「がんばった証」を飾っている
一つでも「できてる」と思えたら、それがもう十分な安心の種です🌱
焦らず、少しずつ“安心して挑戦できる日常”を増やしていきましょう。
🩷まとめ
「できた!」を言わない子どもは、
ほんとうは“安心して失敗できる場所”を探しています。
成功よりも、安心を感じながら挑戦する経験を重ねることで、
子どもは自分を信じて「できた!」を言えるようになります。
親のまなざし一つで、子どもの心の中に「大丈夫」が育っていく。
それが自己肯定感のいちばんの根っこです。
関連記事
ホーム » “できた!”を言えない子どもの心理|安心体験で育つ自己肯定感
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。