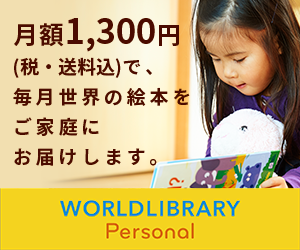今日からできる!子どもの共感力を育てる習慣10選
子どもとの会話で「わかってもらえた」と感じさせる小さな習慣は、自己肯定感を育てる魔法のような力があります。ここでは、親が今日から実践できる具体例を紹介します。
1. 「今日どんな気持ちだった?」で1日を振り返る
登園前や帰宅後に、1分だけでも聞いてみましょう。
例:「今日、楽しかったことはあった?」
短くても共感のやり取りを積み重ねることが大切です。
2. お絵描き・ぬりえ中に気持ちを聞く
子どもが絵を描いているときに、色や形について話を聞きます。
例:「この赤を選んだのはどんな気持ち?」
遊びながら自然に気持ちを言語化できます。
3. 「話してくれてありがとう」を必ず言う
子どもが話した内容に対して、聞き終えた後に一言添えます。
例:「今日も話してくれてありがとう。嬉しかったよ」
感謝の言葉は安心感と自己肯定感を高めます。
4. 相づち・うなずきを大げさにしてみる
話を聞くときに、テンポよく「うんうん」「へぇ〜」「そうなんだ」と反応。
大げさにやることで子どもは楽しく話せます。
5. 気持ちに名前をつけてあげる
「悲しい」「悔しい」「うれしい」など、子どもの感情にラベルをつけます。
例:「順番抜かされちゃったんだね。それは悲しかったね」
感情を整理する力が育ちます。
6. リピート・オウム返しで聞いていることを示す
子どもの言葉を繰り返して返すだけでも、安心感が生まれます。
例:
子ども:「友だちに怒られちゃった…」
親:「怒られちゃったんだね。そりゃイヤだったね」
7. 家族の出来事を話題にして共有
自分の1日の出来事を少し話すだけで、子どもも話しやすくなります。
例:「今日ね、スーパーで転んじゃったの。ちょっと恥ずかしかったよ」
親が共感を受け入れる側にもなることで、会話のキャッチボールが生まれます。
8. 失敗談を交えて安心感を与える
「私も子どものとき似たようなことがあってね…」と、自分の失敗体験を話す。
子どもは「失敗しても大丈夫」と思えるようになり、自己肯定感が育ちます。
9. 食事やおやつタイムを会話のチャンスに
ごはんやおやつの時間は、ちょっとした気持ちの整理タイム。
例:「今日の給食で一番おいしかったのは?」
楽しい質問で気持ちを表現する習慣が身につきます。
10. 寝る前のふりかえりトーク
一日の終わりに、短くても振り返る時間を作ります。
例:「今日、嬉しかったことと困ったことは?」
就寝前の安心感と自己肯定感の両方につながります。
ポイントまとめ
- 共感は特別なスキルじゃなく、日々の積み重ねで育つ
- 1回の会話で完璧を目指さなくて大丈夫
- 「話してくれてありがとう」「わかるよ〜」を自然に繰り返すだけで、自己肯定感がぐんと育つ







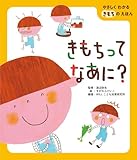

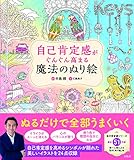





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a21f051.8e280e79.4a21f052.b4a891df/?me_id=1381750&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fluckyspread%2Fcabinet%2F07240546%2F10248259%2Fimgrc0078419063.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)