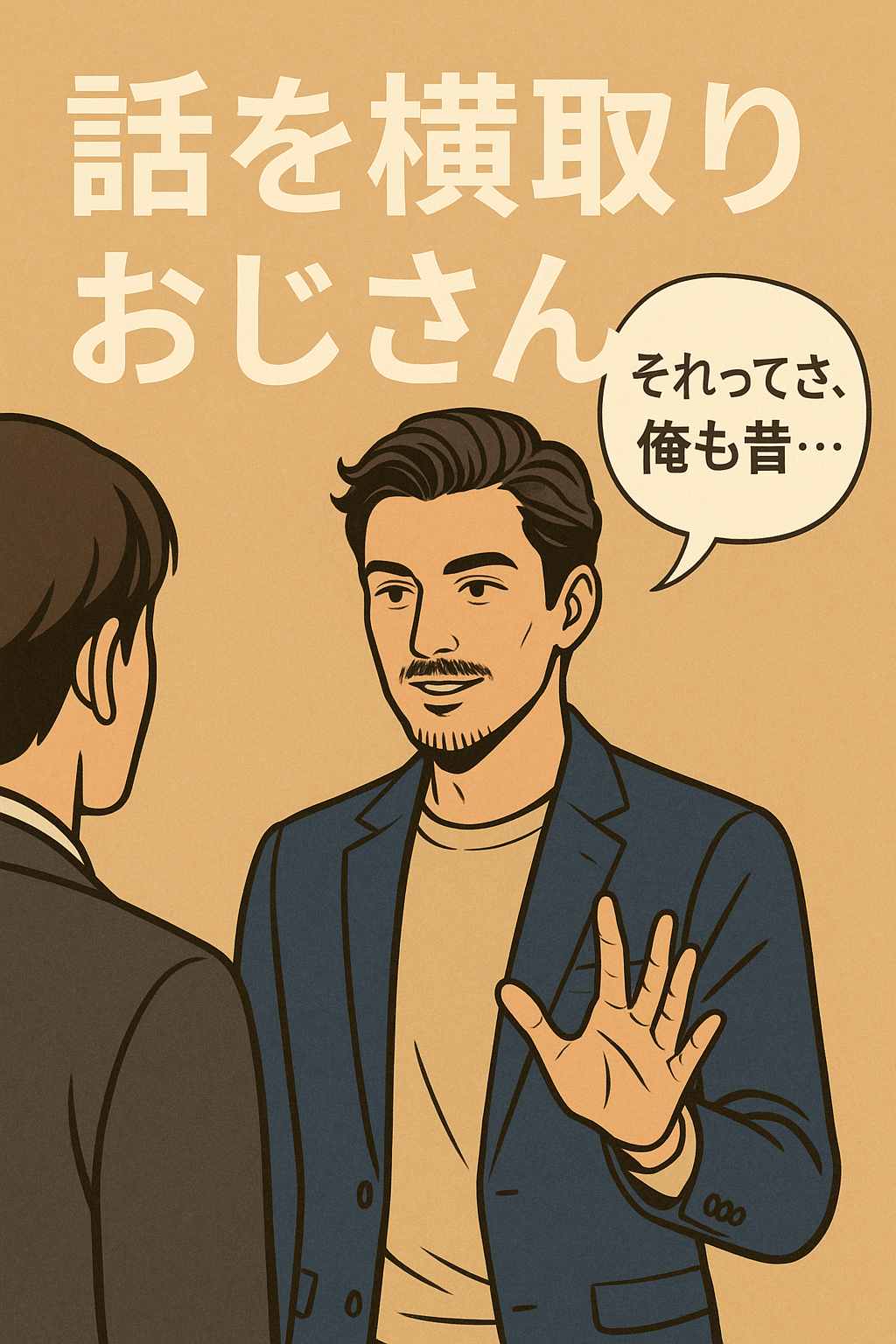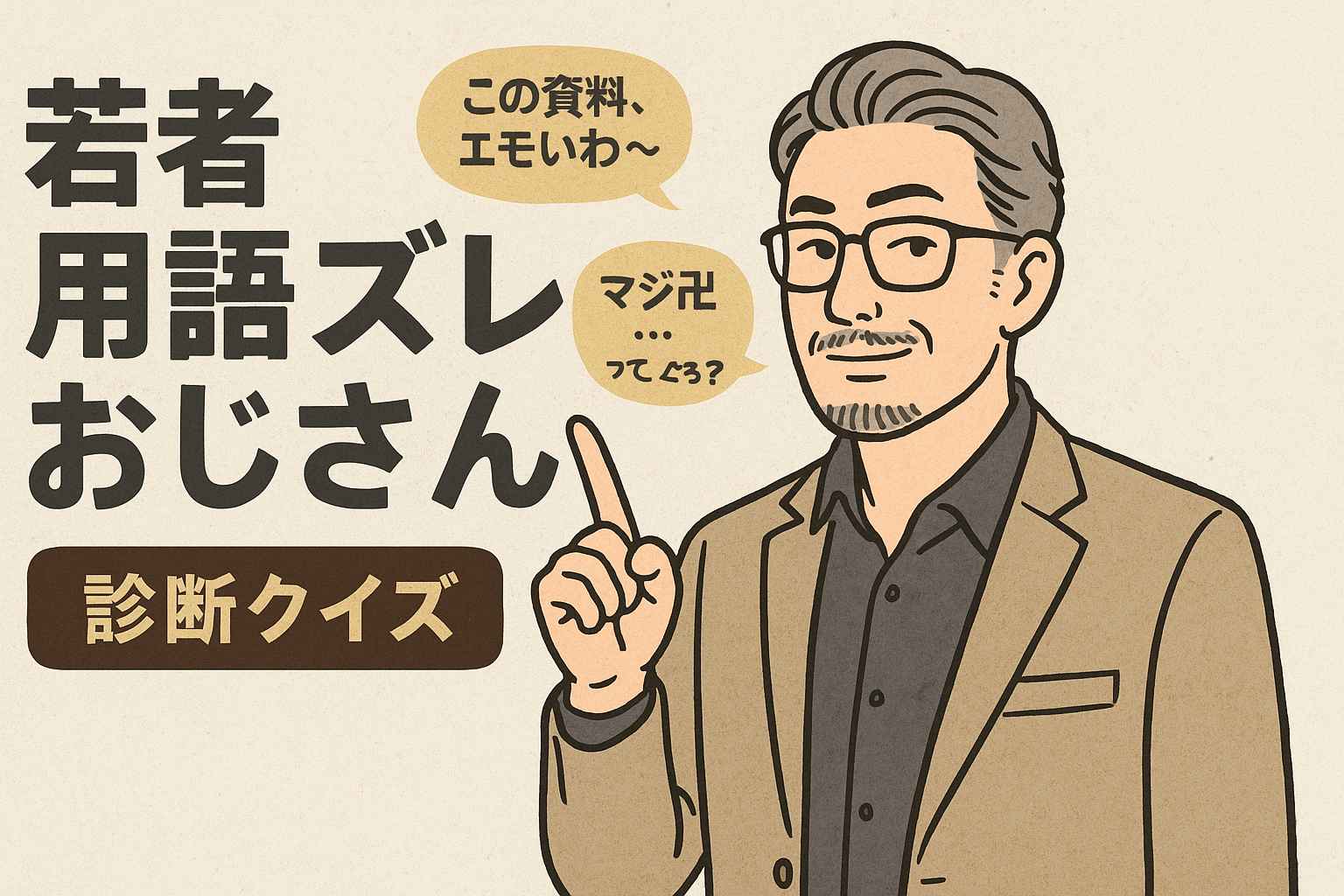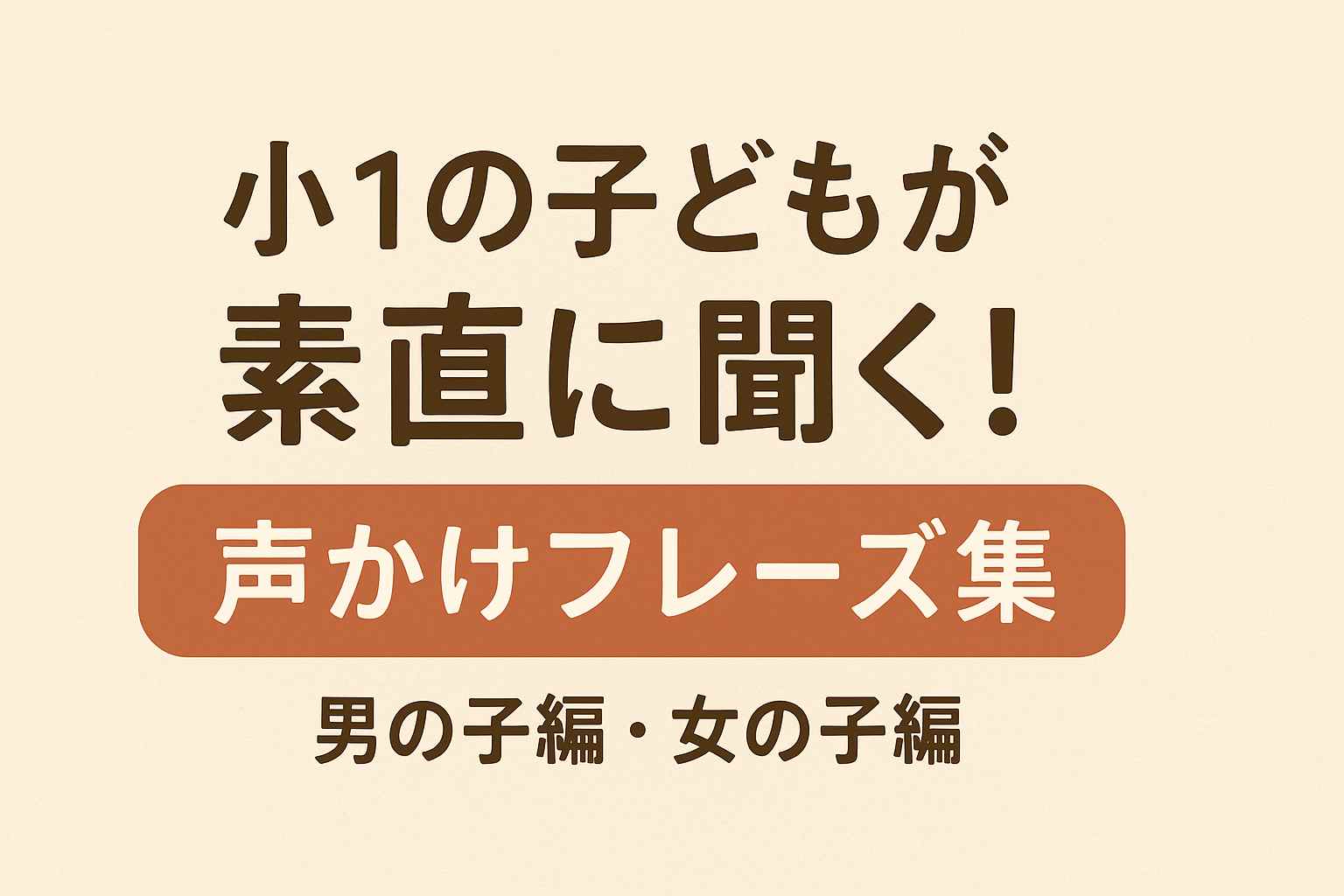著者:ITTI
更新日:2025-09-16
読了目安:7分
小学校1年生の子どもが初めて迎える「友達関係」には、さまざまなトラブルや悩みがつきものです。親としては、子どもが直面する心の葛藤にどう寄り添うべきか迷うこともありますよね。
この記事では、小1の子どもが抱えやすい人間関係の悩みや、親ができる見守り方について、元教諭の視点から具体的にアドバイスをお伝えします。
この記事の内容
小1の人間関係で親ができる見守り方
小学校生活の変化と子どもの心の成長
小学校に入学すると、園生活とは大きく環境が変わります。
- 毎日同じクラスの友達と過ごす時間が長い
- 勉強や遊びで協力する場面が増える
- 先生や友達とのやり取りの中で「社会性」が育つ
しかし、小1の子どもはまだ「相手の気持ちを想像する力」や「自分の気持ちをことばで表す力」が発展途上です。だからこそ、冗談やちょっとした強い言葉が誤解を生み、トラブルに発展しやすいのです。
親が気を付けるべきサインとは?
「今日は誰とも遊ばなかった」「明日学校行きたくない」などの言葉が出てきたら要注意。体調不良を訴えたり、表情が暗くなったりすることもサインの一つです。
大切なのは「子どもがどう感じたか」を尊重すること。「気にしすぎ」と切り捨てず、子どもの思いをそのまま受け止めてあげましょう。
小1の友達トラブルにどう対応するか|よくあるトラブルの例
- 遊びのルールをめぐってケンカになる
- 「入れてあげない」と仲間外れにされる
- 言葉づかいがきつくて傷つく
- 一緒に遊びたい相手が重なってモメる
この時期の子どもにとってはよくある出来事ですが、本人にとっては大きな悩みです。
親の言葉で心を支える方法
お子さんが「○○ちゃんにそんなこと言われた」と報告してきたら、まずは気持ちを受け止めましょう。
- 「そんなこと言われて嫌だったね」
- 「悲しい気持ちになったんだね」
こうした共感の言葉は、子どもに安心感を与えます。
その後で「じゃあ、どうしたらいいと思う?」と一緒に考えていくことで、問題解決力を育むことができます。
傷ついた子どもをどうサポートする?
トラブルが起きた時、親がすぐに「相手が悪い!」と決めつけたり、「気にしなくていいよ」と片付けてしまうのは逆効果です。
子どもは「自分の気持ちをちゃんと聞いてもらえた」と思えることで、立ち直る力を持てるようになります。
こどもの自己肯定感を育てる親の声かけ・かかわり方
今日から使える具体フレーズで、叱る前に「気持ちを受け止める」関わりへ。 家の中に「安心できる場所」を増やしましょう。
学校でのトラブル、先生に相談するべき?
相談するタイミングと親のサポート方法
繰り返しトラブルが続く場合や、子どもが強く落ち込んでいる時には先生に相談することを検討しましょう。
ただし、最初から「どうにかしてください」と丸投げするのではなく、
- 子どもから聞いた状況を淡々と伝える
- 相手を一方的に責める言い方は避ける
- 家庭でどんなサポートをしているかを共有する
このように先生と協力体制を築くことが大切です。
子どもに安心感を与える言葉とは?
「学校で困ったことがあったら、先生に話してみようね」
「お母さん(お父さん)も一緒に考えるから大丈夫だよ」
こうした言葉をかけておくと、子どもは学校で安心して過ごしやすくなります。
\ 栄養が偏りがちな子におすすめ!/
給食が苦手で「栄養は大丈夫かな…」と不安になること、ありませんか?
うちでは おやつ感覚で食べられる成長サポートサプリ『ノビルン』 を取り入れています🍬
- モンドセレクション金賞を9年連続受賞
- シリーズ累計300万袋突破!
- カルシウム+ボーンペップで成長期をサポート
- ラムネ・ココアチョコ・ぶどう・パインの4つの味
「自分から食べてくれるから助かる!」と口コミでも評判です😊
心の成長を支えるために親ができること

つらい経験をどう乗り越えるか
友達関係で傷ついたり、悔しい思いをしたりすることも、子どもにとっては大切な経験です。
「なぜこうなったのかな?」と考える過程で、人との関わり方を学び、自分なりの解決法を見つけていきます。
親子で共感する大切さ
親が「つらい経験も成長の糧になるんだよ」と言葉で教えるよりも、まずは気持ちを共感することが第一歩です。
「そうだったんだね」「そう感じたんだね」と寄り添うだけで、子どもは安心して気持ちを整理できるようになります。
まとめ
小1の友達関係は、子どもが社会性を学ぶ大切なステップです。
親ができるのは「気持ちを受け止めること」と「安心感を与えること」。トラブルを乗り越える経験は、子どもの心を強くし、成長につながります。
焦らずに、温かく見守っていきましょう。
関連記事
👉 こちらもおすすめ:
・子どもの絵に出る“環境変化のサイン”とは?親が気づけるヒント
・夏休みのポスター宿題を親子で乗り越える方法
「うちの子、作文となると筆が止まっちゃうんです…」というご相談、よく伺います。最近はマンガ仕立てで書く力を伸ばせる教材も登場しており、楽しみながら文章力を育てられる工夫が増えました。添削コメントが丁寧で「また書いてみたい!」と前向きになる子も多く、作文への苦手意識をやわらげるきっかけになります。

\子育て心理に関する人気記事/
こんな記事も読まれています/
\こんな記事もおすすめ/
ホーム » 小1の人間関係で悩むお子さんへ!親ができる見守り方と心のサポート
おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。