この記事の内容
子どもが“手をつなぎたがる”理由は、甘えじゃなく「安心の欲求」だった。わが家の「カピバラ・マッサージ」が教えてくれたこと
こんにちは。
子育てをしていると、ふとした瞬間に「これっていつまで続くんだろう?」と立ち止まってしまうこと、ありますよね。
最近、公園でこんな場面を見かけました。
小学生くらいの男の子が「手、つなご?」とお母さんに手を差し出したんです。お母さんは少し照れくさそうに、でも優しくその手を包み込んで歩き出しました。
とっても微笑ましい光景。けれど、よく聞くのは「もう小学生なのに、いつまで甘えるの?」「私の育て方が依存させすぎちゃった?」なんて、不安や焦りを感じてしまう方も少なくないようです。
でも、安心してくださいね。 子どもが手をつなぎたがるのには、ちゃんとした“理由”があります。
それは、単なる「わがまま」や「甘えすぎ」ではなく、もっと深くて、これからの自立に欠かせない「心の栄養」なんです。
今日は、つい「もう一人で歩きなさい!」と言いたくなってしまう自分を少しだけお休みさせて、子どもの差し出す手のひらの向こう側を一緒に覗いてみませんか?
「まだ手をつなぎたがる」ことに戸惑う親心
「うちの子、学校ではしっかりしてるって聞くけど、外に出るとすぐ手を繋いでくるんです」
「低学年ならまだしも、中学年になってもこれって普通なの?」
そんなふうに悩む親御さんは、実はとても愛情深い方なのだと思います。
「自立させなきゃ」と思うのは、お子さんの将来を真剣に考えている証拠ですから。
でも、買い物袋で両手が塞がっているときや、下の子を抱っこしているときに「手をつなご?」と言われると、正直なところ「今は無理!(白目)」と叫びたくなる瞬間もありますよね(笑)。
実は、この「手をつなぐ」という行動。子どもにとっては、私たちが想像する以上に大きな意味を持っています。成長とともに少しずつ「自立」を意識する時期だからこそ、実は「心の安全基地」を確認するサインが増えることもあるのです。
手をつなぎたがる心理|「甘え・不安」は成長のもと
小さな手でぎゅっと握ってくる。それは、ただの習慣ではありません。 「安心感」や「信頼関係」を身体全体で確かめようとしている、とても自然な行動です。
子どもが親の手を求めるのは、決して「愛情が足りないから」ではありません。むしろ逆です。 「この人は絶対に自分の手を受け止めてくれる」という強い信頼があるからこそ、手を差し出すことができるんです。
特に、以下のような場面で「手つなぎ」が増えることはありませんか?
・知らない場所、慣れない道を通るとき ・学校や園で、少し頑張りすぎた帰り道 ・連休明けなど、心のリズムが不安定なとき
そんなときに手をつなぐのは、スマホの充電器にプラグを差し込むようなもの。 外の世界で消費した「心のエネルギー」を、親というルーターから補給している最中なのです。
スキンシップが「自己肯定感」の根っこを育てる
最近よく聞く「自己肯定感」。これは、言葉での褒め言葉だけで育つものではありません。まずは「身体の感覚」としての安心感が土台になります。
「ぎゅっと手を握ってもらえた」
「自分のぬくもりが相手に届いた」
こうした小さな安心の積み重ねが、「自分はここにいていいんだ」「守られているんだ」という確信に変わり、やがて「一人で歩き出す勇気」へと繋がっていきます。
「甘えさせると自立できない」と不安になることもありますが、実は「十分に甘えられた子こそ、安心して自立していく」のが、子どもの心の不思議な仕組みなのです。
🌸 「甘え」は、幸せな記憶のバトン
実は私自身、子どもの頃はかなりの「甘えん坊」でした。 今でも鮮明に覚えているのは、自分のお母さんにしてもらう「耳かき」の時間です。
お母さんの膝枕、鼻をくすぐるお母さんのにおい。耳かきがカサカサと鳴る音を聞きながら、ただ身を任せているあの時間。世界で一番安全な場所にいるような、ふわふわした気持ち。
「あぁ、お母さんにくっついてると気持ちいいな」という感覚が、私の心の奥底に今も温かい灯火として残っています。
だからこそ、わが子がベタベタしてくるとき、私はときどきこんな話をします。
「お母さんもね、子どもの頃はお母さん(おばあちゃん)に耳かきしてもらうのが大好きだったんだよ。くっついてると安心するよね。だから、あなたも甘えていいんだよ」
そう伝えると、子どもは少し驚いたような、でも誇らしげな顔をします。 「甘え」は、恥ずかしいことじゃない。大好きのバトンなんだ。そう思えるだけで、親子の距離はもっとあたたかいものになります。
♨️ わが家の秘密兵器は「カピバラ・マッサージ」
とはいえ、現実問題として外でずっと手をつなぐのが難しい時もありますよね。 そんなとき、わが家で取り入れているのが、お家での「先回り充電」です。
その名も……「マッサージ屋さんごっこ」!
私が「お、今なら心に余裕があるぞ!」というタイミングを見計らって、軽やかに声をかけます。
「はい、お待たせしました。今ならもんであげられますよ〜♡」
すると、わが子がトコトコやってきて、嬉しそうに背中を差し出します。 もみ始めると、もう顔が「温泉につかったカピバラ」みたいに、とろ〜んと溶けていくんです(笑)。
「もっと上!」「あ、そこもっと下……」
なんて、なかなかに注文の多いお客様ですが、この声はきっと「もっと触れていて」「もっとそばにいて」という心のアンコール。
「お客さん、凝ってますね〜」なんて言いながら、合間に「かわいいねー」「大好きだよ」を挟み込む。 そんなふうにふざけながら肌と肌でやり取りしていると、子どものトゲトゲした気持ちや不安が、お湯に溶けるみたいに消えていくのがわかります。
連休明けの「マッサージして〜」は、立派なSOS。 家でしっかりカピバラ顔になって充電できた子は、外に出たとき、不思議と自分から「今日は一人で歩く!」と手を離していけたりするものです。
手をつなぐ代わりの「心のアンカー」
外でどうしても手が離せないときの、ちょっとした工夫もご紹介しますね。
・「裾つかみシステム」 「今はおてて使えないから、ママの服のここをギュッとしててね」と裾を渡します。これだけでも「つながっている安心」は届きます。
・「指一本契約」 「小指だけなら空いてるよ!」と、最小限の面積で契約。お互いの負担を減らしつつ、ぬくもりはキープ。
・「見えない糸の魔法」 「離れていても、見えない糸でつながってるから大丈夫だよ」と伝えて、ときどき目を合わせてニコッとする。視覚的なつながりも、手のぬくもりの代わりになります。
まとめ|手のぬくもりが教えてくれること
「手をつなぐ」ことは、単なる移動の手段ではなく、親子関係の中で安心感と自己肯定感を育てる大切なコミュニケーションです。
子どもにとって、手をつなぐ時間は「心のごはん」のようなもの。 しっかり満たされた子は、いつか必ず、自分の足で力強く歩き出します。
「いつまで続くの?」と不安になることもあるけれど、こちらが手を繋ごうとしても「やめてよ」と全力で拒否される日は、案外すぐそこまで来ています。
だから今は、そのちょっと汗ばんだ小さな手の感触を、「期間限定の贅沢品」として味わってみませんか。
無理に急がなくて大丈夫。 つないだ手のぬくもりは、やがて子どもの心の中で「自分は愛されている」という確かな土台になります。
今日、もし余裕があったら。 「今ならもんであげられますよ〜♡」って、わが家のカピバラさんを誘ってみてくださいね。

ぎゅっと手を握ってもらった
抱きしめてもらった
自分の気持ちを受け止めてもらえた
こういう「安心の積み重ね」が、自己肯定感の土台になるんですね。
🔗「叱る」より「導く」へ。心理学でわかる子どもの自己肯定感を守る言葉
🔗「いい子」でいる子の心の声|親にだけ見せる“安心のサイン”
親子のスキンシップは「甘やかし」ではなく、「自律」につながる力。 観察と声かけの工夫で、子どもの“心の根っこ”を育てたい方におすすめです。

目がキラキラ輝く子に育つ自律脳の育て方 ―スキンシップ・観察・伝え方の3つを工夫するだけで大丈夫!―
📘おすすめ絵本|不安な気持ちに寄り添う時間に
子どもが「なんだか不安そう」「甘えんぼうになってる?」―― そんなときに読みたい、心がふっと軽くなる一冊です。 親子でページをめくりながら、「不安な気持ちってあってもいいんだね」と 安心感を共有できる絵本です。
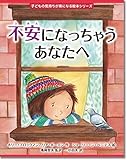
不安になっちゃうあなたへ(子どもの気持ちが楽になる絵本シリーズ)
行動の裏にある「伝えられない気持ち」へ
自己肯定感を育てる親の声かけ・かかわり方
今日から使える具体フレーズで、叱る前に「気持ちを受け止める」関わりへ。 家の中に「安心できる場所」を増やしましょう。
🔗優しすぎる子が小学校でつまずく理由|“自己主張できない”は家庭で変えられる
📚関連記事
🔗【癇癪・黙る・ふざける】子どもの“困った行動”
🔗夜に泣く理由、実はコレかも?「甘え」と「疲れ」の見分け方
🔗急に甘えん坊に!? 子どもがベッタリする本当の理由
📗おすすめ絵本|不安な気持ちに寄り添う“おたすけモンスター”シリーズ
子どもが「心配」「こわい」「うまくいかない」と感じたとき、 その気持ちを受け止めて、前に進む力をくれる絵本です。 読みながら、「大丈夫だよ」「がんばってみようか」と、 親子で安心感を共有できる時間をつくってくれます。
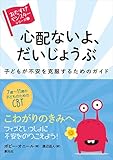
心配ないよ、だいじょうぶ ―子どもが不安を克服するためのガイド〈おたすけモンスター〉シリーズ―
ホーム » 子どもが手をつなぎたがる理由は「甘え」じゃない|安心の欲求と自己肯定感を育てる関わり方
このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、
子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。
ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪
育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊
この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!
正解を探すより、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。
※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。
\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /
ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、
実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。
教科書通りの正解に傷ついたとき、
「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、
静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。
このブログはPRを含みます
いっちー
元教諭(15年+)&プロカメラマン。
わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。
教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。
キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。
「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。
子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。
今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。


